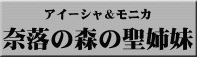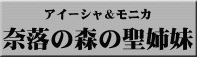|
その若いエルフ(亜人間)の女は、何処ともしれぬ薄暗い穴ぐらの中に、無惨な姿で囚われていた。
全裸で、両手を後ろ手に縛られ、首には犬などのつける緑色の首輪が、まるでアクセサリーのように巻かれている。
手首を縛め(いましめ)ているのは、何か動物の組織を編んだようなグロテスクな縄様のもので、その同じ素材が首輪からも上に伸びて、ややゆとりをもたせて天井の金具に結ばれている。
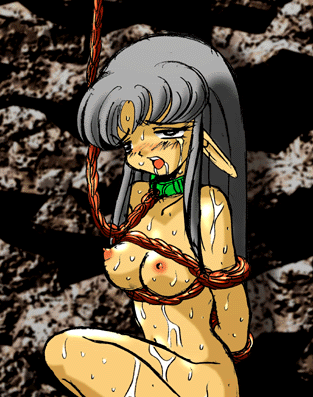
輝くような銀色の髪、同じく銀色の瞳、エルフ族特有の、長く尖った両耳、すっきりと形の良い鼻と唇・・・。
女の美しさは申し分無かったが、そのあられもない姿とひどく気怠げな表情が、女の印象をくずれた、淫らなものにしていた。
「うぅ・・・ふぅ・・・」
かすかに呻いた口の端から驚くほど多量の涎が溢れ出て、形良く盛り上がった女の胸を濡らしてゆく。
その視線は焦点を結んでおらず、どうやら彼女はほとんど正気を失っているらしい。
(・・・ここは何処だろう?どうして私は、ここにいるのだっけ?・・・)
霞がかかったようにハッキリしない頭の中で、彼女は独りごちる。
辺りに見えるのはじめじめと湿気を含み、冷たく脆そうな泥質の岩肌。そこを浅く穿って立て灯された、蝋燭のわずかな明かりだけである。
こんな所で、なぜ自分は家畜にも劣る扱いを受け、浅ましい姿をさらしているのか。
(どうして?・・・何も分からない・・・。そもそも、この私はどこの誰だったろう?・・・ああ何も思い出せない・・・)
おぼろげながら、自分には何か大切な使命があったような気がする。そして本来の自分は、華やかな栄光の中で、多くの人々に畏敬をもって迎えられていたような気も・・・。
だがそれは、そんな気がするだけだ。
確かなことは何も思い出せないし、特に思い出したくもない。
昼も夜も定かでないこの闇の牢獄で不自由に繋がれ飼われているというのも、今の彼女にはそこそこに気楽で不快ではない。
それに、こうしておとなしく夢幻をすごしていれば、時折何にも代えがたいめくるめくような至福が与えられるのだ。
それは・・・。
と、その時、彼女を取り巻く闇の一部がかすかに動き、そこから白い人の手がスーッと突き出されてきた。
手は粗末な木製の椀を持っており、中には何か透明な粘い液体が、七分目ほど注がれている。その液体こそ、彼女が夢にうつつに待ちこがれた、素晴らしい至福の源だった。
「うッ、うッううーッ!」
ようやく訪れたご馳走に我を忘れ、女は獣のように浅ましく鼻を鳴らして椀にむしゃぶりついた。
ずずっ、ずずーっ。
下品な音を立て、中の液体を無我夢中ですすり込む。
白い手は注意深く椀を傾けて彼女が餌をむさぼるのを助けていたが、やがてそれが空になると、高く持ち上げて「もうおしまい」というようにヒラヒラと振って見せた。
「・・・・・・」
口元から顎の下まで、呑み込みそこねた液体とよだれでベトベトにして、女は再び岩肌に身をもたせかけると満足げに目をつむる。
程なくして、その全身に変化が現れた。
「んん・・・んフうッ!・・・」
豊かな両の乳房がブルブルと震えながらさらに大きく張り、固く尖りだした乳首を頂点として、細かな汗の粒が一面に浮いてくる。
「んッ、んッ・・・」
汗はやがて全身に吹き出して照り光り、それにつれて身体が小刻みに揺れ悶え始める。
「あッ・・・ハッ、ハッ、ハッ・・・」
次第に呼吸を荒げながら女はやおらに上体を深く折って乳房を激しく振り、今は完全に勃起した乳首が太ももに擦れると、快感のあまり感電したように勢い良くのけぞった。
「くひイイーッ!」
汗とよだれがしぶきとなって飛び散り、豊かな白銀の髪が空中に扇のように広がり波打つ。
「えはァァ・・・」
全身をすっかり上気させ、堪りかねたようにゴロリと横たわって、女は脚を大きく開いた。
じゅッ、ちゅッ、ちゅッ、ちゅッ・・・。
彼女の秘部は既にすっかり露を含み、内股のひくつきにリズムを合わせて淫らな音を立て始めている。
くだんの液体は、恐ろしく強力な、即効性の媚薬だったのである!
女の理性をわしづかみにして握り砕き、過去も、名前すら意識から溶かし去って、一匹の浅ましい牝犬へとおとしめた猛毒の水・・・・・それが今また彼女の中で猛威を振るい、歓喜の波をその身体の隅々にまで送り込みつつあった。
そしてその波はみるみる彼女の忍耐の喫水を越えるほどに高まり、激しく打ち寄せる!
「 あクウウッ、あクウウッ!」
言葉にならない声を上げ、背中に束ねられた両腕が何とか自由にならないかと、必死で身をもがく。
(おッ、お願い、誰かこの縛めをほどいてッ!この手であそこをこね広げたいの!思うさま、奥の奥までかきまわしたいのォーッ!)
心中でのその浅ましい絶叫が聞こえたかのように、正体不明の白い手は、椀を下に置くと女の股間をまさぐり苛み始めた。
じゅッ、チュッ、チュプッ、チュプッ・・・。
ふくれあがった陰核を小刻みになでさすられると、サーモンピンクの内壁がみるみるまくれはじけて、透明な樹液をとめどなく溢れ出させる。
「くハッ、あくひャアアーッ!」
もはや人としての誇りや、羞恥心のかけらも無い。淫らな喜びをむさぼり尽くそうと、女は獣のように喚き、首を振り、身をよじった。体液が細かく舞い、首輪の金具がガチャガチャと音を立てる。
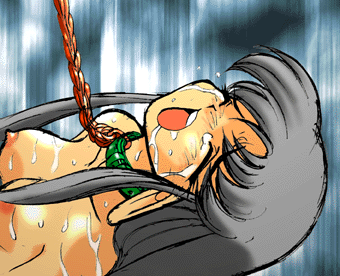
と、闇の中から、今度は黒い蛇のようなものがスルスルとしなやかに伸びてきた。
所々にぶくぶくと醜い突起のある表面は、てらてらと何かに濡れて光っている。
ぎゅッ、ぎゅッ、ぎゅッ・・・。
不気味な音を立て、狙いを定めるかのように一度、二度と鎌首をもたげると、それはやおらに女の股間に向けて突進し、秘唇のあわい目に分け入り貫いた!
「いヒィイーッ!」
絶叫と共に、女が大きくのけぞる。
みチッ、みチッ・・・。
肉の襞をかき分け、身をよじって押し入ってくるその毒蛇を、女の花芯は喜びの涙を溢れさせて迎え入れた。そしてふくれあがったその先端を、子宮の筋肉ががっちりとくわえ込み、快楽のほんの一しずくまでも逃すまいとする。
(ああッ、なんて素敵なのッ!こんな目の眩むような喜びを、私はほんの最近まで知らなかったんだ。なんとつまらない世界に生きていたのだろう。ああ、もっともっと奥まで来てッ!もっともっと、私に天国を見せてッ!)
女の意識が桃源郷に踏み入りかけた時、闇の奥から、邪悪な響きを帯びた忍び笑いが、小さく漂いもれてきた。
「クク・・・クククククク・・・」
例の白い手の主が、初めて発した声であった。
「いいザマだな。すっかり夢見心地かい?」
甲高いその声音は、男とも女とも判然としない。
ただ一つ確かなのは、それが何かまがまがしい、よこしまな気配を感じさせるということだけだ。
しかし女は、その謎の声の揶揄に何ら恥じ入るでもない。そう、今はそんなことはどうでもいい。それどころではないのだ。
ほら、見通せない奥の闇の中から、盛んに物をねだるようなくぐもった呻き声が、次第に高く大きく響いてくるではないか!
(ああそうだわ・・・私同様に、この至福の瞬間だけを渇き待ちこがれている者が、まだ何名か繋がれ囚われているのだっけ。だけどイヤよ!今度はいつ訪れるやも知れないこの幸せな瞬間を、もっともっと味わい尽くすまで、微塵でも他人に分け与えたりするものですか!)
輝く銀髪の女は、さらに貪欲に快楽をむさぼろうと、ともすれば遠く薄れそうになる自分の意識に鞭をくれ、喘ぎ、のたうち、淫らな声をあげ続ける。
そしてそれに応呼するかのように、例の笑い声があざけりの調子を強くしながら、次第に高く、大きく、薄暗い穴ぐらの奥へと響き伝わっていった・・・。
→2を読む
→最低書庫のトップへ
|