|
淫虜〜樹(いつき)〜
樹(いつき)は、自らの汗と愛液、それに数知れぬ男達の獣気に湿ったマットレスの上で荒い息をついていた。
日々、樹の中を通りすぎていく見知らぬ男たち。つい今しがたも、脂ぎった初老の男が、その娘といっても若すぎる樹から、あらん限りの媚態と嬌声を絞り上げて部屋を出ていったばかりであった。
(憲次さん、わたし、もう、憲次さんの知ってる樹じゃなくなっちゃったみたい…)
樹は、間断無い性の開発を続けられて、今では常にホゥッと火照ったような熱さを帯びている自分の身体の急所を、引き寄せた箱から取り出したティッシュで清めながら哀しげに独白した。
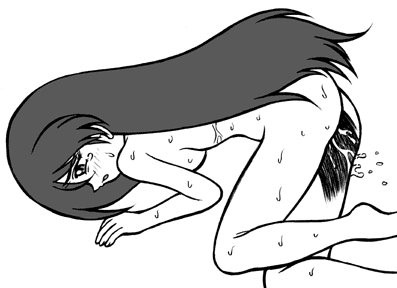
樹は、都内の女子高に通う高校2年生であったが、青年起業家の憲次(けんじ)と交際をしていた。樹はどちらかといえばおくてで控えめであり、男と本格的につきあったことなどなかったが、あるとき樹が通学に利用する駅で少し緊張したような面持ちで樹を待ち受け、
「あのっ、前から君のこと、見てたんだ! これ、読んで。返事はまた明日、待ってるから」
と、いまどき中学生にも珍しいようなうぶなラブレターの渡し方をして去っていった憲次に、何となくほほえましいような好意を覚えて、翌日すぐに承諾の返事をして、以来清らかで穏やかな交際を続けてきたのであった。憲次は去年、都内の有名国立大学を卒業して、卒業後すぐに趣味の語学を活かしていわゆるベンチャービジネスを創業したというが、そうした人物にありがちな思い上がりや自我肥大も見受けられず、むしろ、高校生の樹から見ても世間知らず過ぎるのではないかと思われるほどに人のいい性格であった。
(憲次さん、いい人だけど、こんな人が悪い人にだまされたりしないで、ちゃんと会社やっていけるのかな…?)
時折、樹は不安に思ったが、頭脳は明晰な憲次の経営手腕に支えられて、事業の経営はそれなりにうまくいっているようであった。
「樹、すっごーい、彼、エリートじゃない。憲次さんの友達、紹介してよぉ」
学校の友人たちに囃し立てられると樹はいつも
「もう、憲次さんはお友達で、彼氏っていうわけじゃないんだから…」
と、困ったような、恥ずかしそうな様子でそれをさえぎったが、内心では、優しく、そして凡百の若い男とは違った憲次のことを誇らしく思ったものだった。
しかし、ある日突然に、憲次の事業に対する樹の漠然とした不安が現実のものとなり、そしてその数奇な人生の荒波は樹自身にも覆い被さってきたのである。
「樹、ぼく、もう、樹に会えなくなるかもしれない」
ある日、何だか会ったときから元気が無く、樹の話に力なく相づちを打つだけであった憲次が、別れ際に樹に向かって切り出した。一瞬、樹は何を言われているのかわからず、次の瞬間、咄嗟に自分が憲次に振られるのだと思い、
「…え、…どうして? 樹、何か、悪いこと、した?」
と、もう夏になろうというのに異常な肌寒さのようなものを感じて、かちかちと歯のなりそうな、こみ上げるような震えを抑えつけながら憲次の目をまっすぐに見詰めて問い掛けた。
「…」
それに対して、やや言葉に詰まった憲次は、樹の視線を避けるようにうつむくと、搾り出すようにして言った。
「違うんだ…ぼく、…ぼく、海外の悪質な会社に騙されてしまって、そいつらが、ヤクザっていうか、アジア系のマフィアみたいな連中と関係してて…。何だか、とんでもない額の手形がいつのまにか振り出されたことになってて…」
樹は、いつだったか憲次に見せてもらった、見なれない書面のようなものを思い出した。
『樹、これ、手形っていってね、ただの紙切れみたいに見えるけど、ほら、ここに2000万って書いてあるよね。この紙切れ自体が、2000万円の現金と同じ価値があるんだよ』
当時、憲次の言うことは、あまりにも高校生である樹の日常生活とは縁遠いものに感じられて、
『ふーん、すごいのねぇ』
と、今一つ感動にかける反応をしたものだった。
「…それで、あいつら、僕のこと殺すって…、期日までに米ドルで五千万ドル払えなければ、僕に保険をかけて殺すって…!」
呆然としていた樹は、憲次の思いつめたような言葉で我にかえった。
(殺す…? 殺される? 憲次さん…、憲次さんが死んじゃう?)
初め、まったく現実感をともなわなかったその言葉が、何度も心中で反芻するうちに次第にはっきりとした形をもって、恐ろしい現実を樹につきつけてきた。
意外にこんなときは女のほうが大胆なものかもしれない。錯乱気味の憲次を叱咤して樹が聞き出したところによれば、明日、憲次は相手方と秘密の交渉を行うことになっているらしかった。
しかし、悪くすれば明日、その場所ででも憲次の命はどうなるともわからないという。樹は、決心した。
「憲次さん、明日、私も一緒にいく。相手の人達も、憲次さん以外の人間がその場所に来るなんて思ってないでしょうし、わたしが憲次さんと一緒にどうにかされれば、パパやママがその日のうちに警察に連絡して大騒ぎになるわ。絶対、わたしも一緒につれてって、でなきゃ、憲次さん、この腕、離さないから
ねっ!」
憲次は、樹の申し出を聞いて、それは危険過ぎる、と初め拒否したが、交際し始めて初めて見せる樹の意外なほどの強情さに首を縦に振らざるをえなくなった。
翌日、一見するとごく普通のオフィスビルに見える建物の一室にしつらえられた会見場を憲次と樹は訪れた。二人を迎えた男達は、意外なことに憲次と連れ添って歩く樹を見ても特に何もたずねようとはしない。憲次と樹が並んでソファに座ると、男達の代表者らしき黒いスーツ姿の長身の男がデスクを立ってやってきて、二人の向かいに腰を下ろした。
「ようこそ、三城社長、それに、社長の彼女の、」
そこでいったん間をおいて、
「樹さん、でしたかな?」
男の口から樹の名が出たことで動揺する憲次と樹をにやにやとみつめながら、男は続けた。
「ちゃんと、存じ上げておりますよ。三城社長が当社に対する借金をお支払いになれないだろうと見積もった時点で、当然、社長に彼女でもいらっしゃれば、その方にも御協力願おうと思って準備しておりましたからね。いや、驚きましたよ。社長ご自身、お若いが、樹さんは高校生だっていうんですから。しか
も、写真で見るよりも、とびきりにかわいらしい」
獲物を見据えた蛇のような光を独特の三白眼に浮かべながら、すさまじい笑みを浮かべて男が身を乗り出した。樹は思わず、ソファの背に身を沈めるように身を引く。
男も、一旦身体を後ろに引いて、足を組み直し、しかし、にたにたとした笑みは相変わらず浮かべたままで、言った。
「社長、率直に申し上げましょう。樹さんに借金返済の協力をしていただきませんか?我々の組織で働いてくれれば、樹さんなら、数年もかからずに社長の借金を返済していただけると思うのですが? その、すばらしい若い肢体でね」
「な、何を言うんだっ!」
瞬間、男の言葉に激昂した憲次が、樹にすら初めて見せるすさまじい勢いで腰をソファからあげて男の胸倉につかみかかった。
しかし、男は余裕だった。スーツの襟にかかった憲次の手首を軽くひねると、どうしものか大した力も加えていないように見えながら、憲次は
「ぐ、うぁぁっ!」
と悲鳴を上げて床に崩れ落ちてしまった。憲次の腕をきめた状態のまま、男は乱れた襟元を他方の手で直し、
「おい、三城社長は何だか、こちらの親切な申し出に御賛同頂けないようだ、ちょいと、説得に加わってくれねぇか?」
と、左右に待機するがらの悪そうな男達にむかってあごをしゃくった。すると、それまで直立不動の姿勢で居並んでいた男たちが、床にひざまずいている憲次の周りに素早くむらがり、と思うやいなや、よってたかって革靴で猛烈な蹴りを入れ始めた。
「や、やめて下さい!」
樹は思わず、憲次の上に身を投げ出して男達の蹴りの嵐から憲次をかばう。ものの数秒のことであったが、横隔膜に正確に入った蹴りのために憲次はすでに息も吸えない状態で床に転がっている。
「憲次さんっ! 憲次さん、しっかりしてっ!」
必死になって憲次を介抱しようとする樹を見下ろして、長身の男はさらに暴行を加えようとする男達を制した。
「ね、樹さん、どうします? 愛する三城社長は、このままじゃ明日には東京湾に浮かぶことにもなりかねやしませんよ。一つ、ここは樹さんの愛で、救ってやってもらえませんかね?」
相変わらず、不気味な笑みを浮かべたままで長身の男がしゃがみこみ、樹の顔を覗き込むようにして声をかけた。
「い…つき、だめ…だ」
苦しい息の下、憲次が声を振り絞ると、
「るせぇぇんだよっ!!」
突如、豹変したように浮かべていた笑みをかなぐり捨てて長身の男が立ちあがり、すさまじい蹴りを憲次の胸先に叩き込んだ。
樹の腕から引き剥がされた憲次の身体は壁際まで吹き飛ばされてもんどりうち、肺か口内から出血したのだろう、量は大したことがないものの、口からしぶきのような鮮血がとび散った。
「け、憲次さんっ!」
泣きじゃくった後のように横隔膜が痙攣してしまい、裏返った声しか出すことができない樹が憲次にかけよる。
「い…いつ…だめ…だ」
ほとんど声にならないつぶやきが憲次の切れた唇からもれる。
「ねぇ、樹さん、どうします? 社長は勇敢なお人だ、死ぬのも怖くなくって、樹さんを守ろうってことなんでしょうが…、しかし、わたくしたちも人が死ぬところなんて見たくはないんですよ。ここは、樹さん、あんたの気持ち一つですよ、どうしますぃ? 社長を見殺しにしますか? それとも、命をはって
樹さんを助けようっていうこの人のために、一肌、脱いでくれますか?」
男は、樹に決断を強いているようであったが、実際には樹に選択権があるわけではなかった。樹に、しゃくりあげながら涙に濡れた瞳でこう言う以外、どのようなすべがあったというのだろう。
「わ、わかりました…、私が、お金を返すのに、協力します…」
長身の男は、それを聞くと、再び例の薄笑いの表情に戻って、
「おぅ、聞いたか? 借金を返してもらえるとなりゃ、社長は大切なうちのお取引先だ、丁重に手当てして差し上げろ。」
と、部下に命じた。悔し涙に顔を濡らし、しかし逆らうどころか身動きすらできない憲次が男達の手によって室外に運び出されて行くと、長身の男は樹の脇にしゃがんで、樹の耳の近くに口を寄せて囁いた。
「そして、樹さん…いや、樹、お前は、大切なうちの商売道具、特製娼婦にうまれ変わるんだ、丁重に、いろんな技術を仕込んでやるよ、特別な性技をな…」
樹にはすでに、胸元のボタンをはずして二つの膨らみの上に這いこんでくる男の手を払いのける気力は無かった…。
「ふっ、あん…、樹のなか、気持ち…いいですか?」
客の男にまたがって、双臀をゆらめかすボンデージ姿の樹が悩ましい声音でたずねる。
「あ…あぁ、樹ちゃんはほんとにイヤらしくって、かわいい奴隷だ…、くっ、もう、いくぞっ!」
プロの調教師に、徹底した性奴調教を受けさせられて、いまや組織のSM売春クラブ中でも屈指の特殊娼婦と生まれ変わった樹のテクニックの前に、客の男は、もはや耐えきれないというように叫ぶと、大量のしぶきをあびせかける。
「あ、あぁっ、樹も、いっちゃいますっ!」
それに合わせるように樹も上体を弓なりにそらせ、今日一日でもはや数え切れないほど繰り返された絶頂の痙攣を伝える。

「ふ、ふぅ…ふぅ、樹ちゃん、今日も良かったよ、またすぐに来るから、今度もかわいい鳴き声を聞かせておくれよ」
「はぁい…いつも樹をかわいがってくれて、ありがとうございます。また、淫乱な樹の身体を、いっぱいいかせてくださいませ」
エナメルの拘束衣をまとったまま、激しい絡み合いの余韻に荒い吐息をつきながらも、艶麗な笑みを浮かべて客を送りだす樹の媚態に満ちた姿は、一月前までの清楚可憐な女子高生のそれとは似ても似つかないものであった。
しかし、客を送り出してしまうと、樹の表情にふと、暗い陰りが落ち、性の欲望に穢れきった自らの肉体を嫌悪する色が浮かぶ。そこには、かつての樹とまったく同じであるわけではないものの、普通の少女であった頃の理性の面影が見え隠れする。
(憲次さん、わたし、もう、憲次さんの知ってる樹じゃなくなっちゃったみたい…)
樹は、何度まぶたの裏に浮かぶ憲次の面影に向かって呟いたかわからない独白を繰り返した。そして、今日までに取った客の人数を指折り数えると、
(これで、やっと十万…ドルか…)
いまだ遠い、借金返済の道のりを思うのであった。
※※※ ※※※ ※※※
「へっへっへ、樹はいい特殊娼婦になったぜ、今日のあがりだけで1000万円はくだらねぇ。金持ちのじじいども相手に、立派に真性M奴隷としての勤めをはたしてらぁ」
例の、長身の男が笑いが止まらない、というように樹が稼ぎ出した札束を数えている。
「へへ、で、そのうちのどれだけが樹の借金返済分になるんですか?」
正面に座った若い男がたずねる。
「それは、言わない約束だろ? 樹に回るのはその1パーセントってところだ。ま、目一杯稼いでもらわなきゃな」
「ひどいっすねぇ、で、いつも通り、延々と続く借金の返済が終わった頃には、樹自身がMの快楽の虜になってるって寸法ですか? 鬼ですねぇ」
若い男の言葉に、にやっと笑うだけで返事をしなかった男は、ついと立ちあがると、部屋の一隅のモニターのスイッチを入れた。
『あ、ヒィ、う…いぃぃぃ、いいのぉ…、い、樹、樹、いっちゃうぅぅぅぅっ!』
モニターには、樹が娼婦として働かされている一室に備えつけられたテレビカメラから送信されてくる映像が映し出され、スピーカーからは淫欲にまみれた少女奴隷、樹のよがり声が響く。
自らが性技をしこみ、娼婦としての教育を施した、かつての清らかな少女の慣れの果てを眺めながら、ふと、哀れみに似たような不思議な表情を浮かべた長身の男が、若い男に向かって言う。
「なに言ってやがる、三城社長…だっけか?適当な偽名で、青年実業家とかふいて樹をだまし、今もあいつの純真を弄び続けているおめえに言われたかねえぜ、士型よ」
「へへ、本名で呼ぶのはやめて下さいよ、うっかり樹の前で、苗字の士型にしろ、名前の彩雲にせよ、もれちまったらもともこもねぇじゃねえですか」
その言葉を交わし終わると、二人の悪党は、酷薄な笑みを浮かべてモニターの樹の、男の腰の律動に合わせてふるふると揺れ動く双乳に見入った。
(これで、10万…………)
10万をひとつの区切りと感じ、この営みにいつか終わりが来ると信じているのは、あわれ、性交少女、樹ひとりだった。
了
→戻る
|