|
鈴神楽氏・作
鈴神楽さんによる「名探偵コナン」のエロパロ小説です。 灰原さんが、かつて組織で研究していた媚薬。それが彼女自身にも秘かに投薬されていて・・・というヤリまくり狂いまくりのエロいオハナシです。 |
|
鈴神楽氏・作
鈴神楽さんによる「名探偵コナン」のエロパロ小説です。 灰原さんが、かつて組織で研究していた媚薬。それが彼女自身にも秘かに投薬されていて・・・というヤリまくり狂いまくりのエロいオハナシです。 |
| あたしの名前は、宮野志保。 しかし、この名前で呼んで欲しい人は、もう誰も居ない。 そしてあたしは、宮野志保としての姿も無くして、ここに居る。 子供の姿、灰原哀と言う名前で小学生としての生活を送っている。 純粋な少年探偵団の子供達、優しい毛利蘭、そして自分の命も顧みないで奴等、組織と戦う工藤君。 全てを無くした筈のあたしに新しい護る物が出来た。 そんな事を考えながらあたしは、何時もの様に薬の研究を続けていた。 そんな中、その発作が起こった。 「おかしいわね、暑いわ」 あたしは、汗を拭いながら温度計を見て、眉を顰めた。 「汗をかく様な温度じゃ無い?」 しかし、あたしは、暑さを感じていた。 全身になんとも言えない違和感を覚え、上着のボタンを外していった。 「ハアァ、どうしたのかしら?」 我慢できず、あたしは、博士が居ないのを幸いに服を脱ぎ、下着姿になった。 それでも、体が火照る。 そして、あたしは、気付いてしまう、下着の股間部が変色していることに。 思わずその部分に触れた時、あたしの体を衝撃が走った。 それは、大人の体の時、数えるほどだったが、行った自慰行為で感じた、それだった。 あたしは、慌てて手を離し、困惑する頭を落ち着かせる為に深呼吸をする。 「冷静になるのよ、普通に考えて、性感は、第二次成長に影響受けやすい。それは、体内フェロモンによる働きに大きく関係している為。かといって、小学生が性感を感じないことは、ありえない事では、ない。ましてや、この体では、そういった物の働きが通常と同じとは、考えるのも間違い。そうよ、あの薬の影響による、異常フェロモンの働きの可能性も……」 思案するあたしにある事が思い出された。 「まさか、あの薬があたしにも……」 あたしの脳裏に組織に居た時に立ち会った、ある実験が思い出された。 その実験は、組織にどうしても必要な人材の逃亡を防ぐための薬の実験と言われた。 最初にそれを見た時、あたしは、鼻で笑った。 「お粗末な考え方ね。性欲で人を束縛するなんて不可能。第一、そんな状態では、ものの役にも立たないと思うわ」 あたしの答えに担当の科学者の男が苦笑する。 「無論、これは、性欲自体で人を束縛する物では、ありません。大切なのは、その効果の持続性です」 「持続性?」 疑問を問いかけるあたしにその男が答える。 「生物の三代欲求、睡眠欲、食欲、性欲。これだけは、人間が生物である上、克服できない欲求です。その為、それを利用した洗脳術も多く開発されてきました」 あたしが頷く。 「確かに、でも睡眠欲は、頭脳の働きに直径し過ぎているため、過剰な薬物投与は、被験者を壊す可能性が高く、食欲は、肉体的な制約にとらわれる、そして性欲に関して言えば、個人差が大きく、そして薬以外の要素が高くなり過ぎるため、一定の効果を生み出すのは、難しい筈よね」 男は、深く頷く。 「直接洗脳という使い方をすれば、そうでしょうね。さっきも言ったとおり、今回注目したのは、その持続性、そして、秘匿性です。今回の薬では、通常の体内発生物質以外の成分は、発生しません。ただ、定期的に特殊な薬を飲んだ人間の精液を摂取しない限り、性欲が蓄積されていくだけ、その過程では、ただ本人の性欲が溜まっているだけにしか感じられない。しかし、いったん溜まってしまえば、先程述べた精液を吸収するまで性欲が収まらなくなる、彼女の様に」 そういって男は、実験室のカーテンを開く。 『お願い! 誰でも良いから、あたしのオマンコにチンポを入れて! 大量のザーメンを飲まして!』 そこには、涎や涙、小水を垂れ流し、自分の手で限界まで割れ目を広げる、色欲に狂った女性が居た。 あたしが言葉を無くしている間に男が指を鳴らすと一人の男性が入っていき、その女性と交尾する。 『良い! いい! イイィィィィィィ! いっちゃうぅぅぅぅぅ!」 そういって女性が乱れ、そして男性が射精をする。 『熱い! サイコーーーーー! イックゥゥゥゥゥ!』 女性は、白目を剥く。 数分後、目を覚ました女性は、自分の姿に顔を真赤にしている。 そして、科学者の男がマイクで告げる。 「もう解っただろう、お前は、組織の男以外で満足出来ない体になったんだ。このまま強情をはれば、永遠に欲情し続ける事になるぞ。さあ、最終判断だ、やつ等を裏切るか?」 女性は、激しい葛藤の末、告げる。 『……組織に忠誠を誓います』 その女性が悪魔に魂を売った瞬間だった。 女性が組織の人間に連れられて行った。 「この薬も完成に近づいたのですが、問題が発生したのです」 男の言葉に苛立ちを隠しながらあたしが返す。 「問題、何か副作用でもあるの?」 男が困った顔をして言う。 「この薬自体には、問題は、ありません。問題は、男性に飲ませる薬の方です」 あたしは、眉を顰める。 「どういうこと?」 男が薬の錠剤を見せて言う。 「この薬は、強力な精力剤にもなるのですが、強力過ぎて、男性に負担がかかるのです。それともう一つは、薬を飲んだ男性の精液が一種の麻薬の様な中毒症状を起こすこと。一回や二回なら問題ないのですが、一度に大量に吸収すると吸収した女性が、その精液を激しく求めるようになります。麻薬同様に取り続ければ取り続けるほど、その症状は、酷くなります」 肩を竦めるあたし。 「セットで使用する薬剤に中毒性があるとしたら、薬としては、欠陥品ね」 苦笑する男。 「そこで貴方には、この欠点の改良をお願いしたいのですが」 成分表を受け取るあたし。 「比較的簡単な成分ね。解った研究をしておくわ」 あたしは、その成分表をもって部屋を出た。 その夜、あたしは、自慰行為で絶頂を感じ、それから数日後、姉の死を知った。 あの時の状況を思い出して、男性用の薬の成分表と一緒に渡された幾つかの実験内容を脳裏に浮かべる。 そして、その経過状態と自分の今の状態を照らし合わせ、苦々しい顔をしてしまう。 「あたしにも投薬されて居たって事ね。しかし、この状態は、確かかなり進行が進んでいるわ。今からあたしの体内の薬の中和薬を作るのは、不可能、そうなると残された手段は……」 「おーい灰原、急用ってなんだ」 玄関を開けて、工藤君がはいってくる。 あたしは、動くだけで疼く体を必死に押さえながら工藤君の所に行く。 「どうしても協力して欲しい事が出来たの、こっちに来て」 「あまり夜中に呼ぶなよ、蘭を誤魔化すのも大変なんだからな」 工藤君のその言葉に、あたしの胸に複雑な痛みが走った。 多分、蘭さんへの罪悪感……の筈。 あたしは、自分の下手に連れて行き、工藤君を椅子に座らせる。 「本気でどうしたんだ?」 ここに来るまでの間にあたしを観察して異常を察知したのか、工藤君の口調は、真剣の物になっていた。 あたしは、正直に今の状況を説明すると流石の工藤君も困惑した表情で言う。 「どうにか、中和剤を作れないのか?」 あたしは、首を横に振る。 「女性に投与した薬の成分表は、貰ってなかった。もしかしたら、その時からあたしに薬を投与する予定だったのかもしれないわね」 工藤君は、頭をかきながら言う。 「お前が正気を保てる内に組織から薬の中和剤を手に入れるしかないな」 あたしは、錠剤を工藤君に見せる。 「さっき言った男性側の錠剤よ、これを飲んで、あたしを抱いて、それが一番簡単な方法だわ」 工藤君は、慌てる。 「バーロー、そんな事が出来るか!」 あたしは、真摯な目で言う。 「それしか方法がないわ。薬の性質上、中和剤は、必要性が無く、あったとしてもそう簡単に手に入るものじゃない。性欲の進行状態から考えても先にあたしが正気を失う可能性が高い。それに症状が現れたら、そこからあたし達の正体が組織にばれる可能性も高い、どっちにしても時間は、殆ど無いのよ」 「だがよ……」 工藤君も理性では、理解している筈、多分、工藤君を躊躇させているのは、蘭さんへの罪悪感。 あたしは、恥ずかしさを堪え、着ていた白衣を脱ぐ。 「バーロー、何をしてるんだ!」 白衣の下に何も着ていないあたしの裸を見て、工藤君が怒鳴るが、あたしは、自分の乳頭を弄る。 「見て、あたしがどれだけ、苦しんでるか」 あたしの乳頭は、硬く勃起していた。 軽く弄っただけであたしの息が荒くなる。 そしてそのままあたしは、股間の割れ目を広げると愛液が滴り落ちていく。 「もう、限界に近いのが、解るわね?」 顔を真赤にしながら工藤君が言う。 「だからってな……」 あたしは、工藤君に密着して言う。 「これは、治療よ、人工呼吸の時にキスをするのと一緒よ。だから、お願い」 哀願するあたし。 正直、あたしの頭の中には、もう工藤君にセックスされる事しか無くなっていた。 ここで、工藤君とセックスをしなければ狂って、誰彼構わずセックスを求めたくなる、それだけは、嫌だった。 工藤君は、錠剤を飲み言う。 「治療だからな! お前も犬に噛まれたと思って気にするな!」 あたしは、驚いた、もしかして工藤君が躊躇していたのは、蘭さんへの罪悪感からじゃなく、あたしの事を思って……。 あたしの胸に性欲とは、違った暖かさが灯った気がした。 「そうね、犬に噛まれたと思っておくわ」 きっとあたしの勘違いだ、こんな憎まれ口をたたくあたしを真剣に思ってくれる訳がない。 「バーロー」 そのまま、工藤君があたしをベッドの上に押し倒した。 そこで工藤君が戸惑う。 「やっぱ、入れる前は、揉み解したりした方が良いのか?」 苦笑するあたし。 「あら、てっきり蘭さんと経験済みかと思ったわ」 顔を更に真赤にする工藤君。 「蘭とは、単なる幼馴染だ!」 その態度が蘭さんを大切にしている証拠だとあたしには、解った。 その途端、さっきまでの暖かさが消え、性欲の熱だけがあたしを攻め立てた。 「もう、十分に濡れているからそのまま入れて」 「解った」 それだけいうと工藤君は、ズボンを脱ぐ。 そこには、体には、不釣合いな程に勃起した男性の性器、チンポがあった。 「行くぞ」 工藤君がそういって、あたしの中にチンポを埋めて来た。 最初に来たのは、処女膜を切り裂かれる激しい痛み、しかしこれは、長続きしない。 肉体的に男を欲求している今のあたしには、その痛みは、余計な物と処理され、鎮痛の脳内麻薬が発生し、その麻薬の働きであたしの中の快感が更に高まる。 「工藤君、もっと、もっと激しくして!」 自然とそんなはしたない言葉を口にしてしまう。 工藤君も我を忘れた様に腰を動かす。 「良い! いい! イイィィィィ!」 あたしは、工藤君のチンポを少しでも深くまで咥え込もうと腰を動かす。 「バーロー、そんなにされたら直ぐ出ちまうぞ!」 「出して! 熱い精液をたくさん出して!」 あたしは、本能のままに叫んで居た。 「どうなっても知らないぞ!」 工藤君が深く股間を押し付ける。 工藤君のチンポがあたしの膣の奥の奥まで貫き、そこで熱い精液を放った。 「イィィィィィクゥゥゥゥゥゥ!」 あたしは、その瞬間に果ててしまった。 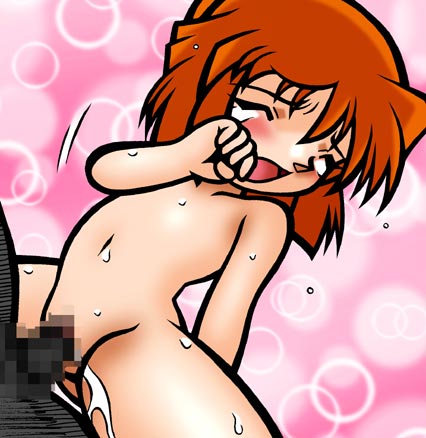 あたしが目を覚ました時、工藤君は、優しく問いかけてくれた。 「大丈夫か?」 あたしが笑みを浮かべて言う。 「意外と激しいのね」 耳まで真赤にしている工藤君。 「バーローそれより、早く中和剤を手に入れないとな」 「そうね、あたしの方でも頑張って作ってみるわ」 その日からあたしと工藤君の二人だけの秘密が出来た。 例の発作は、一ヶ月に一度のペースで襲ってきた。 その度にあたしは、工藤君とセックスをした。 蘭さんには、悪いが、これも治療なのだと自分達を誤魔化していた。 何時もの様にベッドで眠ろうとした時、例の発作に襲われた。 「又なのね」 小さくため息を吐き、かばんに例の錠剤を入れる。 「明日、工藤君にしてもらわないとね」 工藤君との行為を思い出し、オマンコが濡れだす。 「これも発作を少しでも沈める為よ」 あたしの手が自然と割れ目に近づく。 そして、割れ目をなぞる。 何時もの甘美な刺激が走る。 そして、そのまま割れ目を開き、指を工藤君のチンポに見立てて動かす。 「工藤君、もっと、もっと激しくして!」 あたしは、我を忘れて、それが本当の工藤君のチンポと思って感じた。 激しく感じる体、しかし、性質上、工藤君の精液が無い限り、発作が鎮まる事は、無い。 あたしは、そのまま眠れぬ夜を自慰し続けるしかなかった。 「哀ちゃん、大丈夫?」 吉田さんは、目の下にクマを作ったあたしを心配そうに聞いてくる。 正直、かなりきつかったが、そんな事を言っても仕方ない。 「大丈夫よ、それより、江戸川君は、遅いわね」 それに対して、吉田さんが不満そうな顔をして言う。 「それが、なんか毛利の叔父さんと一緒に事件の調査をしてて、来られないんだって。ずるいよね」 「嘘!」 あたしは、思わず立ち上がっていた。 吉田さんは、びっくりした顔をする。 「本当にずるいよな」 小嶋くんがあたしの言葉を勘違いして、同意してきた。 「本当にコナンくんだけずるいですよね。灰原さんが驚くのも無理は、ありません」 円谷くんも頷いてくるが、それどころじゃない、あたしは、慌てて廊下に出ると携帯で工藤君に連絡する。 「学校を休むなんてどういうこと!」 あたしの言葉に工藤君は、悪戯がばれた子供の様な声で言う。 『もう、伝わってるのかよ。すまない、元太達は、上手くなだめておいてくれ』 あたしは、慌てて言う。 「そんな事より、あたしの話を聞いて!」 『すまん、灰原、今大切な所なんだ、後で連絡する』 そのまま電話が切れる。 「工藤君の馬鹿!」 あたしは、力の限り怒鳴った。 その後は、地獄だった。 唯一の希望だった工藤君が居なくなった今、あたしには、体を這い回る快楽という淫靡な蛇に抗う術は、無かった。 授業中なのに関わらず、あたしの指は、自然と割れ目を擦り、その上にある淫核を弄り続ける。 恥ずかしさと快感に何度も気が遠くなる。 そんなあたしを見て、吉田さんが言う。 「先生、灰原さんが気持ち悪そうです!」 それを聞いて先生がこっちに来る。 不味い、性に対して知識の無い周りのクラスメイトならともかく、先生があたしの状況を見たら、解ってしまう。 あたしは、慌てて隣に居た小嶋くんの手を引っ張り言う。 「彼に保健室まで連れて行って貰います」 「え、俺がか?」 面倒そうな顔をする小嶋くん。 「元太くん!」 吉田さんに睨まれて渋々小嶋くんが席を立つ。 「解ったよ」 そしてあたしは、小嶋くんと保健室に向かった。 「本当に大丈夫か?」 小嶋くんが心配そうに言ってくるが、今のあたしにそれに答える余裕が無かった。 あそこはグチョグチョで、愛液が腿を伝わって踝まで垂れてきている。 もう限界だった。 誰でもいいから精液を飲みたかった。 「おい、灰原!」 こっちを見てくる小嶋くんをあたしも見つめる。 そうだ、彼が居た。 「小嶋くん、あたしを助けてくれる?」 「おう、何をすれば良いんだ」 小嶋くんの言葉にあたしは、工藤君に飲ませる為に持ってきた錠剤を見せて言う。 「あそこで、コレを飲んであたしを治療して」 あたしは、使われていない部屋を指差す。 「解った!」 あっさり乗ってくる小嶋くん。 部屋に入り薬を飲んだ後は、簡単だった。 「灰原、俺のチンチンが変だ!」 初めての勃起に戸惑う小嶋くん。 あたしは、ズボンを脱がして言う。 「大丈夫、直ぐに楽にしてあげるから」 あたしは、小学生の物とは、思えない勃起をあそこに当てて、腰を沈めていく。 「アァン!」 入れた瞬間、軽くいってしまった。 そして、小嶋くんもチンポからの快感に雄の本能が目覚めたのか、腰を動かし始める。 「灰原、腰が、腰がとまんねえよ」 「良いの、良いのよ! もっと、もっと、もっと激しく動かしてぇぇぇぇ!」 あたしも体全体で小嶋くんのチンポを味わう。 「何か出る!」 小嶋くんは、あっさり果てた。 「あたしも、イクゥゥゥゥゥ!」 あたしも激しい絶頂に達した。 そして、あたしは、意識を失った。 あたしが目覚めた時、あたしは、快感が続いている事に戸惑った。 「灰原!」 小嶋くんは、気絶したあたし相手に腰を動かし続けていたのだ。 「小嶋くん、もう駄目!」 あたしは、慌てて離れようとするが、昨日からの疲れで、腰が思うように動かない。 「また出る!」 そういって、何度目か解らない射精をする小嶋くん。 そして、それは、あたしにも激しい快感を与える。 そのまま小嶋くんは、精根尽き果てるまであたしの中に射精を続けた。 その日の内に小嶋くんとあたしは、入院した。 学校側は、今回の事を表立てにしないよう必死に動いたが、そんな事は今のあたしには、どうでも良かった。 あたしは、いま強烈な禁断症状に襲われていた。 「ザーメンが欲しい」 錠剤を呑んだ小嶋くんからの大量の精液摂取は、あたしを精液の急性中毒にした。 あたしの頭の中は、もうザーメンの事で一杯になっていた。 そしてそんなあたしの所に、円谷くんだ見舞いに来た。 「灰原さん、元気ですか?」 花を持ってきた彼、しかし、今のあたしには、もう彼は、ザーメンを精製する雄にしか見えなかった。 あたしは、震える手で錠剤を取り出し、円谷くんに差し出す。 「これを飲んで!」 円谷くんは、鬼気迫るあたしの様子に戸惑いながら、錠剤を呑んだ。 「灰原さん、僕、また出ます!」 「出して、出して、出して! あたしの中に熱いザーメンを一杯出して!」 錠剤を呑んだ円谷くんは、病室だって事を忘れて、あたしとセックスをした。 それは、ナースが気付くまでひたすら続いた。 「シェリー」 その声にあたしが頭を上げると、そこには、ジンが立っていた。 あの騒動であたし達の事が組織にばれた。 そしてあたしは、こうして捕まっていた。 しかし、そんな絶望的な状況に関わらず今のあたしの頭の中にあるのは、ただ一つだった。 「ザーメンを頂戴!」 憎い組織の男にそんな要求をしなければいけない事は、激しく悔しいが、もう我慢できないのだ。 「何でもいう事を聞く、薬の研究も続けるから、ザーメンを頂戴!」 それに対してジンが言う。 「その言葉を嘘は、無いな?」 あたしは、躊躇があったが頷くとジンは、指を鳴らす。 ドアが開いて、ウォッカが工藤君を連れてきた。 「工藤君!」 そしてジンは、あたしに注射機を握らせる。 「ザーメンは、あの坊主から搾り出せ。例の錠剤の成分を濃縮したこの薬をうてば、お前を犯してザーメンを吐き出す以外の事は、考えられなくなる」 「そんな事を出来るわけ無いでしょ!」 あたしの言葉にジンが言う。 「だったら好きにしろ、俺もウォッカもあんな危険な薬は、使わない。お前を満たしてくれるのは、そのガキだけだ」 そのまま部屋を出るジンとウォッカ。 あたしは、薬で眠らされているのか目を覚まさない工藤君を見ながらも、体がザーメンを求めて灼熱の炎に燃えていた。 手の中の注射器を見て言う。 「もう我慢出来ない」 あたしは、工藤君に注射した。 「シェリー、研究は、順調か?」 ジンの言葉にあたしは、膨らみ始めたおなかを擦りながら言う。 「もう少しよ、この子が生まれる前には、出来上がってる筈よ」 ジンが淡々と言う。 「そうか、それなら良い。セックスにするのは、良いが、それで遅れるような事があったら、そのガキを殺すぞ」 あたしは、睨む。 「そんな事は、させない、工藤君をころしたら、薬を二度と作れなくしてやるわ!」 あたしは、そういってから、あたしを下から犯し続けている工藤君にディープキスをする。 舌打ちをするジン。 「とにかく、研究は、急げ」 そのまま出て行くジンを無視してあたしは、あたしの中を満たす工藤君の精液を感じて呟く。 「工藤君、あたし、最高に幸せ、この子と一緒に幸せになろうね」 あたしは、二人の子供との幸せな毎日を思い浮かべながら絶頂に達した。 |