|
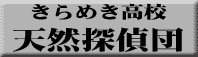
(1)天然探偵団誕生!
日の落ちかけた通学路・・・
きらめき高校二年生の古式ゆかりは、テニス部の練習で火照った肌に風を心地よく感じながら、家路を急いでいた。
急いでいた、と言っても、その足取りは常人のそれに比べてかなりモッサリしている。カメが寝ぼけながら歩いているかのようだ。
それもそのはずで、彼女は学内でも有名なおっとりさんであり、また頭のネジが100本くらい飛んでいるのではないかというほどのスーパー天然少女なのだ。
と、ゆかりの前方で大型のランクルが不意に停車し、男が1人降りてきた。
「やあ、古式さん、会えて良かった!」
馴れ馴れしく話しかけながら近寄ってくるその男は、ゆかりと同い年くらいの少年で、別の高校のモノらしいブレザーの制服を身に着けている。
ちょい見た目、ホスト風の美男子なのだが、いかにもナンパの虫が頭にわいていそうなニヤケ面でもあり、ために何とも崩れた物腰に見える。
「あらァ〜、あなたはァ〜、ええとォ〜・・・」
相手の顔や制服に何となく見覚えがあり、しかし誰だったかは思い出せなくて、ゆかりが逡巡していると、
「何だよ、オレのこと忘れちゃったの?こないだの練習試合で会ったじゃない。七光高校の金巻ハジメだよ」
「ああ〜、テニス部のォ〜」
ゆかりはようやく思い当たってうなずいた。
七光高校は同じ市内にあるブルジョア向けの私立校だ。と言って特に品が良いわけではなく、金満家のボンボンやお嬢様が大勢通っているというだけなのだが。
その七光高校ときらめき高校のテニス部同士が先日練習試合を行い、ゆかりも部員として参加をした。
金巻ハジメも相手側のテニス部員として参加していたのだが、試合などそっちのけで、きらめき高校の女生徒をナンパしまくって回り、その時ゆかりも声をかけられたのだ。
「思い出した?オレ、結構印象薄かったとか?」
「いえいえ、覚えてますよ〜(少しだけど)。こんなところでお会いするなんて、偶然ですねェ〜」
「偶然じゃないって。オレ、キミに会いに来たんだもん」
「ええ〜、どうしてですかァ〜?」
「どうしてって、こないだも言ったじゃん」
金巻ハジメは苦笑した。
「オレ、キミのことが好きになっちゃったんだ。それで、ちゃんとコクろうと思って来たワケ。どう、オレと付き合わない?」
完全に白痴のセリフである。
「はあ〜、それはお断りします〜」
ボンヤリと間延びした口調のまま、しかしムチャクチャ直截に、ゆかりは答えた。
「私には今、お慕いしている殿方がいるのです。他の殿方とは交際は出来ません〜」
「な、何だよそれ。ちょっとヒドくねェ?」
いきなり激して顔を強張らせ、ハジメは噛み付くように言った。
「オレはさ、わざわざチョクでコクりに来たんだぜ。それをさ、他に好きな野郎がいるって、オレのメンツみたいの丸つぶれじゃん」
そんなことはゆかりの知ったことではないのだが、こういう、バカのクセにプライドだけは人一倍高いお坊っちゃまは、他人から拒絶されるということがガマンならないらしい。
「オレは引き下がらないぜ。とにかくオレの車に乗れよ。二人でどっか行って話とかすればさ、キミも絶対オレのこと好きになるって。さあ!」
男はグイとゆかりの腕をつかみ、彼のマイカーらしいランクルへ連れ込もうとする。
さすがにノンビリ屋のゆかりも恐ろしくなり、悲鳴を上げかけたその時・・・・
ゆかりと同じきらめき高校の制服を着た女生徒が1人、すぐ近くの角を曲がってこちらへ歩いてきた。
ハジメとゆかりが揉み合っているのに気付いたその女生徒は、すかさず、
「あーッ、痴漢だッ!不審者だッ!皆さーん、ハンザイコウイですよーッ!」
街中に響き渡るような金切り声を張り上げる。
「な・・・」
呆気に取られて立ちすくむハジメに向かって、その少女は腕をブンブン振り回しながら駆け寄り、
「悪いヤツは退治しちゃうよ!喰らえーッ!」
奇声と共にラリアットを繰り出す!
「わわッ!」
とっさに少女の攻撃をスカしたものの、虚を突かれてすっかり戦意を喪失したハジメは、慌ててランクルに飛び乗ると、そのまま夕暮れの中へ走り去ってしまった。
「大丈夫ですか?」
ボンヤリとその場に突っ立ったままのゆかりに、少女は声をかけた。髪を大きなリボンでポニーテールに束ねていて、ひどく子供っぽい印象に見える女の子だ。
「何でもありません〜。ありがとうございます〜」
相変わらずのノンビリ声で答えながら、ゆかりは相手の顔を見てアラッという表情になる。
「まあ〜、あなたは早乙女優美さんではないですか〜」
「えっ?あっ、古式センパイ!」
優美と呼ばれた少女も、相手が誰なのかに気が付いて驚いた声を上げた。
二人は、ちょっとしたという程度ではあるが、互いを見知っていた。
ゆかりの所属するテニス部は、雨天でコートが使えないとき、体育館内で筋トレをする。
その際、いつもそこで練習をしているバスケ部と交流をする機会があり、その部員である優美とも知り合ったのだ。
優美の兄である早乙女好雄はゆかりと同級生だから、そんなことを話題に会話がはずんだのだった。
「一体何があったんですか、センパイ?さっきの男子に何をされたんです?」
「それがァ〜、私にも良く分からないのですが〜・・・」
正味良く分かっていないなりに、ゆかりが一通りのいきさつを説明すると、
「ううん、これは事件ですね!インボーですよセンパイ!」
やたら興奮し始めながら、早乙女優美は叫ぶように言った。
「よぉし、優美に任せてください!優美がセンパイを守ってあげます!」
「ええ〜、どういうことですかァ〜?」
事件とか陰謀とか、突拍子もない方へ話が転がり、ゆかりは目をパチクリさせて言った。
「分からないんですか?センパイは狙われているんですよ!あの男子は、きっとセンパイを自分のお嫁さんにしようとしてるんです!それでセンパイをユーカイしようとしてるんですよ!」
口角泡を飛ばして優美はまくし立てる。
言っていることは意味的に合っていなくもないのだが、しかしどうにもズレて馬鹿馬鹿しく聞こえるのは、優美のキャラクター故であろう。
何しろこの少女、性格的に静と動の違いこそあれ、ゆかりに勝るとも劣らない、超天然ボケボケ娘なのである。
「『お嫁さん』ですかァ〜?それは困りますゥ〜」
ホントに困ってるのかそうでないのか少しも分からない口調で、ゆかりは言った。
「私にはもう、心に決めた殿方がいるのです〜。その方以外の人とは結婚は出来ません〜(作者注・それは『イカくさい』という名前のプレーヤー=オレ様のことだぜ)」
「ヘェ〜、そうだったんですか!それじゃ婚約者じゃないですか!それってどんな人ですか?」
優美は一瞬、ミーハー根性丸出しの下卑た顔付きになったが、すぐに慌ててかぶりを振り、
「ってそうじゃなくて、センパイがヘンな人に無理やりお嫁さんにされないよう、優美が守るんですよ!守ってみせますよ!」
「はァ〜、そうですかァ・・・」
「そのためには、さっきの男子の正体を突き止めて、詳しく調査をしないとイケマセンね。・・・これはアレですよ、探偵ですよ!少年探偵団ですよ!」
先日読んだばかりのジュヴナイル小説を思い出し、優美は叫んだ。
「少年探偵団〜?」
「お兄ちゃんが小学生の時に読んでいた小説のタイトルなの。こないだ貸してもらって読んだんだ。少年探偵団はアケチ探偵を助けて悪人をやっつけるの!すごくカッコイイんだよ〜!」
「はあ・・・」
「優美も今日から少年探偵団になってセンパイを守るよッ!あ、優美は少女だから、少女探偵団だねッ!」
すっかり興奮して、優美は辺りを跳ね回る。
「お一人なのに、『探偵団』というのはおかしくないですかァ〜?」
肝心なことはボケボケのクセに、どうでも良いことには鋭いツッコミを見せて、ゆかりが言った。
「うーん、そうかな?・・・」
優美はちょっと考え込んでから、
「あー、それなら古式センパイも少女探偵になればイイんですよ!優美と二人で少女探偵団ですよ!」
「わ、私も探偵さんですかァ〜・・・」
ゆかりの頭はやたらと混乱し始めた。
・・・何かが根本的に間違っている気がする。
相手の正体を突き止めるも何も、ゆかりは金巻ハジメの素性を知っているのだから、調査をする必要などは全くないのだ。
そもそも、話の流れからして、自分は守ってもらう立場のはずなのに、いつの間にか守るべき立場の『探偵』ということになってしまっている。一体何がどうなっているのだろう?
しかし目の前でハシャぎ回る優美を見ていると、彼女の提案に素直に乗ってあげるのが吉という気もしてくる。
何より、他人のことでこれほど一生懸命になってくれている後輩にすげなくすることは、底なしにお人好しのゆかりにとって本意ではなかった。
「少女探偵団、本日結成ですよ、センパイっ!」
「はァ、そうですね・・・」
「優美たちは探偵団っ!正義だよ!カッコイイよ!ウォーウォー!」
おかしなかけ声と共に拳を突き上げる優美を見て、ゆかりも思わず雰囲気に飲まれ、自らもノロノロと手を差し上げる。
「わ、私たちは探偵さんなのです〜。うお〜」
フニャけたゆかりボイスが、夕暮れの路上をゆったりと伝っていく。
きらめき高校の少年探偵団、もとい少女探偵団、ていうか「天然探偵団」がいきなり結成された、トホホな瞬間であった・・・
ⓤ進む
ⓤ書庫別館のトップへ
|