|
第七章 ある同人漫画家の休日
今日は文化の日。言うまでもなく祭日だ。
つい先日のこみパで色々とインスパイアされた俺は、朝から部屋にこもってネームを描きまくっていた。次から次へと描きたいシーンが浮かんでくる。俺は創作意欲(劣情でもあるが)の赴くままに、ノートにシャーペンを走らせた。前回は南さんに羞恥責めを加える目的もあって、ストーリーやギミックに工夫できなかった分、未使用のアイディアも溜まってきている。
時々手を休めて、こみパで仕入れた同人誌をぱらぱらめくる。
――みんな頑張ってるなあ。俺もやらねば。
気持ちを新たにしてネームに戻る。
そんなことを何回か繰り返し、俺は1冊のコピー誌を手に取った。
「あの娘の本か……」
艶やかな黒髪の美少女の顔が鮮明に思い出される。
「黒い……」
ページをめくると、異常な量の描き込みで黒くツブれた紙面に苦笑してしまう。
そのまま、ついつい読み耽った。――うーむ、やはり抜群の物語性を秘めてるな……。持ち味が独特すぎるのがナンでアレだが。
最後まで目を通すと、小さく手書きの奥付が書いてあるのに気付いた。会場では見落としていたようだ。
誌名、サークル名、発行日が入っているのは当然だが……。
これはどうかと思う。
著者/長谷部彩
住所/新宿区代々森1−××−××
電話/03−××××−××××
俺は思わずガラステーブルに突っ伏した。……個人情報ダダ漏れじゃん。注意してやれよ誰か。千堂とか、南さんとか。
まあしかし、おかげでようやくあの娘の名前がわかった。
長谷部彩、か……。
――他の情報も期せずして判明してしまったが。どうやらかなり近所に住んでいるようだ。考えてみればバイト先が代々森駅前なんだから、住んでるのもこの近所なのは充分考えられる状況ではあった。
「ま――次に会ったら注意しておこう」
俺はシャーペンを手に取り、ネームに戻った。
「よく晴れてるな……」
ちょっとアイディアに詰まったので、気分転換に外に出てみた。近くの大きな公園に足を向ける。
ぽん、ぽん――と乾いた花火の音が聞こえた。音楽や放送の声なんかも耳に入ってくる。公園の向こうの私立大学からのようだ。たぶん学園祭だろう。文化の日だもんな。
俺はネームのノートを手に、11月とは思えない陽光を浴びつつ公園内をのんびり散策した。俺と同じように散歩する人やベンチで日光浴をする人もちらほら見られる。
あてどなくふらふら歩いていると――なんだか見慣れない一角に迷い込んだ。
「……静かだな。この公園にこんなとこあったんだ」
常緑樹に隔てられ、周りからは視認しづらい上、歩道も植え込みを縫うようにあってわかりにくい。
「へえ。こりゃ、ちょっとした穴場……」
呟きを飲み込む。
壁のように植えられた低木を背にしたベンチに、彼女はひっそりと座っていた。
スケッチブックを手に、無言で手を動かしている。
噂をすれば影が差すと言うが……。
それはまぎれもなく、さきほど名を知ったばかりの、画材屋で出会った少女だった。
「やあ。こんにちは」
声をかけると、彼女は静かに顔を上げる。
「――あ…。四堂さん…。…こんにちは」
相変わらずひと目で見分けてくれた。
「今日はバイトじゃないのかな?」
こくり、と頷く。
「週の半分の……シフトですから…。それも、今月いっぱいですけど…」
「え、あの仕事辞めちゃうの?」
こくり。
「あんなに画材に詳しいのに…。向こうに引き止められなかった?」
「受験が終わったら、またおいで、と…」
「――ああ、来年から受験勉強なんだ」
「…いえ…。来月から……」
「…………」
「…………」
「……ん?」
何となく違和感を覚えて首を傾げる。
……一応確認してみよう。
「あの…来年から3年生で、再来年受験なんだよね?」
ふるふる。
「今、3年……です……」
「ふーん、そうか。――――って、来年受験かよ!?」
こくり。
うあ。そりゃまた、えらく危機感の薄い話のような……。俺なんか去年の今頃は、予備校に通って追い込みに忙しかったような記憶があるが。それとも彼女、実はめちゃめちゃ成績よくて、それほど勉強しなくても楽勝だとか?
あ。あるいは、さっきの画材屋の話、「受験に失敗したら、今度は正社員として就職においで」とか言う意味だったり……。
「……勉強、来月からで間に合うの?」
余計なお世話だとわかってはいるが、つい聞いてしまう。
彼女は首をかしげ、ぽつりと答えた。
「……さあ…」
――おいおい。自分のことだろ……。
「それじゃ今は、バイトとマンガと勉強を全部並立させてるの!?」
こくり。
改めて聞き直すと「今も勉強はしてます」と言うことだった。バイトは学費の足しとこみパの参加費&本のコピー代稼ぎに続けているらしい。――つまり、ぎりぎりまで同人活動を続けるつもりのようだ。
……なかなか、いい根性してんな……。
「さっきは、スケッチしてたんだ?」
「ネームに…詰まったので……。気分転換に…」
「へえ。俺と同じだね」
ふ、と顔を上げ、まっすぐ見上げてくる。
「四堂…さんも……?」
「うん。で、散歩してたらここに迷い込んでさ。ちょっとした穴場だよね、ここ。キミの秘密の場所かな?」
こくり。
「お休みの日は……時々、ここに来ます…」
「そうなんだ。えーと……長谷部彩さん、でいいのかな?」
少し首を傾げる。
「…名前……どうして…?」
「本の奥付に書いてあった」
「――あ。…はい…」
こくり。
「彩ちゃん……で、いいかな? 馴れ馴れしすぎる?」
「……いえ」
彼女の口の端に、微かな笑みが浮かんだ。わずかな変化だが、茫洋とした表情に突然多彩な情感があふれたように感じる。一瞬見惚れてしまった。
「…じゃあ、彩ちゃんって呼ぶね。俺も名前で呼んでいいから」
「はい。――和巳さん……。…ふふ」
今度ははっきり微笑む。くすぐったそうな笑みが気になって聞いてみる。
「? どうしたの?」
「……和樹さんと……同じ、呼び方です……」
「………」
微妙に面白くないが……彼女が嬉しそうだから、まあ、よしとしておこう。
――あ、そうだ、思い出した。
「そうだ、彩ちゃん。奥付のことなんだけど」
「…?」
わずかに首を傾げる。
「本名を載せるのはやめた方がいいよ。電話番号も書かない方がいい。できれば住所もやめにして、メールアドレスかなんか載せておけばいいと思う」
「――? どうして…ですか…?」
本気で不思議そうだ。
「彩ちゃん、すっごく可愛いからさ。こみパのブースで目をつけて、よからぬことを考える奴とか、いたりするかもしれないじゃない?」
だから著者名はペンネームを使って、どうしても住所を載せる場合は『長谷部方』として名前までは入れないこと。とやや強めに言い聞かせると、彩ちゃんはわずかに目を見開き、びっくりしたような顔(多分)をしていた。そんな可能性を考えたことはなかったのだろう。でも、世の中善人ばかりではない。…無論、俺も含めて。その辺をきっちり理解させとかないと、いつか火傷しそうで危なっかしい。
「わかった?」
「…………あの。…可愛いって……私が……?」
――そこかよ。
「うん。初めて会ったときも、あんまり美少女だったから見惚れちゃったしね」
ぱっと見、えらく地味だけど。彼女のマンガと同じだな、その辺。
「そ――そんなこと、言われたの……初めてです……」
彩ちゃんは真っ赤になって俯いてしまった。スケッチブックを膝に置き、両手で赤い頬を押さえて恥じらう。
なんつーか……恥ずかしがってるときの微妙な仕草がめちゃめちゃ可愛い。
黙りこんでしまった彩ちゃんと俺との間の静寂に、少し遠い花火の音が響いた。
よく考えたら俺もかなり恥ずかしいことを言った気がする。俺は気まずい空気を振り払うように声を上げた。
「そ、そうだ――彩ちゃん、よかったら気分転換ついでに、一緒に行ってみる?」
「――?」
ぎこちなく顔を上げた少女に、音の聞こえる方を指差して微笑む。
「そこの大学祭」
少し考え込んで……彩ちゃんは、こくりと頷いた。
かなりフランクな学園祭らしく、部外者大歓迎、老若男女おいでませ、と正門に幟(のぼり)が立っている。入り口で入場者に無料配布しているパンフレットを受け取り、俺と彩ちゃんは一緒にあちこち見て回った。辺りには縁日の出店のような模擬店が軒を連ね、パンフレットを見ると、他にも真面目・不真面目取り揃えた各種展示、イベントや公開実験、上映会や上演会が目白押しで、果ては目玉企画だとかでアイドル声優のコンサートまであった。
彩ちゃんはかなり少食らしく、食べ物の屋台では一人前買って少し彩ちゃんが食べ、残りを俺が食べるパターンになった。他の出店では――意外にも彼女、金魚すくいと射的がめっぽう上手かった。
褒めると彼女は頬を染め、「小さい頃お父さんにコツを教わった」と答えた。その時の顔が何となく寂しそうだったのでつい小さい子にするように髪を撫でると、別に嫌がるでもなく薄く微笑んでくれた。
せっかくいっぱい掬った金魚を彩ちゃんは「飼えないので」と店番の学生に返し、彼はそれじゃあ代わりにと、色々と学内割引チケットをくれた。おかげで、もともと安い模擬店をより安く楽しめた。まあ、可愛い女の子と肩を並べて歩くだけでも、充分楽しくはあったのだが。
「はい、彩ちゃん」
「…あ、はい……」
差し出した紙コップを受け取る少女。中身は、少し先の野外カフェで買って来たミルクティーだ。
喧騒と人混みに疲れ、俺達は中庭の一角に来ていた。この辺は出展エリアから外れているようで人が少なく、休憩するにはちょうどよかった。
芝生にハンカチを敷いてちょこんと座った彼女の隣に、直接腰を下ろす。11月とは言え、風が弱く陽気がいいため、ひなたの芝生はぽかぽかと暖かい。日向ぼっこには最適のロケーションだ。
しばし無言で休んだ。無理に言葉を交わさなくても、別段退屈じゃなかった。横目で確かめると、表情の変化が乏しく気分の読みにくい彩ちゃんではあったが、何となく楽しそうに見える。
何かくすぐったい気分だが……こう言うのも悪くない。
俺と彩ちゃんは、しばらく静かな時間を共有した。
さざめきのように遠く流れる喧騒。時折上がる景気のいい花火の音。何処かで演奏するバンドのリズムが微かに響く。少し離れた講堂からは、男達の歓声がここまで聞こえてくる。
俺は我知らず微笑み、冷めかけたミルクティーを口に含んだ。
と――講堂から聞こえる歓声が変化した。
「――? 怒号……? 確か、アイドルか何かのコンサートだよな、あそこは…」
ノートに挟んでいたパンフレットを開いて確認する。
よっぽど盛り上がってるのか? ――何かそんな感じの声じゃない気もするが……。
首を傾げていると、そっちの方から走ってくる人影が見えた。ひらひらで派手な色合いのドレス姿の女の子だ。何かのコスプレ? と一瞬思ったが……もしかしてアレは、ステージ衣装、とかじゃないのか…?
まさか……コンサート中のアイドルが、逃げた!?
――いや、まさかな。いくら何でもそんな…。
とか思っているうちに、講堂の方からもう一つの人影が走ってくるのが見えた。今度は男だ。ちょっと垢抜けた感じの青年。ここの学生かな?
派手な服装の少女はぱたぱたと走って、中庭の木立の一本に顔を埋めるようにしがみついた。講堂からは影になる位置だが……ここからは丸見えだったりする。青年はきょろきょろ辺りを見回しながら走り――ほどなく少女を見つけ出した。
何やら言い争いを始める。ここからは15メートルくらい離れているので、声は聞こえるものの、何を話しているかまではわからない。ところであの二人、何か妙に見覚えがある気がするのだが……。
どこで見たんだろう…?
首をひねって考えていると、隣でじっと同じ二人を注視していた彩ちゃんが答えを出してくれた。
「――和樹…さん……」
「――――え」
慌てて目を凝らした。
するとあれが、千堂和樹か!?
言われてみれば――鏡の向こうによく見る顔だった。
――ホントに似てやがる……。
じっと観察を続けていると、別のことにも気付いてしまった。
千堂が少女の肩を抱き、髪を撫で、何やら硬軟織り交ぜて説得する様子はやたらと親しげだ。と言うか、傍から見ても少女への気遣いと情感に溢れている。少女の方も千堂をよほど信頼しているのか、何だかショックを受けていた様子だったのが、千堂になだめられ、説得されて、急速に落ち着きを取り戻していく。
よくよく見れば凄い美少女だった。ちょっと内気そうではあるが、それが可憐な魅力をいっそう引き立てている。
泣きじゃくっていた少女はいつかぎこちない笑みを浮かべ、頬を朱に染めると、ぱっと千堂の胸に飛び込んだ。千堂も優しく抱き返し、何やら囁きかけている。少女はこくこくと頷き返す。
そっと少女を押し返し、まっすぐ目を見て何か言い聞かせる千堂。大きく頷いた少女に千堂は満面の笑みで返し、手を握って走り出した。
固く手を繋いで講堂に駆け戻っていく二人を、俺はただ見送るだけだった。
――どう見ても恋人同士だよな。
可愛い彼女がいるなあ、千堂。別に今さら、うらやましくはないが。
…………。
――はっ!?
慌てて彩ちゃんの様子を窺うと、彼女は千堂達の行方を見送ったまま固まっていた。
た、確か彩ちゃん、千堂に惚れてたよな?
あの光景はかなりショックだったのでは……。
「あ、あの――彩ちゃん……?」
おそるおそる呼びかけると、彼女は三拍くらい間を置いてから、錆びた機械のようにぎこちない動きでこちらに顔を向けた。
――表情がないのが怖い。
そのまま数秒見詰め合ってから、彩ちゃんはのろのろと口を開いた。
「――――帰り…………ます…………」
ふらふら立ち上がり、よろよろ歩き出す彩ちゃん。
…うわ。やっぱめちゃめちゃショック受けてる。
「ちょ、ちょっと待って。――送ってくよ」
とりあえず公園に戻ってきた。
彩ちゃんの足取りは幽霊のように頼りない。敷いていたハンカチとか、スケッチブックとか忘れそうになってたし、危なっかしくて仕方がなかった。
最初のベンチに腰を下ろし、蒼茫と放心する彩ちゃん。
「――彩ちゃん、大丈夫?」
ゆーっくりと俺を見上げてくる。
「――――綺麗な…人…でした……。…とっても……仲、よさそうで……」
……どっちも否定できない。彩ちゃんもあの娘に負けないくらいの美少女ではあるのだが……とにかく地味だし。
あの二人、好き合ってそうなのは間違いなさそうだし……。
彩ちゃんが参戦したとして、勝ち目は……うーん、どうだろう……?
あの娘の情報が何もないことに改めて気付いた。これでは判断のしようがない。が――あの親しげな様子から見て、現状でかなり近しい間柄なのは確かだろう。
「ま――まあ、もしかしたら従妹とか、幼馴染みとかかもしれないし…」
俺から見てもあれは血族の親密さではなかったが、半ば気休めで言ってみる。案の定説得力を感じなかったのか、彩ちゃんはふるふると首を振った。
「――いいんです…。例え、あの人が…そうでなかったとしても…和樹さんには、きっと…ああ言う、元気な人の方が…似合って、ますから……」
相変わらず千堂のことになるとよく喋るが……発言内容はめちゃめちゃ後ろ向きだった。しかし彩ちゃん、自分に元気が不足しているのをきっちり自覚して、しかもそれを気に病んでいたらしい。見たところあの娘もそれほど「元気!」と言うタイプではなかったようだが、彩ちゃんと比較してしまうと、かなり活発に思えてくるから不思議だ。――多分、あの娘に限ったことじゃないが。
「それに…和樹さん、とってもマンガ、お上手で……すごくいっぱい、売れてるのに……私は、全然……」
本が売れないのも気にしていたらしい。
「…和巳さんに…色々、教わって……私も、上手になれたら、いいなって……思って……で、でも、もう…………」
後半は嗚咽になった。ベンチに腰掛けた体が小刻みに震えている。伏せた顔から、膝の上にぽつぽつと水滴が落ちた。かちかちと小さな音が聞こえる。歯が鳴っているようだ。
え、えーと……どうしよう?
泣いてる女の子のなだめ方なんてわかんないよ、俺。こ、これも千堂のせいだ。おのれ千堂!
とか八つ当たりしてる場合じゃなくて。
と、とにかく何か言わんと。
「その…さ。そんな、部数がどうとか、気にすることはないんじゃないかな。本が売れなきゃ、人を好きになる資格はないって言うの? 違うだろ?」
ふ、と顔を上げる彩ちゃん。
……一瞬見惚れた。
ぽろぽろと透明な涙をこぼす泣き顔は、普段の無表情を崩し、雄弁に哀しみを主張している。べしゃべしゃに崩れるような泣き顔じゃない。それはいっそ、鮮やかで――美しい。
どくん、と胸が高鳴った。
この娘……泣き顔が、一番可愛い……。
何だかかなり危険な衝動が溢れてくるのを慌てて抑え、俺は真面目な顔を保った。
「それに、その…千堂を好きになったことで、マンガに対する向上心が生まれたって言うなら、それはそれでいいことじゃないか。別に、千堂のためにマンガを描いているわけじゃないだろう?」
「あ……」
俺がそう言った途端、彩ちゃんは愕然とした顔で口を押さえた。
「……?」
いっそう顔色が悪くなったような……。俺、何か悪いこと言ったか?
「…………わ……私………わた、し……そんな……そんな、ことも……忘れ、て………」
「ちょ、ちょっと、彩ちゃん!?」
がくがく震え出した彩ちゃんの肩を慌てて押さえた。顔色は真っ青だ。
「あ……ああ……あああああっ! ――――うわぁああああああーーーーっ!!」
「え、え――!?」
普段の彼女からは想像もできない姿。彩ちゃんは、大声で泣きじゃくり始めてしまったのだ。
――俺の胸に顔を埋めて。
「え、えーっと……この場合、俺は、どうすれば……?」
途方に暮れつつ、何とかなだめようと、小さな子にするように背中を抱いて頭をそっと撫でた。――これは……泣きやむまでしばらく待つしかないか……?
俺の対応はそれほど間違ってはいなかったようだ。
しばらく泣いて少し落ち着いた彩ちゃんは、まだちょっとぐずりつつ、俺の胸から顔を上げないまま、ぽつりぽつりと心情を吐露し始めた。
要約すると……彼女がマンガを描き始めたのは、小さい頃に亡くなった父の影響らしい。
病気で入院した父に何度か絵を描いて見せに行き、褒められたのがきっかけだとか。父親はその病気から回復することなく世を去ったが、彩ちゃんの心に、絵を通して人に何かを伝えられるようになりたいと言う強い想いを残していったようだ。彼女のマンガに満ちる物語性、その正体がこれだった。切実なまでに「伝えたい」とする強烈な想い…。それが彩ちゃんのマンガの原点であり、かつ最大の魅力だった。
だが、千堂と知り合い、彼を慕うようになって、彩ちゃんはその歓心を得たいと考えるようになっていった。千堂との差を思い悩んで、彼に相応しい自分になりたいと願うあまりに、読んでくれた人にマンガを通じてメッセージを伝えることよりも、ただ販売部数のみを気に病む彼女。そこには、最初に抱いていたはずの想いを失くし、メッセージを伝える対象である読者の姿を見失って、空虚な空回りを続ける自分があるばかりだった。
――何のためにマンガを描いていたのか。
俺の言葉でそれを思い出した彼女は、自分で自分の純粋な願いを穢してしまっていたことに気付いて、さきほどの慟哭へと至った、と言うことのようだった。
何と言うか……本当に純粋、と言うか純真だよな、この娘……。
俺みたく薄汚れた人間にとっては、いささか眩しすぎるんですけど。
彩ちゃんの述懐を聞いた俺は、少し考えをまとめてから、なるべくゆっくり穏やかに話し始めた。
「――別に、いいんじゃないか?」
え、と俺を見上げる、驚くほど儚く透き通った泣き顔に寸時眼を奪われる。
「最初の想いを大切にしたいって、彩ちゃんの気持ちは大事だと俺も思う。それを忘れてしまっていた自分を責める気になるのもわかるよ」
ぴくっと震えて目を伏せる彩ちゃんの艶やかな髪をそっと撫でた。
「でも。それと、彩ちゃんの千堂への気持ちってのはまた別の話だ。誰かを好きになるのって、凄くエネルギーの要る行為だと思うよ、俺。それだけで目一杯になってしまって、他のことが少々おろそかになっちゃっても仕方ないくらい。彩ちゃんが一時、そっちを優先しちゃっても、それはそれでいいと思う」
「…………」
明らかに納得していない目つきで静かに見上げてくる彩ちゃん。よっぽど、千堂のそばにいて恥ずかしくないようになりたくて、部数ばかり気にしていた自分が許せないらしい。しかも、同人誌さえ売れれば千堂に相応しい自分になれると言うのも勝手な思い込みであることに半ば気付いているように思える。それがまたいっそうの自己批判――と言うよりもはや自己否定――へと繋がっているのだろう。
ワリと自分でも思いつくままに喋っているので、どう話を進めたもんだか不明瞭なまま、それでも黙っていることはできずに俺は言葉を続けた。何故だか、自責の念で潰れそうな彼女をこのまま放っておくことだけはしたくない。
「今日、俺と話してて、何度か千堂のこと思い出してたろ、彩ちゃん」
ちょっと躊躇ってから、こくり、と頷く。
「彩ちゃん、自分で気付いてた? そう言う時の彩ちゃんってさ、すっごくいい顔で笑ってるの」
「………え…?」
わずかに目を瞠って、頬に手を当てる彩ちゃん。
「目元がふっと緩んでさ。唇がすごく自然にカーブして、ほんのり頬が桜色になって。微妙な表情の変化なんだけど、輝くような笑顔ってこう言うんだなって思った」
「……な――何、を……」
俺の褒め言葉がよほど意外だったのか、泣くのも忘れて慌てている。
「彩ちゃんはさ……千堂を好きになったこと、間違いだったと思うかい? つらいこと、嫌なことばっかりで、楽しいことも嬉しいこともなかった?」
「…そ、そんな……こと……」
慌てて首を振る。
「――違うよね。胸がどきどきして、会えるだけで嬉しくて、生まれ変わったような、それとも世界が輝きを増したような……不思議で素敵な気分になれた。そうじゃないかな?」
うう、考えがまとまらない。口が勝手に喋ってるような。自分が何を言っているのか頭に入ってこない。でも何か言わなきゃ、と言う思いに急き立てられ、俺はどんどん語を継いでいった。
「それが、気分だけじゃなくて、彩ちゃん自身も素敵にしてくれていたんだと俺は思うよ。恋は必ず叶うものじゃないけど、誰かを好きになるってことは、それだけでもとても貴重な経験なんじゃないかな。――彩ちゃん、マンガをおざなりにしていたことに気付いて自分を責めていたみたいだけどさ……例えば、千堂と両想いになるためにマンガをやめなきゃならないってことになったら、マンガをやめられるかい?」
泣き出してしまうほど真摯で純粋な気持ちを漫画に向けている彼女が、それを捨てられるわけがない。案の定、しばらく逡巡した後、彩ちゃんは小さく首を左右に振った。
「だったら、いいじゃないか。ちょっとぐらい遠回りになったっていい。何ならしばらくマンガなんか忘れてしまっていたって構わない。マンガ以外にも色んなことを体験して、色々なことを考えて、知らなかったことをたくさん覚えていけばいい。そうやって少しずつ成長していけば、マンガで伝えたいこと、伝えられること、段々増えていくはずじゃないかな」
微妙でわかりにくいが、ぽかんとした顔になる彩ちゃん。今まで思いもしていなかったようなことを言われて、虚を突かれたらしい。いつの間にかすっかり泣きやんで、俺の言葉にじっと耳を傾けている。
う。思いつきで喋ってるんで、そう真剣に聞き入られると困ってしまうのだが……。
「俺は千堂と会う前の彩ちゃんを知らないけど、今の彩ちゃんはすごく魅力的で輝いて見える」
これは本音だ。一見地味でとっつきにくい彩ちゃんだが、彼女を知れば知るほどどんどん味と深みが増していくように思われた。――スルメみたいなムスメだ。
「千堂を好きになったことがきっと、彩ちゃんにとってプラスになっている証拠だと思うよ。苦しいこと、楽しいこと、無駄になるものは何もなくて、全部が彩ちゃんの糧になっている、と――俺はそう信じるよ。……実際、動機はともかく、千堂に追いつきたいと思ってマンガが上手くなりたいって意欲を持ったわけなんだから、それだけでも彩ちゃんの気持ちが無駄にはなってないってわかるだろ? いくら何か『伝えたい』って思っても、人に見てもらえない現状では結局何も『伝えられていない』わけだし。これから上手くなっていけば、たくさんの人に彩ちゃんの思いを伝えられるようになるはずだよ」
「……私の、マンガ……本当に……見てもらえるように…なる、でしょうか……」
「ああ。俺が保証するよ。――千堂ほど売れてもいない俺の保証じゃ、今イチ信じられないかもしれないけど……」
俺の胸に額をつけて、ふるふる、と首を振る彩ちゃん。癖のない漆黒の髪を梳くように撫でた。めちゃめちゃ手触りいいなあ。千沙も南さんも郁美も、髪質では誰一人彩ちゃんには敵わない。
――ふう。しかし、だいぶ落ち着いてくれたようだ。必死に説き聞かせた甲斐があった。
よかったよかった。
しかし俺、夢中で色々喋ったけど、どんなこと言ったっけ。
えーと……。
…………。
改めて思い返してみると――もしかして、何だか死ぬほど恥ずかしいセリフ言ってた? 俺。
うわ〜、歯が浮きそう……。我ながら、どの面下げてあんなこと言ってたんだか、もう。
頬が熱くなってるのがわかる。暴れ出しそうに恥ずいが、この体勢ではそうもいかない。
う、うう〜む…。
内心悶えまくる自分の気をそらすように、俺は腕の中の彩ちゃんに話しかけた。
「そ、それにさ、彩ちゃん。千堂のことも、ただ諦めることはないんじゃないかな。相応しいとか相応しくないとか、そんなの千堂に言われたわけじゃないだろ。思い切って気持ちをぶつければ、もしかしたら応えてくれるかも知れないし……最初から諦めるくらいなら、ダメで元々、結果は同じなんだからトライしてみる価値はあると思うよ」
「和巳…さん……」
「もしダメだったら、気晴らしのデートくらいなら、また付き合うからさ。――ははっ、なーんて、それじゃ俺だけ美味しい思いしてるかな?」
「え。……『また』……?」
ふっ、と驚いたように顔を上げる彩ちゃん。
「……? 何、どうしたの?」
「…………。あの……今日の、コレ…って……。デ、デート……だったん…です、か……?」
「…………」
血縁でもない、年頃の男女二人で遊びに行けば立派にデートだと思うが。
「――楽しくなかった?」
「い――いえ――きょ…きょきょ、今日は……ちょっと、ショックでした…けど……楽しくて……嬉しかった、です……」
かーっと真っ赤になって俯き、上目遣いにおずおずと俺を見上げてくる彩ちゃんの仕草はめっぽう可愛かった。
「…あ」
ようやく自分が俺にしがみつき続けていることに気付いたのか、彩ちゃんはますます赤くなって慌て始める。
「ご、ごめんなさい、私……」
「あ、ごめん……嫌だった?」
俺もずっと彼女の背と髪を撫でていたことに気付き、だが急に放すのも惜しくて、最後にあやすようにぽんぽんと背中と頭を叩いた。
彩ちゃんは恥じらうのを中断して、何だか不思議な眼差しでぽーっと俺を見上げてきた。
至近距離で見つめ合う危険な数瞬が流れる。
――ここでキスしたりしたら……今までの説得、全部ムダになるんだろうなぁ……。
一瞬、それでもいいかなー、とか考える阿呆な自分を振り払って、俺は妙な雰囲気の彩ちゃんにそっと声をかけた。
「……どうしたの? 彩ちゃん」
はっ、と我に返る彩ちゃん。
「あ、あ。べ、別に、何も…そ、そんなに、嫌じゃ、なかった、ですし…」
珍しくかなり焦った様子を見せる。恥じらいを再開し、真っ赤になって一歩離れる。
「和巳、さん……。和巳さんって……」
「ん、何?」
「…………。いえ……何でも…ないです…。今日は…いっぱい、ご迷惑を…おかけしてしまって…ごめんなさい。それから…ありがとう、ございます…。また…色々…ご相談しても……いいですか……?」
「え、ああ。俺でよければ」
そう答えると、彩ちゃんは口元に淡く、けれどびっくりするほど魅力的な微笑みを浮かべて見せた。それは、そう――千堂のことを嬉しそうに話していたときのような――。
「さ、上がって上がって」
「…お邪魔します」
土曜日、日暮れ時。空は曇りで、そのため暗くなるのが早く、気温も低い。夜半には雨だとか天気予報で言っていたっけ。
俺は訪ねて来た南さんを部屋へ上げ、ガラステーブルの前のクッションに座らせた。無論俺が呼んだのだ。この間の、返事を聞くために。
南さんはだいぶ表情が硬い。心を明け渡すか、こみパで嬲られ続けるか――。俺が押し付けたのは、彼女にとっては一種究極の選択と言えるものだったろう。深刻になるのも無理はない。
「ちょっと待ってね」
言い置いて流し下から出したミルクパンをコンロに置き、パックの牛乳を注いで火にかけた。その間に、食器棚から出したカップに市販の粉を目分量で入れる。温まった牛乳をカップに注ぎながら、菜箸で掻き回して粉を溶かす。最後に市販のホイップクリームをてっぺんに搾り出して完成。
例によって市販品を組み合わせただけだが、ぱっと見は本格派風に見えなくもないミルクココアをティースプーンと一緒に南さんの前に置いた。
「どうぞ。外、寒かったでしょ。あったまるよ」
屈託のない笑顔で勧める。
「あ、はい……」
戸惑ったように見上げてくる南さん。だが、俺にしてみれば彼女に突きつけたそれは究極の選択でも何でもなく、どっちに転ぼうが大差はない。気楽にもなろうというものだ。
俺も自分の分のカップを手に、ガラステーブルを挟んで腰を下ろした。黙ってココアを啜ると、南さんも俺に倣ってカップに口をつける。
しばし沈黙が流れた。会話はないが穏やかな時間――と思っていたのは俺だけで、彼女にはもしかしたら針のムシロだったかもしれない。居心地悪そうに視線をあちこちに泳がせている様子を見ると。
一息ついてもらってからと思ってたが……。
「さて」
「は、はい」
案の定過敏に反応する南さん。相当緊張している。これはとっとと本題に入った方がいいな。
「一週間考えて、決心はついた? 南さん」
「…………」
ズバリ切り込むと、彼女は脅えとも迷いともつかない不思議な眼差しを向けてきた。
「――?」
迷ったような落ち着かない様子を見せる南さんが口を開くのをのんびり待つ。覚悟は決めてきたとは思うのだが、実際に選択を口にしてしまうことには躊躇いがあるのだろう。その辺りは寛大に対応してあげようと思う。
そう長く待つこともなく、重い沈黙は破られた。
「私……私、変なんです」
南さんが搾り出したのは、そんなセリフだった。
「あれからずっと、私……考えていました。御主人様が、おっしゃったこと…」
逡巡するように一旦言葉を切る。俺は黙って続きを待った。
「答え自体は――割と早い段階で、出ていたんです。こみパは、私の夢ですから……どんなものと引き換えにしても、奪われたくない、って」
ふむ。その辺りは、郁美を堕としたときと似たような理屈かな?
「……それで?」
「はい…。それで、ですから私、練習してみたんです。だって私、あんな風に無理矢理奪われて、それをビデオに撮られて、脅迫されて、その、奴隷に……されてしまって。正直、恨んでいましたから……御主人様が求めるような態度が取れるのかどうか、不安だったので…。でも、そうしたら……」
困ったように眉をハの字にして頬を薄く赤らめ、俯き加減で上目遣いになる南さん。
「その……寝る前とかにベッドで、意識して御主人様のことを考えるようにしてみたんです。御主人様に甘えて従順にしている自分を想像してみたりとか……。そうしてると、何だか興奮してきてしまって。で、何回も自分で――して、しまったりして……。そのうち、そう言う想像が……嫌じゃなくなっているのに…気付きました」
頬が赤みを増し、あちこちに視線を泳がせながら語を継ぐ。
「そうなると、自分でもわからなくなってしまって……。御主人様に服従するの、悔しいと思っていたはずなのに、何だかそれも、無理に意地を張っていただけのような気もしてきて」
そこで口を閉じ、俯いてしまう。かなり混乱しているようだが……狙った以上に上手く誘導できたのかな? もしかして。
黙って待つと、南さんはぱっと顔を上げ、レンズ越しの瞳を不安げに揺らした。
「何が本当なのか……わからない、わからないんです……! 私、私一体、どうなってしまったんでしょう…? 御主人様は、私に一体何をしたんですか…?」
「別に何もしていないさ。南さんに、俺以外の誰にもあげられない快楽を教えてあげただけだよ。南さんが、俺から離れられなくなるようにね」
「――――。そう……そうかもしれません。私もう、御主人様から、離れられない……。でも……でもどうして私、それが――それが嫌じゃないの……?」
苦しげに葛藤する南さん。ここで安易な回答を押し付けるのはワリと簡単そうだが……それでは少々つまらない。彼女自身の言葉を聞きたかった。
「それで――南さんは、どうしたいの……?」
ゆっくり切り出した中に何か感じるものがあったのか、南さんははっとして俺の目を見つめてくる。
「どうするかの答えはもう、出ているんでしょう?」
誘惑するかのようにそっと囁くと、南さんはおずおずと口を開いた。
「私……御主人様に従順な演技をしよう――御主人様が好きな振りを――そう思い込んで、そう言う態度を取ろうって――思ってました。でも、この一週間、そう出来るように練習していたら、わからなくなってしまって……もしかしたら……そう、もしかしたら……」
戸惑った様子で頬を濃い桜色に染める。
「もしかしたら、私――本当に、御主人様のこと、好きになってしまったのかも……しれない、って……」
恥ずかしさに耐えかねてか、肩を竦めてまた俯いてしまう南さん。
俺はテーブルを回り込んで、彼女の頬に掌を添えた。びくっと震える彼女の顔を上げさせ、潤みかけたその瞳を覗き込む。
「それで。南さんは、俺にどうして欲しいの…?」
さっきと似て非なる問い。南さんは震える唇をそっと開いた。
「もう私、自分で自分がわからない。だから……だから、御主人様が…決めてください。私に、御主人様を好きに――させてください」
「……どうすれば、いいのかな?」
よく似た三度目の問い掛け。
「お願い――お願いします。どうか今だけ……今夜だけ、普通に愛してください……!」
俺の胸にしがみつき、搾り出すように告げる。そう大きな声ではないが、彼女の言葉は深く胸に響いた。
何だろう、この状況、強い既視感があるような……?
……あ、彩ちゃんか。最近、何だか女の子が胸の内を吐露する場面にいることが多い。今回は半強制だけど。
「――わかったよ。それで、南さんの気が済むのなら……」
俺を見上げる瞳から、澄んだ雫が零れ落ちる。涙の理由は――俺には特定できなかった。
抱き上げた南さんを、そっとベッドに横たえる。が、彼女は俺の首に回した手を放さず、恥ずかしげに囁いた。
「あの、御主人様……名前で呼んでも……いいですか……?」
「ああ……いいよ」
「――和巳、さん……」
眼鏡の向こうの濡れた瞳を見つめながら、できる限り優しい手つきで髪を撫でる。
「あ……」
どこか切羽詰まっていたような表情が弛むのを見て取り、俺はそっと顔を近付けた。
「そうやって恥じらってる南さん、すごく可愛いよ」
「ああ……和巳さん、そんな……」
耳元で低く囁くと、いっそうの恥じらいと、わずかな陶酔の色が優しげな美貌に浮かぶ。
「南さん…」
髪を撫で続けながら名を呼び、さらに顔を寄せる。
「和巳さん…ああ…んっ……」
睫毛を震わせながら、彼女はそっと目を閉じた。
ゆっくりと唇を重ねる。触れ合うだけの、優しいキス。数秒間続けてから唇を離した。はあっと互いに熱い吐息を洩らす。
「南さん……もっと、キスしたい。――いい?」
「あ、ん……はい……もっと……もっと、キスして、ください、和巳さん…」
許しを得て俺は何度も唇を合わせていった。餅肌で元々化粧の薄い南さんはルージュを引いていないみたいだけど、唇はほのかに柑橘系の香りがして甘い。リップクリームの味だろうか。それとも南さん本来の? どちらでもかまわない。俺は彼女の唇の柔らかさを堪能するように、飽きることなくキスを繰り返した。キスを交わすたび、二人の吐息と共に情感までも混じり合っていくように感じる。
少なくとも、彼女の吐息も唇も次第に熱を帯び始めているのは錯覚ではない。
充分に気分が高まって来たところを見澄まして、直接耳に吹き込むように言葉を注いだ。
「南さんの、もっと綺麗な姿……見たいな……」
「あ……」
恥ずかしくて声を出すこともできないのか、彼女は小さく頷くだけで応えた。
今さら恥ずかしがる姿も可愛い。その恥じらいが、彼女にとって今回のこれがある意味純潔を捧げる儀式に等しいことを示していた。そう――心の純潔を捧げる儀式に。
今日の南さんの服装は、ごく薄いパープルのブラウスにパールホワイトのネクタイカラー、その上に織り目の粗いクリーム色のVネックセーター、下は膝上までのややタイトなグレーのスカート、その下に濃い目のストッキングと、この時期にしては薄着だった。来た時にはこの上から厚手のコートを着ていたが。
彼女のセーターを少しだけ捲り上げ、片手を中に忍ばせてブラウスのボタンを先に外していく。その間、もう片手で頬や髪を撫でたり、キスしたり耳に息を吹き込んだりして気を逸らせる。ブラのフロントホックも外し、柔らかな双丘をそっと手で覆った。
「ふっ……」
直接乳肌に触れられた南さんが艶っぽい吐息を洩らす。もっとそれを聞きたくなって、俺はセーターを脱がせないまま、しっとりと肌理細かな肌触りを堪能するように、乳房の曲面に沿って掌を滑らせた。
「ん、んっ……」
過敏になった表面をごく軽く撫で回された南さんの乳房に、ぞくぞくっと震えが走るのを感じる。キスと毛糸の摩擦で感じてしまったのか、両乳首が既にぴんと尖り立っているのがセーターの生地越しに見えていた。敢えてそこには触れず、ゆっくりと撫で続ける。
微妙な刺激に耐えかねた南さんが縋るような眼差しを俺に向けた。
「ああ……和巳さん、それ、切ないです……」
「どうして欲しい、南さん? 南さんのして欲しいようにしてあげるよ」
「あ、そんな…恥ずかしいです」
「恥ずかしいようなこと、して欲しいんだ?」
羞恥に視線を泳がせる南さん。まあ、今回はあまり苛めなくても……とか思っていたら。
「お…願い、もっと……もっと強くして……。乳首も、触ってぇ……!」
恥ずかしがりながらもはっきりと、えっちなおねだりをしてきた。……ホント可愛いなあ、今日の南さん。
「いいよ。今日は南さんのして欲しいこと、何でもしてあげる」
優しく囁きながら、リクエストにお答えして、乳房を覆った手に力を込める。手触りのいい乳肉に指が埋まっていく。どこまでも柔らかいその感触は、搗き立ての餅のようだった。
強すぎない程度の圧迫で握力を緩め、リズミカルに揉み立て始める。セーターの粗い編み目の間から上下左右に乳首が揺れるのが見える。手の位置を少し変えて、人差し指と親指で乳首を軽く摘んだ。そのまま少し弱めに揉んだり転がしたりしごいたりして愛撫する。これも強すぎず弱すぎないように。
「んっ……はぁっ……和巳さん…優しい……。ん、んんっ…」
多分今夜だけだけどね、こういうのは。
俺は南さんがもっとも望む強さとやり方になるよう気をつけながら乳揉みを続けた。――なかなか難しい。千沙が俺に口奉仕するときには実に自然にやってのけてるので、もっと簡単かと思ってたが。それでも細心の注意を払いつつ何とか続ける。そのうち南さんは切なげに小さく体を揺らし始めた。
「んっ…んっ……。は、あっ……ふぁあっ……」
甘い吐息が俺の耳を心地よくくすぐる。訴えるような潤んだ瞳に応えて、南さんの唇をそっと奪った。さっきまでよりも激しいキス。南さんは従順に俺の求めに応じ、唇を開いて互いの舌先をちょんちょんとつつき合った。彼女の舌の動きがためらいがちに強くなっていく。やがて俺達は貪るように舌を絡め、吸い合っていた。
この間もずっと乳房への愛撫は続けている。自然に力が入り、触れ始めたときよりだいぶ強く押し揉んでいたが、南さんが苦しがる様子はなかった。
「あっ、はっ、はぁあっ…。和巳、さぁん……」
ぞくっとするほど艶っぽい喘ぎ。そこに含まれる濃い欲情の色に、俺の興奮も否応なく煽られる。
「お願い……もう……」
はっきり口にはしないが、彼女の望みは言われなくてもわかる。今度は意地悪せず、髪を撫でて軽くくちづけた。
「いいよ。それじゃ、脱いでごらん。……それとも、俺が脱がしてあげた方がいい?」
「あ、あの…。自分で、脱ぎます。――和巳さん、後ろ、向いててもらえますか…?」
恥ずかしげに頬を染める南さん。……何で着替えを見られるのを恥ずかしがるのかよくわからないが、ご希望に沿うことにした。この間に俺も着ているものを脱ぎ捨てる。
振り向くと、生まれたままの姿になった南さんが、ベッドの上でぺたりと座り込んでいた。もじもじと身を揺するのは恥ずかしいためもあるのだろうが……。
「あ……」
肩に手を添えてそっと彼女の体を横たえると、愛撫で張り詰めた乳房が柔らかく揺れた。先端で赤く色付く乳首は円筒形に屹立し、大いに自己主張している。
俺は南さんの美しい裸体を隅々まで観賞した。全身どこに触れても柔らかいに違いないしっとりした肌は淡く桜色を帯び、桜を練り込んだ餅菓子を思わせる。静脈が透けて見えるほど白い、むっちりと肉感的な腿をひと撫でして、軽く力を加える。困ったように眉根を寄せつつ、それでも逆らわずに、南さんは押されるがままに脚を開いた。
露になった秘唇はぷっくり膨れて綻び、蜜に濡れて光っている。
――案の定、身を揺すっていたのは欲情を抑えきれずにいたためもあったようだった。
「恥ずかしい…です、和巳さん……。あんまり、見ないで……」
と言いながら、あふれる愛蜜の量が少し増したように見える。見られることで興奮を煽られているのは間違いないが、まあ指摘せずにおく。
「綺麗だよ、南さん。ほら、南さんを見てたら、もうこんなになっちゃったよ」
いきり立って脈動する肉棒の腹を、彼女の姫貝の肉襞に沿って滑らせる。
「ふ、はっ……。熱い……」
とか言っているが、とろとろの秘肉も負けずに熱気を帯びている。俺の頬にかかる吐息も熱っぽい。
「それじゃ……いくよ、南さん」
頬をついばむようにして囁くと、情感と情欲に蕩けた視線で俺を見つめつつ小さく頷く。
ちゅっと唇を軽く合わせてから、俺はおもむろに肉棒の先端を膣口に押し当て、ゆっくり腰を押し出した。
「はぁああ……っ」
濡れ咲いた秘花を貫いていくと、それに押し出されたように感極まった吐息を洩らす。やがて亀頭の先がこつんと膣奥に当たると、眼鏡の奥の瞳をうっとりと細めた。――いい表情するなあ、相変わらず。
「ふぅう…っ」
俺も溜めていた息を吐き出す。待ち兼ねていたように収めた陰茎を咀嚼する肉鞘の感触がめちゃめちゃ気持ちいい。突発的な射精衝動を抑えるだけで一苦労だ。
そう言えば、この一週間原稿描いてばっかで抜いてなかったなあ。息抜きはしたけど。あ、いや、考えてみると、こみパでも本番はなかったし、その前も原稿の追い込みでヤッてなかったような。かれこれ10日以上禁欲してたのか、俺?
言いなりになる奴隷が3人もいるのに、何でまた。俺って一体。
とか首をひねっているうちに、放出の欲求はやり過ごせた。
「はっ、はっ、はぁ……っ」
南さんの息も少し落ち着いて来ている。どうやら入れただけで軽く達してしまっていたらしい。
「もう、動いても大丈夫かな?」
俺はいかにも南さんが落ち着くのを待っていたとでも言わんばかりに、優しく囁いた。
「あっ……はい……」
はにかんだ笑みを見せるレンズ越しの眼はうっとり細められている。『大事に、優しく』扱われるのには、本格的に弱いみたいだ。
ゆっくりと腰を揺すり始める。くちゅっ、くちゅっと濡れた音が小さく鳴った。リズムをつけて、浅く浅く深く。時折南さんの弱いところを責めつつ。南さんの弱点はおおむね学習済みだ。いつもはとことんよがり泣かせて楽しんでいるが、それだと感じすぎてつらいはずなので、今は時々に留める。普段は、つらかろうが何だろうが俺が楽しめればいいので、気にせず責めまくっているのだが。
「あ、はっ……ふぁあっ……うぅんっ……」
抽送のリズムはちょうどよかったようで、南さんは気持ちよさそうに目を細めて喘いだ。焦らしすぎたり責めすぎたりしないよう注意しつつ、互いに快楽を高めていく。徐々に募る性感に、南さんも次第に恥じらいを薄れさせ、俺の突き込みに合わせて腰を捻ったり、腿が俺を迎えるように開いていったり、俺の手を自ら胸に導いて控え目に愛撫をねだったりし始めた。
高まりながらも乱れ切らず、必死に自制している様子が、奥ゆかしくて大変可愛い。募る愛しさに任せて、俺は南さんを抱きすくめた。
「きゃ……?」
一瞬驚いた声を上げるが、そのまま柔らかな乳球にキスし、舌を這わせて愛撫していくと、再び甘く蕩けた喘ぎに戻る。聞いているだけで牡の劣情に響く声。が、暴走しそうになる欲望を何とか抑え込み、意識して抽送を緩める。このまま思い切り突き込み続けたら、射精まで止まれない。
俺は一番奥で一旦腰を止め、捏ねるように回した。
「ひぅ……! んあっ…奥……奥が、ごりごりって……はぁああっ!」
たまらないほど切ない表情で泣き喘ぎ、南さんは俺の頭をぎゅうっと抱き寄せた。どこまでも柔らかい双乳に俺の顔が埋まる。少々苦しいが、構わず再奥部で細かく突き上げと回転を繰り返した。

「あああっ! 和巳さん、それ、それ…凄いです…っ!」
子宮口付近は南さんの弱点の一つだ。集中的に責められ、膣肉が反応してきゅうっと食い締めてきた。
「――っ」
危ない。動いてたら耐えられなかったかも。ぞわぞわと別の生き物のように蠢いて絡みつく肉襞は、正直めちゃくちゃ気持ちいい。
だが、南さんの味わっている快楽はおそらく俺を凌いでいる。直接伝わってくる早く強い拍動と、俺を抱きしめる両腕の震えが充分すぎるほどそのことを伝えていた。
俺は一時腰の動きを止め、南さんに一息つかせた。と言うか、そうしないと俺自身、物理的に息がつけずに窒息しそうだった。
力の弛んだ彼女の腕を解いて深呼吸し、荒い息をつく南さんに微笑みかけた。
「イかせてあげるね、南さん。俺もそろそろだから……一緒に、気持ちよくなろう」
とろりと蕩けた瞳で頷き返してくる南さん。
「は、い……。一緒に……一緒に、イきたい、ですぅ……」
従順にねだる餅肌美女にキスで答え、俺は腰の律動を強めた。と言うか、そろそろ抑制できない。湧き上がる獣欲のまま、腰を叩きつける。
「はぁあああっ! 凄いっ……強いの、イイ…っ!」
時折ぎりぎりの抑制が働いて突き込みが弱まるのが、いいアクセントになっているようだ。すっかり我を忘れた南さんは、全身を桜色に染め、腰を浮かせて、俺のピストンにあわせて自分から小さく揺すった。
「くぅううっ……!」
互いに求め合い、高め合う情欲の心地よさは筆舌に尽くしがたい。何もかも忘れ、俺は南さんを求めた。
「南さん……南さんっ!」
「はぁっ! あぁああっ! かっ、和巳っ、さんっ! かずみ、さぁあんっ!」
呼び合いながら、俺は彼女を抱きしめ、最奥で腰を止めて最後の引き金を引いた。
「おおおっ…!」
「あああぁああああ……っ!!」
凄い勢いで精液が俺の肉棒を駆け上がっていく。南さんの胎内で俺の欲望が弾けるたびに、彼女は小さく震えて絶頂に至った。断続的な射精と完全に同期して、彼女の膣肉がきゅうきゅうと収縮する。同じ快楽を共有している実感があった。
しばらくは呼吸も忘れていた。やがて白く染まっていた視界が戻り、ぼおっとけぶるように俺を見上げる南さんの潤んだ瞳と見つめ合う自分に気付く。
――思いっきり精を放った実感がある。
ふと気付くと、彼女の手が俺の肩をぎゅうっと握っている。いや、最後のときからずっとそうだったのだろう。今まで感じてすらいなかった微痛が、思い切り食い込んだ爪が背中の皮膚に食い込んでいることを教えていた。
それでも何となく動きたくはない。しばらく甘美な余韻に浸っていたかった。
南さんも同じ考えなのか、俺にしがみついたまま動きを見せない。
が、それは外見上だけのことだった。
うわ……っ。
射精して萎みかけていた俺のものに、彼女の複雑な襞のうねりが絡みついてくる。調教が上手く行っていれば、彼女の体はもう俺にしか満足させられないようになっているはずだ。言わば俺の禁欲は彼女の禁欲とイコールで結ばれている。
深く溶け合うような絶頂とはいえ、一度だけで今の南さんの体が満たされるはずはなかった。南さんの感触を味わううちに、俺のものも硬度と容積を取り戻していく。膣洞を内側から押し広げられ、切なそうに眉を寄せる南さん。
俺は彼女にのしかかるように体重を預け、耳元で囁いた。
「俺、もっと南さんを抱きたいな……」
眼鏡越しの瞳がぱっと輝く。
「は、はい。私も、もっと和巳さんに抱いて欲しいです……」
俺に釣られるように、素直に欲望を口にした。
深いキスを交わしてから、おそらくは一度きりの甘い夜を続けるために、俺達は深く深く繋がりを求めていった……。
いつしか降り出した激しい雨の音が、防音の効いた窓越しにかすかに響いている。11月の冷たい雨は気温を急降下させ、部屋の中の空気はかなり冷え込んで来ていた。
お互いにたっぷり汗をかいている。このまま冷えたら風邪を引いてしまいそうだ。俺は毛布を引き寄せ、俺の胸に頭を乗せて眠る南さんと一緒にくるまった。気を失うまで責め抜くのはいつものことだが、今夜は一緒に快楽を求めたため、俺もだいぶ消耗していた。
寄り添う体温の心地よさ、南さんの体の柔らかさ、甘い体臭、腕に伝わる穏やかな鼓動。常になく優しい気持ちに包まれつつ、俺は彼女の額にかかった前髪をそっと払って、疲労に任せて目を閉じた。
夢は見なかった。
雨は明け方には上がっていた。レースのカーテン越しに窓から差し込む朝日を浴びて、眼鏡の奥の瞳がゆっくりと開かれた。半覚醒のまま俺の目をじっと見つめる。
俺は柔らかく彼女に微笑みかけた。
「おはよう、南さん」
スイッチが入ったように、瞳に理性の光が戻る。同時に昨夜からのことを思い出したのだろう、頬にさあっと桜色が刷かれる。おずおずと微笑み返してきた。
「お、おはようございます……和巳さん」
顔を寄せると、恥ずかしげに目を伏せるが、逆らわず力を抜いた。軽く、だが少し長めにキスを交わす。
唇を離し、ほおっと熱い吐息をつく南さんの髪を撫で、優しく囁いた。
「どう? 南さん。答えは出たかな……?」
敢えて漠然と問いかけると、自分の内面を見つめるかのように黙り込んだ。急かさずに答えを待つ間、彼女の髪を撫で続ける。
「――はい。答えは出ました」
たっぷり1分以上考えて、彼女はそう告げた。目線で続きを促すと、南さんは少し身を起こし、自分から俺にくちづけた。
「私の心は……貴方のものです。御主人様」
ディープなキスで、健気なセリフに答える。たっぷりと呼吸と唾液を交換して上気した優しげな美貌に、一言囁きかける。
「――南」
「あ……」
一言名を呼ばれ、何を感じたか切なげに身じろぎするのが密着する肌から感じられた。
「これからは、そう呼ぶ。いい?」
「はい」
とろりと蕩けた瞳で頷く南さん――いや、南。
「私からも、一つ、お願いがあります」
急にそんなことを言い出した。まあ、叶えてやる必要はないが、聞くだけならいいか。
「言ってごらん」
「あ、あの……」
そして、もじもじと落ち着かなげに顔を伏せ、上目遣いになった南は、こう言ったのだ。
「時々でいいですから……和巳さん……って、呼んでも、いいですか……?」
飼い主としてはきっぱり拒絶するところだったかもしれないが……はにかむような仕草があまりに可愛かったので、俺はつい頷いてしまっていた。
「――他の奴隷がいないときだけ、な」
「はい……!」
苦笑して言うと、南は嬉しそうにほころんだ笑みできゅっと俺に抱きついてきたのだった。
こうして南は俺に身も心も捧げることになった。
彼女は賢く従順で、俺の命令には極めて忠実で、以前のような嫌々従属する様子はかけらもない。心から俺を慕う態度はいじらしささえ感じさせ、俺の支配欲を大いに満たしてくれた。
だが――それでも俺は、自分のセリフを忘れてはいなかった。
『演技でも、自分を騙してでも何でもいいから、俺の前ではそういう態度を取れるようになれ』
先週のこみパで――俺はそう言ったのである。
健気なセリフも、従順な態度も、すべては演技なのかもしれない――。
もし演技だとしたなら、おそらく無意識の領域まで自分を騙した「なりきり」のものだろうが……俺は、その可能性を捨ててはいなかった。
演技なら演技でかまわない。俺が欲しいのはその忠実な振る舞いだけだ。だが、その前提があるからには、必要以上に彼女に入れ込む気になれないのも確かだった。
そして、この薄紙一枚挟まったようなわずかな隔意が、何故か残念なような気もしているのだ。心から南の忠誠を信じられたらどんなにいいだろう、と。
――ま、スリリングな騙し合いと思えば、これはこれで楽しめるところもあるがね。
狭いユニットバスで一緒にシャワーを浴び、体を洗い合った。軽くいちゃつき合いはしたが、腹も減っていたので汗を流しただけで切り上げる。
一応自炊できるだけの調理器具は揃っており、朝食は南が作った。ここはこれしかないだろう、と言うことで、裸エプロンに首輪姿を要求する。恥ずかしげに頬を染めながら、だが逆らわずに命令に従う南。さすがにエプロンまで持参していたわけではないので、部屋にあったズック地の飾り気のないタイプのものだが、これはこれでよし。……そのうち裸ワイシャツもさせよう。
買い置きの食材では大したものも作れないかと思ったが、ご飯、豆腐の味噌汁、野菜の味噌炒め、目玉焼きを手早く作った手際は見事と言うしかない。彼女は嬉しそうに料理を作り、嬉しそうに一緒に食べ、嬉しそうに給仕をして、嬉しそうに後片付けにかかった。料理は素朴な味わいながら確かな味付けで美味かった。
南の淹れてくれた玄米茶を飲みながら食休みを取り、洗い物を終えた南を呼んで今日の調教を始める。まずは軽くエネマ責めをして腸を綺麗にしてやる。昨夜はいわゆる「普通の」行為ばかりで、アナルには触っていない。そのためもあってか、浣腸されただけで、南の肉体は肛虐への期待に発情してしまう。
すっかりできあがった様子の南に俺は敢えてキッチン周りの掃除を言いつけ、戸惑いながらも従う彼女のすぐ後ろに立って、指先で尻穴を軽く弄ってやる。
「ああ……ふぁん……御主人様ぁ……」
今朝までは聞いたことがなかった南の甘え声が、俺の鼓膜を快くくすぐる。凌辱を期待してひくつく菊孔から腸液がにじみ出し、秘唇からはもっとあからさまに淫蜜が溢れて内腿を伝い落ちていた。
そのまま焦らすように愛撫を続ける。南はちらちらと背後の俺に哀願の視線を投げつつ、命令通りシンク回りの掃除をしていた。次第に彼女の腰がもじもじと揺れ始める。焦らしに耐えかね、俺を誘うように動いた。
だがまだだ。ちらっと時計を見る。そろそろのはずだが……。
思うが早いか、ピンポーン、と柔らかいチャイム音が響いた。玄関に向かい、来客を迎え入れる。
「いらっしゃい。さ、上がって」
「…………」
「はいです、御主人様!」
開いたドアの外に立っていたのは、沈んだ面持ちの郁美と満面の笑顔の千沙だった。
「寒かったろ? 南、お茶を出してあげて」
「……はい、御主人様」
一瞬間があったのは戸惑いのせいだろう。
コートとマフラーを脱いだ郁美は、トレーナーとデニム地のミニスカートにオーバーニーソックスと言う格好。フード付きのもこもこコートを脱いだ千沙は、ブラウスとVネックセーターとキュロットと黒タイツと言う格好だった。加えて、千沙は嬉々として首輪を取り出し、首に巻く。それを見て、嫌そうに郁美も千沙に倣った。
二人が来たのは無論、事前に呼び出してあったからだ。連れ立って来るとは思わなかったが。
「ちょうどそこで郁美お姉さんに会ったです」
「もう仲良くなったのかと思ったよ」
「にゃああ。きっとこれから仲良くなれるです。南お姉さんも、郁美お姉さんも、千沙と同じ、御主人様の奴隷ですから」
ぱあっ、と明るく微笑む。その笑みを目にして、逆に悲痛な表情になる郁美。
「四堂さ――いえ、御主人様……。千沙さんのような子まで奴隷にするなんて」
強い非難のこもった眼差し。
「いいじゃないか。本人は嫌がってないだろ? な、千沙」
「はいです! 千沙は、御主人様の奴隷になれて、とっても嬉しいです」
間髪入れず俺の望む答えを返し、そればかりか甘えるように擦り寄ってくる千沙。
「くっ……。こんな素直な子を洗脳するなんて……っ」
おいおい。人聞き悪いな。まあ、完全な間違いじゃないような気も、我ながらするが。
それはそうと、何だか今までの会話に軽い違和感を覚えるが……?
「それで、今日は千沙達にどんなご用ですか? 御主人様。何でも言ってくださいです、千沙、頑張りますから」
ホントにいい子だなあ。思わず髪を撫でると、千沙はくすぐったそうに目を細め、いっそう密着してくる。
「お前達を呼んだのは、調教のためだ。まだまだ奴隷として覚えさせなきゃならないことが多いからな。みっちり仕込んでやるから、しっかり覚えるんだぞ」
「はい、御主人様!」
「……はい、御主人様」
「御主人様に悦んでいただけるよう、頑張ります。どうか、御主人様のお好みどおりに躾けてください」
千沙の元気な声。郁美の嫌そうな声。南の情感たっぷりの声。
郁美の不審そうな視線が南に向けられた。こみパの時は郁美に近かった態度が、今やすっかり千沙寄りになっているのだ。そりゃ、なにがあったのかと疑いたくもなるだろう。だが説明してやる義理はない。郁美は、従順に躾ける気は今のところあんまりないし。
俺はまず郁美と千沙に、着ているものを全部脱ぐよう命じた。ほどなく首輪だけ残して全裸になる二人。南は首輪エプロンのまま据え置きだ。
千沙の体つきもかなり幼いが、郁美は輪をかけて発育不良だった。
「う……千沙さんに負けた……」
小声で呟く声を聞きつけ、苦笑する。
「そりゃそうだろう、だって……」
言いかけて、さっきの違和感の正体に気付いた。
――郁美『お姉さん』?
千沙は年齢より子供っぽいし、郁美は逆に年齢より遥かに落ち着いて大人びているので、当たり前のように聞き流してしまっていた。
「……千沙の方が年上だからな」
説明を言い終えると、奴隷達は『え?』と声を揃えて動きを止めた。
「郁美は中二。千沙は高二。……って、三歳も違うのか!?」
自分で言っていて驚いた。実際には2年4ヶ月違いだと言うのは後で確認した事実だ。
『ええっ!?』
奴隷達も揃って驚愕の声を上げる。特に郁美の衝撃がでかいようだ。……そりゃ、今まで年下だと思っていた子が、実は三学年も上だと知った日にはな……。南も千沙も驚いてはいるが郁美ほどではない。二人とも天然入ってるしなあ。
まあいいや。話を進めよう。
「さて。それじゃまずはフェラ調教から始めるぞ。講師は千沙な」
「ふえ? 千沙が教えるですか?」
「ああ。千沙が一番フェラが上手いからな」
「にゃああ……千沙のご奉仕、上手なんですか。嬉しいです、御主人様ぁ」
心底嬉しそうな笑顔を見せる千沙。俺に褒められるのが嬉しくて仕方ないようだ。
「それで、千沙はどうすればいいですか? 御主人様」
正直言って、千沙のテレパシックな洞察力を身につけるのは、他の誰にもできないだろうと思う。だが、巧緻な技巧を表面的に模倣させることくらいはできるんじゃないか?
そんな風に予想してみた俺は、まずは跪かせた南の前に立った。そのすぐ後ろに千沙を立たせる。郁美はとりあえず見学。
「これから南に奉仕させるから、千沙は俺と南の様子をよく観察して、よくないところを指摘して直すように」
「はい……やってみますです、御主人様」
使命感に燃える千沙の手にアクリルの30センチ定規を手渡した。
「それじゃ、始めるんだ、南」
髪を撫でて命じる。くすぐったそうに目を細めて、南は頷いた。
「ご奉仕させていただきます、御主人様」
そう挨拶してから、まだ元気のない俺のモノをぱくりと咥え込む。
「んっ、ん、ふ……くぅん……」
たちまちとろんと蕩けた瞳になり、くちゅくちゅと口内の牡肉を舌で転がす。なかなか気持ちよかったが、千沙のチェックは厳しかった。
「御主人様だけ見なきゃダメです」
ぱちん! とアクリル定規が南のお尻にヒットする。それほど力を入れている様子はないが、ちょっといい音がした。南の尻肌に艶やかに脂が乗っているからだろう。
「ご奉仕すると頭がボーっとなって気持ちいいですけど、ご奉仕は御主人様を気持ちよくするためにするのであって、自分が気持ちよくなるためじゃないです。それを忘れちゃダメですよ」
……南が自己陶酔しかけたのを敏感に察したらしい。ものすごい感知力だ。既に俺にフェラ奉仕するときの精神感応モードに入ってるのかもしれない。
年下の少女に叱られた南の眼差しが真剣味を帯びる。俺のどんな反応も察知しようとアンテナを広げた様子は、そう言えば最初の頃の千沙に酷似していた。南の気構えが変わったのを捉えた千沙は満足そうに頷き、後ろ手に縛られた南の手を褒めるように優しく叩いた。
「じゃ、ご奉仕を続けるです」
継続を指示され、南は熱心に口唇奉仕に励み出した。今さっきの奉仕で半起ちになっていた俺のペニスは、すぐに彼女の口中で完全勃起を遂げる。
「そこは、舌の根でゆっくり舐めるです」
「そこは、ほっぺたの内側でぐりぐりするです」
「そこは、前歯で優しく擦ってあげるです」
「そこで2秒強く吸うです」
千沙の指示は恐ろしいほど的確だった。南の口の中が見えているんじゃないかと思うほどだ。おかげで、そこそこ気持ちよかった程度の南の口唇愛戯は、千沙のやり方を模倣したものに変わっていき、驚くほど急速に俺の快楽嗜好にぴったり合致したものになっていった。
「ダメです!」
ピシッ! とまたアクリル定規が飛ぶ。
「勝手に御主人様をイかせようとしちゃダメです。御主人様がイきたいときにイかせてさしあげるのが奴隷の役目です。自分がイかせたいときにイかせようとするのは奴隷じゃありませんです」
言い聞かせるように、もう一度、少し強く定規を振り下ろす千沙。
バシィンッ!
「奴隷は、自分の意思を、持っちゃダメですっ!」
ババァーン!
と書き文字を付けたくなるほどきっぱりとした宣告だった。
千沙の場合、どうやら技術的な部分よりも、こういう精神的と言うか、奴隷として持つべき姿勢と言ったものへの追求の方が厳しいらしい。いつの間にやら、奴隷の心構えみたいなものまで確立しているようだし。
と、南はしゃぶりついていた俺の肉棒から口を離して振り向いた。
今の、よっぽど痛かったかな?
とか思って見下ろした横顔は、驚いたように目を見開いている。
「そうか……。そうなのね。御主人様の意思が私の意思。御主人様の願いが私の願い。そして、御主人様の悦びが……」
「……千沙達、奴隷の悦びです」
目を見交わして頷き合う。……何だか妙な悟りの境地に至ったらしい。
「千沙ちゃん、ありがとう。私、今初めて本当の奴隷になれた気がするわ。千沙ちゃんは私の恩人ね。先輩奴隷だし……そうね、思い切って『お姉様』って呼んじゃおうかな?」
「にゃああ。それなら、千沙は『南』って呼び捨てちゃうですよ?」
「お姉様……」
「南……」
――えーっと。突っ込んだ方がいいのか? 年の差、えー……7歳近い逆転姉妹かよ。いくら天然同士でも、本気じゃないよ、な? ――な?
この二人のことだから、「絶対ない」とは言えない辺りが何とも……。
「二人とも、その辺にしときなさい」
半眼でたしなめると、二人は『はぁい』と声を揃えてかしこまった。息の合い方はホントの姉妹のようだ。
……だが、今の一幕は、ただのミニコントではなかったらしい。
「うお……っ?」
再開した南の奉仕は、技巧的にはどこがどう変わったとも思われないにもかかわらず、驚くほど千沙の奉仕に近いものに変貌を遂げていたのだ。南の口にした、本当の奴隷云々と言うのはあながち妄言でもなかったのだろう。何しろ、そう、上手く表現できないが……俺への奉仕に対する、姿勢と言うか真摯さと言うか、その精神性が千沙のそれと瓜二つなのだ。
全身のセンサーを総動員して俺が何を望むのかを感じ取ろうと努め、あらゆる技巧を尽くして俺の欲求を満たそうと一心に励む。千沙はもう言葉をかけず、お仕置きもせず、満足そうな笑みで南のやりようを見守っている。
そうだ、それは――絶対的な『献身』の姿だ。
もしもこれが演技だとしたならば、彼女の自己暗示能力は極めて高い域に達していると言えるだろう。
性急に追い上げるようでなく、焦らすようでもなく、俺を悦ばせることだけを念頭に置いた愛撫を受けて、俺はじわりじわりと込み上げてくる快楽をたっぷり楽しんだ。本家の千沙にこそ及ばないものの、俺の好みに合わせるべく最大限の努力を見せる奉仕は素晴らしく気持ちいい。
ちょっと名残惜しいが、俺は限界が来る前に南の奉仕を中断させた。先は長い。さすがにいちいちイっていたら身が持たん。
南はフェラ講習は合格と言うことで、郁美の番になった。
が――。
バシッ! バシッ! バシィンッ!
「うっ…! んんっ……! むぐぅ………っ!」
郁美の小さなお尻に、アクリル定規が容赦なく振り下ろされる。千沙の指示で技術はそこそこ上がってはきたものの、根本的に熱意に欠ける郁美は、奉仕の気構えを重視する千沙にとっては、いくら注意しても悪いところを直そうとしない劣等生だった。自然、お仕置きも厳しさを増していく。
だが、いくら打たれようとも、郁美は強制されて嫌々従っているというスタンスを崩すことはなかった。
郁美の場合、その嫌々感が、無理やり従わせている事実を明確にしてくれて、嗜虐心を満たしてくれていたりするのだが……。
結局、そんな俺にとっての郁美の価値観を薄々察したらしく、千沙は郁美の態度の矯正を強行しようとはしなかった。
そんなわけで、フェラ調教の成果は、南は文句なしで郁美はテクだけ少し上がった、というところに落ち着いた。
「はひぃいいいい〜〜〜ッ!! ぃあ、ひゃふ、はぉおお……へぁああああああッ!!」
固唾を呑んで見守る奴隷少女達の目の前で、首輪エプロンのおっとり眼鏡美人が半狂乱でよがり泣いていた。
ベッドに腰掛けた俺の胸に背中を預けた南は、俺の腰に跨って後背座位で肉棒を受け入れている。両手でエプロンの前垂れを持ち上げ、千沙と郁美に股間をさらけ出している。二人の凝視は、俺と南の交わる一点に注がれている。屹立が埋めるのは、彼女の膣ではなく直腸だったのだ。
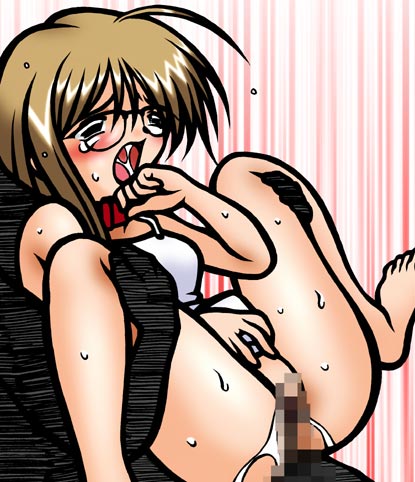
俺の命令で自分から腰を下ろして迎え入れた尻穴は、エネマの後軽い愛撫に終始したため疼きを溜め込んでいたのだろう、苦もなく柔軟に広がり、俺のペニスを嬉々として呑み込んだ。エプロンをめくりながらするよう命じていたので、この様子はすぐ前に座り込んだ二人に丸見えだった。決して細くはない俺のモノが排泄孔を貫いていく衝撃的な光景に、千沙も郁美も驚愕に眼を見開き、呼吸も忘れて見入っていた。
そして、俺が下からぐいぐい突き上げ始めると、南はアナル快楽に我を忘れ、身も世もなく泣き喘ぎ、乱れ狂った。激しい菊孔凌辱に彼女がこの上ない官能を掻き立てられているのは、充血して腫れ上がり、物欲しげにひくつく肉襞、ぷちゅっ、ぷちゅっと断続的に淫蜜を噴き出す膣孔、厚手のエプロンの上からでもはっきりわかる勃起乳首などを見ればあまりにも明白である。
「ひゃぁああああっ! ご主人ひゃまぁっ! らめぇ! そこっ……そこ抉られたらぁっ、南、すぐに、すぐにイっひゃいまひゅぅうううううっ! はひィっ、イくぅううううううううううーーーーッ!!」
びゅびゅっ! と潮を吹いて、年上の美女が壮絶な尻穴アクメを迎える瞬間を、呆然と眺める奴隷少女達。
「――さて」
くたり、と脱力してもたれかかってきた南を支えながら声をかけると、二人はびくっと肩を震わせて脅えた視線で見上げてきた。これから何が起こるのか、何となく察してはいるようだ。
「奴隷は、こっちの穴でも主人を楽しませるようにならなければならない。と言うわけで、千沙、郁美、これからお前達のアナル調教を始める」
俺の命令には忠実な千沙も、さすがにちょっと不安げな顔になった。郁美の方は、敢えて説明するまでもないが嫌悪と屈辱に歪んだ表情である。よく見ればそこに微量の恐怖が混じり込んでいるだろうか。
俺の指示で、郁美はクッションをいくつか置いたフローリングに仰向けになり、千沙はその上に上下逆に四つん這いになった。いわゆるシックスナインの態勢である。そうしておいて俺は二人にそれぞれ器具を手渡した。千沙には、小さめのビー球が縦に連なった棒状のもの。郁美には、ユニコーンの角を思わせるねじれた棒状のもの。どちらも一端には持ち手がついている。おまけでベビーローションの小瓶もサービスすると、郁美の顔色が急速に悪化していった。千沙の方は首を傾げてきょとんとしている。
ネットで無駄な知識を山ほど仕入れている郁美には、手渡されたアイテムの用途が理解できているようだ。
渡しはしたものの、もしかしたらローションは使わなくても間に合うかもしれない。南のアナル絶頂の迫力に感化されてか、彼女達の秘裂は自家製のそれでしっとり潤っていたのだ。
「じゃあ、まずはソレでお互いのおマ○コを擦って、たっぷり蜜を絡めてごらん」
「はいです、御主人様」
躊躇う郁美と対照的に、千沙は髪の毛一筋ほどの逡巡も見せず、俺の命令に従う。
「ひぁんっ! ち、千沙さん……や、あ……」
ずるるるっ、ぬるるるっ、と、とろけかけた陰唇をシリコン球の連なりに刺激され、郁美がこらえきれず甘い喘ぎをもらす。組み敷かれて淫具で弄ばれる大人びた少女に、俺は重ねて指示を出した。
「ほら、郁美。お前もお返しするんだ」
「う……は、はい……御主人様……」
渋々頷き、郁美は螺旋棒を千沙の秘唇に沿って滑らせる。愛液が絡み、空気を巻き込んだロッドが、粘膜を掻き分けながらぷちゅるるるっ、と水音を立てた。
「にゃああぁっ……! あっ、あ、それぇ……何か、変、ですぅ……」
バイオリンのように姫割れを奏でられた千沙も、のけぞって快感の声を上げた。
おれはそのまましばらく、奴隷少女達の戯れを観賞した。
二人とも小柄で折れそうに細く、胸の膨らみはごくわずか、恥毛は千沙は薄っすら生え、郁美に至っては完全に無毛。つるぺたロリの美少女達が、可愛い喘ぎを上げながら淫らな交歓に耽る姿は、たまらなく背徳的で扇情的な見世物だった。
これを一人で見物するのはもったいない。俺は腰を突き上げ、半失神状態でぐったりしていた南を叩き起こした。
「ひやぁああああっ!?」
びくん、と悦楽の叫びとともに覚醒した南の視線は、誘導するまでもなくすぐ目の前の淫靡極まる絡み合いに吸い寄せられる。下手をすれば小学生にも見えかねない二人の、あまりにも反道徳的――に映る――淫戯は、滅多に見られるものではない。
だが、背徳の宴はこれからが本番だった。陰唇、膣口、尿道口、陰核をまんべんなく刺激され、陰具には二人が分泌した蜜液がたっぷりと絡んでいた。
「よし。それじゃ、ソレをお尻の穴に入れてごらん」
「――にゃ?」
さすがの千沙も、今度は即座に従うことはなかった。びっくりした目で俺を見上げ、互いの体越しに郁美と視線を絡ませる。二人の表情には不安と脅えの他に、隠しきれない好奇と欲情の色がほの見えた。何しろ、目の前で美人のお姉さんが肛虐の愉悦に乱れまくる姿を見せつけられたばかりである。不浄の器官への接触に抵抗があるのはもちろんだが、それによってどれほどの官能が得られるのかと言う興味は抑えようがないはずだった。
「先っぽで弄ってほぐしてから、ゆっくり入れるんだ。無理はしなくていいから」
重ねて命じると、二人は強硬に拒むでもなく、躊躇いがちにアナルロッドの先端をお互いの菊孔に近付けていく。
「あっ……」
「ひゃっ……」
敏感な窄まりに濡れた淫具が触れると、小さく驚いた声を上げるが、俺の命令通りに丸みを帯びた先端で菊皺をほぐし始めた。他人にある意味もっとも恥ずかしい場所を弄られて、違和感に眉をひそめながらも、動きに停滞は生まれない。
「はぁっ、はぁっ……」
「んっ、んんっ……」
息を荒げながら懸命に俺の言葉に従う少女達の健気さが快かった。
やがて頃合いを見て、俺は次の指示を出した。
「そろそろいいだろう。中に入れてみな。少しずつね」
湿った吐息の中、こくりと喉が鳴る音が俺の耳に届いた。誰のものかはわからない。
ぐ、と2本のアナルロッドに力が込められ、ぬるっ、ぬるっとほぐされた裏門を貫いていく。
「にゃぁあああ……」
「あ、ああ、あ……?」
排泄孔を逆流してくるかつてない感覚に、少女達には戸惑いの色が濃い。それでも手は止めず、相手の腸内に愛蜜まみれの責め棒を飲み込ませていく。
少女達の見せる痴態に、南は凝然と見入っているようだった。
乱れた呼気と煩悶の声が、しばらく部屋の中に流れる。やがて、千沙ががくりと潰れて上体を郁美の腹の上に突っ伏した。
「はぁ、はぁ、はぁ……」
強烈な違和感に耐えるのに相当消耗したらしい。千沙のうなじは鳥肌を立てながら、じっとりと脂汗に光っていた。
……うーむ、やっぱいきなりアナル性感に目覚めたりはしないか。南と違って。
いや、そう言えば南も高校時代に先輩に開発されたとか言ってたっけ。
じゃあどうしようか。うーん。
「まあ、とりあえず休んでいていいや。頑張ったみたいだしな」
千沙がかすかに頷くのが見えた。返事もできないほど疲れているようだ。
あっちはしばらく置いておこう。代わりにこっちを……。
「――南。これを」
「え、はい……えっ?」
手渡されたものを見て、眼鏡越しの瞳が見開かれた。
形状といいサイズといいかなり凶悪な、上級者用のバイブである。
「あの……これを、一体」
どうしろと、と振り向いて目顔で問いかける南に、俺は優しく微笑みかけながら命令した。
「それでオナニーしてごらん」
「――――」
ぐらり、とかしぎかける南の上体を支えてやる。
「さあ、ほら」
促すと、南は脅えたような表情で小さく左右に首を振った。
「そんな、ダメです。今そんなことしたら……ひゃぅんっ!」
軽く腰を突き上げてやると、南は甘い悲鳴を上げて言葉を途切らせた。――軽くって言っても、この体勢で突き上げるのってかなり腹筋使うな。
「今やったら、どうなるんだい?」
「ん、あ……今、したら……きっと、気持ちよすぎて、変になっちゃいますぅ……」
イヤイヤ、と首を振る南。
「気持ちいいのがイヤなの? 南は」
耳にキスしながら囁くと、ふるるっ、と首筋に慄きが走るのが見えた。
「はぁあっ……。だって……気持ちよすぎると……私が私でなくなってしまう気が、して……怖いんです……」
脅え混じりの述懐に、俺は頷きを返した。
「いいんだよ、それで」
「え……」
「南はもう、俺の奴隷なんだ。どんどん変わってしまってかまわないよ。どんな風になったって、南が俺の奴隷だってことだけは変わらない。だから、どんな南のそばにも俺がいるよ。溺れてしまっていいんだ。わけがわからなくなるほど南を感じさせられるのは、俺だけなんだから。そうだろう?」
甘い誘惑を囁き、欲望に歯止めをかけようとする理性のブレーキを外してやる。
「あ、あ……。私……私……。いいんですか……? 気持ちよすぎて、変になって……どうにかなってしまっても……いいんですか――御主人、様ぁ」
快楽への期待に、眼鏡越しの瞳も、唇から洩れる吐息も既に甘く蕩けかけていた。
「いいんだ。そうなった南を見たいな。南を俺が支配しているって実感できるから」
さあ、と三度催促すると、もはや南は逆らわなかった。かすかに指先を震わせながら、バイブを股間に近付けていく。俺の位置からは見づらいが、秘唇がほぐす必要がないほど蕩け、濡れそぼっているのは確信できた。
「ん、はぁああああ…………っ」
深い吐息と共に、南は愛玩具を膣孔に沈めていく。膣と直腸を隔てる肉壁越しに、バイブの突起が俺の肉棒の裏筋をごりごり刺激してくる。当然、直接に抉られる南はその数倍の激感を味わっているはずだ。
じゅっ、ぐちゅっ、と濡れた音を立てながら、淫具が彼女の胎内に飲み込まれる。途中何度も背筋がびくっ、びくっと震え、アナルもきゅっきゅっと収縮して俺を締め付けていたが、手を止めることはなかった。
「――ふ、は、あっ」
膣道を拡張しつつゆっくり進んでいた野太い擬似男根が、くん、と軽い抵抗感とともに動きを止めた。奥まで達したらしい。多分南にとっては「ごすっ」と突き上げられたような感じだったことだろう。
くたっ、と脱力して俺に寄りかかってきた南を支えながら、また耳元に口を寄せる。
「入れただけじゃダメだろ、南。動かしてごらん」
「あ、はぁあ……ふ、んっ……は…はい、御主人様…っ。で、でも……ちょっとだけ、待って、ください。入れただけで……軽く、イっちゃいました、から、ぁ……」
切れ切れに訴えてくるので、一分ほど待ってやった。
呼吸が落ち着いてきたところでもう一度命じると、南は小さく頷いて、下腹を満たした質量を恐る恐る動かし始める。
「ふぁっ……はぅんっ……。あ、あっ……ふぁああっ…!」
俺に背中を預けたまま、甘い喘ぎを上げつつ性玩具に細かい抽送や振動を加えていく南。それは同時に、俺の肉茎を膣肉越しに淫具で擦りたてると言うことでもあった。器具を動かすたびにきゅうきゅうとリズミカルに締め付けてくるアナルの感触と相まって、かなり気持ちいい。
次第に手の動きが大きくなってきたところを見計らって、次の指示を出した。
「左手が遊んでるね。胸も揉んでごらん?」
「ああ……は、はい……」
躊躇いがちに、だが従順に左手が動いた。
「――んっ!」
ゆっくり伸びた手が自らの乳肉を柔らかく変形させると、押し殺した喘ぎが洩れ聞こえる。今の南は全身が性感帯のようなものだ。元から性感の発達している乳房を弄ぶのは、さぞたまらない快感だろう。
快楽に飲まれかけているのか、南の腰が控えめにうねり始める。右手でバイブを動かし、左手で乳房を愛撫して、深い息をつきながらアナルで俺の肉棒を食い締める。許容量を超える快感を自らの手で掻き立てていきながら、俺の命令通りの動きを続ける南の姿は、俺が彼女を支配していると言う実感をもたらして、ひどく心地がいい。
気分よく俺は右手を動かした。
「こっちは俺がしてあげるよ」
そう告げて、空いている南の右乳へと掌を向ける。
「ああ……」
声の震えは、脅えのためか、期待によるものか。
「――ひゃふっ…!」
俺の手の下でどこまでも柔らかく形を変えていく美乳。しっとりと手に吸い付く餅肌の感触は絶品で、欲情に朱を刷いたとろけるような乳肉は、搗き立ての桜餅を思わせる。乳首の感触だけがこりこりと硬く、手の中で転がり、くじられ、胸肉に押し込まれる。南自身の左手とリズムを合わせて乳房を揉みしだいていくと、最初はひんやりしていた乳塊は、俺の掌で次第に熱を帯び始めた。
「や、あ、あ……。は、ひ、ふぁ……っ!」
両手と腰の蠢きのペースが上がり、かなり出来上がってきたのが見て取れる。とろとろに蕩けた腸の奥が蠢き、俺の先端に絡みついてきた。S字結腸の蠕動だろうか。
どうであれ、めちゃめちゃ気持ちいい。気を抜くとすぐにでも射精してしまいそうだ。
俺は南にもとどめを刺すべく、指示を追加した。
「それじゃあ……そろそろ、スイッチを入れてみようか」
「――――!!」
息を飲む南。今まで彼女はそれをディルドゥとしてしか使っていなかったのだ。本来の使い方を命じられた南の乳首が、俺の手の中でびくんと跳ねた。
「あ……ああ、あ……」
俺の胸に密着した背中越しに、早鐘を打つ南の拍動がはっきりと響いてくる。優しげな美貌に動揺と躊躇の色が浮かんでいるのが、見なくてもわかった。だが、右手の指先は、脅える心と別の意思を持っているかのようにバイブ後端のスライドスイッチにかかる。
かち。
乾いた小さな音が鳴り、即座にバイブはモーターを稼動させて、振動しつつうねり始めた。
「――ひぁああああああああああッ!!」
一拍置いて甲高い悲鳴を上げる南。ぎゅうぎゅうと締め付ける括約筋が、彼女が味わっている衝撃的な快楽の深さを物語っていた。
と言うか、膣壁と腸壁越しに淫具の振動はばっちり響いてきて、かなり効く。その上こう食い締められては、俺の方があまり我慢できそうになかった。
それでも根性でもうしばらく耐え抜き、我を忘れてよがり泣く南の痴態を堪能する。
「はぁああっ! ひはぁあああっ! んんっ、くぅうううう〜〜んッ!!」
切なそうに身をよじり、甘えたような声音で泣き喘ぐ南の艶姿は、こうやって南の快楽を俺が支配している事実を強く意識させ、どす黒い優越感をもたらした。この精神の愉悦に比べれば、肉体的快楽などどれほどのものだろうか。
いや、もちろん気持ちいいに越したことはないが。
いい加減俺も南も限界と見て、俺は腹筋に力を込めて軽く上体を起こした。――けっこうキツいが頑張って耐え、後ろ手に支えていた左手を南の前面に回していく。ウエストを巻き、ゆっくり下腹部に伸びる俺の手に、悦楽に酔う彼女は気付かない。
俺の指先は、あやまたず南のクリトリスを捉え、強めに転がしていた。
「――きぁあああああ〜〜〜〜ッ!!」
充分すぎるとどめだった。南はぎゅうっとのけぞり、強烈な絶頂に身を震わせた。
痛いほどのアナルの締め付けとひときわ強くなった腸奥の蠕動が俺の肉棒を熱い快感で包む。逆らわず、俺は耐えに耐えていた射精の引き金を引いた。根元を締め上げられたペニスが、激しい勢いで精液を噴き上げる。
言葉もなくびくびく痙攣する南は、天井を見上げるようにのけぞらせた頭部を俺の肩に乗せていた。絶頂感が退かないのか、蕩けきった瞳を宙に泳がせている。みっちり調教した南の肉体は、ほとんどの女性が一生味わうことのない極限の快楽を味わっていることだろう。おまけに、俺に忠誠を誓ったことで、今までかけていた精神的なブレーキも外れてしまっている。おそらくは、これまでで最高の悦楽が身も心も溶かしきっているはずだった。
ようやく忘我の状態から半ば戻った南の唇を奪うと、彼女は嬉しそうに目を細めてキスに応えた。
ふと視線を下げると、千沙も郁美も、目論見通り南の嬌態にすっかり目を奪われていた。観察すると、二人とも年上の美女の絶頂に当てられて官能を高めている様子が見て取れる。無論、それぞれアナルロッドを尻穴に埋め込んだままである。
「千沙。郁美」
声をかけると、二人はびくっ、と震えて我を取り戻した。
「あ、はい……」
「はいです、御主人様っ」
俺の腕の中では、絶頂の余韻が退ききらないうちから休みを知らないバイブに責め立てられた南が「んっ、んっ」と小さく喘いでいる。俺は射精後の気怠い気分のまま、充分体力が戻ったように見える二人に命令を下した。
「気持ちよくし合ってごらん」
「……?」
「え、それって……」
郁美は表情を強張らせ、千沙は不思議そうに首を傾げる。郁美はわかっているようだが、千沙にもわかるよう、噛み砕いて言い直した。
「愛撫してイかせ合うんだ」
あからさまに直球で指示を出すと、郁美は逡巡していたが、千沙はあっさり「はい、御主人様」と答えて、迷わずすぐ下にある郁美の無毛の淫裂に顔を埋めた。
「ひやぁ!? ちょ、あ、千沙さん……! やめ……くはっ!」
ぴちゃぴちゃと、子猫がミルクを舐めるような音が響く。郁美の腰が逃れようとするように左右に揺れる。だがその表情を見ると、快感に耐えかねて身悶えているだけかもしれない。千沙の舌使いはよほど巧みらしい。
千沙の絶妙のフェラテクを考えれば不思議はないのかもしれなかったが、正直意外だ。
「くあっ……ああんっ……や、あ、は…っ。ふぁああっ……!」
必死に快楽に抗おうと身を固くする郁美。おそらく同性の千沙に弄ばれるのが屈辱なのだろう。あるいは、感じている姿を俺に見られるのが嫌なのかもしれない。
「郁美も千沙にお返しをするんだ。してもらうばかりじゃ不公平だろう?」
俺の命令に従うと言うよりは、与えられる快楽から気を逸らすため、そして千沙の集中を乱して愛撫を止めさせるためと言う感じで、郁美は首をもたげて千沙の秘唇にむしゃぶりついた。
「――にゃぁああ……!」
びくん、と千沙が背を反らす。千沙も発情具合は郁美と変わらない。郁美の目算通り、郁美の口唇愛撫のもたらす鋭い快感に飲まれかける。が、千沙の俺への忠誠心は郁美の計算を超えていた。ちらりと俺に目線を飛ばして自分を取り戻した千沙は、再度郁美の幼い性器に口をつけ、小さな舌で挑みかかっていく。愛撫してイかせ合うという、俺の命令通りに。
「ひぁっ、ああ、そんな、ぁ…。ん、く……んちゅ、んんんっ……!」
驚いた声を上げながらも、負けじと郁美も舌を蠢かせる。

シックスナインで快楽を貪り合う少女達の姿は、実に背徳的で魅惑的な光景だった。眺めるうちに俺のペニスが力を取り戻していく。バイブの振動のせいでもあったが。
敏感なアナルを内側から肉栓に埋められ、南が甘く鳴いて身じろいだ。
くぐもったよがり声を上げながら、郁美と千沙がレズ愛撫に没頭していく。充分に高まった頃を見計らい、俺は追加の指示を出した。
「二人とも、そのまま舐めながら、お尻の方ももう一度始めるんだ」
悦楽で判断力が低下しているのか、郁美もそれほど躊躇を見せず、二人はお互いの菊孔に刺さったままのアナルロッドに手を伸ばす。
「うにゅ……」
「ふぁ……」
最初のときほどの違和感はもはやないだろう。加えて、絶え間なく快楽を掻き立てられながら直腸を擦られて、千沙と郁美は以前よりはるかに官能を帯びた吐息を漏らした。
いきなりアナル性感だけを目覚めさせようとするのは無理でも、他の性感と絡めながら調教すれば、それなりに慣れてくるだろうという目論見である。
「ああ、あああっ、はぁあああっ……」
「にゃああ……あああ……ふはぁあああ……」
しっとりと汗ばみながら、二人は俺の目算通り、次第にアナルの刺激に慣れ始めているみたいだった。
二人がイくまでそれを続けさせ、少し休ませた後、今度はベッドに拘束した郁美に千沙と南をけしかけてみた。
「ちょ、あ、あ、やっ……! ひぁ、あっ、ダメ、ダメですっ! そこやぁ…ひぁんっ! ふわぁああああっ!」
さっきから郁美の切羽詰まった喘ぎ声が絶え間なく響いている。
首輪を着けた三人の奴隷が絡み合う姿は大変見応えがあった。二枚の舌と二十本の指が、まだ十四歳の少女を逃れようのない官能の高まりに追い込んでいく。
「あ、あっ……! ああああっ、ダメ、もう、ダメぇええっ……!」
だが、いよいよ絶頂に追い上げられようとすると、二人の愛撫は途端にポイントを外したものになり、少女を煩悶させた。
「嫌ぁあああっ……ああっ、そんなぁ……!」
南と千沙には、決して郁美をイかせないように厳命してあった。
少し興奮が治まると、二人の愛撫は再び性感帯を責め始める。南と千沙は、同時に郁美の乳首を唇に含んで舌先で転がしつつ、千沙の指が秘唇外縁とクリトリスをなぞり、南の指が膣孔と尿道孔をくすぐっていた。余った手は内腿や脇腹や恥丘や首筋を優しく撫でている。
二人の息は驚くほどぴったりだった。しかもどうやら愛撫の主導権を握っているのは千沙らしい。時折目配せして南に行動を促しているのが見える。何だかなあ。まあいいが。
ねっとりした愛撫が続き、何度も何度もお預けを食わされているうちに、郁美の理性は限界に近付いていった。
「ああああっ! 嫌ぁあっ! もうダメ……お願い、イかせてぇえええっ!!」
ついに、自ら絶頂をねだる言葉を口にする。南は同情に満ちた眼差しで少女の狂態を眺めている。かつては南が同じ目に遭わされ、俺への隷属を強いられたのだ。千沙はちらりと俺に視線を向けてから、何やら郁美の耳元で囁き始める。何を吹き込んでいるのか、郁美ははっと眼を見開いてイヤイヤと首を振るが、クリトリスを摘まれながらさらに何事か言い含められると、くたりと体の力を抜いた。
屈辱と諦念に泣き濡れた瞳で、傍らで一部始終を見物していた俺を見上げる。
「御主人様……お願いします……。どうか……どうか郁美を……イかせて……ください」
声には苦渋がにじんでいる。俺に絶頂を哀願しなければならないのがよほど悔しいらしい。
「郁美。奴隷は自分が気持ちよくなることより、主人を気持ちよくすることを優先するものだぞ? どうも郁美は奴隷の自覚が足りないなあ」
わざとらしい口調でそう言ってやると、郁美は唇を噛んで黙り込んだ。無論、郁美に奴隷の自覚を本気で促すつもりなど最初からない。どうかキミはそのままずっと心からは屈服しないままでいてください。その方が楽しいから。
「まあ、郁美は一番後から奴隷になったから、その辺は大目に見てあげるとして」
期待を持たせるような言い方をすると、郁美ははっと顔を上げた。この間も、郁美を絶頂寸前に留め置くための千沙と南の愛撫は続けられている。
「イかせてやってもいいぞ」
「ああ……ほ、本当に……?」
恥辱を噛み締めながらも、縋るような眼差し。だが俺はさらなる恥辱に郁美を誘うべく、言葉を重ねた。
「イかせてやってもいいが……で、具体的にどうして欲しいんだ? 言ってごらん」
「え。具体的に……って……」
俺の意図を察して、郁美は真っ赤になって言い淀んだ。
それ以上は言わず、じっと待つ。
「ん、く……。あっあ……ひぁ、ああああっ! あ……あああ……また、ぁ……」
千沙と南は俺の命令に忠実に、郁美を頂点間際まで追い込んでは引き戻す残酷な愛撫を続けた。
郁美はまだしばらく粘っていたが、いつまでも生殺しに耐えられるはずもない。焦らし責めに屈し、震える唇を開いた。
「お……お願い、です……御主人様。い、郁美の……ぐちゃぐちゃにとろけた、淫らな奴隷の、お、おマ○コを……御主人様の……おチ○ポで、め、めちゃめちゃに……犯して、郁美の子宮に、たっぷり、せ、精液を注ぎ込んで……御主人様のことしか考えられなくなるくらい、思いっきり、イかせてください……っ!」
淫猥に飾り立てた哀願を、恥辱を押し殺して吐き出す。
やっぱり、賢いな、郁美は。何も言われずとも俺の無言の要求を汲み取っている。
「――よし、いいだろう。たっぷり犯してあげるよ、郁美」
快い嗜虐の酩酊感を味わいながら、俺は拘束された郁美の肢体にのしかかっていく。待ちかねたようにぱくぱく口を開く淫孔に俺のモノの先端を押し当てると、郁美は切なげな吐息をついて体の力を抜いた。
さすがにこれ以上焦らすのは可哀想だ。
俺はぐっと腰を突き出し、一気に郁美を貫いていた。
「あっ……ふぁああああああああああ〜〜〜〜ッ!!」
甘い絶叫を上げ、郁美は瞬間に絶頂に達する。ただでさえ狭い郁美の膣内は、エクスタシーの締め付けで痛いほど肉棒を食い締めてくる。
「……くっ」
気を抜くとすぐにでも射精してしまいそうだ。
郁美が呼吸を思い出すのを待って腰を使い始める。極限まで敏感になっていた郁美の体は、面白いように簡単に何度もオルガスムスを迎えた。引き抜くとき雁がGスポットを擦るとイき、突き込むとき先端が子宮口を小突いてイき、抽送でクリトリスが擦れてイき、しまいにはただ膣襞がペニスに掻き回されているだけでイった。
「はぁああああっ! いぁあああああっ! くぁああああああっ!!」
今や、一突きごとに郁美は軽く達するほどになっていた。
よしよし、この調子。
ちなみに、郁美をイかせまくっているのは、もちろんイジメ――もとい、調教の一環ではあるのだが、ふと思い返して俺のモノでイかせたことがなかったのに気付いたためである。反抗心は残っていてかまわないが、体は俺が与える快楽に従属してくれないと困る。その精神と肉体のギャップが今後郁美で遊ぶのに楽しめるポイントになるはずだからだ。
さらに、そうは言っても、郁美の深層心理には俺への畏怖を根付かせたいと言う狙いもある。と言うわけで、イきすぎて朦朧とした郁美の耳に、腰を使いながら問いかけてみる。
「どうだ郁美! 気持ちいいかっ!」
「いいぃぃっ! 御主人様の、おチ○ポ、いいッ! 気持ちいいですぅっ!」
既に判断力は蒸発しているらしく、ただ感じたままを口にする郁美。
「お前は俺のものだ! そうだな郁美!」
「はっ、はいぃっ! 郁美はぁ……御主人様の、モノ、ですっ! ひぁあああっ、あああっ!」
「お前は、何だ! 郁美ッ!」
ごりごりと子宮口を抉りながら聞くと、拘束された郁美は過剰な快楽に首を振りたてながら、ほとんど反射的に答えた。
「郁美は……奴隷です! 御主人様の、忠実な、性奴隷ですっ! ああああっ、凄い、またイくぅうううううう〜〜ッ!!」
それから何度も似たような質疑を繰り返し、郁美の心の奥に奴隷の自己認識を植え込んでいった。多分我に返れば元の態度に戻るだろうが、それでいいのだ。でないと郁美に羞恥と屈辱を味わわせ続けられなくなってしまう。そして、そうであっても俺の命令には逆らえなくなって欲しい。これはそのための予備調教だった。
「……くぅううううっ!」
「すっ、凄ッ……! 来る、凄いのが……! あああああっ、ひはぁああああああああッ!!」
俺が郁美の膣奥にたっぷりと白濁液を注ぎ込むと、郁美は今までで最大の絶頂に放り込まれ、喉を振り絞ってよがり泣いた。そして強烈すぎる快楽の爆発に耐え切れず、意識を失ったのだった。
――そんなこんなで、この日は休憩や食事を取りつつ、一日三人を調教して過ごした。えらく退廃的な休日の過ごし方だったが、まあ充実はしてたな。
夕食後、愛用のボロい軽自動車を引っ張り出し、三人を送っていくことにする。南と郁美は駅、千沙は自宅だ。と、その前に――。
「千沙、郁美。お土産だ」
二人に紙袋を手渡す。
「わあ。何ですか? 見ていいですか?」
嬉しそうに千沙が言うのに頷きを返す。紙袋の中をのぞいて、千沙は何とも言えない表情になった。それを見て、不審そうに袋の中を検める郁美がぴきりと固まる。
中にはローションと、様々な形とサイズの、アナルロッド、アナルパール、アナルバイブなどが各種取り揃えられている。
「宿題だ。自分でアナルの拡張と調教をしておくこと」
そう命じると、郁美は嫌そうに、千沙はよくわかっていなさそうな笑顔で、共に頷いた。
「――はい、御主人様……」
「はいです、御主人様」
俺は三人を促して軽に乗り込み、ハンドルを握った。
今日はたっぷりリフレッシュできたし、明日からまた原稿頑張ろう。ちなみに今夜はもう無理。さすがに疲れたよ……。
満足はしたけどな。
|
![]()
![]()