|
第六章 ある同人即売会の風景
朝8時半。俺は東京湾埋立地の某展示場にいた。
今日は10月の最終日曜日。そう――月末恒例、言わずと知れたこみっくパーティーの開催日だ。こんなのは「社会の基礎知識」なので知らない人などいるわけはないと思うが、一応説明しておくと、こみっくパーティー(公式略称:こみパ)とは日本最大の――イコール、世界最大の同人誌即売会である。同人誌即売会とは、自筆のマンガ・小説・エッセイその他(まあ主にマンガ)を印刷・製本して作った同人誌を持ち寄って売り買いし合うイベントのことだ。8月と12月、夏と冬がもっとも大規模で、日に15万人もの参加者が集まる。無論その全員が本を作るわけではなく、大半は買い物専門のいわゆる一般参加者だ。対して本を作って売る参加者をサークル参加者と呼ぶ。
すなわち、俺がそうだ。
サークル参加者には事前に準備会からサークル入場チケットが3人分送付されてくる。1つのサークルにつき3人までが開場時間前に会場内に入場でき、開場までの間に事前準備を済ませることになっている。前回までは俺の1人サークルだったために、あらゆる準備を1人でこなさなければならなかった。……まあ、前回の場合は準備段階で何もかも終わってしまったわけだが……。
だが今回は一味違う。
夏冬ほどではないと言え、それでも雲霞の如く湧き出し行列を作って座っている何万人もの一般参加者の列を遠くに見ながら、俺はサークル参加者入場口へと足を進めた。コートの懐から3枚綴りのサークルチケットを取り出し、1枚切って、傍らを歩く少女に渡す。
少女は無言のまま受け取り――俺と共に会場に入った。
尋常でない広さのホールには、これまた尋常でない数の長テーブルが並べられていた。誇張でなく、見渡す限りに。
何も知らない人にいきなり見せたら、目を剥いて絶句しそうな光景ではある。
売り手で参加する同人サークルは、1サークルにつき長テーブル半分の販売スペースを割り当てられている。延々と果てしなく並ぶテーブルの列を初めて見たときには、自分のスペースを探し出すことすら至難に思えたものだが……。実際は一定のルールに沿って置かれており、それさえ把握すれば、あらかじめサークル毎に割り振られた配置番号を頼りにたどり着くのはさして困難ではない。まあ――少なくとも、開場前の段階なら。
「よし――ここだ」
ブロックナンバー、テーブルナンバー、テーブルのどちら側か、を記した配置番号を元に自分のスペースに到達する。同じテーブルを使うお隣のサークルさんはもう来ていて、出展準備を始めていた。反対側の隣はまだのようだ。
「隣同士ですね。今日はよろしくお願いします」
「あ、どうも。こちらこそよろしく〜」
隣のサークルの人と愛想良く挨拶を交わし、島(並べたテーブルで長方形を作ったエリア)の内側に入る。この辺りの人々はみんな、俺の同志と言っていい。仲良くするのに努力は要らなかった。
各サークルは無作為に配置されているわけではなく、申込書に記載した情報に従って、なるべく同一ジャンルで固まるようスペースを割り振られている。俺の本のジャンルは『男性向け創作(要はエロ)・マンガ・オリジナル・調教モノ』ってところか。つまりは俺のスペースの周辺には、俺のと同じような内容の本ばかりが並べられていると言うことだ。――購入者の行列が発生するような人気サークルの場合は、この限りではないが。そういうサークルはホールの壁際に沿って配置され、行列によって通行が妨げられにくく配慮されている。
さて。俺にとっては2ヶ月振りのこみパだ。気合い入れていくぞ〜!
「それじゃ、準備を始めるか――郁美」
「……はい」
俺と対照的に、まったくやる気の感じられない暗い眼差しで、傍らの立川郁美は小さく答えた。
開場までの間に、やるべきことはいくつかある。
同人誌の搬入、販売スペースのディスプレイ、釣り銭の用意、スタッフに見本誌を提出して内容をチェックしてもらうこと、など。
俺は郁美に手伝わせ、テーブルの半分に用意してきたクロスをかけ、これまたあらかじめ作って来ていた、サークル名と配置番号を記したポップスタンドを立て、新刊用の値札や簡単な内容表示のミニポップなどを用意し、着々と準備を整えた。
今回の新刊ははっきり言って自信作だった。今までより部数が多いので完売するかどうかはわからないが、そこそこ売れる自信は充分にあった。
あったのだが……。
肝心要の、本がまだ来ない。
おかしい。9時には来るという話だったのだが……。
ただいま9時40分。開場まではあと20分しかない。
俺達より遅かった反対隣のサークルの人達も既に入場し、本を並べてすっかりディスプレイを終えている。
サークルスペースにはパイプ椅子が2脚、備えつけられている。テーブルの売り手側に、俺と郁美が並んで座っていた。そう。今回郁美は、俺のサークルの売り子としてイベントに参加しているのだ。――参加させた、と言うのが実情だが。
郁美は髪をいつもの特徴的なツインテールではなく、ゆるい編み下げにしている。着ているのはゴスロリ風のエプロンドレス。ちなみにフリルもレースも、エプロンまで真っ黒だ。頭にはヘッドドレスと言うかブリムと言うか、そんなものを着けている。これも黒。顔には細いフレームの丸眼鏡。度は入っていない。――まあ一言で言うならば、黒いメイドさんだった。数少ない色彩は、襟元を飾る真っ赤なリボンタイと、それを留める楕円形の澄んだグリーンのブローチ、それと三つ編みの先っぽに結んだ、タイと同色のリボンだけだ。
俺はというと、襟を高く立てたダークブラウンのコートと目深に被った同色のソフト帽、という装い。胸ポケットには赤いバラの造花を挿し、首からは真っ赤なネクタイがだらしなく垂れ下がっている。コートの中にのぞくシャツの襟は黒。黒シャツに赤ネクタイと言う気障ったらしい装いだった。
俺のこの格好は、実は変装であり、コスプレでもあった。しばらく前の、かなりマイナーだが一部に熱心なファンがついた『ラグサーガ』と言うゲームのキャラの服装を模している。――好きでやっているのではない。前回のこみパの騒動の再現を避けようと言う試みだった。これなら千堂と間違えて難癖つける奴もいないだろう。ちなみに郁美も同じゲームの、俺のキャラのパートナー役を務める無表情系メイド少女の服装である。こちらは、郁美が18禁同人誌の売り子をしているのが彼女の兄にバレないようにとの配慮だ。どうやらあの男、頻繁にこみパを徘徊しているらしいので。
色々考え合わせた結果こうなった。ことこみパ会場内に限っては、ヘタな変装なんかより、素顔がわかりにくくなる類のコスプレの方が、よっぽど周囲に溶け込みやすいのだった。
――え? 何でそんなマイナーなゲームのコスプレなのかって?
いいじゃん、俺好きなんだよあのゲーム。これならしっかり顔も隠れるし。
……いや、だから、好きでやってるんじゃないってば。
まあそれはそうと。そんなわけで、準備万端整っているのに、売るべき本だけがないという本末転倒な事態に陥っていたのだった。
じりじりしながら座っていると、遠くから物音が近付いてくるのが聞こえた。
――ガシャーン
――にゃああああっ!?
――ズドーン
――ご、ごめんなさいですぅうう
――ドッシャーン
――にゃ、にゃああああっ!
な、何だかえらく嫌な予感が。いや、予感と言うより確信に近いが……。
およそ十秒後。
漠然と予測した通り――梱包した本の山を積み上げた台車が、俺のスペースに突っ込んで来るのを、俺は諦めに似た気分で見上げていた。
「……あの……見本誌の回収を……」
おずおずと女性の声がかけられた。ひっくり返った長テーブルを戻し、隣のサークルスペースの人達と協力して(と言うより謝りつつ)大慌てでディスプレイをやり直しているところだった。誰にも大した怪我がなかったのは幸いだったな…。
振り向くと、優しげな眼鏡美人が困惑した表情で立ち尽くしていた。こみパスタッフの青い制服がよく似合っている。
「おはよう、南さん」
「お……おはよう、ございます。……和巳、さん……」
視線を逸らし気味に挨拶を返してくる。まあ、ここで「御主人様」とか言うわけにはいかないものな。その呼び方で許してあげよう。
とか思っていたら。
「にゃあああ〜、ごめんなさいです、御主人様ぁ〜!」
小柄な少女が俺の背中に抱きついてきた。慌てて周囲を一瞥する。郁美と南さんの頬が一瞬強張るのが見えたが、他の連中はどうやらそれどころではないようで、少女のセリフを聞き咎めた様子はなかった。
「こら、千沙。ダメだろ、ここでは」
「――あ、はい。よそでは『和巳おにーさん』でした」
「よし」
がしがしと強めに髪を撫でてやると、千沙はくすぐったそうな表情で目を細める。それからはっと気を取り直して、眉をハの字にした。
「にゃあああ〜、ごめんなさいです、おにーさぁん〜!」
「いや、それはもういいから。――郁美、ちょっと」
「――はい」
作業を中断して歩み寄ってくる。
「ちょうどいいから紹介しておくよ。こちら、こみパスタッフの牧村南さん。この子は印刷屋さんの塚本千沙ちゃん。こっちは今回ウチのサークルの売り子を頼んだ立川郁美ちゃん」
にやりと笑って小声で付け加える。
「――みんな俺の奴隷だ」
はっとして他の二人の顔を見比べる南さんと郁美。二人が浮かべているのは、驚きと悲哀の混じった痛ましげな表情だった。対して千沙は――。
「あ、そうなんですか! えーと、南お姉さんと、郁美お姉さんですね☆ これからよろしくです〜」
悲痛の「ヒ」の字も見られない満面の笑顔で、元気に挨拶をかましてくれた。
「え? え、ええ……」
「よ――よろしく……」
南さんと郁美の顔には戸惑いの色が濃い。何の屈託もない千沙の態度に強烈な違和感を覚えているのだろうとは、容易に想像できた。
俺はこっそりとコートのポケットに手を忍ばせた。
「ところで南さん。――ちゃんと、言った通りにして来た?」
「え――は、い……きゃうっ!?」
眉を曇らせて俯きかけた南さんは、突然悲鳴を上げて背を跳ねさせた。
「あ、あ…ダ、メ…それ、やめ、やめて…ぇ…」
俺につかまって爪先立ちになり、歯をかちかち鳴らしながらかすれ声で囁く。頬は急速に桜色に染まりつつあった。苦しげなその表情は、だが、至近で見るとやけに色っぽい。

「お、お願い…です…。ここでは……こみパでだけは……許して、ください…」
すがるような眼差しには激しい苦悩が浮かんでいる。よほどこみパ会場で嬲られるのが辛いらしい。
「それじゃ、どうして俺の言う通りにしてきたの? 南さん」
「だ、だってそれは……」
次第に蚊の鳴くような声になっていく。最後のセリフはかろうじて聞き取れた。
「――御主人様の、命令…だったから……」
…………。
うわ、可愛い。
耳まで桜色にして俯く南さんを思わず抱きしめかけ、慌ててその手を引き離す。危ねえ。一瞬場所と状況を忘れそうになった。
健気なセリフに免じて、俺はバイブ機能付アナルプラグのリモコンをオフにした。今日自分で入れてくるようにと命じて、事前に渡しておいたものだ。
はぁあ〜、と安堵の吐息をつく南さん。
「命令どおり入れてきたから、今は許してあげるよ」
「い、今は、って……」
俺のセリフの含みに気付き、南さんは表情を引きつらせた。
「それはそうと、見本誌の回収だったよね」
さらりと流して話を元に戻した。
「あ、はい……」
不安そうな顔の南さんをそのままに、千沙が配送して来た荷物の包装を破って本を1冊取り出し、ぱらぱらとめくってチェックする。うむ、ビバ印刷技術。素晴らしきかな機械製本。科学文明って偉大だ。ありがとうつかもと印刷……とは思いにくいのは、最後に千沙が大ポカをやらかしてくれたからだが、印刷そのものは極めて美しい。コピー誌とは比べ物にならない、この黒ベタのインクの乗りよ。
「――と言うわけで今回からはオフセットです」
ぽん、と南さんに手渡した。
「は、はい。それではチェックします。…………。――え…!?」
ぱらぱら、と最初のうちは手際よくページをめくっていた指先が、ほどなく凍ったように動きを止めた。
「な――こ、これ……」
今回の新刊、その内容は――。
こみパスタッフの眼鏡美人、マナミさんが拉致監禁され、執拗なアナル調教で性奴隷に堕とされる、と言う……。
要するに、南さん自身のアレを元に再構成したものだった。調教の流れもかなり忠実かつ緻密に再現していた。違いは、ヒロインがこみパスタッフの制服姿で調教されるところくらいだろうか。
そう言う意味では、今回はジャンルに偽りがあったかも知れない。オリジナル創作ではなくドキュメンタリーに近い……が、無論そんなことは黙っていればわからない。
マンガキャラっぽくアレンジ&デフォルメしてはいるが、ヒロインは明瞭に南さんの面影を残している。ちなみに、ヒロインのフルネームは「ミキムラマナミ」さんだ。言うまでもないが、見る人が見れば南さんがモデルなのは一目瞭然だった。わかる人でも、実在のこみパスタッフをモデルにした妄想マンガとしか思わないだろうと言うのも、確実ではあったが。恥毛の生え方まで本人とそっくりに描いてあることなど気付くヤツがいるわけもない。――本人以外には。
「あ……あ……っ」
俺は口元に意地悪い笑みを刻みつつ、かたかた震えて固まっている南さんにそっと囁く。
「――どうしたの、南さん? ちゃんと消しも入ってるはずだし、内容に問題はないでしょう?」
まあ一般常識だとは思うが、消しとはベタやモザイクなどで性器の直接描写を避けることを言う。同人誌でも、消しの入っていないブツを領布すると『ワイセツ図画の販売』に当たるとして摘発対象になり得る。一介の同人えろマンガ描きとしては、そんなもん規制することに何の意味があるのやらさっぱりわからないのだが。ちなみに創作における性表現そのものを規制しようとか言う偏執狂的な規制案も実際に存在するが…。こっちに至っては発案者の正気を疑うより他、反応のしようがない。
ま、それは置いておいて。
マンガでとは言え、自らの痴態を不特定多数の参加者に知られてしまうと知った南さんは、なかなか硬直状態から戻らない。このマンガを見られないためには販売停止処分にでもするしかないが、そんなことをすれば後で俺にとびきりきついお仕置きを受けるのは火を見るより明らかだ。どうすることもできず、彼女は俺の視線を避けるように俯き、必死で平静を装った声を絞り出した。
「は、はい……結構です……見本誌票も…貼ってありますね。――では、これで……」
思いもかけない羞恥責めに、困り顔を朱に染めた南さんは、逃げるように小走りで去っていった。て言うか逃げたな、あれは。やや足取りがぎこちないのは、はめっ放しのアナルプラグに菊孔を刺激されるせいだろうか。
いじめられた子供のように半泣きで駆け去る南さんを見送って、俺は自然に湧き上がるにやにや笑いを抑えつつ、自分のスペースへ向き直った。ようやく本も到着したことだし、早いとこ出展準備を済ませないと。
「これはこっちでいいですか?」
「あ、待って、千沙さん。そんなに積んだら……」
「にゃああああっ!? 崩れるです〜っ! にゃぁ…お、重い、重い、重いぃい〜〜!」
「あ、ちょ、待……あ、あ、あ……」
ぐら〜……どどどどんっ!
「にゃあああああっ!!」
「きゃああああっ!?」
…………。
仕事、増えてるんですけど……。
『……ただいまより、第××回こみっくパーティーを開催いたします』
女声のアナウンスが流れると共に、わぁっと会場内が拍手で満たされる。午前10時。こみパの開幕である。
俺と郁美は、同調して拍手をするでもなく、ぐったりとパイプ椅子に座り込んでいた。
何とか超特急で出展準備を整えた疲労も無論あったが、最後の5分で、千沙が『ご迷惑をおかけしたので、何か手伝わせて欲しいです。千沙、頑張るですから!』とか、極めて有難迷惑な誠意を発揮してくれたのを、郁美と二人がかりで必死になだめすかし、説得して思いとどまらせた精神的疲労も大きかった。何と言うか――千沙の純粋な善意が「これでもか」と伝わってくるだけに、傷付けずに断るのにやたらと神経を消耗してしまった。
拍手が静まると、一拍置いて地鳴りのような重低音が聞こえ始める。
「会場内は走らないでくださーい!」
「走らないでー!」
スタッフの張り上げる声が切れ切れに響くが、社会性ゼロの徹夜オタクどもが一秒でも早く大手同人の列に向かう傍若無人な突進を留める効果はほとんどない。
「走んなドアホ!!」
「走っちゃダメですの〜!」
とか言う声が微かに聞こえ、直後にずどん! と重い炸裂音と共に吹き飛ぶ有象無象の人影が彼方に見えた気がしたが……見なかったことにしとこう、うむ。君子危うきに近寄らずである。
自意識の肥大化したルール無用のダメオタ軍団の怒涛が流れ去ると、最低限他人に迷惑をかけない分別くらいは備えた少しマシな連中がやや早足で流れて来る。彼等の目標も大手同人である。何故なら、時間が早いほど行列が短く、少しでも早く目的の同人誌が購入できればその後の行動も前倒しで早く進むからだ。言い換えれば、分刻みで行動するほど多数のサークルを回って買いまくる、と言う事である。――まあ、多少マシとは言っても所詮同人オタ。社会的にダメだろコイツは、と言う部分には根本的に違いはない。
何やら特にディープな即売会参加者をこき下ろしているように聞こえるかもしれないが、この辺自虐入っているのでお目こぼし願いたい。…って、誰に言ってるんだ俺は。
まあとにかく、何が言いたいのかと言えば、ウチみたいな零細無名サークルは、概して開場後1時間くらいは暇だってことだ。うちの主客層である、落穂拾い&無名サークル回りをする連中が徘徊するのは大体昼前くらいからか。
以前はウチの本は全てコピー誌だった。例えば36ページの本を作るのに、1冊分印刷(コピー)するだけでも18回のコピーが必要である。この場合、10冊作るだけでもコピーの回数は180回に達するわけなので、そうそう何十部も作れないのは自明だろう。そんなわけなので、少数だがこんな嬉しい人もいる。
「(中身を見もせずに)新刊1部ください! ――あ、今回オフなんですね。いつものコピーで、早く売り切れたらまずいと思って、一番に来ちゃいました」
「毎度ごひいきに。前回はちょっと事故があって本を売れなかったんで、今回は気合い入れました」
「お、それは楽しみですね。これからも期待してるんで、頑張ってください」
「ありがとうございます!」
……ホントにありがたや、常連さん。それじゃ、と手を上げて去っていく名前も知らない同好の士を笑顔で見送る。うむ、やっぱ読み手さんとの触れ合いがあると嬉しさもひとしお。今後の活動にも熱が入ると言うものだ。
感慨に耽る俺を、郁美が何か言いたげな複雑そうな目で見つめていた。
そんなこんなで、まばらに何人かの客が訪れ、中身を見て行ったり買って行ったりしてくれる。
郁美も渋々ながら売り子を勤める。次第に慣れ、緊張が解けてくると、固いながら戸惑いがちな微笑まで見せるようになってきた。そうなると素地のいい美少女だけあって、ぱっと花が咲いたように華やかな印象になる。可憐なゴスロリメイド少女に惹かれて寄ってきたような客も何人かいた。郁美は、積極的に呼び込みまでするようなことはないが、見るからに暑苦しいような同人オタクに話しかけられても嫌がらず、丁寧に応対している。態度だけ見ると、実年齢より2〜3歳、あるいはそれ以上に大人びて見えた。
前述のように元々客の多い時間帯ではないのだが、美少女売り子の威力もあってか、そこそこ途切れずにウチのブースをのぞいていく人がいる。いくつかの理由から俺はあまり手を出さず、もっぱら郁美に接客させるようにした。早目に売り子業務に慣れさせたかったのと、買い手のヤロー共(ウチの客層は、言うまでもなく100パーセント男性だ)も可愛い女の子が相手の方が嬉しかろうと思ったからだ。激エロの本を中学生の女の子から買うのに抵抗があるような可愛い神経の持ち主は、ウチに来る買い手にはいない(断言)。――言い切れてしまうのも微妙に寂しい気がするが、まあ事実なので諦めよう。
一時客が途切れると、郁美はふうっと息を吐いて肩の力を抜いた。俺に強制されて始めた同人誌の売り子だったが、命令に従属すると言う以上の熱意を持って取り組んでいるようだ。どうやら、新奇な体験に楽しさを感じ始めているらしい。
だが俺としては、郁美を喜ばせるためだけに売り子をやらせているわけではなかった。
そろそろ頃合いか……。
俺はさりげなく手を動かし、郁美の腰の横に触れた。衣装にふんだんに使われているフリルのため、多少の接触には気付かないようだ。俺はそのまま手を動かし――するり、と郁美のスカートの中に差し込んだ。磁器のように滑らかな郁美の腿の感触が手に触れる。
「――――!?」
びくっ、と震える郁美。一瞬だけ俺に脅えたような、あるいは咎めるような視線を向けるが、すぐに唇を噛んで目を逸らし、俯いてしまう。
ひらひらの多いデザインのスカートのサイドには、触ってよく調べないとわからないが、中へと続くスリットが作られていた。少し大き目の、底の抜けたポケットのようなものだ。
差し込んだ手を、俺は郁美の足の付け根へと伸ばした。下着はつけないよう命令してある。俺の指に、郁美の無毛の恥丘の感触が触れる。そのまま下へ滑らせ、幼い縦割れに直接指を這わせた。
「んっ……」
押し殺した喘ぎが微かに聞こえる。下着をつけさせなかったことで予想はしていただろうが……それでも実際にこんな場所でそんなところを触られると本気で考えてはいなかったのか、がちがちに緊張して、硬直が解ける様子がない。人の溢れたイベント会場で悪戯される羞恥は格別のようで、郁美は俯いたまま顔を上げようとしない。
先週の日曜に無残な凌辱を加えてから、郁美には何もしていない。男に――特に俺に秘部を触れられるのは、郁美にとってただ極限の苦痛を思い起こさせるだけの体感のはずだ。
今日は、それを崩すのが目的の一つである。
俺はできるだけ優しい動きで、郁美の秘所をそっと指でなぞっていく。前の時に快感すら苦痛の呼び水に使ったせいか、少女の体は緊張し続けている。この段階ではしょうがない。郁美の反応は棚上げして、肉体に性的刺激を与えていくことに意識を集中した。
「くっ…んんっ……」
蚊の鳴くような呻きをBGMに、俺は慎重に指先を動かし続けた。やがて根負けしたように郁美の秘裂が少しずつ潤み始める。当たり前の生理的反応ではあるのだろうが、頑なな郁美が俺を受け入れ始めているような気分で、何となく嬉しい。――自分のことながら、実に単純だ…。
郁美自身の潤滑液の助けを得て、俺は指の動きを少しずつ強めた。すべすべした皮膚を撫でていた指先の感触が、ぬるぬる滑るものに変わる。頃合いを見計らい、俺は人差し指と薬指で秘唇をくつろげ、中指でそっと粘膜に触れた。だいぶこう言うこと器用になってきたな、俺も。手探りでやってんのにな。
「――――っ…!」
秘粘膜に直接触られた郁美は、きゅっと肩をすぼめ、唇を噛んだ。小さくなって震えている姿は脅えた小動物を思わせ、ちょっといじらしい。
敏感な姫肉をいたわるように、力を加減しながら愛撫を続けると、膣襞は次第に熱く柔らかくなり、潤いも急速に増してきた。
ふっ、ふっ、ふっ、と小刻みに浅い呼吸を繰り返す郁美の肩は、小さく震えている。
くるくると指先を回して膣口をほぐし、おもむろに膣内に挿入していった。
「ひぅ………っ!」
じわじわと胎内を侵蝕する異物に、郁美は押し殺した悲鳴を洩らした。
処女を強奪してから一週間。傷口はもう塞がっていると思うが、処女肉を掘削貫通された強烈な記憶は簡単には消えないのだろう。かちかちと奥歯が触れ合う音が微かに聞こえ、全身にいっそう力が入ってがちがちに固くなっている。膣口だけでなく膣肉もきゅうっと窄まり、俺の指にぴっちり食いついて来た。愛蜜のぬめりを借りても楽に指を動かせないほどきつい。
俺はちょっとずつ拡げるように、微妙に指先を抜き差しし始めた。郁美の発育しきっていない未熟な襞の畝が、指紋に引っかかるのをはっきり感じるほどの微弱さで。
「はぁあ……っ」
明らかに脅えのためではない慄きが郁美の背を微かに震わせ、懸命なまでの締め付けがふっと弛んだ。少しだけ自由に動かせるようになった指の腹で、郁美の膣道を慎重に探っていく。膣襞の隅々まで触れてあらゆる反応を確かめるように。いわば触診だ。
「ん、ん……」
膣内の異物感にも慣れてきたのか、郁美はほんの少しだけ、全身に入っていた力を抜いた。こわばっていた表情もちょっとだけ弛む。と――まるでそれを見計らっていたような絶妙のタイミングで、声がかけられた。
「――すいません。いいですか?」
慌てて顔を上げる郁美。テーブルの向こうで愛想笑いを浮かべる兄ちゃんが、ウチの本を指さしている。俺は何も言わず、視線で郁美を促した。
「あ、は、はい! どうぞ、ご覧になってください」
「それじゃ、失礼して……」
彼は1冊を手に取り、ぱらぱらとめくって内容を確認していく。俺の経験上から言えば、絵柄と話の傾向を確認し、充分趣味に合うと判断すれば財布と相談して購入を検討することになる。印刷部数が多いほど1冊当たりの単価が減少するのだが、中堅どころのサークルでも同人誌の印刷数などせいぜい数百部。数千部から数万部も刷るような一般の商業出版物に比べれば、ページ数当たりの単価はどうしても割高にならざるを得ない。ぶっちゃけて言えば、同人誌は薄いワリに高いのだ。ちょっとでも欲しいと思った本を全て買っていたりしたら、いくら予算があっても足りない。自然、慎重な吟味が必要になる。
――予算度外視、分秒を争って駆けずり回るダメオタどもはこの限りではないが。
「――ひ…!」
強張った営業スマイルを浮かべて緊張していた郁美が、鋭く息を飲んで小さく跳ねた。
「……?」
不審そうに顔を上げたお客様に、郁美は慌てて何でもないと言う素振りで手を振る。一瞬首を傾げつつも、彼は本に視線を戻した。それを確認してから、郁美が責めるような縋るような視線を俺に送ってきた。
素知らぬ顔で、俺はまた指を動かして郁美の膣肉を抉った。
「…………っ!」
声にならない悲鳴が聞こえた気がした。
一度弛みかけていた膣道は、緊張のためだろう、きゅうっと痛いほどに俺の指を食い締めている。そのため余計に、ほんの僅かな動きでも数層倍に増幅されて郁美を苛んでいるようだ。
「すいません。これいくらですか」
「は、い……1部700円に、なります……」
答える郁美の声は微妙に震えている。
経費を印刷部数で割った値が同人誌の原価になる。経費に何を含めるかでも話が変わってくるが、俺の場合、主として印刷代に、こみパ参加費と交通費を含めた金額で算定している。この原価を下回る値段をつければ言うまでもなく赤字だ。原価と売値の差額が純利益となるわけだが……当然あまり高い値をつければ売れ行きが落ち、売れ残りが出るのでその分売り上げが減る。ま、今さら言うまでもない商業原則の初歩だが。
商売でやっているのではない趣味の同人活動なので、俺としては、完売すれば多少は利益が出るかな、と言う程度の、原価ギリギリの価格設定をしていた。それでもこの値段なのは、ページ数が多く印刷部数が少ないためだ。何しろ今までコピーで細々とやってきたので、印刷してどの程度売れるのか予測できず、勢い部数も抑え気味にせざるを得なかったのだった。
……え、ページ数が多いのは何故かって? いやほら、前回アレで本が出せ――もとい、売れなかったんで、今回頑張りすぎたってゆーか。……すいません、描き過ぎました。
郁美は差し出された千円札を受け取って、お釣りの百円玉を拾い上げようとするが、指が震えて上手くいかない。やっとのことで3枚手に取り、同人誌と一緒に手渡す。
「あ、ありがとう……ございました…ぁ……っ」
恥ずかしさに上気した頬で、必死に上辺を取り繕って客を送り出す郁美。やっぱ、年齢に似合わない驚異的な精神力してるよなあ。その彼女が意を決したように、小声で抗議してきた。
「御主人様……ダメです……やめて、ください……」
「――どうして? 気持ちよくないかい?」
「そ、そういう問題じゃないでしょう。こんなところで……。バレたら、御主人様だって困るはずです…」
何だか物言いが妙に理性的なのが面白い。
「なあに。郁美が上手いこと何もないフリを続ければバレないさ。――頑張るんだぞ」
無責任に応援してやりながら、指先を微妙に蠢かし始める。
「そんな……あくぅ…っ…!」
とにかくしばらくは、郁美に徹底的に羞恥と快楽を味わわせてあげるのは既に決定事項なのだった。
「ほら、次のお客だぞ」
指をひねりながら囁く。膣肉が巻き込まれてよじれる感触にかすかに身悶えつつ、郁美は慌てて顔を上げた。
「い、いらっしゃいませ、お客様。――どうぞ、ご覧になって行ってください……」
嬲られながらも、郁美の接客はかなり板についたものになってきている。順応が早い。やっぱり頭いいわ、この娘。
テーブル越しに郁美が相手をする見知らぬ客の眼前で、その蜜壺を弄ぶ。愛液の分泌量は加速度的に増している。他人の目にさらされながら嬲られることに慣れつつある――どころか、倒錯的な愉悦すらをも覚え始めているように思えた。郁美自身がそこまで意識できているかどうかは知らないが。高い知性と矜持を持つ女ほど、かえって精神的なマゾ性は仕込みやすいとか聞いたことがあるが、もしかしたら郁美もそう言うタイプなのかもしれない。
ふむ……郁美には野外調教を多くしていこうかな。他人の目を感じただけで発情する、露出マゾの体に躾けてやったら、面白いかもしれない。まあそれは今後の課題だが。
俺はあくまで優しく穏やかな――言い換えればバレにくい、微妙な愛撫を心がけ、郁美の性感をとろ火であぶる作業に没頭した。
30分ほどもそうして嬲り続けると、郁美は欲情の証を隠し切れなくなり始めたようだった。頬を桜色に染め、瞳はとろんと蕩け、薄めの唇は常時小さく開き、熱く深い吐息を洩らす。時折こくりと唾を飲み、甘い鼻声をかすかに洩らす。指先は細かく震え、同人誌やお金のやり取りにも必死だ。中学生ながら、その横顔は充分に「女」を感じさせ、かなり色っぽくもある。
――驚くべきは、この期に及んでも郁美の取り繕う「平気なカオ」が致命的な破綻をきたしてはいないことだった。尋常な精神力ではない。本気で感心してしまった。まあ、その分嬲り甲斐があるけど。
だがしかし、後天的に育んだに違いない驚異的な自制心をもってしても、いい加減限界が近いようなのははっきりしていた。
こっちもう指の皮が相当ふやけてるし、ずっと同じような姿勢でいるためあちこち疲れてきてたりするので、そろそろ一区切りつけたいところだ。
早朝組の入場は大体終わったものと見えて、落ち着いた感じの参加者の姿が増え始めていた。つまりはウチの客の増え始める時間帯と言うことだ。さらに言えば――そろそろ郁美一人では手が足りなくなりかけていたりする。行列ができるほど混んでるわけじゃないが、まだ多少不慣れな上に他のことに気を取られかけている郁美に、複数の客を一度に捌くだけの余裕はないようだった。
郁美の胎内からは熱い蜜が絶え間なく湧き出してきている。屈んだり腕を伸ばしたりするときにびくっと小さく震えるのは、勃起した乳首が布地と擦れて刺激されるためだろう。充分以上に出来上がっている郁美にトドメを刺すべく、俺は指先に神経を集中した。
「すいません、1部ください」
「あ、こっちも」
「は、はい、ちょっと待ってくだ――ひぅ!?」
郁美は鋭く息を飲んで、本とクッキー缶(小銭入れに使用)を往復していた手を止めた。膣孔にぬめり入った俺の指先が、これまでの半時間で発見、あるいは新たに開発した郁美の特に敏感な性感スポットを集中的に刺激し始めると同時に、今までまったく触れなかった急所――まだまだ未発達だが精一杯充血して尖り立ったクリトリスを、親指の腹で転がしたのだ。
たっぷり30分かけて蓄積された欲情に点火するにはそれで充分すぎた。必死で耐えようと身を強張らせる郁美の制御を離れて、官能のとろ火で煮込まれた肉体が瞬時に崩れ、全身に快楽の火を巡らせていくのが明確に感じ取れる。
「…………――――〜〜〜〜っっっっ!!!!」
ぶるぶるっと身を震わせて、顔を真っ赤にした郁美はついに絶頂に達していた。
――それでも声を上げずに耐え抜く辺り、大したものだと言わざるを得ない。
「はぁ――――っ、はぁ――――……」
深く息をついて快感の残響に震える郁美を、客達が怪訝そうな眼差しで見つめている。さすがの郁美も強制的に押し上げられた快楽の頂点の余韻の中では、外面を取り繕うどころではないようだ。

最後に内側と外側、中指と親指でクリトリスを軽く揉み潰すように可愛がって、郁美のスカートから手を抜いた。
「はひ…!」
その刺激が気付けになったか、郁美はびくんと反応して顔を上げ、慌てて左右を見回した。一瞬意識が飛んでいたらしい。衆人環視の元で絶頂を極めさせられた事実に気付くと、羞恥のあまりだろう、熟れたリンゴのように真っ赤になって俯いてしまった。
一時的に機能停止状態に陥った郁美に代わり、ハンカチで手を拭いた俺は満足感と共に接客をし始めたのだった。
ぱっと見携帯に似た機械を手に、俺は会場内をゆっくり移動していた。一歩遅れて、黒い可憐なゴスロリ衣装をまとったメイド少女が続く。ゆっくり移動しているのは、それしかできないからだ。広い会場だが、それでも無数の机を並べた上に数万人もの人間を詰め込めば、通路部分の人口密度はただごとでは済まない。なるべく広い通路を選んで歩いてはいるが、時には人波を掻き分けるようにしなければ望む方向へ動けないこともある。
「郁美、大丈夫?」
「……大丈夫です。御主人様……」
ただでさえぞろっとした衣装を着ているのだ。人が多い場所での移動はその分大変だろう。病み上がりの上、元々体力あまりなさそうだし。背、低いし。そんなわけで郁美がついて来れるよう移動速度を遅めにしているのも、ゆっくり動いている理由の一つではある。
ちなみに、南さんや千沙と違い、郁美には公然と「御主人様」と呼ばせている。いや、メイドだし。この衣装でなら、この会場内に限っては、その呼びかけを不審に思われることはまずない。
手にした機械の画面には光点が一つ浮かび、俺達が歩を進めると次第に画面の中心に近付いてくる。大器からレンタルした品で、範囲は狭いが高精度の探知機――別体の発信機とセットの受信機――だそうだ。
――ちなみにサークルスペースの方は、俺の本を買いに来た当の大器を捕まえて店番に任命してきた。いつもながら便利な、もとい、頼りになるヤツ。しっかり頼むぞ大器。
ホールの一番角近くに来ると、光点はほぼ中心の位置になった。
「……こちら、最後尾ではありませーん! 『CAT or FISH!?』最後尾は、あちらの列の先――ホールの外となっておりまーす!」
大手サークルの列整理のため、声を張り上げるこみパスタッフを見つける。……大手だったら、列整理用の人員くらい自前で用意しとけばいいのに……。よっぽどトモダチいない作家なのか?
――ところで、何故「最後尾ではない」のかと言うと、長大な行列を切れ目なく伸ばしてしまうと、列によって通行が遮断されてしまうため、邪魔にならないところで一旦列を切って通路にしているわけだ。で、切った前の方が少し進んでスペースができると……。
「はーい、前2人の方、手を上げてくださーい! そのまま4列で、前の列の後ろについてくださいねー。表示札を受け取るのを忘れないようにー」
手を上げた8人が、人の流れを横切って分断された前の方に追いつき、前の方の後端のヤツが持ってたパネルを受け取って後ろに手渡す。そこには手書きの絵と文字が描かれていた。「『CAT or FISH!?』最高尾じゃないよ!」とか書いてある。そうやって主張することで、勘違いや故意による横入りを防止しているわけだ。……ところで、小学生レベルの誤字があるのは、狙ってやってるのかどうか。
まあとにかく、そうやって列をちょっとずつちょっとずつ前へ送り、通行の確保と列の進行の円滑化と言う対立する命題を、手間暇をかけることで実現しているのだった。
それを実践しているのは、こみパスタッフの制服に身を包んだ優しそうな眼鏡美人である。
俺と郁美は、人の流れからやや外れているが、充分彼女を視界内に収められる位置に退いた。郁美を横目で見て、彼女の方へ視線を送って促す。郁美は困惑した表情で黙り込んでいた。
「――どうした、早くしろ」
「ですけどこれ、もしかして……」
手の中の小さなプラスチックケースを見下ろして戸惑う郁美。俺がさせようとしていることを漠然と察して無意識に拒否感を覚えているようだ。勘がいいのは結構だが――その行動は命令不服従に当たるって自覚してるかな、郁美?
俺はポケットの中から、郁美が手にしているのとよく似たプラスチックケースを取り出した。真ん中にボリュームつまみと言うか、ロータリースイッチがついただけの代物だ。ポインタの位置はOFFになっている。俺は郁美によく見えるようにしながら、つまみを少しひねってONにした。
「――ひぁうっ!?」
びくん、と震えて小さく奇声を発する郁美。そのままじわじわとボリュームを上げる。
「あ、あ、あ、あ、あ……!」
びくびくと跳ねる郁美の方から、微かな振動音が聞こえ始めた。
「く、あっ……や、め…やめ、てぇ……っ」
「ほーら。言うこと聞かないと、どんどん強くしちゃうぞ?」
「ひぃ、あああ……わ、わかり、ました、からぁ……」
「だったら早くしな」
「はっ、はいぃ…!」
ここまで来る途中、物陰で膣奥に仕込まれたローターの振動に急き立てられて、郁美は手にしたコントロールボックスのダイヤルスイッチをONに入れる。
こみパスタッフの女性――牧村南さんが、今しがたの郁美同様、びくんと過敏に反応するのが見えた。一瞬よろめきかけるのを堪え、慌てた様子で周囲を見回す。
すぐに俺に気付いたらしく、目が合った。あまり視力はよくないはずの南さんだが、開場前に会った俺の衣装を覚えていたんだろう。
ローターの振動を弱めてやりながら小声で指示する。
「ちょっとずつ上げてやるんだ」
「は、はい……」
頬を上気させた郁美が、言いつけ通り徐々にダイヤルを回していく。
南さんはぎゅっと自分の体を抱きしめ、何かに堪える仕草を見せている。よく見ると膝が小さく震えていた。
段々強くなる振動に脅えたのか、南さんはじっと俺を見つめて、縋りつくような眼差しを送ってきた。
そう言えば、さっき郁美もそんな眼をしていたけど……キミたち、そんなに俺が甘っちょろい飼い主だと思ってるわけかな?
俺は素早くいくつかの指示を与えた郁美をその場に置いて、悠然とした足取りで南さんに近付いていった。
「――すいません。ちょっといいですか?」
聞きたいことでもあるかのように白々しく話しかける。
「は…はい…。あ、少し待っていてくださいね」
行列の連中に断って何歩か離れる南さん。
「あ、あの……和巳さん。お願い、ここでは……」
話しかけてくる南さんの言葉に取り合わず、俺は片手を背中に回して悠然と立ち、もう片手の中のリモコンを彼女の目の前で操作した。
「あ、あ、あ、あ、あ…!」
じわっ、じわっと段階的に強まる振動に、南さんは立っていられず俺にしがみついてくる。
「あ、ひっ! くぅうんっ…! ひぅ、やぁあ、ダメぇ…!」
強くしたり弱くしたりしながら、全体的には少しずつ激しくなっていく振動に翻弄され、南さんの腰が小さく左右にくねり始めた。
「ひぃい…っ! だ、め……そんなに、しちゃ……ダメ、です、ぅうんっ…!」
かちかち歯を鳴らし、俺のコートを掴む手にはぎゅっと力が入り小さく震えている。よーく耳を澄ますと、喧騒の中、低い振動音が微かに聞き取れた。この至近距離でようやく聞こえる程度の微音ではあるが、体内で直接感じている南さんには何十倍にも増幅して聞こえているだろう。
「ほらほら、南さん。そんなに嬉しそうに腰振っちゃって。さっきからバイブ音もしてるし、もうちょっと我慢しないとバレちゃうよ? 南さんが、こみパ会場でオモチャを入れて仕事するヘンタイだってね」
「そ、そんな……っ!」
南さんは首筋まで桜色に染めて俯き、雨に打たれた仔犬のように震えている。実際には、腰の動きは微妙なものだし、振動音もほとんど聞き取れるものではないが、おそらく本人にはどちらも、誰かに気付かれないのが不思議なほどあからさまに感じられているはずだ。
「いやぁ……! イヤです、言わないで…。お…お願い、お願いです……ここでだけは……こみパでだけは、堪忍してくださいッ…! お願い――御主人、様ぁ…」
耳元で熱い服従の囁きをそっと舌に乗せる南さん。耐え難い羞恥と快楽に襲われた彼女の表情は、ぞくっとするほど艶っぽい。この辺は千沙や郁美には到底出せない味だ。
それに免じて、と言うわけではないが――。
「――しょうがないなあ。はい、南さん」
コートに縋る手を解いて、ぽん、とリモコンを置いてやる。南さんは一瞬きょとんとして目を見開いた。お、その顔可愛い。
一拍置いて、慌てて回転スイッチを回す南さん。逆時計回りに一杯に動かす。操作にワンテンポ遅れて振動が弱まり、ほっと息をつく。安心して油断した彼女の横からひょいと手を伸ばし、くるっとダイヤルを半分ほど回してやった。
「――ひぁあ!? や、ダメ、やめて……ッ!」
南さんは俺の手が届かないようにリモコンを抱え込み、焦ってまた弱める方向に操作する。
だが――。
「――ひぅうんっ!?」
振動は弱まるどころかいっそう強まり、耳を澄まさなくても羽虫のような振動音が聞こえ始めていた。
操作を間違えたのかと思ったらしく、南さんは慌てまくって反対にダイヤルを回した。振動は一瞬弱まり――彼女がほっと息をつく間もなく、再び強くなる。
「ひぁ、な、な――!?」
何が何だかわからないと言う顔で、彼女は左右にぐるぐるとスイッチを回す。振動の変化が一拍遅れて来るのも、どういう連動をしているのか混乱させるのに一役買っているようだ。
彼女がめちゃめちゃな操作を始めた時点で、少し離れた位置から「あっ、くぅっ……ん、はぁ…っ!」とか、女の子の喘ぎが微かに聞こえてきていたのだが、パニクっている南さんはその声に気付くことも、仕掛けを見抜くこともできずにいるようだった。
「ひっ、あっ! はひっ、ひぃいっ!」
押し殺したよがり声を上げながら必死にリモコンを操って身悶える南さんの耳元に、再び囁きを注ぎかけた。
「ホントに淫乱だね、南さんは。みんなに見られながら、自分でリモコンを使ってよがりまくっちゃってさ。周り中から蔑むように見られて、笑われてるのがわかる? でも周りの連中も、南さんがどれほど本物のヘンタイかって知ったら、笑うどころか引くんじゃないかな。何しろ――お尻の穴をオモチャで苛めて悦んでる、ド変態だものね?」
もちろん周りの人間は何が起きているのか気付いてすらいないが――既にまともに周囲が認識できていない南さんには、俺の言葉は絶大な羞恥責めの効果を発揮していた。
「や、やっ…ちがっ、違ぁ……っ! あくぅううううっ!」
未だにそれが自分のアナルプラグのコントローラーではないことを理解していない――あるいは理解する余裕すらない南さんが、リモコンをめちゃくちゃに操作し続ける。ちらっと振り返ると、郁美が唇を噛んで、南さんの操作でほとんどランダムに変化するローターの振動に耐えながら、手にしたリモコンで南さんのアナルを虐め続けていた。ちなみに背中に回した手で郁美にハンドサインを送って操作の方法を指示していたのだが。
もはや状況は、南さんと郁美の責め合いの様相を呈していた。十メートル近くを隔てた美女と美少女が、無機質な機械を操って互いを快楽の淵に追いやろうと相争っている。美女の方にはその自覚はないが。どっちにしろ、かなり倒錯的かつ刺激的な見世物ではあった。
――事情を知っている俺にとってだけは、だが。
もう郁美にも俺の指示など見えていないらしく、お互いに無秩序な操作を続けるだけの二人。頬を染めつつ必死に声を押し殺す様が色っぽい。
先に力尽きたのは南さんだった。たっぷり調教した彼女のアナルが、まだこなれていない郁美の膣よりも遥かに優れた快楽受容器官として機能していたのに加え、俺が与えた架空の侮蔑の視線にさらされる羞辱が、南さんを急激な背徳の絶頂に押し上げていく。
「――くふぅうううううッ…!!」
辛うじて噛み殺した極まりの声が彼女の唇から洩れた。だが――そうして無理やり抑え込んだのがかえって快楽の反響を深めたのか、南さんはかくんと膝を折って崩れ落ちた。
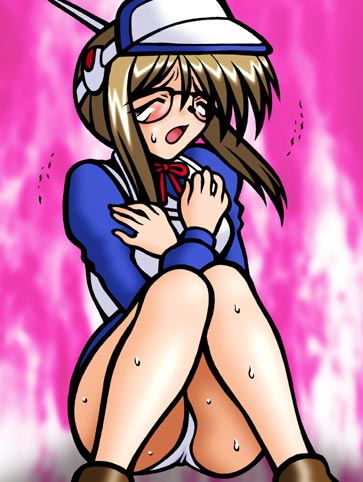
「うわっと!」
床に倒れる前に何とか抱きとめる。
「ふぅう……はぁあう……」
南さんは赤い顔で目を閉じ、小刻みに震えていた。……虐め過ぎたかしらん。
俺は握り締めていた南さんの手からリモコンを取り、郁美に目配せしてスイッチを切った。郁美も頷き返してリモコンスイッチをOFFにする。
「南さん、大丈夫? ……あれ、南さん。南さん?」
返事がない。どうやら失神しているようだ。
やっぱり虐め過ぎたみたいだ。
「ちょっとちょっとぉー! 何してんのよ! 何で列動かさないのよ!? 前の方なくなっちゃったじゃない!」
と、少女の怒声が降って来た。何だか無意味に偉そうな響きを帯びている。見上げると、高校生くらいの女の子が腕を組んで立っていた。見ればややラフなショートヘアの、なかなか整った顔立ちの少女だったが……女の子にしては太めの眉をきりりと吊り上げ、口をへの字にして仁王立ちしているのでかなり台無し感が強い。と言うか声だけでなく態度も無意味にエラそうだった。
「って、ああー!? こらぁー! アンタ、ウチのレツタイに何しちゃってんのよぉ!?」
こみパスタッフの南さんを自分のサークルの列対(行列対応要員)扱いですか。
「……何様?」
ついつい突っ込みを入れてしまう。と、何を思ったか、少女は満足げににまりと微笑んだ。
「うふふふふ。『様』づけで聞いてくるとはなかなかしゅしょーなココロガケじゃない。このアタシを知らないとは減点だけど、ま、いーわ。教えてあげる」
…………『何様』という言葉に含まれる非難のニュアンスは綺麗さっぱり無視したようだ。あるいは気付かなかったのだろうか。だとすると相当アタマあったかそうだが。
「ちょお大手サークル『CAT or FISH!?』主宰サマ、こみパの女王、大庭詠美とはあたしのことよ。どお、おそれいった? あははははっ!」
腰に手をやり、口元に手の甲を当ててのけぞって高笑いする「オオバエイミ」とやら。
確信する。
――コイツはかなりバカだ。関わり合いにならないほうがいい。
「――って、何よ、ポチじゃないの。ムダな自己紹介させないでよね。……あ、そうそう、それで南さんに何したのよ一体!?」
が、俺が逃げ出すより早く、彼女は俺の顔をのぞき込んでそんなことをのたまった。
今度は初対面の俺を下僕扱いですか。
ん? いや待て、まさか……。
「俺と話してたら急に倒れたんだ」
「ふぅん――」
一瞬、表情が心配そうに曇る。無防備なその顔は妙に不安げで、幼げにも見えた。
「――大丈夫なの?」
「まあ、呼吸は普通だし顔色もそう悪くないから……過労じゃないかな」
「そう……よかった」
白々しく『推測』してみせると、彼女はひどく素直に頷いた。さっきまでの高飛車さは今は欠片もない。南さんを見つめる少女の横顔は気弱げで、可憐ですらある。戸惑って見つめると、気付いた彼女はぱっと頬を染め、わざとらしくふんぞり返った。
「そ、それじゃ、南さんは保健室に運んでもらって――アンタ、ウチの列整理手伝いなさいよ。ヒマなんでしょ。お礼に今度、あたしの勉強見させてあげるから」
……かなり意味不明の発言だった。しかし、まさかと思うが、この偉そうな態度って、照れ隠しとか自己防衛なのか? もしかして。
それにしても保健室はないんじゃないか。この場合、医務室とか救護室とか、そんな感じだろう。まあニュアンスはわかるが。
今の態度がどういう理由によるものかはともかく、アタマ悪そうなのだけは確かだった。
やっぱ、関わり合いにならんどこ。
突然倒れたスタッフの姿に、周囲に人垣ができ始めている。その隙間からのぞく郁美に、目顔で先に戻っているよう指示して、俺は軽く息を吸い込んだ。
「それじゃ南さんを救護室に連れてくので俺はこれで」
しゅたっと片手を上げて一息に言い切り、南さんを抱いて立ち上がる。
「う――お、お姫様抱っこ……?」
何故か、がーん、とショックを受けたような顔をする少女をそのままに、俺は肩で押すように人垣を割り、小走りにその場を離れた。
「あっ、ちょ、ちょっと、こらぁー! 置いてかないでよぉ、せんどーかずきぃー! ふみゅうううーん!」
背中を、置いてきぼりをくった子供のような半泣きの声が追いかけてくる。意外と寂しんぼらしい。
しかし……やっぱり千堂の知り合いだったか。
千堂――お前の周りって、ほんと、ロクな女がいないんだな……。
胸中の慨嘆には、俺にしては珍しく、多分に同情が混じっていた。だがもし千堂がこれを聞いたら、『大きなお世話だ』と答えるに違いない。話したこともない相手なのに、その想像は妙にリアルに耳に響いた。
救護室の場所は心得ていた。何のことはない、先月俺自身がお世話になったばかりだからだ。……ヤなコト思い出したな。
正確にはそこは救護「スペース」と言うような場所だった。ベッドもないし、床に敷いたシートに何人か寝かされているだけだ。一応枕替わりのクッションくらいはあるようだが。
俺は「貧血みたいだ」と告げて南さんの体をシートの一角に横たえた。よほど強烈な絶頂だったのか、ここに至ってもまだ目覚めない。
知り合いだと言うことで彼女の傍らに付き添いつつ、周囲を見回す。十人くらい寝ているようだ。多分寝不足と栄養失調による貧血が大半だろう。夏ならこれに熱中症が加わって人数が倍加するに違いない。
「ん、ん……」
ここに来て数分で、南さんは小さく呻いて薄目を開けた。
「――気が付いた? 南さん」
幾分まだぼーっとした目で俺を見上げ、のろのろ半身を起こして左右を見る。
「ここは……私は……」
そのまま数秒ぽやーっとしていた南さんは、やおら「あっ!」と声を上げて立ち上がりかけた。が、途中で今度は「ふぁん…っ」と微妙な声を洩らして止まってしまう。
……察するに、気絶する前のことを思い出して慌てて立とうとしたところ、急に動いたため嵌めっぱなしのアナルプラグにお尻を抉られて、思わぬ刺激に凍りついた、と。
ま、どの道正気に戻ったのは確かなようなので、ちょっとつついてみることにする。
「それにしても失神しちゃうなんてね。皆に見られながらお尻でイくの、そんなに気持ちよかったんだ」
「――――ッ!! や、やっ! やぁああああ……っ!」
南さんは目元から頬、耳や首筋まで桜色に染めて、耳を塞いでかたかた震えた。ぎゅっと瞑ったまぶたから、ぽろぽろと涙を溢れさせる。泣くほど恥ずかしかったらしい――もとい、現在進行形で今も恥ずかしいらしい。
と――何を思ったのか、南さんは突然、横に座っていた俺の胸元に顔を埋めた。こみパスタッフのバイザーが弾かれて床に落ちる。
「え、ちょっと。南さん?」
意図がわからず戸惑う俺の胸に額をつけて、彼女は震える声で囁いた。
「お願い……お願いぃ……」
「…………。って、何を?」
「お願いします……どうかもう……こみパでだけは……許してください……他のことなら、何でもします……何でも、言うこと聞きますから……」
嗚咽混じりの懇願。必死な声音が、本心からの言葉だと伝えていた。
ふむ――。
何でもする、か。
もしかするとこれは、南さんを完全に屈服させるまたとない機会かもしれないな。
「――本当に、なんでもするかい?」
低い俺の声に不吉な響きを感じ取ったのか、彼女はぶるっと背を震わせるが、衆人環視の会場内での責めがよほどこたえたのか、必死に何度も頷く。
俺はゆっくり南さんの背に手を回して優しく抱き寄せ、耳元に口を寄せた。考えをまとめ、唇を舐めて話し始める。
「それじゃあ――南さんの、心をもらうよ」
え? と泣き濡れた顔を上げる南さん。困惑を浮かべる優しげな美貌に、俺は微笑んで語を継いだ。
「南さんさ。いつも、俺の命令に従う時、夢中になってくるとともかく、普段はどこか嫌々と言うか、脅迫されてるから仕方なくって態度でしょ」
「…………」
「それを、改めてもらおうかな」
「あ、あの……。それって、どう言う……」
「心から俺に従属しろってこと。いつも俺のこと、俺を気持ちよくすることを考えていて、しかも心から望んでそうするようになってもらう。要するに、俺を好きになって、俺のそばにいるだけで嬉しく感じるようになればいい」
「なっ、そ……そんなっ! こ、と……」
目を瞠って絶句する南さんに、俺は苦笑を返した。
「――まあ、何も本気でそうなれって言ってるわけじゃない」
「……え…?」
「つまり……演技でも、自分を騙してでも何でもいいから、俺の前ではそういう態度を取れるようになれってこと。それができると言うんだったら――お望み通り、こみパで苛めるのだけは勘弁してあげる。どう?」
「…………。それは……私……。ああ……どうしたら……」
「そうだな。すぐに答えを出せることじゃないだろうしね。今日を入れて一週間あげるよ。土曜の夜、返事を聞かせてもらう。それでいいね?」
「は…はい…。御主人…様……」
「それまでに、俺が言った通りにできるのかどうか、試しに練習してみるといいよ」
「あ…はい……」
混乱している様子の南さんは素直にそう返事をした。その時点で、俺の条件を受け入れる方向に半ば誘導されていることに、今の彼女は気付いている様子はなかった。それ以上深く考える暇を与えず、床に転がっていたバイザーを拾い上げて手渡す。
「さ、みんな心配してるだろうし、そろそろ仕事に戻った方がいいよ。今日はもう何もしないから。何なら、ソレ抜いちゃっても許してあげる」
「あっ……は、はい…」
こみパへの使命感を掻き立てられたためか、それとも責め具の取り外し許可が効いたのか、南さんは慌てた様子で立ち上がった。
救護室を出て南さんと別れた俺は、一旦自分のサークルスペースに戻ってから、再度人波を掻き分けて移動していた。開場前に挨拶できなかった知り合いのスペースに向かうためである。こみパ会場は大体3つのエリアに分かれているが、開場時間が迫るとエリア間の移動ができなくなる。そのため、他のエリアの挨拶回りは、開場後一段落ついたこの時間帯に行こうと言うわけだ。
――いやまあ、と言うか、普段はそうなのだが……今回は開場前にばたばたしていたため、同一エリア内の挨拶回りもまだだったりする。本が来るのもぎりぎりだったし。次回はもうちょい早く持って来てくれると助かるが――千沙だしな…。あまり期待しないでおいた方がいいか……。
知り合いに配る新刊本を何冊か、それと念のためスケッチブックも持って出ている。いや、何か急にデッサン取りたいものを見つけないとも限らないし。そう考えればデジカメでも持ち歩けばいいのかも知れんが、最近の俺は大器に色々機材を借りているとはいえ、基本的に貧乏なのでそんなもの買う金はない。それくらいだったら印刷代に回したいし。
館内は一応暖房されているのに加え、何と言っても人口密度が高いため、コートをすっぽり着込んだこの格好は正直言って暑い。だがこれを脱いでまた千堂に間違えられて騒動に巻き込まれるのはご免だし。そう言えば、南さんのこともあってとっとと逃げ出してしまったが、さっきの大手サークルはあの後どうなったんだろうか。大庭詠美とか言ったっけ、あの女。
そんなどうでもいいことを考えつつ、俺の足は暑さを避けるために、ホール出入り口にまっすぐ向かう人の群れから外れ、多少遠回りでも人の少ない方へと動いていた。
「……ふう」
一息つく。
ここら辺りは閑散として静かなものだった。他のブロックと較べて、売り手も何だか穏やかな感じだ。いくつか本の表紙をのぞくと、キャラとかに見覚えがない。どうやらオリジナル創作・非18禁(一般向けとも言う)のブロックのようだ。
体の熱が引くまで急いで動く気になれなかった俺は、この列に並べられた本の表紙を眺めながらゆっくり歩いた。中には熱心な売り手もいて声をかけてきたりもするが、そのほとんどは本のジャンルをアピールするものだった。
まあ、中身がわからなきゃ食指も動かんわな。
そんな売り手がいても、このブロックは他のところよりも格段に静かだ。
――静謐。
ふっとそんな言葉を思い出す。
しっとりと濡れたような黒い髪の少女の、整った顔立ちが連想される。視界にオーバーラップするその姿を振り払おうと頭を振るが、イメージが消えない。
俺の顔を見上げる深い深いその瞳――。
……見上げる?
ふと気付くと、俺は立ち止まって見詰め合っていた。
サークルスペースのテーブルの向こうに腰掛ける、見覚えのある少女と。
――って、イメージじゃないじゃん!
「き、キミ――!?」
驚いて声をかけると、画材屋でバイトをしていたその少女は、捉えどころのない瞳で、立てた襟の奥の俺の顔をじっとのぞき込んだ。
「――――あ……四堂さん…」
相変わらずきっちり見分けてくれた。
「キミも同人やってたんだ?」
見ると、スペースには少女が一人。2つ目のパイプ椅子は開かれもせずにテーブルに立てかけてある。彼女の一人サークルなのはまず間違いない。
「見ていいかな?」
テーブルに積んである同人誌を指さして確認する。別にお義理で聞いたわけではなく、この少女が一体どんな本を作ったもんだか、興味津々だったのだ。
こくり、と頷きかけるのを視界の端に捉えて一番上の1冊を手に取る。端っこがホチキスで閉じられている。コピー本だ。
表紙を見ると……うーん、シンプルで地味だ。よく見るとデザイン性はけっこう高いが、彼女の美少女振りと同じく、よく見ないとわからないという類のシロモノだった。
ページをめくる。
……うわ、黒。
よく見ると、それは描き込みだった。キャラといい背景といい、驚くほど細かく描き込まれている。コピーで再現しきれずに線が潰れかけているため、よけいに紙面が黒い。絵柄も妙に写実的で、社会の教科書とか昔の新聞なんかに載ってそうなタイプの絵だ。もっと可愛らしい少女漫画チックな絵を漠然と想像していた俺は、あまりのギャップに一瞬凍りついた。思わず少女の顔とページを見比べてしまう。
「……?」
俺の態度に、少女は不思議そうに首を傾げていた。
自覚、ないのか……。どうやらわざとやってるわけじゃなさそうだ。
まあとにかく通して読んでみよう。俺は紙面に集中して、彼女が描いたマンガを読み始めた。
ありもしない夢を語る老人と、夢を忘れてこすからく生きるスリの少年の物語。
淡々と、だが不思議に生活感に溢れた筆致で物語は進む。
誰も気付かないままひっそり訪れる奇跡。老人の言葉は幻想ではなかった。少年と老人だけがその奇跡を共有する。
少年の胸に夢見る心が戻る――。
……はっ。
のめり込んで最後まで読んでしまった。
この語りの上手さは何だ!?
こんなに地味でとっつきにくい絵なのに。説得力と言うか……恐ろしい「実在感」に満ちている。描き込みが凄すぎて余計とっつきにくいとか、紙面構成が地味に過ぎるとか、欠点はたっぷりあるが、それを上回る長所が隠れていた。問題はその「隠れている」ってとこだが。作品に流れる生活感が漫然とした繰り返しの空気を助長するため、地味さに耐えて最後まで読み切らないとストーリーテリングの妙が味わえない。
何て言うか……同人誌向きじゃねえ。
だが、確実に一つ言える。
「面白かった!」
心からそう告げると、少女はびっくりしたような眼で固まっていた。
「1冊買うよ。いくら?」
「……え」
さらに目を見開く少女。いつも茫洋としたような表情に、今は明確に驚きが浮かんでいる。
「……本当……ですか……?」
「……え、何が?」
「あの……本気で…?」
黙って見つめ合う。
本気って? 本気で面白かったのか、かな? それとも本気で買うつもりですか、と?
……どちらにしてもある一つの事実を示唆していることに気付いた。
一応聞いてみる。
「……そんなに、買う人少ないんだ?」
「…………」
――黙って俯かないように。イジメたみたいじゃないか。
呟くようにぽつりと答えが返ってきた。
「……大体……1冊も……」
「………」
「………」
き、聞かないであげた方がよかったか…。
「……以前…和樹さんが、1冊買ってくれました…。…それから、少しずつ……お話するようになって…お会いしたときには…本を差し上げるように……しています……」
「だから買ってくれてはいない、と」
「…あ、でも……和樹さんの本を……お返しに、いただいてますから……その……」
「千堂を悪く思わないでくれ、って?」
「……はい」
――ふーむ。一つ、発見したな。
「画材以外でも、千堂のことになるとよく喋るんだ?」
「……あ……」
かあっ、と少女の白い頬が真っ赤に染まった。
肩をすぼめて顔を俯け、恥じらう姿はめっぽう可愛い。
何だか千堂に惚れてるっぽいけど、こんな娘なら、応援してやってもいいかという気になる。
――だが、うらやましいぞ千堂。
彼女が落ち着くのを待って聞き直した。
「それで、1冊いくら?」
「――あ……200円…です……」
――安っ。このページ数で200円? 1枚10円のコピーだったら確実にアシが出るぞ。
俺は複雑な顔をしながら100円玉2枚と本を交換し、紙袋に仕舞った。
少女は物問いたげにこちらを見上げてくる。
「――何?」
「………。…あの。……本当に……面白かったですか……?」
「ああ、うん。お世辞抜きに面白かったよ。地味だったけど」
「……地味……ですか……」
「この話、最後まで読まないと面白さがわからないけど、ぱっと見の印象がえらく地味だから最後まで見てもらえずに損してるんじゃないかな」
俺の感想に、じっと考え込む少女。何か思い決めたように、ふっと目を上げる。
「あの……いいですか?」
「な、何?」
「どうすれば……見てもらえるように、なると…思いますか?」
真摯に見上げる瞳。
「…教えて……ください…」
……その瞳とその囁きに、正面から対抗できる男がいるなら教えて欲しかった。
「つまりほら。ぱっと開いたときに紙面が真っ黒で、どこ見たらいいのかわからないじゃない。不要な部分は線を減らして、見て欲しい部分に視線を集める工夫が要るんじゃないかな。例えばほら、こんな感じで…この辺が描かれてなければ、こっちを見せたいんだなってわかるでしょ」
スケッチブックを開いて例を描き込むと、隣に座った少女は熱心にこくこくと頷いた。
「あと、コマの構成で流れを見せるようにした方がいい。――このページなんか見ると、こう、こう、こうなって、こう来るから、流れがブツ切りでしょ。例えばこんな風に」
ざっとコマを割り直し、大まかに人物や背景を配置して見せる。
「こんな具合だったら、見る人も自然に流れを追いかけられると思うよ。無論全部流しちゃうと逆に軽くなりすぎちゃうから、じっくり見せたい場面ではわざと流れを止めてそこに注目させてやりたいよね」
ぱらぱらページをめくり、ちょうどいい場面で前後数ページのコマをフリーハンドで割り直して見せる。
「ね。こんな感じ」
こくこく。
少女に請われ、俺は彼女のスペースにお邪魔してマンガ教室を開いていた。
色々聞いてみて驚いたのは、あんなに画材に詳しい彼女に、マンガの知識がほとんどなかったことだった。全部独学。マンガに関する全てを自分ひとりで試行錯誤して身に付け、習熟して来たのだ。
ある意味天才と言っていい。
彼女の独特のタッチを殺さないよう、マンガの最低限の約束事だけを伝えるようにすることに、俺は意を砕いた。素晴らしく光るものを彼女は持っている。ごくごく普通の、どこにでもあるような売れ筋のマンガを描くようには、なって欲しくなかった。無駄な渋さ・地味さを少しずつ直していけば、あのストーリーテリングの才に合致した絵柄に到達できるのではないか。俺はそんな風に感じていたのだ。
20分くらいかけて、基礎的なことを教え終わった。
「とりあえずこんなもんかな。今言ったようにすれば、だいぶ見やすくなると思うよ」
こくこく。
少女は熱心に頷いた。
「…ありがとう…ございます。あの…四堂さん…絵、お上手なんですね」
「え、俺が?」
「…はい。だって、こう、ぱっぱっと」
スケブに描き込む仕草。
「……四堂さん……マンガ…描いてるんですよね…?」
――うっ。
や…ヤバい流れだ…。
「四堂さんの…マンガ。……見てみたいです……」
――――。
ぐはぁっ!
純粋な視線がハートにぐっさり突き刺さる。
正直、めちゃめちゃ痛ぇ…!
曇りのない憧憬の眼差しに耐えられず、俺は視線を逸らした。
実は手元に知り合いに配る用の新刊がある。今回のアレは、余分なギミックとか入れなかった分、絵や構成に関しては確かに自信作だ。自信作だからこそ、余計に見せられん。
「……四堂さん……」
懇願の声が胸に苦しい。だが、考えてみれば、今後も同人活動を続ける以上、いずれは俺の描くマンガは彼女にバレることだろう。隠していて、そうなってから責められるよりは、最初からバラしておいた方がまだ楽かも知れん……。
だって俺、あっち系やめる気はさらさらないし。
でもなあ…。
「お――俺のマンガみたら、キミは俺のこと軽蔑するかもしれないよ」
「……?」
首を傾げる。多分きっと、まったくわかっていない。
「それでも――見たいかい?」
こくり、と頷く少女に、俺もハラをくくった。
「それじゃあ――これ」
紙袋から新刊を出して手渡す。ほのかに嬉しそうな表情でページをめくった。
ぱら。ぱら。ぱら。
意外に無反応でページを繰り続ける。最後までめくり終え、こちらを向いた。
「これ……全部、四堂さんが……?」
「ああ」
不利な裁判の判決を待つ被告人の気分だった。
「…凄いです。絵の省略とか、コマの流れとか……言われたように、しっかりしていて」
「……はい?」
「…お話は……よく、わかりませんでしたが…」
ごん、と音がした。
俺の頭が長机にぶつかった音だ。
ほ……ホントに、わかってねえ……。
一瞬このまま誤魔化して流してしまおうかとも思ったが、そうもいかない。俺は少女の耳に口を寄せ、こそこそと説明を始めた。周りの人間に聞かれたくなかったからだ。
「……はい? …はあ。…濡れ場……え……はい。……アブノーマル? って? ……はい。……はい。……え? ええ…? …は、はい……。…………」
しっかりばっちり詳細に説明してやると、ようやく俺の本の内容を理解した少女は、真っ赤になって凍りついていた。耳まで赤い。頭から湯気が出そうな雰囲気だ。
「どう? わかった?」
こくこくこく、と小さく頷く。
「…………。……ごめんなさい……私…そっちのお話……詳しくなくて…。……びっくりしました……」
真っ赤なままの頬を両手で押さえて、ぽつぽつとそんなことを言い出す。
……何か予想したリアクションと違うな。
「俺のこと、嫌いになったんじゃない?」
「……? ……どうして…ですか…?」
いや、不思議そうに首を傾げられても。
「女の子って、こう言うお話――って言うかエロマンガ嫌いでしょ?」
しかも凌辱調教系だし。
「……そうなんですか?」
「………」
「………」
コイツは――相当な変わりモンだ。俺は前回の精神疲労を思い出し、それが倍になってのしかかってきたような気分を味わった。
少女の「また色々教えてください」との言葉を背に、俺はその場を辞した。
――何かヤバいセリフだな、それ。
いいのか? 色々教えちゃうぞ?
危険な妄想を暴走させつつ、当初の目的を果たすべく別エリアへ向かう。
――少女の名前すら聞いていないことに俺が気付いたのは、かなり後のことだった。
知り合いのサークルを回り終え、いくつか贔屓のサークルを見てから、人波を泳ぐのに疲れた俺は、休憩を兼ねて中央通路の2階部分に上がった。ここではいくつか売店のスタンドが出ている。
――郁美に食べ物でも買っていってやるかな。
そう思って店の物色を始めた俺の背中に、底抜けに明るい声がかかった。
「あーっ、それ、ラグサーガのバネットだよねぇ?」
振り向くと、短ランを袖まくりしてハチマキを絞めた人物が、懐っこい笑みを浮かべていた。学ランの下に着たTシャツの胸は盛り上がっている。ズボンを穿き、男装ではあるが、女だ。
「よくわかるな、翔クン」
この女のは、有名な格ゲーキャラのコスプレだった。
「にゃはははっ。こーんなマイナーキャラのコスする人がいるとは思わなかったよぉ」
言いながら珍しげにこちらをのぞき込む。……ずいぶんテンションが高い。物怖じしてねえし。こみパだからかな、浮かれてるのは。
と、彼女はびっくりしたように目を丸くした。
「って、あれぇ? 千堂クン?」
…………コイツもか。
俺は相当渋い顔をしていたらしい。
「何ブッチョーヅラしてるの、千堂クン。にゃはは、コスしてるとこ見られたくなかったとかぁ?」
「……悪いが俺は千堂和樹じゃない」
「えー? 今のオレはバネットだ! ってぇ? なり切ってるねぇ、千堂クン♪」
「やめてくれ。俺はそいつのせいで酷い目に遭ったんだからな」
俺はポケットから免許証を探し出し、彼女に見せた。
「え? ……四堂、和巳? ――えええっ? 本当!? ネタじゃなくってぇ!?」
……気持ちはわかる。俺も千堂の写真を初めて見たときは、自分だと信じて疑わなかったもんな。…名前も似てるし。
「ふ――ん、へぇー。……でも見れば見るほどそっくりだよねぇ。それで、酷い目って?」
二人で壁際に移動してから、俺はここぞとばかりに愚痴り始めた。
「まあ聞いてくれよ……」
「にゃはははっ。それは災難だったねえ、しどー君」
「笑いごとじゃねえ」
俺は憮然としてツッコんだ。災難の一言で片付けられてたまるかって。
「ゴメンゴメン♪」
「笑いながら謝っても説得力ないって……」
はぁ、と溜め息をついて顔を覆う。愚痴る相手を間違っただろうか。って、待てよ、そう言えば。
「それで、キミはどこのどなたさん?」
「あ、ゴメーン。千堂クンと同じ顔だから、もう知り合いみたいな気がしてたよ。アタシは芳賀玲子。友達と『チーム一喝』って格ゲーサークルやってるの。都内の短大に通っててぇ、普段はゲーセンで店員さんのバイト。で、趣味はコスプレ☆」
オープンフィンガーグローブを天に突き上げ、ポーズを取って見せる玲子ちゃん。
「いや、コスプレコンテストの自己紹介じゃないから」
すかさずツッコミを入れる。
「あっはっは、ノリがいいねぇ、しどー君」
確かに。このコ、気安いというか、妙に話しやすい。玲子ちゃんはにやっと笑うと、耳元に顔を寄せてきた。
「それでぇ、しどー君。南さんや由宇ちゃんが怒り出すくらいのって、どのくらい激エロだったのぉ?」
興味津々、人の悪そうなにやけ顔を見せる。
俺は重々しく頷いた。
「そりゃあもう、どろどろのエロエロだよ。俺はエロ絵に青春賭けてるからな」
胸を張って見せると、玲子ちゃんは弾けるように笑った。
「にゃははは! どろどろのセーシュンだねぇ☆ ……それでぇ、具体的にはどのくらい……?」
あくまで食い下がってくる。
「……見たいか?」
「うん、見たい!」
明るく即答。
「ふっ。後悔すんなよ」
ニヒルに告げるが、玲子ちゃんの表情はどう見ても期待のそれだ。
手持ちの新刊は全部配ってしまっていたが、まあ、それならそれでやりようはある。
俺は一歩下がって玲子ちゃんを改めて上から下まで眺めた。
「?」
不思議そうな玲子ちゃんに説明はせず、紙袋から出したスケブを開き、シャーペンを走らせる。1分ほどで1枚めくった。
「何? 失敗?」
聞く声には答えず、さっと辺りを見回す。少し向こうを、玲子ちゃんのコスしている格ゲーの女キャラが歩いていた。割と可愛い。よし、あれで行こう。
俺の視線を追って、玲子ちゃんもそのコに気付いていた。ちょっと見つめてからこちらに目を戻す間に、俺はまたケント紙にシャーペンを走らせ始めていた。
ややあって――。
「……まあ、こんなもんかな」
俺は最初に描いたページを開いて玲子ちゃんにスケブを渡した。
「――ひゃああっ!?」
奇声を発して固まる。
当然の反応ではある。描かれていたのは、少しデフォルメされていたとは言え、明らかに玲子ちゃん自身とわかる特徴を備えた娘の――全裸の立ちポーズだったのだから。
そのすぐ隣の絵は、臍下からが紙面の外になる半身像で、こちらは今の玲子ちゃんのコスと同じ服を着ている。ただし、Tシャツを首元まで捲り上げ、胸をはだけた姿だ。しかも、乳房を絞り出すように上半身に縛りが入っている。
このラフイラストを見つめたまま凍りついた玲子ちゃんの顔は、首筋からさあっと紅潮していった。それはもうあっという間に。
――怒り出すかと思ったが、玲子ちゃんは無言のまま、スケブのページをめくった。
はっと息を飲む玲子ちゃん。
今度描かれていたのは、さきほど横を通った少女と玲子ちゃんとのカラミだった。今度はただのイラストではない。見開き2ページのネーム形式でコマ割りしてある。つまり、簡単なマンガにしてあるのだ。勝負に負けた少女を玲子ちゃんが襲っちゃう、と言うシナリオにしておいた。
ぺら、とまためくる。
今のマンガの続き。4ページマンガなのでそこで終わりだ。最後のコマには「続く」と入れてある。
見終えて、玲子ちゃんが、ふはあ、と息をついた。
「おっと――まだ終わりじゃないぜ」
「ええ!? ま、まだ?」
「だが、見るなら覚悟した方がいい。そこから先は問答無用、容赦なしの激エロハードコアゾーンだからね」
玲子ちゃんは頷いて、ほとんどためらわずにページをめくった。
――凍った。ぴき、と音が聞こえた気がする。
形式は同じ見開きマンガで、内容は……玲子ちゃんとさっきの少女が、男達にレイプされちゃう話だ。バージンを犯さないでいてもらう代わりに奉仕を強要され、フェラ、手コキ、パイズリ、素股で白濁液を浴びまくる玲子ちゃんと、その目の前でサンドイッチファックされて泣き叫ぶ少女。やがて玲子ちゃんの体の芯に、ほのかな被虐の悦びの灯が点る――と言うところで「続く」。
あ。ちゃんとそこまでめくってる。錆びた機械のようにぎこちない動きだが…。
「そんなもんだな。どう? ケーベツした?」
できるだけさりげなく声をかける。実際はドキドキものだ。調子に乗って描きすぎた。嫌われたらダメージでかいかも。…最初にマイナスポイントを稼いでおけば、それ以上評価は下がらないだろう、と言う目算もまあ、あるにはあったが。
だが、硬直の解けた玲子ちゃんは、ぶんぶんとかぶりを振った。
「あ、ううん。ウチもヤオイやってるし、ヒトのことは言えないよぉ。…ちょっとびっくりしたけどさ」
顔はまだ真っ赤だ。
「別の意味でもびっくりだよ。しどー君、すっごく上手いねえ。めちゃめちゃ早かったし」
意外にも、誉めてくれた。こっちもびっくりだ。…今日は変わりモンにいっぱい会う日だな。
「ちゃんとアタシとあのコに見えるもんねぇ。恥ずかしいけどぉ」
「このまま続ければもっともっと激エロな展開が待ってるけどな」
「にゃはは…それはぁ……コワいけど、ちょっと見たいかな。でも、これ以上かぁ。千堂クンだって思ってたんなら、そりゃあぶっ飛んじゃうよね、そんなの見たら」
「見たことないけど、千堂和樹のマンガってどんなんだ?」
玲子ちゃんはちょっと考え込んだ。
「うーん、良くも悪くも正統派って言うか。千堂クンの場合、『マンガでどこまで語れるか』って目指してる感じかな。萌え系で描くときとかもあるけど、きっちりストーリー組んであるしぃ」
「なるほど…。エロの場合、ある程度ストーリーとか犠牲になるしな。今まで探求していた部分を切り捨てたように見えたわけだ」
思わず納得する。目指す方向はぜんぜん違うが、俺と千堂って少し似てるかも。
一人で頷いている俺に、玲子ちゃんはまた顔を寄せてきた。
「ねねねね、ところでさ、しどー君☆ ちょっと相談なんだけどぉ……しどー君は、やおいって描けるの?」
「ヤオイ?」
意表を突かれた。
ヤオイか……。そうだなあ…。
「…エロの一表現と考えるんなら、まあ描けなくはないかな?」
俺、エロの求道者だし。
「見てみたいなあ。ちょっと描いてよ、今みたくぱぱっと。ね☆」
玲子ちゃんはねだるように腕に抱きついてきて、ウインクして見せた。
話しててライトな人格が先に来るため意識してなかったが、玲子ちゃんは実のところかなり美形だ。女性にしては背が高いので男装はよく似合っているが、服越しでも柔らかいその胸を押し付けられると、さすがにそう言った部分を意識せざるを得ない。――と言うか、玲子ちゃんにそうやってせがまれるのは、正直たいへん気分がよかった。やる気が湧いてくる。
俺はさっとあたりを見回した。女装の美少年、と言う設定のキャラが一瞬目に付くが、ああ言うのを望んでいるわけではないか……。影のある美少年、こっちか。
ちょっと考える。…行為の描写より心理描写の方が重要な気がするな。セリフ回しに凝らないとダメか。
スケブを開いて、簡単な状況設定を決め、ネームを切る。例によって見開き×2の4ページマンガだ。少し悩んだが、ネームが決まってしまえばさして苦労はなかった。15分ほどで描き上げ、スケブを玲子ちゃんに渡す。
「はい」
無論、描いている途中は見せない。ネタバレはつまんないからね。
「わあ…」
玲子ちゃんは嘆声を洩らしつつスケブを眺めた。
何やら複雑な関係を匂わせる会話をしつつ、微妙に玲子ちゃん似の『翔』が美少年キャラに攻められる、と言う内容にした。ぱっと見の力関係を逆転させることで、倒錯感が出るのを狙ったわけだ。直接の局部描写は控え、なおかつエロくなるよう、何とか工夫してある。『翔』が少年の行為を受け入れつつ、何やら意味深なセリフを吐くところで『続く』。
「ちょ、ちょっとぉ、ここで引きなの? あーん、続きが見たいよぉ」
言いながら、未練がましくもう一枚めくる玲子ちゃん。
ぴき、と凍りついた。
俺はにやりと笑った。イタズラを上手く成功させた気分。
さきほどは「攻」だった少年がどろどろに凌辱される話をもう1本入れておいたのだった。
最後まで読み切って、無言のまま、玲子ちゃんはぱたん、とスケブを閉じた。
がっしり手が握られる。
「な?」
「しどー君! ウチの本にゲストしてくれない!?」
目がマジだった。殺気すら感じる。俺はほとんど反射的にかくかく頷く。
「わわわ、わかった。描く描く」
「ホントね!? 絶対だよっ!! うにゅぁ〜ん、嬉しいよぉ、続きが読めるぅ〜♪」
好物を手に入れた猫の表情。目の中にハートマークが浮かんでいそうだ。
……ヤオイ系の女の子の場合、キャラのカップリングにやたらこだわる子が多いと聞くが、彼女はどうやら、それほどうるさくないタイプのようだった。
「あ、そーだ! しどー君、ちょっとこれコピーさせてもらっていいかなぁ!? ウチのみんなに見せてあげようと思うんだけど」
「あー、何なら、丸ごと貸してあげてもいいけど」
「…そ、それはダメェ」
玲子ちゃんは頬を染めて目を逸らした。
「え、どうして?」
「だ、だってさ…『アタシ』のえっちマンガも描いてあるじゃん……」
さすがに他の人には見せたくないらしい。
結局、ヤオイの4枚だけ切って贈呈することにした。
「いいの? 原稿描くとき困らない?」
俺は、大体覚えてるし、忘れたら別のを描くからいい、と言って手渡す。
その後、互いの連絡先を教えあって玲子ちゃんと別れた。玲子ちゃんは大事そうにケント紙を抱え、ぶんぶん手を振って離れていく。
……さて、だいぶ時間を食ってしまった。郁美に焼きそばでも買って、自分のスペースに戻るとしよう。何しろ、これからまたたっぷり弄んでやるつもりなので、ちゃんと栄養は補給してもらわないと。今日のこみパが終わるまでに、あと5、6回はイかせてやりたい。
ふっふ、楽しみだ。
羞恥と快楽に揺れる郁美の姿を妄想しつつ、俺は周囲の食べ物を売るスタンドを物色し始めた。
|
![]()
![]()