|
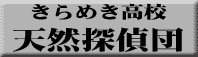
(5)負けるな天然探偵団!(手遅れです)
悪夢の陵辱劇が繰り広げられた日から、ゆかりは連日休むことなく、ハジメによって犯され続けた。
最初のうちは、もっぱらハジメの家で、例の媚薬をふんだんに盛られ、暴力的に抱かれることが続いたが、やがては彼の車の中や、公園等の屋外でも交わりを求められた。
一度など、ハジメはきらめき高校テニス部の更衣室にまでやって来て、大胆にもその場でゆかりを犯したことさえあった。

一方その頃になると、ゆかりの方も女体を完全に開発され、モラールも解体され尽くして、心底からハジメに隷従するようになっていた。
いやむしろ、自分を力ずくで汚したこの男を、深く愛するようにさえなっていたと言えるかもしれない。
経緯はどうあれ、ハジメはゆかりにとって「初めての男」だから、無意識のうちに情が移ってしまうということもあるのだろう。
まして天然大将であるゆかりのことだから、優美ほどとは言えないにしても、気持ちを180度切り替えることに大きな抵抗が無かったのかもしれない。
そしてまた何よりも、ゆかりの肉体の方が、もうすでにハジメとの交わりなくしてはいられなくなっていた。
無理もない。
オツムこそ超の付く天然だが、身体は健康そのものの、しかも性的にお年頃の女体なのである。
官能を受容する能力が元々十分あるのに加え、キ○ガイ科学者の作ったヤヴァイ媚薬を連日投与されては、それが肉の悦びに狂わないわけはなかった。
今ではゆかりの方から積極的にハジメの家を訪ね、交わりをオネダリすることさえ珍しくない。
彼女の日常は、この男とのただれたセックスに明け暮れるだけのモノに、急速に変質しつつあった。
そして、今日も・・・
「んッ・・んんッ・・・」
カラオケBOXの個室の中で、淫靡な鼻声が低く高く続いている。
室内のソファではゆかりとハジメがピッタリと身を寄せ合って座り、濃厚に唇を重ねていた。
「は・・ァ・・・」
長いキスが終わると、ゆかりは上気した顔を仰のかせ、トロンと夢を見るような顔付きになってハジメを見つめる。
それは明らかに、身も心も男の魔性に魅入られ、支配され尽くしている奴隷女の表情であった。
「フン、お前のキスもえらく情熱的になってきたな」
ハジメはあざ笑うように言いながら、ゆかりの制服のスカートをまくり上げ、薄いブルーの下着に指を伸ばす。
「それにここも、ちょいとキスをしただけで、もうベショベショの大洪水だ。ずいぶんと淫乱な身体になっちまったもんだな。ええ、ゆかり?」
「そ、そうさせたのはハジメ様なのですわ・・・」
さすがに恥じらって目元をピンクに染めながら、しかしゆかりは、男の指を追い求めるようにして、自ら腰を突き出していく。
その下着は、ハジメの言葉通り、あふれ出た淫らな蜜によってジットリと湿り、その下で息づいている秘花の鮮紅色が透けて見えていた。
駅近くにあるこのカラオケBOXは、最近学校帰りにハジメとゆかりがよく利用している逢い引きの場所だ。
館内はいつもカラオケの騒音に満ちているから、男女の交わりで多少の嬌声を上げても、他人に聞かれる憂いはない。
しかし一方、個室とは言ってもドアの一部はガラス張りだから、あまり大っぴらに組んずほぐれつをするのは少々はばかられる。利用客の中にはきらめき高校の生徒たちも結構いるからだ。
それでも最近のゆかりは、むしろそうした危ういシチュでの交わりを、自ら積極的に求めるようになっていた。
誰かに見られているかもしれないという緊張感が官能をいや増し、絶頂時の「良さ」を倍増するからだ。
そんな風に、セックスライフの充実を貪欲に追求していくようなメスに、ゆかりはすっかり堕してしまっていた。
「ところでお前・・・」
指を淫靡に蠢かせ続けながら、ハジメはふと思い出したような顔付きになって言った。
「最初にオレがコクった時、他に好きな男がいるとか言ってたけど、その男とはどうなったんだ?まだ続いてんのか?」
「い、いいえ・・・」
次第に息を荒げ、切なげに身体を揺らし始めながら、ゆかりは言った。
「イカくさい様とは、あれきり一度もお会いしていません。ゆかりはもう、ハジメ様だけのモノですから・・・」
「ほォう・・・」
ハジメはニヤニヤと下卑た笑みを浮かべて、
「それじゃ、その男からオレ様に乗り換えたってワケか。それくらいオレにゾッコンだってか?え?」
「は、ハイ、ハジメ様」
「節操のないこった。スカしたお嬢様ヅラしてやがったクセに、大した尻軽ぶりじゃねェかよ。ええ、ゆかり?」
「あうッ!・・・」
下着の上からクリットを指でピンと弾かれ、ゆかりは軽く気を遣った状態となって、男の腕の中へグッタリと身体を預ける。
「ど、どうかもう、イジワルをおっしゃらないで下さいませ・・・」
すっかり涙声になって、ゆかりは言った。
「私は、この世の中に、こんなステキな、気持ちの良いことがあるなど、これまで全く知らなかったのです。それを教えてくださったハジメ様に心より尽くすのが、今のゆかりの幸せです。他の殿方ではダメなんです。ハジメ様だけが、ゆかりを幸せにして下さいます・・・」
「ヘッ、良い心がけじゃねェか」
一度は袖にされた相手が、今や身も心も自分の完全な支配下にあることに満足し、ハジメは鼻をふくらませながら言った。
「それじゃあ御褒美に、もっと『幸せ』ってヤツを与えてやろう。セックス狂いの淫乱お嬢様が、欲求不満にならねェようにな」
パンティがヒザの辺りまで引きずれ下ろされ、ハジメの指が直接秘裂を割ってもぐり込んでくる。
そのゾクゾクするような感覚に、ゆかりが歓喜のこもったあえぎ声を上げかけたその時・・・・
「あ〜〜〜〜ッ!!」
脳天から直接ほとばしったような甲高い叫び声を上げ、早乙女優美が個室の中へ駆け込んできた。
「やっと見つけたよ!優美、ずっとハジメ様を捜していたんだよ!」
「何だよ、オレに用があったのか、優美?」
不意の闖入者に動じる風もなく、ハジメはゆかりの秘部を指先で弄び続けながら言った。
「用っていうか、ハジメ様に会いたかったんだモン・・・」
優美がふて腐れた口調で言う。
「ヒドイよハジメ様。最近古式センパイとばっかり仲良くしてて、優美をほったらかしなんだモン。優美だってハジメ様のドレーなんだよ。古式センパイばっかりイイ気持ちにしてもらうのはズルイよ。ドレーは平等なんだよ!」
他人が聞いたら何を言っているのやらワケワカメかもだが、要するに欲求不満とヤキモチとでイライラしているらしい。
彼女もまた、ゆかりと同様、今や完全にハジメのセックス奴隷と化していた。
「ケッ、どいつもコイツもドスケベの変態奴隷どもめが」
ハジメは苦笑をして座り直し、優美とゆかりの顔を見比べながら言った。
「二人とも、そんなにエッチがしてェのか?オレ様のチンコをぶち込んで欲しいのかよ?」
「うん!優美、エッチしたいよッ!」
「わ、私もして欲しいですわ!」
勢い込み、叫ぶように言う二人の少女を、ハジメは自分の前に並んで立たせ、
「よし、それなら二人とも、そこで裸になりな」
冷たい笑みを浮かべたまま、こともなげに言い放つ。
しかしそのハレンチこの上ない命令に、ゆかりと優美は嬉々として従い、アッと言う間に制服を脱ぎ捨てて全裸となった。
ハジメはその二人にテーブルの上へ上がらせると、まずはゆかりを仰向けに横たえ、その上に優美を、ゆかりとは逆方向に向かせて四つん這いにする。いわゆる6-9の格好だ。
「いいか、これから二人に勝負をしてもらうぞ」
「え?・・・」
「ショーブ?」
怪訝そうな二人に、ハジメは酷薄そうな表情を浮かべて、
「お互いの目の前に、相手の大事な部分が丸見えになってるだろう?それをイジくったりシャブったりして、先に相手をイカせた方が勝ちだ」
「あ〜、前にも優美がセンパイにしてあげたようにすればイイんだね。あーいうの、レズっていうんだよ」
「別にお前たち同士が愛し合ってるワケじゃねェから、レズとは違うだろ。要するに、奴隷同士のクンニ合戦ってだけのハナシだ」
ハジメは苦笑をして言った。
「だがな、遊び半分でやっていたら泣きを見るぞ。この勝負で勝った方にだけ、エッチをしてやることにするからな」
「ええッ?」
「負けた方は、今日のエッチはお預けだ。オレだって少しは精力を温存しねェと身が保たねェからな。いいか、オレ様のチンコが欲しいなら、死に物狂いで頑張って、相手を先にイカせることだ」
思いもかけないハジメの言葉に、ゆかりと優美の間には時ならぬ緊張が湧き起こった。
負けられない。
もしも負ければ、強烈なフラストレーションで地獄を見ることになるのは明らかなのだ。
ハジメは立ち上がり、無造作にポンと手を叩いた。
「じゃあ、始めッ!」
かけ声がかかった瞬間、すかさず行動に移ったのは優美の方だった。
勢い良くゆかりの股間へ顔を埋め、指で恥門をかき分けると、尖らせた舌先を差し込み、淫靡に蠢かせて肉襞をなぶってゆく。
「あッ!むうッ!」
ゆかりは悲鳴を上げて上体をのけぞらせ、突き上げてくるエクスタシーに歯を食いしばった。
ハジメに言われたことは理解しているし、自分も負けずに行動を起こさなければと気は焦るのだが、頭がジーンと痺れたようになって、手足が上手く動かない。
同じ天然同士でも、動物的なカンが発達した優美とでは、とっさの勝負にゆかりが後れを取ることは仕方がなかった。
「あーーーッ!!」
と言う間に勝負は付き、機先を制されたままあえなく絶頂にまで導かれてしまったゆかりは、汗にまみれた裸身をヒクヒクと痙攣させ、テーブルの上に長く伸びてしまった。
「やったァ!古式センパイ、簡単にイッちゃったよ!優美の勝ちだよ!」
顔面をヌルヌルにしてはしゃぎながら、優美はテーブルを降りてハジメの胸へと飛び込んだ。
「これで優美にだけエッチしてくれるんですよね、ハジメ様?」
「ああそうだ。優美の勝ちだからな」
「じゃあすぐにしてッ!優美、もうすごくエッチな気持ちになってるんだよ!ハジメ様にして欲しくて、ガマン出来なくなってるんだよ!」
「分かった分かった」
ハジメはソファに座り直すと、ヒザの上に優美を前方へ向けて乗せ、子供にオシッコをさせるような格好で両脚を抱え上げると、いきり立った肉の槍を一気に突き通した!
「はァあああッ!!」
それだけで瞬時に達してしまった優美は、白目をむき、オルガにブルブルと全身を震わせつつも、すぐにまた我に返り、次なる絶頂をむさぼろうと、自ら腰を揺らし始める。
「ヒモひイイよ!ハジメ様のオチンヒン、すごくヒモひイイ!もっとひてェ!優美、もっともっとヒて欲ヒいよォー!」
ヨダレを噴きこぼし、呆けたような表情で快楽にあえぎ続ける少女には、もはや先日までの、バカなりにウブで純粋だった未通娘の面影は欠片も残っていない。
そこにあるのは、媚薬によって中毒状態にされ、色に狂った、不様な奴隷女の姿だけであった。
「あ・・・」
自失状態からようやく我に返ったゆかりは、激しく交わっている二人に気が付くと、
「は、ハジメ様、私にも、私にもして下さいませ!どうか私にも・・・」
慌てて側にいざり寄って訴える。
「バカヤロウ」
ハジメはにべもない調子で言った。
「何を聞いてやがったんだ。勝負に勝った方だけ抱いてやると言っただろ。お前は負けたんだから、今日はエッチはお預けだ」
「そ、そんな・・・」
「オレのチンコが欲しかったのなら、どうしてもっと気合いを入れて勝負をしなかったんだ?オネダリすりゃあ何でも聞いてもらえるだなんて甘ったれてんじゃねェぞ。お前はオレの奴隷だ。ほどこしをくれてやるかどうかはオレが決めるんだ。分かったか?」
「そ、そうだよ、センパイ・・・」
優美が荒い息をつきながら口を添える。
「勝ったのは優美だもん。だからハヒメ様のオチンチンは、今日は優美だけのもろなんらよ。センパイ、ジャマひないでよ」
「と、いうことだ。すっこんでな、ゆかり」
ハジメは酷薄な口調で言って、
「しかしまあ、ここから出てけってのも可哀想だからな。お前はそこに座って、自分で慰めていろ」
「え?・・・」
「分からねェのか。オレたちがハメてるのを眺めてるだけじゃ退屈だろうから、独りでオナってろってんだよ。別にお前に気をつかって言ってやってるんじゃない。これは命令だぞ。とっとと始めな!」
「は、ハイ・・・」
激しくドヤされて、ゆかりはその場に尻餅をついた格好で腰を下ろし、脚をMの字に開ききると、指先をオズオズと羞恥の部分へ運ぶ。
湧き起こる肉欲を抑えかね、最近では日に幾度となく自慰に興じているゆかりだが、さすがに人前でそれを開陳するのは初めてなので、どうしても物怖じする心境になってしまう。
しかしひとたび肉の門を指で押し開けば、甘い悦びが下腹部から脳髄へと一瞬に突き上げ、その恍惚に恥ずかしさも何も忘れてしまう。後は一気呵成だ。
「はぁうッッ!!」
アッと言う間に新たな絶頂へと達し、ゆかりは鳥肌の立った裸身をブルブルと震わせながらその余韻に酔う。
しかし・・・・
「あ・・むッ・・・」
一瞬後には、オルガはすぐに強烈なフラストレーションへ変化し、少女の肉体を激しい陣痛のように責め立て始める。
その火を抑えようと、再び指を蠢かせて快楽を貪りにかかるゆかりだが、何度達しようとも、いや達すれば達するほど、淫らな渇きはさらに狂おしくなり、容赦なく身体をあぶってくるのだった。

「こ、これじゃ、らめ・・です・・・」
汗みずくになって悶えながら、ゆかりはすがるような顔付きになって訴える。
「ハヒメさまの・・・下さい・・ハヒメ様の、欲ひいです・・・ゆかり、おかひくなってしまいまふゥ・・・」
「だろうなァ・・・」
ハジメは優美を責め立て続けながら、あざ笑うように言った。
「それが『ヤレズゴロシ』の恐ろしいところさ。男のモノが目の前にあるときは、絶対にそれでしか満足を得ることが出来ねェんだ。自分でやってもエロい気分がひどくなる一方でな」
「そ・・な・・・」
「この薬の中毒になっちまったら最後、毎日休まずチンコをくわえ込み続けるか、意地張って頭がブッ壊れちまうか、そのどちらかしか選べねェワケさ。ったく良いザマだぜ」
「くる・・ヒ・・・ど・・か・・・ハジメ様・・おたふけ・・くだハイ・・・ゆかりを・・おたふけ・・だはィイイ・・・」
うつ伏せに床へ倒れ込み、ヒップを高く突き上げた格好で、息も絶え絶えに哀訴を繰り返すゆかり。
それを冷然として見おろすハジメ。
彼に抱えられ、身体を刺し貫かれて、歓喜にあえぎ続ける優美。
三者三様の狂気が絡まり合い、個室内を濃密に満たしていく・・・・
さて、このオハナシはここでオシマイである。
何の余韻も救いもなく、これでチョンなのである。
少女たちは今後も性奴隷として男に蹂躙され続けるのだろうが、まあそれはそれなりに楽しそうでもあるから、特段心配も無用なんじゃないかと思ったり。
何しろ彼女らは我々の常識など全く通用しない超絶お気楽ユニット、「天然探偵団」なのだから。
(おわり)
ⓤ戻る
ⓤ書庫別館のトップへ
|