|
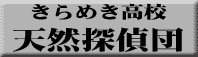
(4)天然探偵連敗(ダメだこりゃ)
古式ゆかりは夢を見ていた。
何処とも知れない闇の中で、仰向けに寝かされた彼女の周囲を、人の腕ほどもある巨大なイモムシが無数に這い回っている。
不潔な獣脂色をしたそれら怪物が肌に触れるたび、何とも言えない、ゾクゾクする異様な感覚が全身に走る。
やがて数匹のイモムシがゆかりの身体に這い上がり、口をこじ割って体内に潜り込もうとし始めた。
「あらあら、イヤですわ〜!」
彼女にしては滅多に上げない大袈裟な、しかし一般人のレベルからすればせいぜいゴキブリに驚いた程度の悲鳴を上げ、ゆかりは目を覚ました。
全身にベットリと寝汗をかいているのが分かる。
普段はお花畑で小鳥がピヨピヨ歌っているような夢しか見ないゆかりにとって、たった今見ていたそれは、まさに悪夢と言って良い忌まわしい内容であった。
「あらァ〜、ここは何処なのでしょうか〜?」
未だボンヤリする頭で周囲を見回し、ゆかりは独りごちた。
そこは見慣れない部屋の中で、フローリングの床の上にはベッドチェアとシンプルな机が置いてあるだけだ。その床の中央付近に、ゆかりは仰向けになっていた。
「ええとォ〜、何がどうしたんでしたっけ?私は〜、確か〜・・・」
どうしてこんな見も知らない場所で眠っていたのか、状況が全く飲み込めない。
とまれ、取りあえずは起き上がって部屋を出ようと考えたとき、ドアを開けて誰かが室内へと入ってきた。
「あ、古式センパイ、起きてたんだね〜!」
甲高い、脳天気な声が響き渡る。部屋に入ってきたのは早乙女優美であった。
「ああ早乙女さん、ええと、ここは何処でしょうか〜?それに・・・」
思わず問いかけて、しかしゆかりの言葉はその途中で凍り付いた。
優美の後に続いて、もう1人の人物が室内に入ってきたからだ。それも、出来れば顔も見たくない、忌むべき人物が・・・
「やあ、オレの家へようこそ」
ニヤニヤ笑いを浮かべて声をかけてきたその人物は、あの金巻ハジメであった。
「え、ここはあなたのお宅なのですか〜?どうして・・・」
「あのね、古式センパイは、ユーカイされたんだよ」
優美が朗らかに言った。
「優美がハジメ様に協力して、センパイをさらったの」
「え?え〜??」
思いがけないことを聞かされ、ゆかりは目を白黒させる。何がどうなっているのかサッパリ分からない。
「覚えていないの?今日の放課後、『少女探偵団』の活動について話し合おうって、センパイを優美の家へ誘ったでしょ?」
「・・・ああ、そう言えば・・・」
ボンヤリと記憶が甦ってくる。
確かにゆかりは優美の自宅を訪問し、そこで出されたジュースを飲みながら、とりとめのない会話をした。しかしその後の記憶がプッツリと途切れているのだ。
「あの時センパイが飲んだジュースにはね、優美がハジメ様からもらった眠り薬が入ってたんだ。それで眠っちゃったセンパイを、ハジメ様が車でここへ運んだの」
「ど、どうして・・・」
さすがに呆気に取られているゆかりに、優美は屈託のない調子で、
「あのね、ハジメ様は、古式センパイを『お嫁さん』にしたいんじゃなかったの。『ドレー』にしたかったんだって。それで優美もね、ハジメ様のドレーにしてもらったの。だから何でもメイレイを聞かなきゃイケナイんだ」
「・・・・・」
「でもね、ドレーって楽しいんだよ。ドレーになると、スッゴく気持ちのイイことをしてもらえるの。だからセンパイも、ハジメ様のドレーになった方がイイよ。優美のオススメだよ、ドレー」
「ワケの分かんねー説明はもういいよ、優美」
ハジメが辟易した調子で割って入った。
「どうせゆかりは、すぐにオレ様の奴隷にしてやるさ。そのための準備も終わってるしな」
ズイとハジメが近寄ってくる。
ゆかりは我知らずに後ろへ下がろうとして、初めて自分が置かれている異常な状態に気が付いた。
「あッ!なんですか〜、これは〜?」
着ていた制服を全て剥ぎ取られ、ショーツ一枚だけの下着姿にされている!
しかも両手首には手錠がかけられ、身体の前で連結されてしまっていた。
「今頃ビックリしてやがる。全くズレたお嬢様だな」
ハジメは苦笑して、
「だけどそろそろ、身体の方の異変にも気が付く頃だろう。どうだい、おかしな感じがしないかい?」
「え?・・・」
そう言われてゆかりは、なるほど肉体の奥からムズムズと突き上げてくる異様な感覚に気が付いた。
それはまるで、あの悪夢の中で、イモムシにたかられた時の触感そのままだ。
肌に粟の立つような気色悪さと、しかし同時に、何か身体の芯がキュンと切なくなるような心地よさとがない交ぜになった、不思議な感覚・・・
それにあおられるようにして、全身が熱く火照り、プツプツと汗が浮いてくる。悪夢による寝汗かと思っていたが、そうではなさそうだ。
「こ、これは一体何ですの?不思議な感じです・・・」
「それはお薬のキキメだよ。『ヤレブッコロス』って名前のお薬なの。スゴク気持ちが良くなるお薬なんだよ」
優美が得意げに説明する。
「『ヤレブッコロス』じゃなくて『ヤレズゴロシ』だよバカ。全然違うじゃねーか」
ハジメはウンザリした口調で言いながら、しかしゆかりの身体にニタニタと好色そうな視線を落として、
「だけどそれが薬の効果だってのは本当だぜ。アンタが寝ている間に注射してやったんだ。その効き目で、じきに天国が見えてくる。いや、もうすでに見えてるのかもな。パンツがスケスケになるほど、スケベ汁で濡れちまってるしよ」
「えッ?あッ!」
ハジメの言葉に驚き、ゆかりは思わず上体を起こして自らの下半身に目をやった。
言われたとおり、パンティはジクジクに湿って肌に張り付き、局所の形をクッキリと浮き彫りにしてしまっている。
「ど、どうしてですの?こんなことヘンですわ。あ、汗、暑くて汗をかいたんですわ、きっと・・・」
自慰の経験が無く、女性のそうした生理現象にも疎いボケボケお嬢様のゆかりは、すっかり動転し、また遅ればせながら羞恥心にも火が点いて、しどろもどろに言い訳をする。
「ヘッ、笑わせやがる」
今や優男の仮面を完全にかなぐり捨てたハジメは、ゴロツキそのものの口調で言った。
「オイ優美、ゆかりのパンツを脱がせてやりな。そんなにビショ濡れじゃあ、はいていて気持ちが悪いだろうからな」
「ハイ、ハジメ様」
優美は素直に答え、ゆかりの前にひざまずいた。
その様子は、命令に従わされていると言うより、むしろそうしたシチュを心底楽しんでいるとしか見えない。
優美がハジメにレイプされてから、まだ二日しか経っていないのだが、今や完全に彼の下僕といった体(てい)である。
元々脳ミソの容量が少ないのだか何だか、この少女にとって、モラールを180度切り替えることくらいどうということもないのだろう。全く大した自称「正義の探偵」である。
「あッ、何するんですの〜?」
優美がパンティを取り去ろうと手をかけると、ゆかりはさすがに激しく動揺して悲鳴を上げ、逃れようと腰をよじり始めた。
しかしすでに薬物の効果でマヒしている身体には、全く力が入らない。
アッと言う間に下着を抜き取られ、脚を大股開きに広げられて、しとどに濡れた女性器が為すすべなくあからさまにされてしまった。
「うわァ、ビチョビチョになってる〜!」
無遠慮に秘部を覗き込み、優美が大きな声を上げる。
「ブッコロス薬ってホントにスゴイんだね〜。アソコがヒクヒクして、どんどんエッチなおツユが出てきてるよ〜。ね、古式センパイ、気持ちイイでしょう〜?」
「そ、そんなことは・・ありません。そんな・・はしたないことは・・・お父様から・・叱られますゥ・・・」
次第に大きく胸を上下させてあえぎながら、ゆかりは正気を保とうと必死に気を張り続ける。
この天然お嬢様の「正気」が常人のそれと同一なのかは怪しいが、しかしこれまで官能というモノを知らなかった少女にとって、それに呑み込まれてしまうことには本能的に恐怖感を覚えてしまうのだ。
「ケッ、この期に及んで『お父様』だってやがる。オイ優美、二度とそんな能書きがほざけないよう、お前がゆかりをメロメロにしてやりな」
「えッ?」
「お前の指と舌で、ゆかりのアソコを可愛がってやれってんだよ。『イク』ってことがどんなもんか、よーく身体に教え込んでやるんだ」
「あー、ハイ、分かりました〜!」
楽しげに言って、優美はゆかりの股間に顔を寄せると、
「センパイのココ、優美のよりも上の方に付いてるね」
天然故に、下卑たことを無邪気に言いながら、目の前の秘裂を指で押し分け、尖らせた舌先を差し込んでいく。
「むッ!・・・」
くぐもった悲鳴を上げ、ゆかりは全裸にされた身体をキリキリと硬直させた。
まるで脳天を電撃で焼かれたかのような、強烈に過ぎる官能の味・・・・人間にそのような感覚が存在することなど、ゆかりのお花畑な脳ミソは、これまで想像だにしたことがなかった。
「へっへ〜、センパイの身体、ブルブル震えてる。優美の舌がキモチイイんでしょ?じゃあもっと良くしてあげるね」
「あ、いけません!早乙女さん、いけ・・うッ!やあッ!・・・」
優美の舌が動きを激しくしていくのにつれ、ゆかりの悲鳴は次第にすすり泣きのような響きを帯び始め、呂律も怪しくもつれ始める。
手錠をかけられた両手で優美の頭を押し戻そうともしてみるが、すでに腕からも力が抜け落ちていて、まるで無駄な抵抗でしかなかった。
やがて、固く充血したクリットが舌先で巻き取られるように刺激されると、
「ひッあああッ!!」
一際激しい悲鳴と共に、ゆかりは汗にまみれた裸身を跳ね悶え、ビクビクと痙攣させた。
頭の中が真っ白にスパークし、目は焦点を失って虚ろに宙を泳ぐ。
少女にとって、生まれて初めて体験させられる、性の絶頂であった。

「あっ、センパイ、もうイッちゃった。とってもカイカンでしょ?それを『イク』っていうんだよ」
得意気に、自分もまだ覚えて間もない言葉を解説しながら、優美は再び舌を蠢かせ始める。
「もっとイカせてあげるね。何度も何度もイカせて、イクことが大好きな身体にしてあげる。そしたらセンパイも、優美みたいにハジメ様のドレーになりたくなるよ」
「だ・・らめ・・・もう、許してくだは・・・うッ!やッ、ああッ!」
優美の舌がラビアをめくり上げ、膣口をなぞり、肉芽をツンツンと突いてくるたび、ゆかりの意識は吹き飛び、脳髄はしびれるような官能に支配される。とどまることのない、速射砲のようなオルガのコンボである。
しかも恐ろしいことに、幾度繰り返し絶頂を迎えても、それで体内の淫らな火が収まることはなく、むしろますます燃えさかって、ゆかりの身心を内からあぶり焦がしてくる。
一昨日優美も味合わされたばかりの「無間オルガ地獄」は、次第に快感というレベルを通り越し、堪えがたい苦しさとして少女を追い詰めていった。
「た、たふけて下はい・・・もう、らめ・・ですの・・・何とかひて下はい・・おえがいです・・おえがい・・・どうかァああ・・・」
むせび泣いてかぶりを振りながら、ゆかりは必死の哀訴を繰り返す。
身体中に重苦しく立ち込め続ける異様な欲求不満を解消しなければ、自分は本当に発狂してしまう・・・本能から来る、そういう確かな予感があった。
「フン、そろそろ良いだろう」
ハジメは優美の肩に手をかけて脇へ押しやり、ゆかりの前に立った。いつの間にか服を脱ぎ捨てて全裸になっている。
「どうだゆかり、頭がおかしくなりそうだろう?」
すっかり勝ち誇った調子で、ハジメは言った。
「その苦しさから逃れたかったら、オレ様を受け入れろ。オレ様のモノになると、自分で誓うんだ」
「ひ、ひかいます・・何でもひかいまふ、から、だから・・・」
「ちゃんとハッキリ言ってみな。『私をハジメ様のモノにして下さい』ってな」
「わ、わらひを・・・ハヒメ様の・・モノ・・・ハヒメ様のモノにひてくらさい・・・たすけて・・ハヒメ様・・どうかァあ・・・」
ハフハフと苦しい息をしながら、何とか言われたとおりに復唱をしようとのたうつ少女を見おろし、男はニンマリと下卑た下卑た笑みを浮かべる。
「そうまで頼まれちゃあ断れねェな。良いだろう、お前を名実共にオレ様のモノにしてやるぞ」
あざ笑うように言いながら、ハジメはゆかりの両腿を抱いて腰を持ち上げ、今や淫らな汗であふれかえっている女体の中心に自らのいきり立ったシンボルをあてがうと、そのまま一気に最奥までを突き通した!
「ぎゃあああああ!!」
一瞬、目を飛び出させそうに見開き、ふくれ上がった舌を突き出して、ゆかりは凄まじい絶叫と共に身をもがく。
優美の時と同様、破瓜の痛みは全く感じられず、代わりにこの世のモノとも思えない強烈な快感だけが、焼けた鉄柱のようにゆかりの全身を刺し貫いていた。
「ヘッ、何度やってもイイもんだな。この『新鉢を割る』って感覚は」
若いクセにジジイみたいなことを言いながら、ハジメは狙った獲物をついに仕留めた満足感にほくそ笑み、床に胡座をかくと、繋がったままのゆかりの裸身をヒザの上に抱え直した。
「あひァああッ!」
自分の体重によって、男の肉体をより奥深くへ受け入れることになり、子宮口をグリッとこじられて、一際強烈なアクメがゆかりの脳髄を突き上げる。
「どうだい、初めて味わう男の身体は?ムチャクチャ気持ちイイだろう?」
「は、はヒ・・・ヒイです、気持ひイイです・・・」
朦朧とする頭で、少女は必死にうなずきながら言葉を返す。
今味合わされている異常な官能が、果たして「気持ち良い」ものなのかどうか、処女を失ったばかりのゆかりには正直良く分からない。
しかし男の身体によってオルガに達している間だけは、最前までのあの恐ろしい苦しさを確かに忘れることが出来る。それは何にも代え難いことであると思われた。
「そんなにイイなら、もっとみっともなくヨガってみせろ!イク、イクとわめいてみせろよ!オラッ!」
下卑た要求を突き付けながら、ハジメは腰を巧みによじってゆかりを揺すり上げ、女壺を責め立てる。
「あうッ!イヒ、イイです!・・イク、イクのッ!ゆかりイキまふゥうう!」
膣が、子宮が、固く屹立した肉槍にゴリゴリと突かれ、こすられるたび、火柱のようなエクスタシーが脊髄を駆け上がる。
それに追い立てられるように、ゆかりは教わったばかりの淫らな言葉を連呼し、頭を振り乱して泣き悶えるのだった。

「これで思い知ったろう」
荒々しく腰を使い続けながら、男は傲然とした調子で言った。
「この間はよくも、この金巻ハジメ様にヒジ鉄喰わせやがったな。お前ごときがそんなこと出来るような立場だと思ってんのか?ああ?」
「ご、ゴメ、なさい・・ひうッ!やッ!・・・」
「お前は『お嬢様』なんかじゃねェんだよ!単なる世間知らずのボケ女だ!身の程ってもんが分かったか!おうコラッ!」
「分かりまひた・・わかりまひたから・・ゆるひて・・あうッ!いッ、いふ・・またイクのォ・・・」
すすり泣いて許しを乞いながら、さらに激しさを増して押し寄せてくる官能によって、少女は為すすべもなく気を遣らされ続ける。
やがてハジメの汚れた精が炸裂し、熱く胎内を満たし始めると、ゆかりは一際甲高い悲鳴を上げて、再びあの悪夢の中へ墜落していった・・・・
ⓤ進む
ⓤ戻る
ⓤ書庫別館のトップへ
|