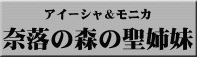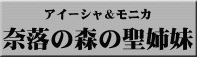|
気負いとは裏腹に、森を圧し包む不気味な緊張感は、気の強いアイーシャにも長く堪えることが荷であった。そこで一息つくつもりで、この花園へと出てきたのである。
森は確かに聖なる神域だが、その暗く重々しい雰囲気は、ややもすると息苦しささえ覚える。しかも今は、そのどこかに邪悪な敵が潜んでいるかもしれないのだ。
それに比べて、この花園の明るく華やいだ様子はどうだろう。それほど広くはないが、様々な彩りの花が咲き乱れ、森の木々の天井がぽっかりと切れた空から、初夏の陽光が惜しみなく降りそそいでいる。ここならば、とてもではないが不吉なことが起こりそうな気配のかけらもない。
アイーシャたち「光の盾」のメンバーもここを「中庭」と呼び慣わし、森を監視する任務の際には、小休止の場として利用するのが常であった。
「・・・・・?」
ふと、誰かの泣き声が聞こえたような気がして、アイーシャは辺りを振り返った。
今、自分が歩み出てきたばかりの森の中は、真昼だというのに薄暗く、奥まで見通すことは出来ないが、それでも近くに人のいる気配のないことはわかる。
「気のせいかしら・・・」
我知らずそうつぶやいた時、今度はハッキリと人のすすり泣く声が耳を打った。
「あ!・・・」
森の中ではなく、彼女のいる花園の反対側の端に、うずくまっている人の衣服らしい、濃い紫色が見える。
(いなくなった神官の一人かもしれない!)
波立つ胸を抑えながら、アイーシャは小走りに花園を横切った。
近づくにつれ、それはまぎれもなく人であることが分かったが、彼女の期待は次第に失望へと変わっていった。
エルフたちが「モナイ(笑顔)」と呼んでいる、うす黄色の愛らしい花の群落に包まれて横たわっているその人物は、まだ年端もいかない、いたいけな幼女だったのである。
(なあんだ、子供じゃないの・・・)
思わず嘆息したアイーシャの気配に気が付いて、女の子は顔を上げた。
おかっぱに切りそろえた髪に、雪のように白い肌。意志の強そうな、太くハッキリした眉の下で、大きなつり眼がちの目が油断なくアイーシャを観察している。なかなかの美少女である。
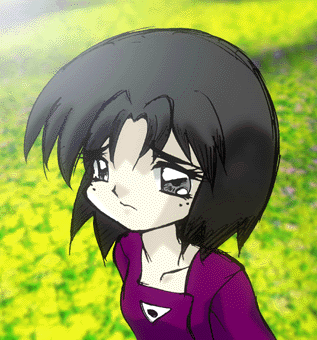
「一人でどうしたの?迷子になっちゃったの?」
我知らず優しい口調になってそう話しかけながら、アイーシャは、少女の耳が長く尖って下に伸びていることに気がついた。
「まあ・・・あなた、エルフなの?」
こっくりとうなずいた少女の目から、再び大粒の涙が一つ二つとこぼれ落ちた。暗い森の中で一人道に迷い、よほど不安だったのだろう。
少女の顔をアイーシャは知らなかったが、人口の極端に少ないエルフ族とはいえ、それでも里には二万人を越す仲間が暮らしているのだ。もとよりすべての者と顔見知りになれるはずなどないし、ましてやこんな幼子では面識がないのも当然と思えた。
「もう泣かなくても大丈夫よ。・・・いいわ、お姉さんが家まで送ってあげる、ね?」
話しかけながら少女を両腕で抱き上げようとした時、アイーシャはふと怪訝な顔つきになって動作を中断した。
「?・・・」
何かが奇妙だった。
アイーシャは大きく振り返り、辺りに人の気配がないのを確かめて、再び少女を凝視する。
少女は、アイーシャの抱擁を期待して前方に両腕を伸ばしたまま、「どうしたの?」というように首をかしげる。
いったいこのエルフの少女は、たった一人で、どうやってここにやって来たのだ?
異なる二つの世界を行き来することは、相応に修行を積み、しかるべき神術を身につけたエルフにしか出来ない。だからこそ、エルフの里は人間たちの暴虐から隔て、守られてきたのだ。ましてやこのような幼子になど!
「あなたは、いったい誰?」
用心深く後じさりながら、アイーシャは圧し殺すような声音で言った。
「どうやって、一人でここへ来たの?いいえ、誰かと一緒にだってそうそう来られるわけがないわ。神域の結界をくぐり抜けられるのは、私たち一部の神官だけだもの!」
「・・・・・」
少女はつかの間、途方に暮れたように腕を差し伸べたままでいたが、やがてふうっと大きなため息をつくと、無言のままゆっくりと立ち上がった。
「あッ・・・!」
アイーシャは目を見張った。
今まで少女が横たわっていた辺りではモナイの花が一様にしおれ、茶色く変色して花弁を巻き縮めつつある。
そればかりかその一帯の地面は薄く蒸気をあげ、土中の虫たちが次々と這い出してくるではないか!
「ククッ・・・」
血のように赤い唇の端をキユーッと歪めて少女が初めて発した声は、嘲笑とも自嘲ともとれる、忍びやかな笑い声だった。
彼女がその全身から発するすさまじく禍々しい気配に、アイーシャはようやく気がついた。
(まさかこんな子供が、「光の盾」の神官たちを・・・?)
「そう、その通り・・・」
アイーシャの心中を見透かしたように、少女は口を開いた。
「あんたが探していたのは、このあたしだよ・・・」
それは確かに甲高い子供の声音なのだが、そこに宿る気配には、聞く者を圧倒するような邪悪な凄みがあった。
「あんたのお仲間たちは、散々なぐさみものにして魂を抜かせてもらったよ。・・・しかし無警戒にあたしを抱き上げなかったところをみると、あんたは他の連中より、少しはおつむが働くようだ」
アイーシャの胸が、早鐘のように動悸を打ちはじめる。目の前にたたずんでいるのは、どう見ても十に満たない無垢な幼子だ。だがその正体は、手練の神官をものともしない、何か恐るべき怪物らしい。
と、少女はふいに深く頭を垂れ、何事かをブツブツとつぶやきはじめた。そのつぶやきがかすかに耳に入り、アイーシャは愕然として身をすくませた。
それは暗黒の神を崇める邪悪な導師らが唱え用いる、恐るべき呪詛の呪文だったからである!
「・・・とく見よ!とく見よ!永劫なる時の端境に、かの人いまそかり!右のかいなは天に、左は地に!その御頭に戴きしティアラを、そのまといし金色の法衣を、乙女の生き血で清めよ!やあ!やあ!・・・」
次第に声高に呪文を唱えながら、少女はやおら着物の裾をひるがえして、アイーシャに向かって一直線に突進してきた!
目の高さで真っ直ぐに前に伸ばした右腕の先からは、強烈な殺気がほとばしっている。呪文を唱え終わった時、そこからはさらに邪悪なエネルギーが放射されてアイーシャをからめ取るだろう。
実戦経験など無いアイーシャだが、その身体は目前に迫った危機に対応すべく反射的に動いた。
野生の鹿のような俊敏な動作で真横に飛びすさり、同時に身にまとった濃紺のケープを左右にはね上げて、両手で印を結ぶ。
「昔いまし、今いまし、全能なるイヴァンの名において精霊たちに命ずる!かの神の健やかなることを、力をもって示せ!天の馬の蹄が及ぶあらゆる地、光には安息を、闇にはいかづちを・・・」
驚くべき速さで攻撃の呪文を唱え続けながら、次々と両手の印を組み替えてゆく。この高速詠唱の巧みさこそが、アイーシャをして、姉には負けないと強烈に自負させている根拠なのだ。
と、彼女の髪が次第に逆立ち、その色を濃緑から淡い黄色へと急速に変えはじめた。この一帯の精霊たちが彼女の呼びかけに応じ、光の力を行使するために活性化を始めたのだ。
同時に辺りの花々が、集結しつつある精霊たちの光の圧力を支えかね、アイーシャの素早い移動の跡に美しい絨毯となって倒れ広がる。
「・・・汝らこの天地のいずくにおるとも、去りて来たりて光のしもべたる我がかいなを支えよ!よや、とく来たれ!」
タタン、とリズム良くステップを踏み、手を打ちながら身体を一つひねったと同時に、アイーシャは千文字を越える長い攻撃呪文を詠唱し終えていた。
謎の少女は自分も呪文を唱え続けながらアイーシャを追って花園を押し渡っていたが、その両目は次第に驚愕の色をたたえて大きく見開かれていった。
アイーシャが尋常ならざる技量の持ち主であること、そして信じがたいが、自分の態勢が不利であることに、ようやく気がついたらしい。
「ギギッ・・・!」
追いつめられたげっ歯類が発するような呪いの呻きを歯の外へ押し出し、少女は呪文の詠唱を中断して歩みを止めた。そして、間合いをはずしてアイーシャの攻撃から逃れようと、あわてて身をひるがえす。
だが、遅かった。
「ブナ・オ・イー(破魔の大槌)!」
花園にアイーシャの澄んだ気合いが響き渡り、高く盛り上がった胸の前で交差させた腕が、まばゆい光を放つ!と同時に巨大な光の柱が天から真っ直ぐに降り来たり、まごつく謎の少女を押しつぶすように屹立した!
ドドドォンンン!
一拍遅れてすさまじい大音響と衝撃波が発生し、辺り一面のか弱い花々をことごとくなぎ倒す。
森全体が、震えどよめいたかのようであった。

「・・・・・」
アイーシャはしっかりと両目を見開いたまま身じろぎもせずに立っていたが、やがて大きく息をついて肩の力を抜くと、組んだ両腕を左右にくつろげ、残心の姿勢をとった。
逆立っていた髪が、徐々に落ちついた濃緑の色を取り戻しながら肩の上に舞い戻ってくる。
胸の鼓動も、すでにおさまりつつあった。
見ると、一瞬前まで少女が立っていた辺りでは、花々が放射状に地につくばい、その中央には彼女がまとっていた深紫のドレスだけが、くたくたと取り残されている。
勝利の感慨が、次第次第にアイーシャの中に高まり満ちてきた。
(やった!あのマグダレナ様でもかなわなかった邪悪な敵を、この私が一人で封滅したんだわ!これでみんなに私の力を認めてもらえる。もちろんお姉さまにだって!)
自らの神術で他人の生命を奪ったのはこれが初めてであり、そのことに心がまったく痛まないではなかったが、光の神術は邪悪なる者のみを滅し、心清らかな者には傷一つつけることはないのだから、それによって散滅した少女は、やはりよこしまな魔物であり自業自得だったと納得できる。しかもこの魔物は、仲間たちを三人も手にかけた憎むべき敵ではないか。
そこまで考えて、アイーシャは我に返ったように辺りを見回し、ついで目の前に取り残された少女のドレスを拾い上げようと身をかがめた。
(いなくなった三人は、まだ死んだとは決まっていないわ。「魂を抜いた。」なんて訳の分からないことを言ってたけど、どこかに幽閉されているだけなのかもしれない。もしそうだとしたら・・・)
その行方をつきとめるために、この忌むべき衣が何かの手がかりになるかもしれない。それになによりも、自分が今回の騒動を単独で解決したことの唯一の証拠、戦利品なのだ。
(ぜひとも持ち帰って、皆に示さなければ・・・)
手を伸ばしてドレスの裾をつかむ。
と、
「・・・?」
意外な手応えに、アイーシャはオヤッ?となって手もとを凝視した。
ドレスの生地は何かよくわからないが、表面の様子から、サラサラとした木綿のような手ざわりを予想していたのだ。しかし。
手に取ったそれは、ベッタリと粘っこく、重たかった。まるで何かでぐっしょりと湿っているかのようだ。
(まさか、あの子の血でも染み込んだのかしら?・・・)
しかしそんなはずはない。光の神術は、相手が邪悪な者であれば、その血の一滴までこの世界から放逐せずにはおかないのだから。
「あッ!・・・」
その時アイーシャは、ドレスをつかんだ右手が激しく引っ張られたような気がして、小さく叫び声を上げた。
いや、気のせいではない。
見るとドレスは端の方からひとりでに細切れとなり、生き物のように動いてアイーシャの手首をからめとりつつあるではないか!
さらに各々の細切れはアメーバの触手のようにその先端を伸ばし、先を争って彼女の肘へ、肩へと、恐るべき勢いで這いあがってきたのである!
「こ、これは?・・・」
一体何が起こっているのか分からず、さしものアイーシャもすっかりうろたえた声を上げた。
さっきまでドレスだったその物体は、今ではすっかり元の形を失って紫の蛇の群のように彼女の首までを被い尽くし、今度は胸元に向かって急速にふくれあがりつつある。
しかも恐ろしいことに、その触手に被われた身体の部位は、まさに蛇の毒に冒されたかのごとく、冷たくしびれて感覚を失ってゆくのだ!
「うぅ、くッ・・・」
すでに上半身をすっかり触手に被われたアイーシャは、自由にならない身体を何とかよじってそれを振りほどこうともがき、かえってバランスを失って、ガックリと両膝をついた。
いつの間にか、顔いっぱいに冷や汗が吹き出していた。
「ク、クククククク・・・」
その時、ゾッとするようなひそやかな忍び笑いが、苦悶する彼女の耳朶を打った。と同時に、息のかかるほどのすぐそばに、何者かの気配が唐突に感じられた。
「だ、誰?・・・」
なんとか首だけを左右にねじって笑い声の主を求め、それを果たしてアイーシャは愕然となった。
ほんの一瞬前、空中に散滅したはずのあの少女が、すぐ右脇に全裸でうつ伏せになり、イタズラっぽい笑顔を浮かべて彼女を見上げているではないか!
「あ、あなた、いったい・・・?」
あまりに信じがたい光景にそれ以上言葉が続かず、アイーシャはただ茫然と少女の美しい肢体を見おろした。
「あんな子供だましの神術で、このあたしに髪の毛一筋ほどの傷でもつけられると思ったのかい、ええ?」
目を細め、口の端をキュッと歪めた得意げな顔で、少女は相変わらずの大人びた口調を使った。
「『勝った。』と思ったろう?そいつが命取りなのさ。ケンカってのはな、いつでも先に歌った方が負けなんだよ!」
「おッ、おのれ化け物ッ!」
激しい怒りと屈辱に呻き、自らの油断に歯がみをしながら、しかしアイーシャは立ち上がることが出来ない。既に、全身の感覚が無くなりつつあった。
それにしても、アイーシャの神術を「子供だまし」と揶揄したこの少女は、いったい何者だろう?
「クククク・・・動けまい?あたしに触れた者は、それでもう助かりっこない、おしまいなのさ。あたしは闇そのものなんだから。もとは普通のそのドレスだって、着古すうちにあたしの力の影響を受けて、強力な闇の生き物に変わったのさ。言ってみりゃあたしの身体の一部なんだ。それに触れたお前は、やっぱりもう逃げられっこないんだよ・・・」
勝ち誇ったようにしゃべり続けながら、傍らで少女が立ち上がる気配がしたが、アイーシャはもうそちらを見ることも、声を立てることすら出来ない。
触手はいまや彼女の全身を覆い、身体中の力を、思考力までをも、急速に吸い取り尽くそうとしていた。
「お姉・・・さま・・・」
か細くつぶやいて、アイーシャはついに頭から散り敷かれた花びらの上に倒れ伏し、気を失った。
「クク・・・クククククク・・・」
4匹目の美しい獲物を仕留め、満足げな少女の忍び笑い、そしてサワサワという触手のさざめきが辺りを支配する。
花園にふりそそいでいた華やかな日差しはいつの間にかすっかりと陰り、上空を不吉な鉛色の雲が分厚く覆い始めていた・・・。
→次章を読む
→3へ戻る
→最低書庫のトップへ
|