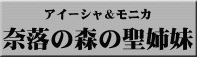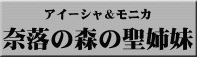|
「んッ、うぅン・・・」
どのくらいの時が経ったのだろうか、アイーシャは深い意識の闇の底からようやくぽっかりと浮かび上がり、仰向けに寝かされた姿勢のまま、ぼんやりと目を開いて辺りを見回した。
(私・・・どうしたのかしら・・・?)
そこはヌメヌメと濡れた灰色の岩肌に囲まれ、奥がほとんど見通せないほど、薄暗く、寒々とした穴ぐらの一隅だった。
(ここは・・・「滴(しずく)の洞窟」?・・・)
イヴァンの森には、イヴァン神がエルフの里への抜け道を押し開けた時に、その腕から流れ落ちた汗が穿ち開けた、とたわむれに語り伝えられる小規模な洞穴が無数に口を開いていて、エルフたちはそれらを「滴の洞窟」と呼び慣わしていた。
ここはそのうちのどれかではないか・・・アイーシャはまだハッキリとしない頭でぼんやりとそう考えたのだが、むろん確かなことなど分かるべくもない。
(・・・・・!)
その時、一切のいきさつ・・・・・エルフの里を襲った不可解な事件、そして勢い込んで出かけて来たものの、不覚にも一敗地にまみれた自分・・・・・が、激しい屈辱感と共に、瞬時に蘇ってきた。
(あの化け物は?・・・)
あわてて身を起こそうとしてそれが全くままならず、アイーシャは自分の身体に起こっている異変にようやく気がついた。
「あッ・・・!」
なんということか。
全身を生まれたままの姿に剥かれ、両腕は背中の後ろに、脚はあぐらをかいた形にきつく縛められ、まだ成熟しきっていない女性自身を、あからさまにさらしてしまっている。
手足の自由を奪っている何か軟質の縄様のものは彼女の胸部にも巻き付けられ、左右の乳房を、それぞれ四角く括った窓から、絞り出すように緊縛している。
もともと大きめに充実した彼女の胸乳は、さらに高く、いびつに隆起して硬く張っていた。
横たえられた体の下には、何か獣の毛皮らしい物が二枚、しとね代わりに敷き広げられて、彼女の裸身を岩床の冷たさから隔てていたが、何よりも、自らのこの屈辱的な恥態が、プライドの高いアイーシャには耐え難い苦痛であった。
(あの悪魔の仕業だわ!・・・おのれッ、絶対にこのままでは済ますものか!)
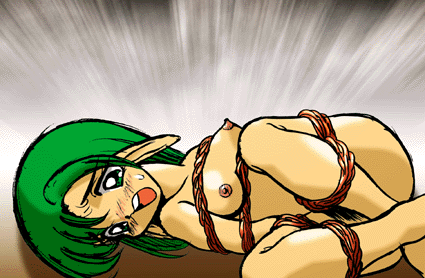
彼女の激しい心中の罵りが耳に入ったかのように、闇の奥からあの少女が朦朧と立ち現れた。
元の様に、あの忌まわしい深紫のドレスを身にまとい、口元には例の邪悪な笑みを張り付かせている。
この洞穴は、この化け物の根城なのかもしれなかった。
「ようやくお目覚めかい、お嬢ちゃん?」
相変わらずの、不敵で高圧的な言葉づかいで、少女は声をかけた。それにしても、明らかに自分より一回り近くは年上のアイーシャに対し、「お嬢ちゃん」とはどうだろう。
「こッ、この獣め!よくもこんな真似を・・・は、恥を知れッ!」
怒りのあまりに上手く言葉が続かない。
例の触手による麻痺はすっかり消えていたが、縛られた身体はやはり自由にならず、アイーシャはもがきながら激しく少女をにらみつけた。
少女は、冷たく微笑んだままアイーシャをじっと見おろしていたかと思うと、やおらにその小さな素足を前に送って、アイーシャのつつましく閉じた無垢な花唇を、親指で乱暴にこじり割った!
「ああッ!」
不意の辱めにうろたえ、またその痛みに耐えかねて、アイーシャは哀れな声をあげる。
「恥を知るのはそっちの方じゃあねぇのかい?無様な格好だぜ、ええ?」
あざけりながらアイーシャを見おろすその目は、いささかの人間らしい情も浮かべていない。
「やッ、やめてッ!・・・やめなさいッ、無礼者ッ!」
誰にも触れられたことのない羞恥の柔肌を弄ばれる屈辱、また秘奥を傷つけられるのではないかという恐怖から、アイーシャはヒステリックに絶叫し、何とか後ずさろうと不自由な身体をもがく。
「フン・・・」
小馬鹿にしたように鼻を鳴らして少女はひとまず足を引っ込めたが、今度はアイーシャのそばに片膝をつくとその髪をわしづかみにし、もう一方の手で、硬く張りつめた乳首の片方を乱暴にひねりつまんだ。
「いギイッ!」
激痛に、思わず身体が弓なりになり、食いしばった唇から苦悶の呻きがほとばしる。
「口のききかたに気をつけるんだね。勝った方にだけ、好きに喋る権利があるっていうのがケンカのルールだよ。お前はもう、あたしの生け簀に捕まった雑魚も同然さ。煮るかフライにするかは、これからゆっくりと決めてやる・・・」
ぐい、と髪を引っ張ってアイーシャの顔を仰のかせようとするその力は、とても七つ八つの子供のものとは思えない。まるで強力自慢の男性のようだ。
そして、間近に彼女を覗き込むその瞳は、ほとんど光沢が無く鈍く濁っている。
「・・・・・」
相手の底知れぬ不気味さ、得体の知れなさに、アイーシャは思わず圧倒されて何も言い返せなくなった。
「ククク・・・」
少女は、アイーシャがひとまず観念したと思ったのか、つかんだ髪をぞんざいに振り放して立ち上がり、彼女を横目に見下ろしながら再び話し出した。
「まあ、お前の神術も筋は悪くなかったがな・・・いかんせん経験不足さ。あと五百年もみっちり修行をすれば、このあたしにたんこぶ程度の傷は負わせられるかもしれないが・・・」
「ご、五百年?・・・」
アイーシャは愕然としてそう聞き返す。と同時に、この不気味な少女の実体の、そのほんの一部が、唐突に理解された!
「わッ、分かったわ!あなた、その見かけ通りの年齢じゃないのねッ!何百年もの年を経た、邪悪な化け物なんだわッ!」
「おいおい・・・」と少女は軽く苦笑して、
「今頃そんなことに気がついたのかい?全く呑気なお嬢ちゃんだよ。まあ正確なところはあたしも忘れちまったが、少なくともお前の百倍分の年月は、この世の空気を吸ってるぜ・・・」
この大人びて高圧的な口調、不敵な物腰、そしてアイーシャの神術をものともしない、練達された闇の法術・・・・・それらは皆、千歳を越えるらしい化け物にして当たり前のことであった。
(く・・・当然気がつくべきだった・・・)
まやかしの外見にとらわれて敵の真の力を見誤った自分のうかつさを呪い、アイーシャは唇をかんだ。
「それにしても邪悪な化け物ってのはひでェな・・・。このあたしだって、見ての通りお嬢ちゃんと同じエルフ族だぜ。確かに多少歳はとってるがな・・・」
「う、嘘ッ!」
意外な少女の言葉に、アイーシャは強い調子で食ってかかる。
「確かにエルフ族は人間に比べれば長命だけど、二百年も生きられればいい方だわッ!千歳を越えるエルフなんて、絶対いるもんですかッ!あなたはただ、エルフの姿をまやかし装っただけの、よこしまな化け物なのよッ!」
激しく言いつのりながら、その時彼女はあることに気がついてハッとなった。
背後に束ねられた両腕の先では手首が十文字に交差し、その指先だけは自由に動かすことが出来る。これならば印を結び、神術を行使して、手足の縛めを振りほどけるではないか!
意識は取り戻したものの、我が身に起こった出来事の異常さにすっかり動転し、こんな簡単なことに今まで気がつかなかったのだ。
(化け物め、私の身体を縛り上げて安心したんでしょうが、とんだ盲点ね。フン、呑気なのはお互い様だわ・・・)
アイーシャの中に、再び敵に対する憎しみと闘志、そして勇気がふつふつと沸き起こってきた。しかし、それを気取られてはならない・・・・・反撃の態勢が整うまでは、絶対に・・・。
じりッ、じりッ・・・。
気付かれないよう用心深く、アイーシャはしとねの上で身体の向きを変え、重ね結ばれた両手首を、少女からの完全な死角へと運んで印を結んだ。そして心の中で、一心に拘束解除の呪文を唱え始める。
(・・・全能なるイヴァンの名において精霊たちに命ずる!汝ら何故あって光りの進む道の監督を怠るか?とく見よ!瞰視せしうつつ世に、影濃き業の有りや無しや?・・・)
口述で唱える場合に比べて、呼びかけに応ずる精霊の数は半減するだろうが、この程度の縄をちぎりほどくことは容易なはずだ。
少女は横を向いたまま、アイーシャの挙動にはまったく気付かない様子で得意げに話し続けている。
「・・・現在のエルフには、お前たちのように光を崇め奉る一族と、その逆に暗黒の神に仕える一族の二種類がいるということを聞いたことがあるだろう?あたしはつまり、暗黒側に与してその力を司る一族の者、闇のエルフなのさ!」
「やッ、闇のエルフ?」
心の中では呪文を詠唱し続けながら、アイーシャは愕然として問い返す。
闇のエルフ!・・・・・確かにその存在は、古くからアイーシャたち光の一族の間でもささやき伝えられてきた。しかしそれは・・・。
「嘘よッ!闇のエルフなんて、根も葉もない単なる言い伝えだわッ!実際に見たり会ったりした者なんて誰もいないんだもの!でまかせはいい加減にして、正体を明かしたらどうなの、卑怯者ッ!」
「でまかせではない!」
やおらに険しい声音になって、少女はアイーシャの方に向き直るとにらみつけた。
企みに気付かれたのかと一瞬緊張したアイーシャだが、ややあって少女は元の不敵な笑顔を浮かべ直し、今度は教え諭すような口調になって話題を続けた。
「いいかい。はるかなる昔、我々エルフ族が忌まわしい人間どもの蹂躙にあい、滅亡の危機に瀕したことは知っているだろう?その時お前たち光の一族は、イヴァンの導きによって隣接する異世界へとのがれ、そこに隠れ住むようになった。しかしあくまでこの世界にとどまり、生き抜こうとするエルフたちも、僅かにではあるがいたんだよ・・・」
話しながら少女は、何故か懐かしむような、妙な表情になった。
もしかしたら本当に、この怪物は神話の太古から生き長らえ、そこに語られる出来事を目で見、耳で聞いてきたのかもしれない・・・。ふと一瞬そんな感慨を覚えて、アイーシャは思わず背筋が寒くなった。
「彼らは人間どもに追われ、逃げ出すことを潔しとしなかったのさ。だってそうだろう?悪いのは無情な人間どもであって、エルフ達は追い立てられなければならないようなことは、何もしていないんだから。そこで彼らは、この世界で人間どもに怯えることなく暮らすために、光ではなく暗黒の神の力を借りることにしたのさ。尻尾を巻くんじゃあなく、逆に人間どもに思い知らせてやるためにね。それがあたし達、闇のエルフ族なのさ・・・」
「そ、その話が本当なら・・・」
アイーシャは呪文を半ば唱え終わり、あとほんのわずかの時間を稼ごうと、自ら問いかける。
「今は仕える神が違っても、あなたと私たちは元々同じ一族、言ってみれば同胞じゃないの!それがどうして、同じエルフ族を傷つけ辱めたりするの?拐かした3人を、いったい何処にやったのッ?」
「ククッ・・・」
少女は短く笑って、
「よく聞きな、お嬢ちゃん。あたしたち闇に仕える者たちはな、お前たち光の一族のように、精進潔斎してりゃあそれで不足無しってわけにはいかねぇんだ。生きていくためには、他人の魂を吸い取り喰らわなきゃあならない。生け贄が必要なんだよ!そのかわり魂さえ喰らっていれば、このように永遠に若く、美しく、身体と命を保てるのだ。そのためには、喰らう魂がエルフのだろうと人間のだろうと、選り好みはしないのさ!」
少女はやおら牙のように伸びた糸切り歯をむき出し、これまでとうって変わった凶暴な笑顔でアイーシャを見下ろした。
「あたしたち闇のエルフを見た者がほとんどいないのは当たり前さ。同じ闇の一族同士で魂を共食いし合って次第に数を減らし、今ではそれに勝ち残った真の強者が、世界にほんの二、三人、生き長らえているにすぎないんだからな。このあたし・・・・ベスマ・アムピトリーテ様が、そのうちの一人なのさ!」
少女が初めて名乗り、獰猛な捕食動物としての素顔をむき出しにした時、アイーシャも呪文の詠唱を終わって、精神の全てを手足の縛めに向けて集中していた。
ついに反撃の時だ!
(イラ・スウォート!)
「神の人差し指」という意のその気合いに応え、精霊たちが身体中の縛めをちぎりほどき、空中に霧散させる!・・・・はずであった。
(・・・・・?)
何の変化も現れないことにうろたえ、アイーシャはおろおろと、胸に脚に巻き付き締めあげている、不気味な肉色のより縄を眺めおろす。
(なぜ縛めがほどけないの?まさか、私に限って呪文の詠唱を間違えたりするはずがないわ!・・・)
「クク・・・クククククク!・・・・・」
再び、あざけるような忍び笑いを始めた少女に驚き、アイーシャは慌ててそちらを振り向き見上げた。
少女はおかしくてたまらないという様に、目を細めて首を細かく左右に振っている。
「言っておくがな、その縛めは神術では外せないぜ。というより、それに縛られている限りは、いかなる神術も行使することは出来ないのさ」
アイーシャは愕然として、少女の白い顔を凝視した。
(すべて見透かされていた!)
百戦錬磨のこの怪物は、やはり完全に抜かりなく、アイーシャを就縛していたのだ!
「はるか東の国に、ギオーイという、闇の力を持った馬鹿でっかいカエルがいてな。その縄は、そいつの腸をよりあわせて作ってあるんだ。黒界鎖といって、その周囲から光の精霊を退け、封じる効果があるのさ」
勝ち誇ったように話し続けながら、少女は不意にかがみ込んでアイーシャのおとがいに手をかけ、その顔を自分の方にひねり向けてじっと覗き込んだ。
「まったく往生際の悪いお嬢ちゃんだよ。あたしからすればあんたなんか赤ん坊以下だってことを、そろそろ思い知らせてやろうかね。その身体にたっぷりとな・・・」
不気味に凄んでみせながら、細かく震えだしたアイーシャの肩を撫でさする。
(まッ、まだあきらめてはダメよ!反撃のチャンスはきっと来る・・・きっと来るわ!・・・・・)
目前に迫った恐怖と絶望から無理やり目を背け、アイーシャは歯を食いしばって自分を叱咤し続ける。これから訪れる、凄絶な地獄を想像も出来ずに・・・。
→2を読む
→前章へ戻る
→最低書庫のトップへ
|