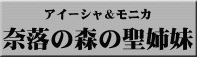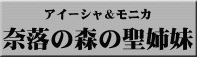|
「ベスマ」と名乗ったその少女(いや、少女の姿をした千古の怪物)は、アイーシャのおとがいを放して元通りに寝かせると、自分も添い寝をするように傍らにうつ伏せになった。
しとね代わりの敷き皮はそれほど幅広ではなかったが、その小さな身体をアイーシャと並び横たえるには十分である。
「魂を吸い取り喰らう」とは、具体的にどのような行為であるのかは分からないが、この怪物が、自分に何か淫らな辱めを加えるつもりであることを、アイーシャは本能的に察知して身を固くした。
「ククク・・・」
その危惧の通り、ベスマは妖しい嬌笑と共に、身動きのとれないアイーシャの裸身に覆い被さると、その血のように紅い唇で、硬く絞り出された薄桃色の乳首を含み吸いあげてきた!
「ああッ!」
プチュッ、チュッ、チュッ・・・・・。
淫らな音色と共に、アイーシャの無垢な桜ん坊は、きつく吸われ、皓歯に軽く噛み挟まれ、舌の先で弄ばれ、そしてまた吸い上げられる。
ただでさえ緊縛によって大きく張り膨らんだ乳房が、ますますはじけるような弾力を加え、乳首はコリコリと硬く尖って鋭敏さを増していった。
「やッ、やッ!・・・」
あえぎ、絶望的に身をもがくアイーシャの頭を万力のような右の腕力で押さえ込み、もう一方の手は、イヤらしく指を踏みながら、きつく縛められた裸身を這い下ってゆく。
その指先が、むごたらしく押し開かされ、固定された両脚の中心・・・・ひっそりと息づいている秘めやかな羞恥の部分を狙っていると知った時、アイーシャはひときわ大きく声を上げて激しく身をよじった。
「やッ、やめてッ!触らないでッ、汚らわしいッ!」
「・・・・・」
意外にもベスマは、アイーシャのその絶叫に応じるかのように手の動きを止め、乳首を辱める作業も中断して、スッと身体を起こした。
「?・・・・・」
アッサリと引き下がった敵の態度にかえって不気味さを覚え、アイーシャは不安げにその白い顔を見上げる。
この化け物が、微塵でも仕留めた獲物に情けをかけるとは、とても信じられなかった。
「フン、汚らわしいは恐れ入ったな」
とベスマは微苦笑して、
「それならば、そのとりすました聖女づらが、どこまで本物か試してやろう。自分の心の内奥こそが、どれだけ汚らわしく、淫らな欲望に満ち満ちているか、思い知るがいい」
立ち上がり、ゆっくりとあの忌まわしいドレスを脱ぎ始める。
今ではすっかり害のない清潔な着衣の仮面を装い、それはサラサラと衣擦れの音を立てて岩床にすべり落ちてゆく。
「あッ!・・・」
衣の下から現れたベスマの裸身に、アイーシャは、小さく驚きの声を上げて目を見張った。
その顔と同様、雪のように白く、輝くような肌。ようやくそれと分かるほどに、ほんのわずかに隆起した胸乳。弛みなく、腰へ脚へとつながる、硬く幼げな線・・・。
永劫の時の間、幾多の犠牲者たちの生命を吸い取ってきたためか、その身体つきも、肌のみずみずしさも、まさしく十にも満たない童女としか思えない。
異様なのは、すべやかな白い双脚の間に挟まれた、その女性自身であった。
まるで熟れた水蜜桃のように露を含んで豊かにふくらみ、これから始まる陵辱の儀式への期待からか、心もち反り返って複雑な肉の内壁を垣間見せているあわい目。
そしてその頂点には、異様に大きく、葡萄色に怒張した肉芽が、黒々とした繊毛に縁どられて顔をのぞかせている。
そこにはまるで、成熟しきった女性のそれのように、毒々しいまでの大輪の雌花が咲き誇っていたのである!
「!・・・・・」
異様な光景に言葉を失って見つめるアイーシャを尻目に、ベスマは自らの手で硬く小さな胸のふくらみを揉みさすると、目を閉じて身体を揺らし始めた。
「ンン・・・」
切なげな吐息とともに、淡い色をした豆粒のような愛らしい乳頭が、プックリと盛り上がって硬さを加えてゆく。そして、内面の高ぶりを表すかのように、白い肌が徐々に薄いピンクに色づき、火照りを帯び始める。
「う・・・」
淫らさに、小さく呻いてうつむこうとしたアイーシャだが、続いて起こった異様な現象に、思わずその目を釘付けにされた。
グチュグチュチュッ!
ベスマの媚肉の亀裂がはじけるようにまくれあがり、いやらしい音と共に大量の果汁を放出し始めたのと同時に、その下腹部が次第次第にと大きくふくらみ、せり出し始めたではないか!
「ううオオッ!」
歓喜とも苦悶ともつかない呻きを上げてベスマが反り返り、その恥骨のやや上の辺りがムクムクとボリュームを増して波をうつ。
まるでその皮膚の下で、凶暴な何者かがうごめいているかのように・・・・。
(なッ、何?・・・一体何が始まるの?)
目前の光景のあまりの異常さ、おぞましさに目を丸くし、アイーシャは息を呑んで凝視をし続ける。
やがてベスマの下腹はまるで妊婦のように膨れ上がり、上気したその肌に、どす黒い入れ墨のようなものが朦朧と浮かび上がった。
(あ、あれは!・・・)
弓のような形が背中合わせに組み合ったその模様は、暗黒の神が自らの下僕たちに与え刻するといわれる、呪われた印形であった!
「オオオォーッ!」
感極まった様子で、ベスマは片手を自分の恥門へと運び、赤黒く勃起した肉芽の先端を勢いよくつまみひねる。
それが、まるでスイッチであったかの様だった。
バシュウウウウーッ!
はちきれんばかりに膨れ、よだれをこぼしながらも口を食いしばっていた女陰が、ついに堪りかねたように大きく扉を開き、体液のほとばしりと共に、驚くべき多量のグロテスクな内容物が、そこから吐き出されてぶら下がった!
「!・・・・・」
あたかも実際に妊婦が破水したかのようなショッキングな光景に、アイーシャは驚き呆れて、膣口からへその緒のように続くその忌まわしい器官を声もなく眺める。
じゅるッ、じゅるるるるッ・・・。
不気味な音と共に、それは粘液にまみれてのたうっていた。
ベスマの幼い身の丈ほどはあろうか、蛇のように長く、表面にはぶくぶくと醜い肉腫が連なり、先端近くには巨大な眼球様の物が二つ、ギョロギョロと金色に輝いて辺りをうかがう。
口吻にあたる部分はその縁がひだ状に盛り上がり、中からイソギンチャクの触手のような物が、オレンジ色の先端を無数に覗かせている。そして腹側からは、細く滑らかな突起が、左右前方にまるで前足のように伸びていた。
この恐るべき魔女は、あろうことか、自らの胎内に別の生物を住まわせ養っていたのである!そしてそれは、アイーシャもよく知っている、忌まわしい害獣であった。
「ぐ、グヌゥフ・・・」
「そうさ。可愛いだろう?もう六百年近くも、あたしと共生してるんだ・・・」
ベスマは、鎌首をもたげたそれをいとおしげに腕に巻き、舐め上げる。
「グヌゥフ」とは弱い闇の力を持った半水棲の軟体生物で、水浴びをしている女性の局部といわず肛門といわずもぐり込み、強力な催淫性の体液を分泌してその人間を廃人にしてしまうことから強く恐れられていた。
しかもベスマがはらんでいたそれは、通常観察される個体よりも倍以上は長大で、永き時を経て強力な魔物と化していることが想像できた。そしてその末端は彼女の肉孔に深く根を張り、組織的に融合を果たしているらしい。
文字どおり、癒着共生しているのだ。
「今ではこいつが、あたしのために餌を取り、咀嚼して体に送ってくれるのさ。そのかわりに、あたしはこいつに安全なねぐらを与える・・・まさに持ちつ持たれつって訳なのさ」

ぎゅッ、ぎゅッ、ぎゅッ、・・・・・。
不気味に音を立て、粘液をしたたらせながら、それは狙いを定めるかのように首を振り立て、アイーシャの方へ伸び進んできた。
ベスマの言う「餌」とは他ならぬ自分であり、相手がこの下等な生き物によって、その身体を、精神を、喰いちぎり辱めようとしているのだと気付いて、アイーシャは激しい恐怖に駆られ悲鳴をあげた。
「いッ、いやッ!・・・こっちへ来させないでッ!」
それを待っていたかのようであった。
恐るべき生きた生殖器は、ムチのようにしなうと、アイーシャの顔面に向けて一気に突進し、そのまだあどけなさの残る桃色の唇を強引にこじ割り押し入った!
「あぉごおッ!」
狼狽して避ける間もなく、生臭いその肉塊を口いっぱいにほおばらされ、アイーシャは喘いだ。
「噛み切ろうったって無駄だぜ。下等とはいえ、闇の祝福を受けた魔物なんだからな。胃袋の奥まで突き通されたくなかったら、舌で優しくご奉仕するんだね」
勝ち誇ってベスマが言う通り、ブヨブヨした表皮の様子とは裏腹に、その下には鉄のように強靭な筋肉がさらに硬さを加えつつあった。
とてもではないが、アイーシャのか弱い顎の力など受け付けそうもない。
じゅぶッ、じゆぶぶッ!・・・・・
「ううあッ!・・・」
のど元深く突き入れられ、吐き気のあまり思わず身をのけぞらせる。はちきれそうにふくらんだその肉栓を何とか追い出そうと舌を押し当てるが、それはたちまち口吻から蠢き出た無数の触手にからめ吸い取られ、逆に抜けなくなった。
「うふゥ、ふッ、ふッ、ふッ・・・」
息苦しさに、鼻だけでつく呼吸が次第にせわしくなり、唇の端からはとどめる術もなく涎が一筋、二筋と流れつたう。
栄えある「光の盾」の新進気鋭は、今やはしたなく裸身を縛め開かされたうえ、淫売婦のような屈辱的な行為を強制されて哀しく喘いでいた。
(か、神の使徒であるこの私に、こんな淫らな仕打ちを、よ、よくも・・・)
思わず悔し涙がにじみ、長い睫毛の先に露のように小さく溜まってゆく。
「おやおや、お楽しみはまだ始まったばかりだってのに、もう泣いてるのかい?そんな頼りない甲斐性じゃ、これから永遠に続く家畜としての暮らしはとても辛抱たまらないぜ」
余裕たっぷりのベスマの揶揄、とりわけ「家畜」という言葉が、アイーシャのプライドをざくりと傷つける。
(ゆ、許せない・・・!)
憎しみをあらわにして敵をにらみ返したその時、口腔いっぱいにふくれあがったおぞましい肉塊の先端から、何か大量の生暖かい液体があふれ出て口中を満たし始めた。
「うォぶォごゥッ!・・・」
思わずむせかえり、顔を激しく振る。
その魔物の体液が、いかに危険で忌むべきものであるかは十分に分かっていたが、きつく栓をされた唇からは、こぼし吐き出す術もない。アイーシャは身の毛のよだつような思いで、その恐るべき毒液を飲み下すしかなかった。
「うッくッ・・・」
彼女が目を閉じ、絶望的な表情で白い喉をこっくりと動かすのを見ると、ベスマは両目を満足げに細め、突き出た犬歯を血のような色の舌で舐め回した。
「どうだい?甘い、闇の蜜の味は?直に天国が見えてくるよ。光じゃない、暗黒の天国がね・・・」
「・・・・・」
その言葉通り、アイーシャの若い肉体は、一分とたたない内に闇の毒液の恐るべき作用に翻弄され始めた。
身体中が内側から熱く火照り、ほの紅く上気してじっとりと汗ばんでくる。そして舌で辱められたための鬱血がようやくおさまりかけた乳首が、再び硬く、高く尖り、そこからジーンという微電流のような痺れが、繰り返し伝わってくる。
「ううッ?・・・」
理解不能の感覚に、アイーシャは信じられないという面持ちで、思わず呻き声を漏らした。
乳首に全身の神経が集中したようになり、そこを誰かに思いきりつまみ、揉みしだかれたい・・・・我知らずにそんな淫らな欲求がふくれあがり、理性を暗く覆っていくのだ。
(何なの?この感じは?・・・あッ!)
背筋を戦慄が走り抜け、全身がピクッと反り返る。
生まれて初めて経験する、官能のうずきであった。自分の内奥にそんな感覚が潜んでいることなど、アイーシャは想像だにしたことがなかった。
(こ、これが・・・処女をも半日で狂い惑わせるといわれる、「グヌゥフの汗」の魔力・・・)
せわしく息をつきながら、次第に強く、大きく、身体中に打ち寄せ始めた異様な恍惚の波に、アイーシャは怯え、小刻みに震え始める。
聖なる神官とはいえ、子供を産める年齢なのだから、性の知識にまったく欠けるということはない。しかし自慰の経験も無い彼女にとって、今全身を侵しつつある官能の熱は、未知の快感であると同時に、おぞましい闇のいざないなのであった。
「う・・くくッ・・・」
眉根を寄せ、必死に声が漏れそうになるのを抑える。
(ま、負けてはダメ!・・・・私は・・光の・・・神・・・官・・・)
まるで突き上げるように襲ってくる強烈な性感に、思考が白く途切れがちになる。
ここでこの恍惚感に溺れて自分自身を見失えば、二度と光に溢れた清らかな世界に帰れないという、本能的な予感があった。
(冷静に・・なるの・・・。心を・・・静めて・・・ううッ!)
しかしアイーシャの必死の抵抗をあざ笑うかのように、肉の痺れはいよいよ女体の中心に集中しつつあった。
内股はいつの間にかすっかり汗の玉に覆われ、その熱い滴りが、堅く閉じ合わされていた羞恥の門の合わせ目に沿って流れ込み、溶かしこじ開けようとする。
「うふうッ!・・・」
アイーシャは思わず縛められた手指をきつく握りしめ、花芯の一帯をキューンと支配したやるせないような切なさに堪えた。
まるで、何者かが媚肉の内側をずりずりと這い回っているような異様な感覚・・・そしてその恥ずかしい部分を、思うさま押し開き、こね回して欲しいという、信じがたい、獣のような淫らな欲求・・・。
(ああ、ダメッ!・・・どうなってしまったの、私の身体は?・・・うッ、いやッ!)
いたたまれずに腰をゆすると、逆にそれが刺激となって、気の遠くなるような恍惚感が花奥から脳天までをズーンと駆け抜ける!
「ヒはああッ!」
必死にこらえようとしていた羞恥の声が一気にほとばしり、アイーシャは上気しきった身体を猛然ともがき始めた!
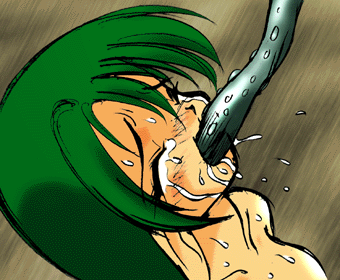
「あくッ、あッ、あッ、あッ、あッ!」
とてもじっとなどしていられない。背中に重ねて縛め敷かれた手首の痛さも忘れ、アイーシャは狂ったように不自由な身体を捩り、首を振り、むごたらしく栓をされた口から嬌声をふきこぼし続ける。
「あふッ、むむ、ふうッ・・・」
口の端からは涎が、睫毛からは涙が、しぶきとなって細かく舞う。その恥ずかしさがさらにアイーシャの官能を高め、動揺を誘うのだった。
「クククククク・・・ずいぶんと気持ちが良さそうじゃないか、ええ、お堅い聖女様?」
ベスマは、その凶暴な生殖器をアイーシャにくわえほおばらせたまま彼女の上に屈み込み、キリキリと充血した乳首を人差し指ではじいた。
「むうッ!」
それだけで目が眩むような快感が頭の中に炸裂して一瞬気が遠くなりかけるのに、ベスマはそのグミの実のような乳首を、さらにクリクリとこね、なぶり、舐め吸い上げる。
「ふあッ、あッ、いふァーッ!」
ガクガクと身体を痙攣させて悶えながら、アイーシャは自分が、底の無い暗黒の穴のふちに、ようやく指の先でつかまっていることを自覚した。そしてその指が、力尽きる寸前であることも・・・。
(誰か助けて・・・私・・・おかしくされちゃう・・・身体中、おかしく・・・ううッ!・・・)
「ククククク・・・・」
今や目の前の美しい獲物が断末魔のあえぎを上げ始めたことに満足げに微笑み、ベスマは細長く尖った乳首を含みなぶっていた唇を放すと、その上体をアイーシャの下半身へずりずりと移動し始めた。
「あッ、あッ・・・」
ベスマの小さな鼻が、頬が、汗にまみれた下腹部をこすり刺激して、アイーシャが小さく悲鳴を上げる。
そして悪魔の指先は、さっきは一端あっさりと引き下がった羞恥の部分を、今度こそ犯し、苛み始めた!
「あぐゥウウーッ!」
最も恐れていた箇所への愛撫にうろたえて一際大きく呻くアイーシャにはかまわず、ベスマはじっとりと湿ったその恥門をつまみ、めくり上げ、亀裂に沿って指を滑らせる。
「ひうッ!」
ププッという微かな音と共に、溜まりに溜まっていた愛の露が、一気に道をつけられて吹き出し溢れ、内股に幾筋も透明に糸を引いた。
同時に、ふくれあがった花びらがはじけるように左右に開かれ、真紅色の内蔵をみるみるあからさまにしていく・・・。
「いふァッ、いふァーッ!」
もはやとても理性で押し殺せるような感覚ではなかった。狂ったように顔を振り、涎をこぼし、身をのけぞらせるアイーシャ・・・。
誇り高き光の聖女は、今や心と身体を二重にがんじがらめにされ、果てしのない恍惚と官能の嵐に弄ばれ、泣き悶えていた。
(あうッ!・・・いやッ!・・・私もう・・あッ!・・・お願い、誰か・・ああイヤッ!・・・)
来るはずのない助けを心中で必死に求め、少しでもおぞましい指をかわそうと身をよじる。あぐらに縛られた脚を何とか閉じ合わせたいという望みのない願いが、鼠径部の筋肉をキューッと緊張させるのが哀れであった。
「クククク・・・思い知ったかい?ええ?」
指のリズムを早めながら、ベスマがあざ笑う。
恐るべき悪魔の爪が、今こそ自分の魂を鷲掴みにし、引きちぎりかけていることを、アイーシャは朦朧とした意識の片隅で悟った。
「聖女様と気取ってみたって、ひと皮剥けばとんだ淫売じゃねェか。あたしに向かって汚らわしいとは、聞いて笑わせるよ。さあそろそろ、とどめを刺してやろうかねェ・・・・」
言いながら、ベスマはしとどに濡れそぼったアイーシャの花芯に顔を寄せ、硬く尖らせた舌の先で、花裂に溜まった蜜をすくい取るように舐め上げる。
そして同時にその指が花びらの上端部をいやらしく揉みほぐし、硬く充血した肉芽を、薄い包皮から引きずり出すようにつまみ上げた!
「あくァッ!」
あらゆる敏感な神経が集まり、むき出しになっている急所をついに蹂躙されて、アイーシャは絶望的に目を見開き、歯を食いしばった。くわえ呑み込まされているのが強靭な魔物の肉体でなければ、喰いちぎっていたに違いなかった。
そしてベスマのもう一方の指先が、まるで仕上げをするかのように、きっちりと絞り込まれた菊の座を丸くなぞった時、アイーシャはついに光の神の姿を見失った!
「やッ、あッ、ィはアアアアーッ!・・・」
縛られた身体を弓なりに硬直させ、清らかな光の世界への決別の絶叫が、塞がれた唇の隙間から嫋々と響き渡る。
やがてその全身から力が抜けると、見開かれた両目から輝きがスーッと失せ退き、同時にこらえていた涙がドッとあふれ出して頬を伝った。
「うぅ、うッ、うッ、うッ、うッ、うッ・・・・・」
汗と体液にまみれた下腹をヒクヒクと波打たせたまま、顔を屈辱に歪め、むせび泣きを始める。
光の聖女アイーシャが、生まれて初めて味わうオルガであった・・・。
→1へ戻る
→3を読む
→最低書庫のトップへ
|