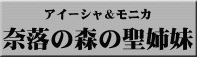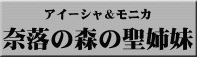|
惨めに縛められた姿のままで、アイーシャは休む間もなく何度も何度も女芯を刺し貫かれ、淫らな声を上げさせられ、気をやらされた。
そしてそのたびに、行為から与えられる気の遠くなるような快楽と引き替えに、何か自分の精神の一部が引きちぎられ、吸い出されるような、理解不能の感覚を味あわされたのである。
(これが、ベスマの言う「魂を吸い取り喰らう」ということなのかもしれない・・・。もし魂を吸い取り尽くされれば、死ぬか気が狂うかしてしまうのだろうか・・・)
時折フッと戻ってくる理性の片隅で、アイーシャはそう気がついて恐怖におののいたが、光の神官としての能力を失った今、もはや抵抗の術は何も残っていないのだ。
どんなに泣いて許しを請うても、ベスマは冷笑を浮かべ、下品な言葉でアイーシャの乱れ様を揶揄しては、残酷に陵辱を続けるばかりであった。
将来を嘱望されていた優秀な光の巫女とはいえ、所詮は処女を失ったばかりの未成熟な女体である。普通ならばとっくに体力が限界を越えているはずだったが、例の恐るべき媚薬を無理矢理飲まされるたびに、再び身体中に、生き生きとした活力と、同時に淫らな欲求が満ち溢れ、我知らずのうちに歓喜の声を上げてしまうのだった。
(このままでは本当に、自分から淫らなことを求めるような身体にされてしまうかもしれない…ああッ、お願いだから誰か助けに来てッ!・・・)
闇の力によって自分の肉体が徐々に作り替えられていくような恐怖感にとらわれ、アイーシャは、差し伸べられるはずのない助けの手を求めて涕泣する。
実際、アイーシャが、よこしまな誘惑に打ち勝つために長い間厳しい修練を重ねてきた光の神官でなければ、とっくの昔に全身を闇の気に支配され、正気を無くしていたに違いなかった。それほど執拗に、悪魔は彼女の破瓜されたばかりの肉体を責め苛み、弄び続けていたのである。
そして、今現在も続けられているこの淫靡な行為は、いったい何度目の交わりになるのか・・・。
「うッ、あッ、はあッ!・・・」
縛められた身体を今度は前に倒され、後ろからヒップを抱えられるようにして、ベスマの長大な生殖器を残酷に突き込まれているアイーシャであった。
ジュポッ、ジュッ、ジュポッ・・・。
青黒く、ブヨブヨとしては見えるが、その実強靭な闇の蛇が、アイーシャの肉壺の底を突き破らんばかりに激しくピストンする。
そこは、つい先程鮮血の涙を流したばかりの無垢の秘唇とは思えないほど、淫らに花開き、ヌラヌラとした鮮紅色の粘膜をのぞかせていた。
アイーシャ自身も、今は既に処女地を踏み荒らされる苦痛をほとんど感じなくなっており、純粋な性のエクスタシーだけに全身を翻弄されていた。毒の酒と暴虐によってもたらされるこの感覚を、エクスタシーと呼べるならだが・・・。
「あくァあああーッ!・・・」
恥ずかしい嬌声と共にあらゆる欲望を吐き出し尽くしてアイーシャが果てると、ベスマは自分も堪能しつくしたかのようにフウッと大きく息をつき、後ろに身を引いた。
肉腫だらけの醜い男根がズルーッと引き抜かれ、二人分の体液が幾筋もキラキラと糸をひく。
「ククククク、すっかり満腹したぜ・・・」
ゆっくりと犬歯を舐め回しながら、引き抜いた闇の毒蛇をねぎらうように腕に巻く。
「うう、うッ、うッ、うッ、うッ・・・」
高く突き上げたままのヒップをヒクヒクと震わせ、再びすすり泣きを始めるアイーシャ・・・。
まるで心臓内の血液をこそげ取られるような「抜魂」の感覚・・・そしていくら押し殺そうとしても淫らな欲望に打ち負かされ、あられもない痴態を演じてしまう自分への嫌悪・・・それらが混然となった絶望感が、洞窟の闇と共に、彼女の心を押しつぶそうとしていた。
そんなアイーシャの汗に光る身体を、ベスマは再び乱暴に引き起こして後ろから抱きすくめる。
「あッ!・・いやッ!」
また陵辱が始まるのかと、思わず泣き声を上げたアイーシャを感心したように眺め、
「ほーお。これだけ責められても未だに正気を失わないとはねェ・・・。ククク・・・お前はなかなか見どころがあるよ・・・」
謎めいたことを言って見せながら、生け贄の火照った耳たぶを唇で愛撫する。
「気分はどうだい、ええ?聖女様は、いったい何回おイキになったんだい?」
「・・・・・」
答えようもなく、目を閉じて顔をそむけようとするアイーシャに対し、ベスマは身体の下から片手を割り込ませて、乱暴に秘部をまさぐった!
「あうッ!」
「・・今さら生娘ぶって気取らなくてもいいじゃねェか、あァ?ここんとこが何べん気持ちよくなったかって聞いているんだぜ!」
「あッ、許してェッ!・・・」
チュクッ、チュッ、チュッ、チュッ・・・。
人差し指と薬指でふくらんだ媚肉を押し拡げ、中指で、勃起したままの核をこすり上げてゆくベスマ。
みるみるうちにアイーシャの雌花はほころびはじけ、ザクロの実のように果肉と果汁をほとばしらせた。
何の防備もままならず、もうその指の動きだけで、絶頂まで一気に導かれそうな危うさであった。
「うッ!・・お願い・・ああイヤーッ!・・・」
「・・さあ白状しな。ここが何回気持ちよくなったのか・・・」
「そ、そんな・・・」
どうしても答えかね、アイーシャは涙を一杯に溜めた眼で、哀願するようにベスマを見上げる。
汚れを知らなかった光の神官にとって、あまりにつらい言葉の拷問であった。
「へえ、そうかい、少しも気持ちよくならなかったのかい?それじゃあ今度こそ良くなるように、もういっぺんこいつをくわえさせてやろうねェ・・・」
意地悪く言いながら、長大な男根を、アイーシャの股間を通して前へ這い出させ、グネグネと蠢かして見せる。
快楽と羞恥の、地獄のような責めがまざまざと心によみがえり、アイーシャは怯えきった悲鳴と共に身をすくませた。
「いやッ、もうやめてッ!・・・気持ちよかったです!・・もう十分、気持ちよかったですから!・・・許して・・それだけは・・・・・」
プライドも、聖女としての貞淑さも恐怖心に打ち負かされ、半狂乱で訴えるアイーシャの顔を、ベスマはニタニタと薄ら笑いながらグイと押さえつける。
「フフン、何回くらいだい?」
「・・・わ、わかりません・・数え切れないくらい・・・何回も・・・気持ちよくなりました・・・・・」
「どんなふうに?・・・」
「・・・何だか、お腹の中が・・・溶けちゃったみたいになって・・・すごく気持ち良くなって・・・・。うううッ、もう許して下さいィイ・・・・・」
次第に涙声になり、ついには顔中をワナワナと震わせて、アイーシャはガックリと首を折った。嗚咽が、食いしばった口元から徐々に高く漏れ出してくる。
「うう、うッ、うッ、うッ・・・・」
「よおしよし、イイ子だね。そんなに気持ちが良かったのかい・・・」
獲物が完全に観念したことを知り、ベスマはこれまでと打って変わった柔和な口調で、アイーシャの髪を撫でつけた。
その表情は、ネコが瀕死のネズミを爪でいたぶる時のように余裕に満ち、しかし一片の憐れみも浮かべてはいない。
「うあウッ、ううッ、うあッ・・・・」
相手が追い打ちの手をひとまず休めたことに安堵したのか、アイーシャは堰を切ったように大きく嗚咽し始め、両目からはこらえていた涙がドッと溢れだした。
美しい顔が、見る見るうちに涙と鼻水にはしたなく彩られ、ますます面持ちの悲壮感を強めていく。
「ううおッ、えッ・・・おッ、お願い・・・うッ・・堪忍・・してください・・・。どうか・・・もう許してくださひィイイイイー・・・・・」
血を吐くようにそれだけを訴えると、後は言葉にならずに泣き崩れるアイーシャ・・・。
完膚無きまでの、惨めな敗北であった。
身体も心も隅々までなぶり尽くされ、抵抗の術を全てもぎ取られたうら若き神官は、いつしかすっかり敬語で魔物に哀訴するだけの、うちひしがれた奴隷と化していた。
これがほんのわずか前まで、自信に満ち、はつらつと神術をふるっていた誇り高き聖女の姿だとは!
「ふん、すっかり大人しくなったね。感心だ、年長者は敬わなくちゃな・・・。さあさあ、もう泣かなくていいんだよ」
ベスマは、泣きじゃくるアイーシャをまるで子供をあやすような口調でなだめ、
「お行儀を覚えたご褒美に、いいものを見せてやろう。その前に、ひとまず脚を自由にしてあげるからね・・・」
そう言うとアイーシャを再びしとねの上に横たえ、小さな手のひらを、彼女の両脚を縛めている肉色の縄に向けてかざす。
「はッ!」
鋭い気合いと共にベスマはかざした手のひらを素早く握り、また開き、再び握った。
と、どうだろう。アイーシャの脚にまとわりついていた縄の表面がみるみる生気を失って白っぽく変色し、やがて粉状になってサラサラと滑り離れていくではないか。
拘束解除の呪文とは違う、何か恐ろしい闇の力であった。
「う・・・」
久しく押し開かれたままだった両の脚をようやく解き放たれ、アイーシャは力尽きたようにくたくたと膝を閉じ合わせた。
ああしかし、ジーンと痺れたままの花壺を支配しているこの違和感は何だろう?
まるで、あの長大な肉の槍が、未だにそこに突き入れられたまま残っているような、奇妙な感覚・・・。
自分が、一日前には想像もしなかった肉体に作り替えられてしまったことを実感し、アイーシャの眼から再び涙が溢れ出た。
(どうしてこんなことに・・・ああ、お願い、夢なら今すぐに覚めて!・・・)
しかし、これが紛れのない現実であることを思い知らせるかのように、ベスマの叱責のの声が激しくアイーシャの耳朶を打つ。
「さあさあ立つんだよ。・・・ほらさっさとしな!」
まるで家畜を追い立てるような傲岸な口調に、言いしれぬ屈辱を覚えながら、それでもアイーシャは、仕方無しに立ち上がろうと脚を突っ張った。しかし長い間縛め固定されていた両脚は、ほとんど麻痺しかかっていて、なかなか力が入らない。
「・・・どうしたんだい。あんまり気持ちが良くって腰が抜けちまったのかい?」
「ううッ・・・」
下品な揶揄に顔をしかめながら二度、三度と前にのめった後、アイーシャは後ろ手縛りのまま、ようやくフラフラと中腰に起き上がった。
逆Yの字に踏ん張った脚がガクガクと震え、今にもその場にへたり込みそうな様子は、まるで生まれたばかりの仔馬のような頼りなさである。
「ようし、じゃあそっちへ向かって歩くんだ。言っておくが、脚が自由になったからといって、逃げようなんて考えるなよ」
命令と共に背中を乱暴に手でどやされて、アイーシャは思わず、ヨチヨチと数歩前に足を送った。
「あッうッ!・・・」
純潔を散らされたばかりの秘唇、そしてまだ火照りの収まらない肉芽にズキンズキンと性感のショックが走り抜け、今にもしゃがみ込んでしまいそうになる。
とてもではないが、走って逃げられるような状態ではなかった。いや、たとえ走れたにしても、この恐るべき魔物から、とても逃げおおせるわけはなかったが・・・。

「何をモタモタしてんだよ。ほら、しっかり歩きなッ!」
再び容赦なく背中からベスマに追い立てられ、アイーシャは泣き声を上げて後ろを振り返った。
「イヤッ!・・わ、私をどうするつもりなんですかッ?」
進むように促された洞窟の奥は暗く闇に閉ざされ、そこではさらに無情な処刑の用意が整っているのかもしれないという不安が、アイーシャの歩みをためらわせていた。
ベスマは立ち止まってククッと短く笑い、
「なにも今すぐ魂を吸い取り尽くして、木偶(でく)人形にしちまおうってんじゃないよ。それどころか、お前が正気を保つよう頑張れば、いつまでだって抜け殻にならずに済むんだぜ。その方があたしだって長く楽しめるしな。わかるだろう?パーポ(鶏のような家畜)は卵を生まなくなったら価値が無いんだよ・・・・・」
ではこの化け物は、自分を文字どおり家畜のように繋ぎ養って、生かさず殺さずにジワジワと生き血をすするつもりなのだ。
処女を奪われ、神術も使えない惨めな身体にされたのだから、もしかしたらもうこれで解放してもらえるかもしれない・・・そんなはかない望みを抱いていたアイーシャだったが、やはり相手には全くその気が無いのだと知って、ガックリとうなだれた。
もう自分には、光に満ちた自由な生活は、二度と戻ってこないのだろうか・・・元は同じエルフ族の魔物に、諾々として魂を吸い取り尽くされるしかないのだろうか・・・。
「クククク・・・・可哀想だが、お前は運が悪かったねェ、お嬢ちゃん」
ベスマは立ち止まったまま、アイーシャの絶望にダメを押すように話し続けた。
「さっきも言ったとおり、あたしはエルフだろうが人間だろうが、容赦なくエサにしてきたよ。とは言っても、普段はもっぱら人間の魂を喰らっているのさ。連中はあたしにとっても仇だし、何しろエルフ族は極端に数が少ないからね。お前たちは知らないだろうが、イヴァンによって守られている光のエルフの居留地は、他にも世界中にいくつかあるんだよ。まあその大半は、あたしたち闇のエルフが襲って滅ぼしちまったけどな。・・・分かるかい?今やお前たち光のエルフの魂は、あたし達にとっても、滅多にありつけないご馳走なのさ。たまに居留地を見つけたって、滅ぼすのがはばかられるくらいにね。人っ子一人いなくなっちまうより、ある程度目こぼして、エルフの人口が増えてくれた方がいいだろう?つまりはエサの養殖ってわけさ・・・・」
「だッ、だったら・・・」
不自由な上半身をよじり、アイーシャは思わず挑むような口調になって、
「私たちの里も、そっとしておいてくれたらいいじゃないですか。私も、いい加減に解放してくれてもいいでしょう?もう決して、あなたに逆らったりはしませんから・・・お願いです・・・」
言い募りながらも、みるみる両目が涙で潤んでゆく。
「だから、お前は運が悪かったと言っているだろう?」
ベスマは「諦めな」というように首を振ってみせて、
「確かに普段だったら、お前たちの居留地も、後のお楽しみにってんで、見て見ぬ振りをしてやったかもしれないよ。いや事実、五十年ほど前にこの辺りを訪れた時には、黙って見逃してやったのさ。さすがのあたしも、イヴァンの聖域たる「エルフの里」へ直接入ることは難しいし、ときたま這い出してくるエルフを、森の中でじっと待ちかまえてるってのも面倒だからねェ。だけど今は、そんなことを言ってられねぇんだ。今年は特別な年だからね・・・」
「と、特別な年って?・・・」
思わず聞き返したアイーシャに、しかしベスマは再び首を小さく振って、
「そいつはまだ知らなくてもいいことだ。とにかく今のあたしには光のエルフ族が必要で、そこへお前が、間抜けにも飛び込んできたってわけだよ。さあ、いいかげんに先へ進みな!いいものを見せてやるって言っただろう?」
強くうながされ、アイーシャは仕方なく、再びとぼとぼと歩き出した。
洞窟は思ったよりも広く、しばらく行った所で三方に分岐していた。指示されて真ん中の枝道に入り、すぐにまた二つに別れる道を今度は右に進む。そこからは心持ち下り坂になり、それを降りきったところで、ベスマはアイーシャを引きとどめた。
そこは枝道よりもわずかに広くなったホール状の小部屋であった。岩壁に浅く穿たれた穴には小さな蝋燭が灯されていたが、その明かりはひどく弱々しく、さほど広くもない部屋も、奥まで見通すことが出来ないほど頼りない。
「・・・・・」
不安げに辺りを見回すアイーシャの顎をベスマは後ろからつかみ、前方の一隅へとひねり向けて、耳元にささやいた。
「何をキョロキョロしてるんだい。ほら、あそこを見てごらん」
言われて見つめた辺りには何かが黒々とわだかまっていたが、闇が濃くて、その正体がよくわからない。
「・・・・?」
なおも見つめるうちに次第に目が慣れてきて、それが、岩壁に寄り添い、横たわった人の形・・・しかも若い女性の身体であることがぼんやりと見えてきた。そしてその、整った顔立ちも・・・・。
「ま、マグダレナ様ッ!」
「ククククク・・・そうさ、お前が捜していたお仲間だよ。ようやく会えて嬉しいだろう?」
その姿は紛れもなく、親衛隊の四方の守護の一翼「南の礎」を束ねる長、マグダレナであった!
しかしこれが、神術の天才といわれ、アイーシャ達の憧れの的であったエリート神官と、本当に同一人物であろうか?
後ろにからめ取られた両腕、だらしなく開き投げ出された脚、そして首にはめられた明るい緑色の首輪・・・。
両目は薄く開かれているが全く焦点をむすんでおらず、意識があるのかどうかも分からない。さらに口の端からはよだれが、鼻からは鼻汁が間欠的に溢れ出て、その顔をはしたなく彩っていた。
なんという惨たらしい囚われ様!
年に似合わぬ重厚な威厳で、さっそうと部下を従えていた姿からは想像も出来ない、変わり果てたマグダレナの姿であった。
「どうだい、無様だろう?魂をほぼ吸い取り尽くされて、木偶同然なのさ。なあ、マグダレナ?」
言いながらベスマは、マグダレナの汗に濡れた乳房をグイと揉みしだく。
「ううふァああ・・・」
痴呆のように弛みきった表情の中にチラリと歓喜の色をのぞかせ、マグダレナは獣のように呻くと、不自由な体をよじった。
そして次第に息を荒げながら、物をねだるような仕草で腰を前へ突き出す。
「へァ、へァ、へァ・・・・」
それはすでに「白銀のひじり」と謳われた誇り高き幹部神官の姿ではなく、まるで自らの汚れた欲望をあさましくさらけ出した、一匹の雌の家畜であった。
「ご覧の通り、死んじゃあいないが、物を考えることはほとんど出来なくなってるよ。性欲だけに支配された、肉の人形ってところさ。前に捕まえた二人も奥の部屋に繋いであるけど、まぁほとんど同じ状態だあねェ・・・」

「イヤっ、イギゃアアアアアーッ!」
唐突にアイーシャは、縛められた身体を猛然ともがきながら絶叫し始めた。
あまりにも無惨なマグダレナの姿に、(自分も今にこうされるのだ!)という凄絶な恐怖が一瞬に身体中を走り抜け、パニック状態となったのである。
そう・・・本能だけの惨めな肉人形と化したマグダレナは、まさしく未来のアイーシャ自身の姿であった。
処女を引き裂かれ、毒の酒に全身を侵され、悪魔の触手で内蔵をかき回される・・・今、自分も味合わされたばかりの地獄の拷問に、昼も夜も翻弄され、さしものマグダレナも、魂を一滴残らず吸い尽くされ、なめ尽くされたに相違なかった。
そしてその精神も限界を越え、後には抜け殻のような肉体のみが残ったのだ・・・。
「ヤッ、ヤあッ・・マグダレナ様ああああーッ!・・・」
同様に責め抜かれれば、いずれ自分も、このような獣同然の姿にされてしまう・・・凄まじい恐怖感に血の気を無くし、眼をかっと見開いて、悲鳴を吐き出し続けるアイーシャ・・・。
「クククク・・・・」
嬌笑を浮かべながら、ベスマはアイーシャを静かに抱き寄せて膝を折らせ、紅唇を重ねた。
「んンン・・・・」
塞がれた唇からかすかに呻き声を洩らし、アイーシャの身体が次第に弛緩していく。
まるで全身の力が、口から吸い取られるような感覚であった。
やがてベスマは、グッタリと抗いをやめたアイーシャから口を離し、その頬を支えるように両手で挟み込むと、言い聞かせるように小さくささやいた。
「・・・どんなに騒いだって逃げられやしないよ。このマグダレナのようになりたくなかったら、何べんあたしと交わっても、理性を失わないように頑張るしかないのさ。もっとも、大人しくあたしのいうことを聞いて、心底から服従するというのなら、これから先の責めには、多少手心をくわえてやってもいいがな・・・・」
「なッ、何でも言うことを聞きますッ。お願い、助けて・・・」
必死に頷き、すがるような哀訴を繰り返すアイーシャ・・・。
絶望的に見開かれた両目の端から、涙が細かく宙を舞った。
廃人同様のマグダレナの姿が、彼女の心から、抵抗の意志を完全に奪い去っていたのである。
あの勝ち気で誇り高い聖女の印象は、もはやどこにも残っていなかった。
「よしよしイイ子だね。そうやって素直にしていれば、あたしだって、お前を今すぐに抜け殻にしちまうようなひどいことはしないよ・・・」
ベスマは紅い小さな舌で、アイーシャの目尻から優しく涙を舐め取りながら、
「さっきも言った通り、今のあたしには光のエルフが必要なんだ。それも『特別』なヤツがね・・・。このマグダレナには相当期待していたんだが、結局たったの二日でこのザマさ。これじゃあ使えやしないよ。だけどお前ならば、今度こそあたしの眼鏡にかなうかもしれないからねェ・・・」
特別なエルフとは何なのか、そしてそれを何に使うというのか・・・ベスマの真意は相変わらず不明だったが、アイーシャはそんなことを気にする余裕さえ失っていた。
この魔物が自分をどう扱うにしろ、今すぐマグダレナのような生ける屍にされてしまうよりは、マシに決まっていたからである。
「・・・それじゃあ手始めに、お前の身の上を色々と聞かせてもらおうか。家族とか、お友達のこともね・・・。あァそうそう、まだお前の名前も聞いていなかったねェ・・・」
うながすようにツンと顎を持ち上げられ、アイーシャは涙にふくれた目で、悪魔の勝ち誇った白い顔を見上げる。
(・・・もうダメ・・・どうやっても逃げられっこない・・・。私は少しでも生き長らえられるように、このおぞましい化け物にかしづくしかないんだわ・・・・)
自分が、恐るべき捕食動物の爪に掛かった哀れな生け贄に過ぎないことを、彼女は今こそ、ハッキリと思い知らされたのだ。
「・・・私は・・アイーシャ・・・。両親は、もういません・・・。家族は・・・姉が一人だけ・・・・」
震え、すすり上げながら、血を吐くような思いで、屈辱的な告白を始める。
固く閉じた睫毛の間からまた涙があふれ出し、痛いほどに固く尖った乳首の先に、ポタポタと滴り落ちていった・・・。
→前章へ戻る
→2を読む
→最低書庫のトップへ
|