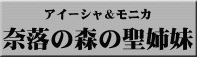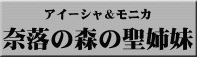|
(一体どうしたというの、アイーシャ?・・・)
自室の窓際に立ち、モニカは先程からイライラと煩悶し続けていた。
唯一の肉親であり、「光の盾」においては部下でもある妹アイーシャが失踪してから、すでに三日が過ぎていた。
親友マグダレナの捜索を持ちかけようと帰宅した我が家から、しかし妹は忽然と姿を消しており、以来行方は杳として知れないのだ。
(・・・私に行き先も告げず、何処へ行ってしまったの?・・・いいえ、多分あそこへ行ったのね。だからこそ、私に黙って出かけたのだわ・・・)
そう、モニカには、妹の行き先はあらまし見当がついていた。そしてだからこそ、その安否が気遣われるのだった。
(・・・森へ、「イヴァンの掌」へ出かけたのね。・・・馬鹿なアイーシャ、なんて早まったことを!・・・)
自分に対して強烈なライバル意識を抱いている妹が、今回の不可解な事件を解決しようと、スタンドプレーに打って出たのはおそらく間違いなかった。そうでなければ、モニカに無断で家を開けるような妹ではなかったからである。
だとすれば、その後の消息が知れないのは、アイーシャ自身がそのトラブルに巻き込まれてしまったからではないのか?
そこまでハッキリ想像がついているのに、モニカはこのことを「光の盾」には報告していなかった。
そんなことをすれば、あの老いて意気地の無くなったハスデイア神官長は、それ見たことかと言わんばかりに、人間世界との通路を封鎖してしまうに違いなかったからである。そしてそれは、愛する妹と親友が二度と戻ってこないということに他ならないのだ。
(決してそんなことはさせない・・・今日こそ幹部会議で、ハスデイア様を説き伏せなくては・・・。そして万が一にも、それがかなわなかった時には!・・・)
もはや一刻の猶予もならないと、モニカは秘かに決意を固めていた。
今日の夜までに幹部会の意志が統一出来なければ、彼女は一人でも「イヴァンの掌」へ赴いて、事件の真相を探るつもりであった。そして妹や親友を捜しだし、このエルフの里へ連れ帰るのだ!
(アイーシャも、そしてもちろんマグダレナも並みの神術使いではない・・・そんな彼女たちが自力で対処できないトラブルとは、いったい何だろう?だけど怖じ気付くわけにはいかない・・・私の愛する者は、私自身の手で守らなくては・・・)
そう、単独で森へ出かけるのは非常に危険であると、モニカにも十分わかっていた。
何よりも、待ち受ける脅威の正体が全く不明なのだから、どう身構えてよいかも分からないのだ。
彼女の決意と勇気を支えているのは、失うわけにいかない家族と友人への強い執着だけであった。それだけが、温和な18歳の神官モニカに、生まれて初めての激しい闘志を燃えたぎらせていた。
「あの、モニカ様・・・」
背後から遠慮がちにかけられた声に、モニカは不意に現実に引き戻されて後を振り返った。
そこに立っていたのは栗色の髪を短く刈った背の低いエルフの少女で、いわゆる美人ではないが、そばかすを散りばめた上向きの鼻は、なかなか愛嬌がある。
「ああヘイゼル、もう『盟約の樹』(光の盾の本部)へ出かける時間ですか?」
「いえ、それにはまだ早いのですが・・・どうか居間の方へいらしていただけないでしょうか?」
ヘイゼルと呼ばれた少女は、何か戸惑ったような様子で、おずおずとモニカに頭を下げた。
モニカより一つ年下の神官である彼女は、控え目で口数も少ないが、神術使いとしては一流の才能を持っていた。
モニカも彼女を信頼して「西の礎」における副指揮官の地位を任せ、アイーシャが失踪したことも、彼女にだけは打ち明けていた。
ヘイゼルはモニカの孤独を案じ、昨晩からこの家に泊まり込んでいたのである。
「何があったのです?」
いそいそと居間へ移動しながら、モニカはせっつくような口調になってヘイゼルを問いただした。
アイーシャがいなくなってからというもの、自分が何かにつけ余裕を無くしつつあるのを感じざるを得ない。
「それが、『精霊の矢文』が現れました。突然、居間に・・・」
「なんですって?」
思わず大きな声を出し、モニカは立ち止まりかけた。
「それでは、アイーシャの?」
「はい、おそらく・・・ですがどうも様子が変です。どうか直接にご覧下さい・・・」
ヘイゼルに促され、モニカは再び小走りになって居間に飛び込む。
この家は、早くに亡くなった両親が、モニカたち姉妹に残してくれた唯一と言っていい財産で、その居間も、狭く粗末な造りであった。
しかし並べてある数々の調度品は、腕のいい職人だった父が目利きをしただけあって、高価ではないが、品のいい落ちついた風情の物がそろっている。
中でも父の最もお気に入りだった樫の木のテーブル・・・質朴な味わいのあるその円卓の上に、問題の物が悠然として浮かんでいた。
「間違いありません!この『精霊の矢文』はアイーシャのものです!・・・ですが、一体・・・・」
一目見てそう叫び、モニカは高まる胸を抑えながら、妹のものらしい「それ」を注意深く観察した。
「精霊の矢文」とは、その名の通り、神官たちが精霊の力を借りて放つ「手紙」で、精神の一部を遊離させることによって、自らの声や姿を、遠くまで一瞬にして送り知らせることが出来る。
言ってみれば自律再生するビデオテープのようなもので、「光の盾」の神官たちも、「イヴァンの掌」から緊急の連絡がある時には、これを用いるのが常であった。
その形は上下を逆にした水滴型で、表面の色や輝きの様子に人それぞれの個性があり、親しい者同士ならば送り主を一目で判別出来るのである。
「も、モニカ様?」
「お下がりなさいヘイゼル。これに触れてはなりません!」
きつい口調でそう言い、モニカは左腕を真横に伸ばして部下を制止した。
目の前に浮かぶ人頭ほどの虹色の滴は、明らかに見覚えのある妹のものだ。しかしヘイゼルが言うとおり、どこか様子がおかしかった。
表面に渦を巻く虹模様が、心なしかギラギラと下品な色合いを帯びて見えるのだ。
それに第一、アイーシャの放った精霊の矢文であれば、モニカの眼前に直接出現してしかるべきであった。
それが居間に現れたということは、アイーシャが精神を集中しきれていない・・・つまり尋常でない精神状態に置かれている可能性が強かった。
「昔いまし、今いまし、全能なるイヴァンの名において精霊たちに命ずる・・・。紅のきざはしに登りて示せ。闇には闇、光には光と・・・・」
静かな声音で短く呪文を唱え、モニカは右手をケープから差し出すと、矢文に向かって気合いと共に振りかざした。
「ハッ!」
瞬間、精霊の矢文はまばゆく光輝き、続いてその表面がサーッと鉛色に変わってゆく!・・・と、次の瞬間には、まるで本物の鉛のように表層がポタポタと溶け落ち、下からは本来の清々しい虹色が、剥き出るように現れた。
しかも驚いたことに、溶け落ちた鉛色の滴はテーブルの上で激しく白煙を上げ、樫の表面を黒々と焼き焦がしていくではないか!
「モニカ様、こ、これは?」
「強烈な邪気をまとっていたのです。あのまま触れば只では済まないところでした。でもこれで、もう直ちに読むことが出来ます・・・」
そう、一刻も早く、その内容を知る必要があった。
神官たる妹の放った矢文が邪気を帯びているとは!・・・彼女の身に何かとんでもない大事が起こっているのは、もはや明らかだった。
はやる心を抑えきれず、モニカはまだ薄く湯気を上げている矢文の上に、右手をグッと押し当てた。すると表面の虹色が見る見るうちに奥へと退き、矢文全体がガラスのように透き通ってゆく。
やがて完全に透明になった滴の中で、何かの影が次第にわだかまり、うごめく様がぼんやりと見えてきた。
それはどうやら、人の姿であるらしい・・・。
「アイーシャ?・・・」
モニカは思わず呟いて身を乗り出したが、鮮明さを増して映し出された人影は、妹とは全くの別人であった。
短く肩で切りそろえた黒髪、太い眉にハッキリとした目、長く尖った耳、細く頼りなげな身体の線・・・・紫紺のドレスを身にまとったその人物は、十にも満たないような幼いエルフの少女だったのである!
「・・・お初にお目もじ、エルフの神官、モニカ・エランツォ様・・・」
白く細い喉をかすかに動かして、少女は滴の中から声を発した。
「あたしの名はベスマ・アムピトリーテ。お前たちが闇のエルフと呼んでいる一族の者さ・・・」
「やッ、闇のエルフ?」
捕らわれたアイーシャと同じ驚惑の声を、モニカもまた洩らした。
エルフの中に闇に仕える一族がいるという話は聞いたことがあったが、まさかそれが実在するなどとは想像もしなかったからである。
「お前の妹は、今身体の調子が悪くてねェ・・・。神術を使えないので、せっかく書いた矢文を送り届けることが出来ないのさ。そこであたしが、親切に飛脚の役をかってでたんだよ。クククク・・・闇の力が染み込んだ矢文で、火傷でもしなかったかい?・・・」

「も、モニカ様、一体この者は?」
不敵に喋り続けるベスマのまがまがしい気配に圧倒され、ヘイゼルはおろおろとモニカの横顔を見上げた。
「わかりません・・・しかしなんという邪悪な殺気!・・・闇のエルフというのが真実かはともかく、この者の見かけの歳や姿に惑わされてはなりません・・・おそらくは、気の遠くなるほどの生を重ねた怪物です・・・」
話しながらモニカは、不吉な想像を、あれこれと胸の内に巡らせる。
(もしかしたらアイーシャは、この化け物に捕らわれているのかも・・・いいえ、この少女の正体がなんであれ、妹の精神の一部をはぎ取って送り付けてきたことからして、それに相違ないわ!そしておそらく、マグダレナたちの失踪にも関係しているのかもしれない!・・・)
「察しの通り、あんたの妹アイーシャは、あたしの所で預かってるよ。」
モニカの不安な胸中を見透かしたかのように、ベスマは薄ら笑いを浮かべながらささやいた。
「なに、心配しなくとも死んじゃあいないよ。今すぐ会わせてやるから安心おし・・・」
外見からは想像もできない不遜な口調でそう言い、ベスマは右手の袖を背後の闇に向けてサッと振って見せた。するとその周囲が次第にうっすらと明るくなり、やがて見覚えのある人影が、まるで幻のように朦朧と立ち現れる・・・。
「あッ、アイーシャっ!」
「アイーシャ様ッ!」
モニカとヘイゼルが同時に顔色を無くして絶叫したほど、囚われたアイーシャの姿は惨たらしく、みじめであった。
そこは薄暗く天井の低い、洞窟のような場所で、その岩壁には黒く錆びついた金具がいくつも打ち込まれている。そしてそれらに結ばれた肉色の縄様の物が、アイーシャの四肢をからめ取り、自由を奪っていた。
その身体は一糸もまとわぬ全裸で、しかも手足を四方にきつく引き絞られているので、羞恥の部分を覆う術もない。
光の聖女たるモニカの妹は、まるで蜘蛛の巣に捕らえられた哀れなカゲロウのように、象牙の裸身をΧ字状に宙に吊られていたのである!
「なッ、なんということを!・・・あ、アイーシャっ!・・・」
「精霊の矢文」によって送られる情報は、任意の時間に記録されたものであって、リアルタイムではない。だからそこに映し出される者に声が届くはずはないのだが、妹のあまりに凄惨な姿に、モニカは我を忘れて激しく呼びかけた。
「このお嬢ちゃんはなァ、身の程知らずにもあたしにケンカを売ってきたんで、きつくお灸をすえてやったのさ。身体の隅々まで念入りにね。なァ、そうだろうアイーシャ?・・・」
闇の魔物ベスマはゾッとするような笑みを浮かべ、惨たらしく展開されたアイーシャの裸身を愛おしげに撫で回す。
「うゥ・・・」
消耗しきったようにガックリと頭を垂れていたアイーシャは、小さな呻きと共に全身を震わせ、ゆっくりと顔を上げて目をしばたたいた。
「さあ、モニカお姉さまにご挨拶をおし!お前のその無様な体たらくを、矢文を通して見ていただくんだよ!」
ベスマは小さな手でアイーシャの顎をつまみ持ち、被写体にカメラの位置を示すかのような仕草で、その顔を斜め正面にひねり向けた。
額にじっとりと脂汗を滲ませ、目と口を半ば開いて喘ぐアイーシャの表情は、快活だった妹のものとはとても思えない。
「も、モニ・・カ・・・姉・・様・・・」
喉を小さく動かし、アイーシャはかすれた声をやっと切れ切れに絞り出した。
「・・どうか・・お許しを・・・このアイーシャ・・力及ばず・・このような辱めを・・・ううッ・・・」
それ以上言葉にならず、アイーシャは肩を震わせてむせび泣き始める。
「うッ、・・・うあうッ、うッ、うッ、うッ、うッ・・・・」
目尻からみるみる涙が溢れだし、顎の先からポタポタと床に滴った。
「クククククク・・・そうだよなァ、お嬢ちゃんの大事な所は、残らず可愛がってやったよなァ・・・。ほォらここも!」
あざ笑いながら、ベスマはアイーシャの左の乳房を鷲掴みにし、
「それからここもさッ!」
もう一方の手で、薄く生え揃った恥毛をかき分け、羞恥の部分をなぶり苛む。
「あッ、ヤッ、イヤですッ!」
吊られた身体を激しくもがいて悲鳴を上げるアイーシャにはかまわず、ベスマは指先を淫らに蠢かして、生け贄を絶望の淵へと追い込んでゆく・・・。
「今さら気取らなくてもいいじゃねェか。こうやって何べんも天国を見せてやったろう?ええ、スケベな聖女様ッ!」
「イヤッ、イヤああッ!」
泣き叫ぶアイーシャの、悲痛な声の調子とは裏腹に、その全身はみるみるほの紅く火照り、乳首が、花芯が、硬く膨れ上がって露を含み始めるのだった。
チュッ、チュプッ、チュプッ、チュプッ、チュプッ・・・・。
指の動きが淫靡なメロディを奏で出すと、ピンク色の内蔵が秘唇から一気にまくれ出て、透き通った樹液をほとばしらせた。
「くくァああーッ!・・・」
くぐもったような絶叫が、食いしばったアイーシャの唇から押し出されて、嫋々と木霊していく・・・。
「ひ、ひどい・・・アイーシャ様ッ!・・・」
ヘイゼルが半ば泣き声で呟き、両手で顔を覆って床にしゃがみ込んだ。
無理もない。
あまりに淫らで残酷な陵辱の様子は、光に仕える無垢な神官にとって、とても正視を続けられるシーンではなかった。
「うッ・・・」
モニカもさすがに堪えかねて顔を背けようとしたが、その時、矢文の表面に大写しになった妹の裸身の異常さに気が付いて、再び息を呑んだ。
充血し、キリキリと尖った乳首には、鈍く銀色に光る金属製らしい小環が、ピアスのように貫通され、はめ込まれていたのである!
そして恥門の合わせ目にプックリと顔を出している肉の芽にも、同じ銀の輪が、惨たらしく貫きぶら下げられていた。
それらはまさしく、闇の力に敗北したアイーシャに刻された、家畜としての烙印であった・・・・。
「おお・・・あ、アイーシャ・・・・」
全身をおこりのように震わせながら、モニカは茫然と呻き声を上げた。いつの間にか、両手は爪が食い込むほどに固く握りしめられていた。
妹がどんなトラブルに巻き込まれたにしても、これほどまでに酷烈な扱いを受けていようとは、全く想像もしていなかったのである。
「クククク・・・さあて・・・」
哀れな生け贄が気をやるほんの寸前に、ベスマはツイと身体を離し、ガックリとうなだれたアイーシャの髪を、グイと鷲掴みにして持ち上げた。
「何かお姉さまにお願いすることがあっただろう、アイーシャ?・・・さあ話してごらん」
「う・・あァ・・・」
薄く目を開き、放心したように呻くアイーシャの乳首を、ベスマは無情にも、引きちぎらんばかりに捻りつまんで声を荒げた。
「いつまで夢心地でいるんだい、この淫売がッ!さっき教えてやった通りに、口上を言いなってんだよッ!」
「うあッ、ぐッ!・・・」
おぞましい銀環ごと乳首をねじ切られるのではないかという恐怖から、アイーシャは全身を細かく震わせて、弱々しく嘆願し始める。
「・・・も、モニカ姉様・・・どうかこの、哀れな妹を・・・お救い下さい・・・。明日・・・陽が真上から差す時刻に・・・神の森の中庭に・・・一人でお越し下さい・・・。お越しがなければ・・・アイーシャは・・・生きては戻れません・・・。どうか、どうかお助けをォ・・・・」
最後は泣き崩れるように言い終わったアイーシャの髪を軽く撫でつけ、ベスマはこちらに向かってヒラヒラと手を振って見せた。
「とまあ、こういう訳なのさ。・・・まさか可愛い妹を見殺しにしたりはしねェよなァ、ええ、お偉い神官様?・・・」
ベスマの花びらのような口元から次々と吐き出される品のない揶揄を、モニカは未だ信じられないという面持ちで聞いた。
この、少女の姿を装った怪物は一体何者で、どれほどの永劫を生き長らえてきたというのか?
「・・・こいつが言ったとおり、明日の昼に、お前一人で森の花園へ来るんだよ、モニカ。少しでもおかしなマネをしたら、妹も、他のお仲間も無事じゃあ済まないからね。・・・まぁどんなに大勢で押し掛けて来たって、あたしは恐かァないけどな・・・」
そう言って、ベスマがあざ笑うように鼻を鳴らした時、顔を肩にうずめて啜り泣いていたアイーシャは、やおら決然として顔を上げ、悲壮な声を張り上げた。
「きッ、来てはダメッ!これは罠ですモニカ姉様ッ!絶対・・・来てはッ!・・・」
最後の勇気を振り絞ったのか、涙に濡れた目をカッと見開いて必死に訴えるアイーシャの顔を、ベスマが無情に押さえつける様子が、滴の向こうに見えた。
「このッ、家畜の分際で余計なことを!」
憎悪のこもった叱責が響き渡るのと同時に、矢文の表面が暗さを増し始め、洞窟内の光景を急速に闇に閉ざしていく・・・。そしてアイーシャの悲痛な絶叫だけが、黒々と変色した滴の中から長く尾を引いた。
「あッ、イヤあッ!・・・やめて下さいッ!・・・やッ、アアーッ!・・・たッ、助けてモニカ姉様ッ!・・・お願い助けてェエエエーッ!・・・・」
一体どんな仕打ちを受けているのか、思わず耳を覆いたくなるほどに凄絶なアイーシャの悲鳴も、次第に小さく切れ切れになり、闇に呑まれていく・・・。

パキーンッ!
乾いた破裂音と共に、精霊の矢文は突然内部から閃光を発し、塵が舞い上がるように空中に散逸した。
記録されていた内容の「再生」が終わり、精霊たちがこの場から退散した証であった。
矢文のあった空間には何も残っておらず、黒く焦げ付いたテーブルだけが、たった今見せられた悪夢のような光景が現実であることを教えていた。
「も、モニカ様・・・」
ヘイゼルが我に返ったように立ち上がり、ささやくような声で、おずおずとモニカに呼びかける。
モニカは身じろぎもせず、矢文の浮いていた辺りを凝視して突っ立っていた。
頭の中では、妹の悲痛な叫び声が、未だにワーンと反響している。
今眼前で繰り広げられたおぞましい拷問劇が、自分たち姉妹に起こっている現実の災いだとは、とても信じられなかった。
(アイーシャ・・・たった三日の間に、なんという不憫な変わりよう・・・)
あれほど勝ち気で誇り高かった妹が、神敵である闇の魔物に、まるで奴隷のようにへつらい、許しを乞うとは・・・。
自分には想像もつかない呵責や辱めを受け続けたのだろうと思い、モニカの心は暗く塞いだ。
最後の意地で、姉に「来てはダメ!」と警告してみせたものの、結局悲鳴と共に救出を乞うて、闇に呑まれていった様子が、かえってアイーシャの追い詰められた心情を表していて哀れであった。
「待っていなさい、アイーシャ・・・」
呻くように一人ごちたモニカの口元を見つめ、ヘイゼルが仰天したような声を上げる。
「も、モニカ様、まさか本当に、お一人で出掛けられるおつもりですか?」
ついで慌てて首を振って見せ、
「い、いえ、アイーシャ様をお助けするのは当然ですが、モニカ様お一人では、あまりにも危険すぎます!どうか、光の盾を挙げて対策を!・・・」
そこまで言いかけたヘイゼルの肩に手を置き、モニカは圧し殺した様な声音を発した。
「・・・いいですかヘイゼル、この事は絶対に他言無用です。ことに、光の盾の耳に入るようなことがあってはなりません!そんなことになれば、アイーシャを助け出すことは、決して叶わない・・・。ハスデイア様は、躊躇無く、神域の通路を封鎖してしまうでしょう・・・」
そう、最前までは、何とかして神官長を説得するつもりのモニカであったが、恐るべき敵の存在が明らかになった今、それは徒労に終わることがハッキリしていた。
「・・・しかもあの口ぶりからすると、マグダレナたち三人も、アイーシャ同様に、あの者に囚われている様子・・・。妹だけでなく、友人までも見殺しにすることは、到底出来ません。それはイヴァン神様もお許しにならないでしょう・・・」
「で、ですが・・・」
とヘイゼルはなおも言い募り、
「見たところ、アイーシャ様は純潔を汚されて、神術を行使出来ない御様子・・・。モニカ様までがそんなことになったら、私は・・・」
最後はほとんど涙声になったヘイゼルに、モニカは厳しい顔つきのまま、静かにかぶりを振った。
「しっかりなさいヘイゼル。アイーシャとマグダレナを打ち負かしたあの怪物が、尋常ならざる力を持っていることは分かっています。・・・私自身が命を、あるいは神官たる資格の純潔を投げ出すほどの覚悟をしなければ、決して道は開けないでしょう。・・・とはいえ、まったく無手で立ち向かうような、愚かな真似はしません。どんな手段に訴えてでも、必ずあの忌まわしい魔物を打ち倒して見せます。・・・そう、例え、『遺物』を用いることになっても!・・・」
「えッ・・・・」
思いがけない言葉に息を呑んだヘイゼルにうなずき、モニカは自らを奮い立たせるように、背筋を伸ばして大きく息を付いた。
幼くして両親を病気で亡くして以来、孤独な身の上を寄せ合うようにして生きてきた姉妹・・・。その絆を引き裂かれることを思えば、どんなに恐ろしい敵であっても、死を賭して戦うことに、何のためらいもなかった。
(今しばらくの辛抱です、アイーシャ。私が必ず、この手で助け出します!・・・)
→1へ戻る
→3を読む
→最低書庫のトップへ
|