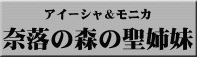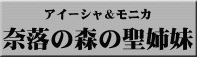|
「うゥ・・うッ・・・」
吊られた裸身に汗を滲ませながら、アイーシャはうつうつと夢幻をさまよっていた。
「精霊の矢文」を通して姉に警告を送ったことがベスマの逆鱗に触れて、昨晩は気が遠くなるほどに女体を責め抜かれ、淫らな声を上げさせられ続けたのだ。
息も絶え絶えに、再びベスマへの服従を誓ってようやく放免されたが、数時間が経った今も、全身の力はすっかり抜け落ちたままであった。
「大人しくしていれば、責めに手心を加えてやる」・・・そうベスマは言ったが、縛め囚われているアイーシャには、多少なりとも呵責の手綱が弛められたという実感はなかった。
なるほど俘囚となった初日の様に、日に十編以上も交わりを強いられることはなくなったが、かといって、半日以上休息させてもらえることもない。
「吸魂の儀式」によるすさまじい虚脱感からアイーシャがようやく立ち直るころ、悪魔は再び、生き血を吸いにやって来るのだ。まさに、パーポ(鶏様の家畜)が新しい卵を生んでいるか確かめに来る、飼育係のようであった。
そして有無を言わさずに含まされる毒の酒、淫らな愛撫、濡れて開いた秘唇に這い込んでくる、おぞましい触手・・・。
急速に開発されつつある性感に抗えず、顔に、声に、歓喜をみなぎらせて悶えるアイーシャを口汚く揶揄し、ベスマは繋がらせた身体を揺すり上げていく・・・。
肉体的にも精神的にもアイーシャをなぶり尽くそうとする悪魔の態度は、いささかも変わらなかったのである。
そのことを強烈に象徴しているのが、両の乳首、そして肉芽に貫き通されている、ピアス様の銀環だった。
泣き叫んで許しを乞うアイーシャにはまるで構うことなく、ベスマは冷笑を浮かべながら、一つ、また一つと、性の急所へ金属環を突き通していったのだ。
「この輪は、言ってみれば、家畜に押す焼き印のようなものさ。お前はあたしの持ち物だというしるしなんだよ、お嬢ちゃん・・・」
あまりの仕打ちに失神しかけたアイーシャの身体を撫でさすり、ベスマは嘲笑ったものだった。
そして、その銀のピアスにも何か闇の力が込められているらしく、はめ込まれた部位をじんじんと淫らに刺激して、アイーシャを悩ませた。ベスマの言うとおり、この烙印が肉体に刻されている限り、たとえどこへ逃げようとも、悪魔の呪縛から逃れられないという気がしてくるのだった。
(・・・モニカ姉様は来てくださるだろうか?・・・この地獄から、私を救い出してくださるだろうか?・・・)
深く首を折ったまま、ぼんやりとした意識の片隅で、アイーシャは一人ごちた。
(・・・いいえ、そんなことを期待してはいけないのだわ。・・・モニカ姉様が、例えどんなに優れた神術使いでも、あの恐ろしいベスマにはきっとかなわない・・・私自身が、お姉様にそう忠告したんだもの・・・。囚われの身となったのは、自らを過信した私の責任・・・お姉様まで、この地獄に巻き込む訳にはいかないわ・・・)
理性ではそう納得するものの、この先、魂の尽きるまで惨めに繋ぎ飼われるだけの我が身を思うと、アイーシャの心は絶望に押しつぶされそうであった。
「お早う、お嬢ちゃん・・・」
闇の中から、ベスマが音もなく立ち現れて声をかけた。なぜか、昨晩の逆上が嘘のように、ご機嫌な声音であった。
「・・・今日は恋しいお姉様にお会いできる日だってのに、元気がないじゃないか。・・・まあ無理もないか、昨晩は激しかったからねェ・・・」
ククッと嘲笑を洩らし、闇の媚薬がなみなみと満たされた椀を、アイーシャの口元にあてがう。
「さあ、たっぷり飲んで栄養をおつけ。お姉様と会うのに、そんな半病人みたいなザマはないだろう?」
「・・はい・・・ベスマ様・・・」
かすれた声で答え、アイーシャは傾けられた椀の中身を素直にすすった。あれほどまでに忌み恐れていた毒の酒を、彼女は今では、ほとんど抵抗なく口にするようになっていた。
拒絶することが出来ないのももちろんなのだが、これを飲まなければ、かえって自らの命を縮めてしまうという恐怖感もあった。
この牢獄に監禁されてから、アイーシャは一度もまともな食事をとっていないが、この闇の液体さえ飲んでいれば、何故か少しも空腹を覚えることはなかったからである。そればかりか、身体中の疲労が一気に消え失せ、ベスマに吸い取られた魂をも、わずかに補填してくれるような感覚があった。
それにまた、性感の一通りを身体に教え込まれた今となっては、媚薬によってもたらされる淫らな快感に、それほどの嫌悪感を覚えなくなっていたということもある。むしろさらなるエクスタシーを、心秘かに期待し始めたのではないかと自問してしまう程に・・・。
闇の酒はまさに、アイーシャの細胞を、一つ一つ暗黒に染め上げつつあった。
ただ、羞恥と屈辱の気持ちだけは、なかなか弱まらなかった。ベスマの言葉を借りれば、「抜け殻にならず、正気を保って」いたのである。
アイーシャの理性をかろうじて繋ぎ止めていたのは、何と言っても、姉モニカの存在だった。
両親を早くに亡くしてからというもの、互いにたった一人の肉親として、慈しみ合ってきた姉妹である。
自分が死人にも等しい「抜け殻」の状態になれば、その姉がどんなに嘆き悲しむか・・・その思いだけが、全てをあきらめてしまいたくなる官能の地獄の中で、アイーシャを支えていた。それがなければ、もうとっくに、マグダレナのような「木偶人形」にされていたに違いなかった。
(・・・でも、これ以上自分を保てるかどうか、とても自信が無い・・・。お姉様に再びお会いできる望みが無いのだとしたら、暗黒に、進んで身を投げ出した方が楽になれるのかも知れない・・・。どうせもう、汚された操は、元には戻らないのだから・・・)
全身を蝕みつつある淫靡な酔いに身を任せながら、アイーシャは、光の聖女にあるまじき思案を我知らず巡らせた。それほどまでに、この四日間に教え込まれた性の味は強烈だった。
含まされた闇の酒によって、身体中に新たな活力が満ち、上気した肌には汗の粒がびっしりと浮かぶ。そして目の眩むような快感が、銀環を打ち込まれた性の急所に、キューンと収斂してくるのだ。
「ふッ、くくううッ・・・」
食いしばった唇から呻きともため息ともつかない声が漏れ、吊られた身体が、押し寄せる官能の波に堪えかねたように、淫らにくねり始める。
(・・ああ・・・またおかしくされちゃう・・・)
快楽への期待と怯えがないまぜになった心境であえぐアイーシャを、ベスマは楽しげに眺めていたが、やがてスルスルとドレスを脱ぎ落とすと、輝くような白い裸身をすり寄せてきた。
「・・・闇の快楽に身体がなじんできたようだねェ、ええ聖女様?・・・」
言いながら、プリプリと尖ったアイーシャの乳首を口に含み、突き通された銀環を弄ぶように舌をうごめかす。
(あッ、ダメッ!・・・気持ちがいいッ!・・・)
思わず身を竦ませ、アイーシャは出かかった喜悦の声をようやく呑み込んだ。しかし、そんなはかない抵抗をあざ笑うかのように、ベスマの指は、羞恥の部分を目指して這い降りてゆく・・・。
「ひッ!・・・」
恥門をめくり上げられ、思わずのけぞったアイーシャの唇から、短く悲鳴がほとばしる。
肉の壺の縁一杯に溜まっていた愛の露が、一気に溢れ出て内股を伝った。
ピチュッ、チュッ、チュププッ・・・。
淫らな音を立てながら、ベスマの指先は秘唇の縁をなぞり、その裏側をこすり上げ、硬くしこった核をつまみ上げる・・・。
みるみるまくれ出た鮮紅色のはらわたは、すでに熟々に溶ろけかけていた。
「あッ・・ああッ!・・・」
堪えかねたように大きな声を上げ、アイーシャはなまめかしく身をくねらせる。
とてもではないが、積極的に味あわずにはおれない、素晴らしい快感であった。
「どうだい、たまらなくイイだろう?」
いやらしい指の動きをそのままに、ベスマは、アイーシャの首筋に強く口づけをして囁く。
「いい加減、心のままを言ったらどうだい?気持ちがいいんだろう、ええ?・・・」
「・・は、はい・・・とても・・・あッ!・・・」
銀環に貫かれたクリトリスをやわやわと揉み込まれ、ついにアイーシャは、自分が淫らな悦びに屈したことを認めた。
そう・・・初めてオルガを体験させられた時と違い、今では朦朧となることもなく、快感をじっくりと味わうことが出来るようになっていた。
もはやアイーシャにとってそれは、純粋に「イイ」感じになりつつあったのである。
「ああッ、いいッ・・・気持ちいいですッ!・・・」
たちどころに一度、二度と絶頂に達し、それでも収まらない官能の波に、今や進んで身を任せてゆく。
自分が光の聖女にあるまじき痴態を演じていることや、エクスタシーの果てに恐るべき虚無感、疲労感が訪れることは、十分すぎるほど分かっていた。そしてこのまま官能に溺れ続ければ、マグダレナの二の舞になってしまうことも・・・。
それでもアイーシャは、目の前の快感を、夢中で貪らずにはおれないのだった。
今この瞬間においては、魂を抜かれて木偶人形になることよりも、ベスマに淫らな愛撫を中断されることの方が、恐ろしくなりつつあった。
(・・・ああダメ・・・もっともっと触って欲しい・・・もっと無茶苦茶にして欲しいッ!・・・)
叩きつけるような官能の波に翻弄されながら、アイーシャは、淫らな願望への抵抗が、もはや不可能であることを悟った。
そして降伏の意を示すかのように、虚ろな目で天井を仰ぎ、大きく吐息を漏らす。唇の端にあぶくとなって溜まっていた涎が、顎から胸へと大量に伝い流れた。

「クククク・・・そう、そうやって素直に楽しめばいいんだよ・・・」
アイーシャの精神が快楽に屈したことを見透かして、ベスマは満足げに鼻先をうごめかした。
「闇の快楽は素晴らしいだろう、ええ?」
「・・は、はいベスマ様・・・。すごく・・・素敵・・・うッ!・・・」
秘唇をグイと押し開かれ、アイーシャの汗に濡れた身体が弓なりになる。さらにベスマの人差し指は、膣口の縁をヌルヌルと撫で回し始めた。
「あッ!・・あッ!・・・」
「そろそろ、ここをどうにかしてもらいたいだろう、うん?・・・」
「そ、そんな・・・うッ!・・・」
思わず頷きかけ、アイーシャは歯を食いしばって、最後の理性を奮い立たせようとした。いくらなんでも、自分から乞うて、ベスマの性のシンボルを迎え入れることには抵抗があった。
「おや、意地を張るつもりかい?素直に楽しめってのがまだ分からないのかねェ・・・」
言いながら、ベスマが焦らすように指を秘唇から遠ざけていくと、アイーシャは我知らずに腰を浮かせて、その行方を追い求めるのだった。
「うう・・・」
「さあ言ってごらん。どうせ我慢なんか出来っこねェんだ。ここを、どうして欲しいんだい?・・・」
再び舞い戻ってきた指先が、肉の襞を絶妙なリズムで刺激し始める。
「あうッ!・・・」
「言うんだよ。な、に、が、欲しいのかなァ?・・・」
子供をからかうように言いながら、とめどなく湧いてくるアイーシャの愛の露を、肉壺の奥へと塗り込めていくベスマ・・・。
もう、限界であった。
「お、お願い…ベスマ様・・・」
「欲しいんだろう?」
「・・・はい・・・・」
顔中を切なげに歪め、アイーシャは消え入るような声で言った。
「欲しいです・・・そこに・・・」
「何が?・・・」
さらに意地悪くはぐらかしてみせるベスマに、アイーシャは意を決したように声高に懇願する。
「べ、ベスマ様のモノが欲しいんです!・・・そこに・・・ああ、お願い欲しいのッ!・・・」
「フフン・・・」
ベスマは、すでに体外にむき出されている長大な闇のペニスをしごきながら、
「あたしのこいつを入れて欲しいんだね?お前のその、汚らしく濡れた場所へ?・・・」
「は、はいッ・・・入れてッ!・・・」
よだれが四方に飛び散るのもかまわず、アイーシャは二度三度と激しく頷いた。彼女の精神の、最後のタガが外れてしまったかのようであった。
「入れてェ!・・・私の汚らしい所へェ!・・・お願い入れて下さいィーッ!・・・」
縛められた腰を必死によじり動かし、姉モニカにはとても聞かせられない、淫らな要求を繰り返す。
四日前まで全く汚れを知らなかった雌花は、熟し切ったアケビの実のように割れ、ネットリとした果肉をむき出しにして、陵辱を待ち受けていた。そして内側の襞という襞は、さらなる快感を期待して露を含み、ジュクジュクと恥ずかしい音を立てている。
「ククククク・・・・」
不意にベスマは、これまで見せたことのない、心底から満足したような表情を浮かべて、アイーシャの胸に接吻した。
「ついに言ったね。自分の口から、あたしが欲しいと・・・。良く出来たよ、可愛いアイーシャ・・・」
そしておぞましい触手を、生け贄の濡れた秘唇に押し当て、
「・・・望み通り、こいつを呑み込ませてやろう。奥の奥までね!・・・」
言うなり、熱く燃えたぎった長大な肉塊が、子宮まで突き通さんばかりに侵入してきた。
ズリュリュウウーッ!・・・
「えはあッ!」
至福の嬌声を上げてのけぞるアイーシャの頬をつまむようにして、ベスマがささやく。
「これが欲しかったんだよなァ、聖女様?気分はどうだい?」
「・・あふぁッ!・・・素敵・・・素敵ですベスマ様ッ!・・・気持ちいいッ!・・・すごく気持ちいひイイイーッ!・・・」
首を振り、よだれをふきこぼしながら、アイーシャは歓喜の声を絞り出した。そして闇の蛇をさらに体内深く迎え入れようとするように、内股をくねらせる。
それはまさに、闇の麻薬に全身を侵されて中毒に陥った、哀れな俘囚の姿であった。
「・・・まったくお前は、あたしが見込んだ通りの、上等な獲物だったよ、ええアイーシャ?・・・お前はマグダレナ達と違って、正気を保ったまま闇に堕したんだ。・・・偉いよ・・・それこそが、あたしの求めていた光のエルフさ。ご褒美に、良い話しを聞かせてやろう・・・」
またも謎めいたことを囁きながら、ベスマは、魚のように口を開いて快楽を貪っているアイーシャの耳元に顔を寄せる。
「あたしが光のエルフを必要としているのは、今年が特別な年だからということは話したね?・・・そう、まさに今年一年は、四百年に一度だけ訪れる、特別な期間なのさ。あたしと、あたしの仕える暗黒神ネラ様にとってな。・・・分かるかい?・・・」
「・・はッ、はい・・・」
電撃のようなエクスタシーの波に揉まれながら、アイーシャは何とか意識にムチを打って、ベスマの話を理解しようとした。
聞かれたことに答えられず、ベスマのご機嫌を損ねては、この素晴らしい闇との交わりを中断されてしまうかもしれない・・・今のアイーシャには、それだけが恐ろしかった。
「・・・ネラ様も、そしてお前たちの崇めるイヴァン神も、この世界における闇と光の勢力争いに、直接力を振るうことはない。彼らにとってこの世界でのことは、いわば『物語の中のこと』みたいなもんだからな。・・・彼らがこの世界での版図を拡げようという時には、それぞれの力の『代理人』を使う訳だ。・・・あたしや、四日前までのお前みたいな、忠実な下僕をね・・・」
「うう・・・ふァ・・・」
(・・・そう、ほんの四日前まで、私はイヴァン様に生涯を捧げた、光の戦士だったのに・・・)
かすかな悲しみ、そして屈辱と共に、アイーシャは、自らを襲った過酷な運命を思い出した。・・・しかしベスマは、今さらそんなことを聞かせて、どうするつもりなのだろう?
「・・・ところがネラ様は、ごくたまに、自分の力の一部を直接行使するための分身を、この世におつかわしになるのだ。・・・簡単に言うと、あたしたち闇の下僕の身体を通して、自らの精をこの世に送り込み、女をはらませるのさ。・・・生まれてくる御子は、この世を闇に染めるための、運命と役割を負っている。何せ暗黒神の力の化身なんだからねェ・・・。四百年前、東の大陸を永い戦乱に陥れた、残虐王ラゴンのことは知っているだろう?あの男も実は、あたしがそうやって人間の女に生ませた、闇の御子の一人なのさ!」
「うゥ?・・・」
話しの雲行きが怪しくなってきたことにようやく気付き、アイーシャは呻きながら、不安げに身じろぎした。
目の眩むような快感と共に、正体の分からない恐怖が、ジワジワと身体に染み込みつつあった。
「・・・その、ごくたまの・・・四百年に一度だけ訪れる闇の受胎の期間というのが、まさに今年なのさ。・・・といっても、依り代(よりしろ)となる母胎は、誰でもいいって訳じゃない。四日前のお前の様に完全に聖なる者では、そもそも拒絶反応を起こして、闇の子を身ごもることは不可能だ。逆にあたしらのように、闇に染まりきった者でも具合が悪い。闇と闇が交わると、何故かひ弱な子が産まれてしまうのさ。・・・雑種強生というのかな、適度に光の因子を持つ母胎からの方が、真に凶悪な、力強い闇の御子が産まれてくるんだよ・・・」
「あ・・・うあ・・・」
目を見開き、アイーシャは言葉にならない呻き声を上げた。眼前の悪魔が得々と語っているのは、逆らえるはずがないと思った至上の快感を、一瞬忘れさせるほどの恐ろしい内容だった。
「・・・分かるだろうアイーシャ?あたしの身体は、今、四百年ぶりに、暗黒神ネラ様と、空間を越えて直接繋がっているんだ。そしてお前にブチ込んだイチモツは、今日は魂を吸い出すためじゃない・・・ネラ様の闇の精を、たっぷりと注ぎ込むためのモノなのさ!・・・」
凶暴な笑みを満面に浮かべ、ベスマは吊るされた獲物の身体を強く抱きすくめた。
「実に名誉な事だろう、ええアイーシャ?お前は、四百年ぶりに生まれる闇の御子の母となるんだよ。マグダレナと違って、闇に堕しても光の記憶を失わなかったお前は、あたしが探し求めた理想の母胎なのさ。ククククク・・・どうかいい子を産んでおくれよ・・・」
「いッ、イヤああーッ!」
あまりの恐怖に顔色を無くし、アイーシャは絶叫と共に、吊られた身体を猛然ともがき始めた!
「やッ、イヤッ、やめて下さいベスマ様ァああッ!・・・そんなのッ、そんなことォッ、絶対にイヤあああーッ!・・・」
処女を踏みにじられたことも、闇の快楽に屈したことも、己の慢心ゆえに課せられた運命と、まだ諦めることが出来た。しかし、光の聖女として生きてきた自分が、よりによって、最も忌むべき暗黒の神の子種を宿すなどとは!
アイーシャにとってそれは、肉体的にも精神的にも、死を宣告されることと同じだった。
「何を悲しむことがある?お前は神の妻となって子をもうけるんだぜ。たいした施しも与えねえイヴァンに一生こめついてるより、よっぽどイイじゃねェか。・・・ラゴン王も、実に凶悪に生まれついた闇の御子だったが、所詮は人間の子だ。魔力も弱いし、寿命も短かかった。・・・しかし今度は違う。お前は優秀なエルフの神官だ。産み落とす子は、何世紀もの永きに渡って、この世に殺戮と混沌をもたらしてくれるだろうよ・・・」
「ゆッ、許してェッ!・・・お願い・・お願いしますッ!・・・」
顔をクシャクシャに歪めて懇願しながら、しかしアイーシャの下半身は、気の狂いそうな快感に痺れてゆく。
体内でどのように蠢いているのか、深々と打ち込まれた闇の男根は、幾本にも枝分かれしてそれぞれに膨れ上がっているような、異様な感触があった。
(やッ!またイカされちゃうッ・・・。助けて、モニカ姉様!・・・お願い助けてェェーッ!・・・)
再会をあきらめたはずの姉の名を心中で叫びながら、アイーシャは、全身の高ぶりを何とか静めようと歯を食いしばる。
自分が再び絶頂に達した時、何もかもが終わるのだという、暗い予感があった。
「あきらめるんだねアイーシャ。・・・言っておくが、お前の生理の都合など関係無しに、受胎は必ず成されるんだよ。・・・なにせ相手は神様だ。注ぎ込まれた精は、その瞬間から、お前の肉体も、精神も、全てを思うがままに支配するのさ・・・」
ベスマは舌なめずりをしながら、
「まあ、お前の身体が拒絶反応を起こして、母子共に死んじまうってことも、万が一にはあるかもしれないがな。そうなった時には、“スペア”を使わせてもらうさ。・・・ククククク・・・そのために、わざわざ呼び寄せておいたんだからね。お前の愛しいモニカ姉様を、予備の母胎として!・・・」
全ての企みをあからさまにした悪魔は、アイーシャの乳首を左右交互に口に含みながら、とどめを刺すかのように激しく身体を揺すり上げた。
グチュッ、グチュッ、グチュッ!・・・・
淫らな音と共に、繋がれた二つの裸体が、妖しいダンスを繰り返す。汗とよだれ、そして愛の露が、二人の全身をキラキラと照り輝かせた。
「ダメッ!もうダメッ!・・・お願いやめてベスマ様ァァーッ!・・・」
これ以上快楽の波に耐えきれないことを悟り、アイーシャは絶望的な悲鳴を絞り出す。
見開かれた目には、いつしか一杯に涙が溜まっていた。
「いよいよだね。さあ受け取りなッ、暗黒の神の魂をッ!・・・」
鋭い犬歯をむき出しにし、ベスマは最後のひと突きとばかりに、華奢な腰を押し上げた。そしてその恥骨のふくらみが、銀環に貫かれた肉の芽を挟みつぶすように刺激した時、アイーシャの唇から、断末魔を告げる絶叫が響き渡った!
「あッ、ィあはあああァァーッ!・・・」
この世のものとも思えない快感と共に、凄まじい喪失感が怒涛のように押し寄せ、アイーシャの中で渦を巻く。
そして次の瞬間、何かおぞましい、闇そのもののような気配が、自分の胎内にまき散らされ、どす黒く充満していくのが、ハッキリと知覚された。
(モニ・・カ姉・・・)
愛する姉に別れを告げる間もなく、アイーシャの意識は、プッツリとそこで途切れた。
弓なりに緊張した裸身がゆっくりと弛緩してゆくのと同時に、絶望をたたえて見開かれていた目が急速に輝きを失い、やがて静かに閉じられる・・・。
両のまぶたの端から、これまでの人生に名残を惜しむかのように、涙が二筋、スーッと流れ落ちた。
十五年間光の使徒として生きてきた「アイーシャ」という少女は、この瞬間、この世から消え去ったのである・・・。

「クク・・・クククククク!・・・・」
四百年ぶりの大仕事を終え、ベスマは満足げに微笑みながら、生け贄の身体から肉塊を引き抜いた。
そして、作業が完了したことを確認するかのように、汗に濡れたアイーシャの裸体をヌルヌルと撫で回す。
その様子はまるで、捕まえた他の昆虫に卵を産みつけ終わってホッと息をつく、狩りバチそのものであった。
「・・・ゆっくりとお休みアイーシャ。・・・目が覚めたとき、お前は生まれ変わっているんだよ。闇の御子の母として・・・新たな暗黒の使徒としてね・・・」
ベスマが言い終わるのと同時に、意識のないアイーシャの下腹に、何か黒々としたシミのようなモノが朦朧と浮かび上がった。
そしてそれは、暗黒の種子が、確かにそこに根付き、息づき始めたことを如実に示していた。
そう・・・次第に鮮明になるその模様は、ベスマの身体に刻されているのと同じ、暗黒神ネラを表す、呪われた印形だったのである・・・。
→2へ戻る
→次章を読む
→最低書庫のトップへ
|