|
第47話 『進軍』
長い回廊を抜けたエリウスが部屋のドアを開けると、中では1人の少女が呆けた表情で辺りの様子を伺っていた。エリウスが部屋の中に入ってもそれに気付いていないのか、周囲を見回すだけでまるで反応を示さない。しばし、黙ったまま少女を見つめていたエリウスだったが、部屋のドアを閉めると彼女に歩み寄ってゆく。
「大丈夫たったかい、サクラ?」
「・・・・・・どちら様でしょう?」
エリウスの問いかけに少女はようやく反応を示し、エリウスの方に顔を向けてくる。そしてしばらくエリウスの顔を見つめていたが、首を傾げながらそう問い返してくる。その言葉にエリウスは思わず仰け反ってしまう。まさかとは思うが彼女が自分のことを本当に認識していないと思いたくなかった。
「君が待っていた者だよ・・・」
「ああ。では貴方様が・・・ノブナガですね??」
自分の言葉にサクラが手を打って反応を示したので、自分のことを認識していたと思ったエリウスだったが、そのあとに続いた言葉に思わずまた仰け反ってしまう。よりにもよって自分が封印していたものと間違われるなど、エリウスには屈辱にも似た思いであった。
「ノブナガは君が封印していただろう?」
「・・・ああ。そういえばそうでしたね。それでは貴方様は?」
「君が会いたいと望んでいたもの、君の意識に何度となく現れた者。そういえばわかるかい?」
未だに自分が誰であるかがわかっていないサクラにエリウスはやや疲れた表情を浮べて言葉を続ける。その言葉にもサクラは何度となく首を傾げている。自分が張った結界を破ってまで自分に会いにくる者など他にいるはずがないのに、それが誰であるかがまるで分かっていないのだ。
「エリウス=デュ=ファルケン。ヴェイグサス神の生まれ変わり、といえばわかるかい?」
「ん〜〜〜??どこかで聞いた気はするんですが・・・」
大きな溜息を漏らしながら語りかけるエリウスに、サクラは小首を傾げたままなかなか思い出そうとしない。まさか本気で覚えていないのではないかとエリウスは不安になってくる。もしかすると記憶が完全に封印されていて、力を取り戻さないと記憶も戻らないのかもしれない。エリウスにはそう思えてならなかった。
「・・・思い出しました〜〜!!」
しばらく首を傾げたまま考え込んでいたサクラだったが、ようやくポンと手を打って何かを思い出した顔をする。ようやく思い出してくれたかとエリウスはほっと胸をなでおろす。もし記憶まで封印されているならば、自分のことを認識できないままに犯さなければならない。それによってサクラの心を傷付けないかと不安に思っていたのだ。しかし、その心配はなさそうだと胸をなでおろしたのだったが、胸をなでおろすのはまだ早かった。
「えっと、えっと・・・どこかの王女様でしたよね?エリウス様って?」
狙っているとしか思えないボケっぷりにエリウスは思わず眩暈がしてきた。どうやらサクラのボケは天然らしく、まともに相手をしていたらこちらの身が持たないかもしれない。そんなエリウスの様子に自分の答えが間違っていたのかと察したのか、サクラはまた考え込んでしまう。
「違うのですか??」
「僕のどこを見たら王女と言えるのかを問いたい・・・」
しばし考え込んでいたサクラだったが小首を傾げたままエリウスに問いかけてくる。その問いかけにエリウスは大きな溜息を漏らしながら自分を指差し、どこが王女なのか、女なのかを問いただす。するとサクラはじっとエリウスの顔を覗き込み、また考え込んでしまう。やっと納得いったように手を打って笑顔を向けてくる。
「エリウス様は王女ではないのですね!!」
「当たり前だろう・・・」
「ではいったい何なのですか??」
先に進まない会話にエリウスは激しい眩暈を覚える。この天然ぶりはくらくらしてくる.。もし彼女とアンが出会い、会話をしたらと思うと背筋が寒くなってくる。いっこうに進まない会話、かみ合わない内容、なのに納得し合う2人の少女。その次元を超えた会話に皆が悶死。そんな光景が脳裏に鮮明に想像される。
「絶対に会わせられない・・・」
その空恐ろしい光景にエリウスは身震いして心に深く誓うのだった。が、今はそんなことを気にしている場合ではない。未だに自分のことを理解していないサクラにそのことを理解させ、何をしなければならないのかを教えなければならないのだ。そしてサクラにそれを遠回しに教えようとしても無駄であることはこれまでの会話からよくわかった。
「率直に言う!サクラ、僕もモノになれ!」
「ダメですぅ〜〜」
あまりにストレートな物言いであったが、サクラの反応は以外にもあっさりとしたモノだった。あまりにあっさりとしているので、エリウスは思わず首を傾げてしまう。まさかと思い、恐る恐るサクラに自分のものになるという言葉の意味を尋ねてみることにする。
「サクラ。今の言葉の意味、わかって答えているよね?」
「???エリウス様のお嫁さんになるんですよね??」
能天気なサクラの答えにエリウスはまたも眩暈を起こしてしまう。確かにその答えは当たらずとも遠からずの答えである。しかし、モノになるということの意味をまるで理解していないことがエリウスにはもどかしかった。そしてこれ以上話を続けていても疲れるだけで、いっこうに話が進まないとエリウスは判断し、実力行使に出ようとするが、サクラはそれを拒む。
「・・・何か不都合でもあるのか?」
「申し訳ありません。私、契りを交わした方が居りますので・・・」
サクラの衝撃的な発言にエリウスは思わず絶句してしまう。まさかサクラがすでにお手つきになっていようとは思いもしなかった。どこの不届き者によって汚されたのかと考えたエリウスだったが、ふとそのときになってある疑問が頭を過ぎる。何故サクラが”巫女姫”としての力、結界の力を行使できたのかが不思議に思えてきた。記憶が戻っていないのにどうして”巫女姫”の力を行使できたのだろうか。これまでも”巫女姫”の力を行使できる乙女達はいたが、その力は本来の力より遥かに劣る。しかしサクラの力は本来の力の限りなく近いものであった。それだけの力をサクラは封印も解かずに使えるようになっていたことになる。それが不思議でならなかった。
「サクラ、聞きたいことがある・・・」
「何でございましょうか????」
「君は何故”巫女姫”の、結界の力が使えるんだ?」
エリウスの問いにサクラは小首を傾げる。問いの意味がわからないのかと思いエリウスが問い直そうとすると、サクラは小さく頷いて話し始める。
「この力は3歳のころに使えるようになったんです」
「3歳の頃?そんな小さいころから力の封印が解けていたのか?」
「はい。先ほどお話しました契りを交わした方と接吻をしたあとからでございます」
ニコニコと笑って答えるサクラにエリウスは訳がわからず、頭を掻き毟る。その男との接吻によって力が解放されたのは間違いないだろう。が、たかが男との接吻で”九賢人”の掛けた封印が解けるはずがない。その程度で解けるならとっくに昔に”巫女姫”たち全員の封印は解かれていたはずである。そう考えるとますます頭の中が混乱してくる。混乱しきった半ばパニックを起こしかけていたエリウスだったが、このまま混乱しきった状態で考えていてもいい答えが出るはずがない。ならば一度頭の中をリセットして考え直すことにする。
(誰に解かれたかではなく、どうして解けたかを考えてみよう・・・)
エリウスはそこから考え直す。”巫女姫”の封印を解けるものは限られている。というか、自分しかいない。いないはずだ。なのにサクラの封印は解けていた。となればサクラの封印を解いたのは自分ということになる。ならば自分はユトユラに来たことがあるのだろうか?色々と記憶をさかのぼっていたエリウスは、ふと10数年前のことを思い出す。
(たしかあれはクリフトとフィラデラと一緒に城を抜け出して・・・)
10数年前、当時魔法を習い始めたフィラデラの転移魔法の練習に付き合わされたエリウスとクリフトは見知らぬ地へと飛んできたことがあった。当時まだ4歳か5歳の頃の話である。飛んできたまではよかったが帰る事ができず、3人で途方にくれたことがあった。さらに運の悪いことに狼に襲われクリフトとフィラデラと離れ離れになってしまった。心細くなり、泣き出しそうになったエリウスに声をかけてきた少女がいた。その少女に励まされたエリウスはその少女に将来結婚しようと約束をし、口付けをかわしたことがあった。(ちなみにその後、心配したアルデラが迎えに来てくれて、クリフト、フィラデラともどもアルデラのお説教を食らうこととなった。)そのときの少女の名前をエリウスは今になって思いだす。
「そうだ・・・あのときの娘の名前は・・・確かサクラ・・・」
「???私がどうかしましたでしょうか???」
「僕の顔に見覚えはないかい??」
エリウスはそう言ってサクラの眼前に自分の顔を突き出す。その顔をサクラはじっと見つめたまま小首を傾げる。しばし沈黙が部屋を支配する。やがてサクラはぽんと手を打って何かを思い出した仕草を見せる。
「ああ、エリウス様・・・」
「思い出したかい?」
「このようなところにほくろがあります・・・」
思い出してくれたのかとエリウスがホッとした表情を浮べるが、サクラは見当違いのことを言ってエリウスの顎の辺りを指差し、触ってくる。その回答にエリウスは思わず脱力し、溜息を漏らす。しかし、これでくじけたら負けだと思いなおし、顔を上げるとじっとサクラの顔を見つめる。真剣な表情でじっと見つめているとサクラはクスクスと笑い出す。
「エリウス様も思い出されたのですね?」
「思い出すって・・・サクラ、君は最初から??」
「はい。だって私の初恋の君で、将来を誓い合った殿方ですよ?忘れるはずがありませんわ」
満面の笑みを浮べて答えるサクラにエリウスは思わず顔を赤らめてしまう。もう10年以上も前に交わした子供同士の約束。それをサクラは今も大切に覚えていてくれたことが嬉しく、同時にそのことを忘れてしまっていた自分が無性に恥ずかしかった。そのことがわかっていてもサクラはそれ以上エリウスを責める事はしなかった。
「じゃあ、サクラ。いいんだね?」
「はい。全てはエリウス様の御心のままに・・・」
エリウスがサクラの両肩に手をかけると、サクラはそう言って両目を閉じる。そんなサクラをそっと抱き寄せると、エリウスは優しく口付けを交わす。甘い、甘いキス。10数年ぶりに味わうサクラの唇は柔らかく、優しい、懐かしい味がした。その懐かしさを感じながらエリウスはゆっくりと舌をサクラの口の中に差し込んでゆく。
「んんっ・・・んふっ・・・・」
サクラの口の中に入り込んだエリウスの舌先がサクラの舌に絡みつく。最初は驚いたように抵抗を見せたサクラだったが、徐々に力を抜いてエリウスの舌の動きにあわせて自分から舌を絡めてくる。舌と舌が絡み合うたびに唾液と唾液も混じりあい、静かな部屋に唾液が交じり合う水音が響き渡る。
「んくっ・・・あふぁぁぁっっ・・・」
口の端から甘い息を漏らしながらサクラはエリウスのなすがままに流される。サクラの体から緊張が解け、力が抜けたころあいを見計らってエリウスは両手をサクラの巫女装束の衿へと移動させる。そしてその端に手をかけると、サクラが抵抗する間も与えずに左右に開き腰の辺りまで一気に引き摺り下ろす。
「あっ・・・」
小さな胸が露になったサクラは小さな悲鳴を上げるが、それ以上の抵抗はしない。サクラは抵抗しないと踏んだエリウスは唇を離し、サクラの胸のほうに口を移してゆく。ぬけるような白い肌にある膨らみは正直お情け程度のものでしかない。同年代のレオナやアリスたちに比べたら本当にかわいそうになるくらいの膨らみである。一言で言ってツルペタである。
「可愛いよ、サクラ・・・」
エリウスはそれだけ言うとサクラの小さな膨らみにそっと手を添える。優しく力を込めないように注意しながらそっと揉みしだく。わずかな膨らみではあるが柔らかさはある。そこを丁寧に揉み上げ、刺激する。徐々にサクラの肌は紅葉し、じっとりと汗ばんでくるのがエリウスの手の平を当してよくわかった。
「ああっっ・・・んはぁぁぁっっ!!」
耐え切れないといった感じにサクラは大きな声を上げて悶える。その甘く切ない声に刺激されたエリウスは膨らみの頂点へと指を伸ばす。硬さを帯び始めたそこを指先で転がしたり、擦ったり、摘んだりして刺激を与える。その刺激に答えるようにサクラの乳首はどんどん硬くなり、尖ってくる。
「サクラの乳首、こんなに立っちゃって・・・」
「あんっ・・・だめです、そんなに弄っては・・・」
「じゃあ、こういうのはどうかな??」
指先でころころと乳首を転がしながらエリウスはサクラの耳元で囁く。その囁きにサクラはいやいやと首を振って切なそうに悶える。そんなサクラの仕草が可愛くて、もっと喜ばせてあげたいとばかりにエリウスは固く尖った乳首を口に含み、強く吸ってみたり、舌先で転がしてみたりし始める。
「あくっ!!だめ・・・だめです・・・そんなの、ああああああっっ」
エリウスの舌の動きにあわせるようにサクラの声も大きく、甘いものに変わってゆく。エリウスの唇が堅くなった乳首を挟み込みこむように優しく噛むと切なげな声を上げる。そんなサクラの声の変化を楽しみながらエリウスはサクラの気分をどんどん高揚させてゆく。その攻めに抗うだけの余力は今のサクラには残っていなかった。
「んくぅっっ!あうっ、エリウス様・・・」
「んっ?どうしたの、サクラ??」
「あの、なにか体がおかしいんです。あうっ・・・体の奥底からこみ上げてくるものが抑え切れなくて・・・」
絶頂に近付いたことにサクラは気分の悪そうな顔をする。自分の体になにが起こっているのかがわからず、戸惑っているのである。そんなサクラの様が可愛らしく思えたエリウスは唇を乳首から離し、指先でそっとサクラの唇をなぞる。そしてそっと優しく語り掛ける。
「それはサクラが僕という存在を受け入れてくれている証拠だよ」
「??それはどういうことでしょう??」
「そのまま僕に任せておけば大丈夫、ということだよ」
エリウスはそれだけ囁くと、片手をサクラの胸から離し、指先で肌をなぞるようにしながらゆっくりと下へと下ろしてゆく。お臍をなぞった指先はそのままサクラの朱色の袴の中にまで伸びてゆく。エリウスの指先の動きにくすぐったそうに悶えていたサクラはエリウスの指が自分の最も大切な場所に延びて行くのを感じ恥ずかしそうな顔をする。
「あの・・・エリウス様??」
「大丈夫だよ。もっと、もっと気持ちよくしてあげるから・・・」
怯えるサクラのそれだけ言うとエリウスは指先を股間にまで伸ばしてゆく。きつく閉じられた合わせ目をそっと指先で擦ると、サクラの体は大きく飛び跳ねる。二度、三度と撫でてやると、その合わせ目の間からじっとりとした汁が滲み出してくるのが指先を通してよくわかった。その液体をもっと搾り出そうとエリウスの指がやや強めに合わせ目を擦り上げる。
「んくっっ!あああんんっっっ!!」
全身を駆け巡るような快感にサクラは一際大きな声を上げて悶える。ヒクヒクと肉貝が戦慄いているのがよくわかる。エリウスは指先で肉貝をなぞりながらもう片手で器用にサクラの巫女装束を逃してゆく。エリウスの愛撫に身を任せていたサクラは抵抗することなくエリウスのなすがままに生まれたままの姿を晒すこととなる。
「きれいだよ、サクラ・・・」
「エリウス様・・・」
「このまま一つになろう・・・」
全裸になったサクラを見下ろしながらエリウスは自分も身につけていたものを全て脱ぎ捨てる。そして逞しく反り返ったものを自分で擦りあげながらサクラにそう囁きかける。エリウスの言葉の意味がサクラにはわかっているらしく、サクラは小さく頷くと自分から足を開きエリウスを迎え入れる格好を取る。そんなサクラの仕草にエリウスはまた疑問を持った。
「サクラ、どうしてそんなことを知って?」
「あの・・・母上様に習いました。殿方は従順な女子が好みだと・・・」
「いや、そうかもしれないけど・・・」
「本来でしたらエリウス様の御印をお舐めして喜ばせて差し上げたいところなのですが・・・」
「そういう嬉しいお誘いはまた今度ね。今は時間が惜しい・・・」
子供にどういう教育を施しているんだとサクラの母親にあきれ返り、サクラのとても嬉しいお誘いをエリウスは丁重にお断りする。大結界が解けようとしている今、いつストラヴァイドとの最終決戦が始まるかわからない。一刻も早くすべての”巫女姫”の封印を完全に解放しなければならない。そのためにもサクラと体を重ねあわさなければならないのだ。エリウスはそそくさとサクラの股の間に自分の体を潜り込ませる。そしてサクラの濡れそぼった秘所に自分の逞しく反り返った御印を宛がうと、一拍置いてグッと押し込む。
「ひうぅぅっっ!!」
硬い抵抗とともに御印がサクラの中にめり込んでゆく。その強い抵抗力に抗いながらエリウスは腰を押し進める。プチプチと何かを引き裂く感触とともに御印が奥へと飲み込まれてゆく。同時にサクラの顔が苦痛に歪み、エリウスの背中に両手を廻してしがみ付いてくる。本来ならもっと丹念に愛撫しなければならないところであったが、時間が押していたのでちょっと無理矢理の開通となったため激しい激痛がサクラを苛んでいるのだ。それはわかるが止めるわけには行かない。エリウスは大きく息を吸い込むと、もう一度力を込めて御印を奥へと押し込む。
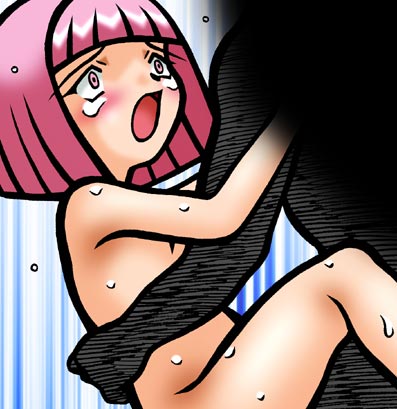
「ひぐぅぅぅっっっ!!いた・・・・い・・・」
「繋がったよ、サクラ・・・」
強い抵抗を引き裂いてエリウスの御印がサクラの命の泉まで到達する。引き裂かれた道からは赤いものが滴り落ち、サクラがエリウスのモノとなったことを如実に現していた。ギチギチと締め付ける感触にエリウスは顔を顰めながら、ゆっくりと腰を動かし始める。まだ傷ついて間もない膣道をペニスが何度も出たり入ったりするため傷ついた膣壁がズキズキと痛み、サクラは目に涙を浮べてエリウスの背中に廻した両手の力を込める。しかし、それ以上は何も言わず、必死に痛みを堪えながら声を押し殺す。そんなサクラの仕草がエリウスにはいじらしかった。
「サクラ、サクラ・・・」
彼女の名前を何度も呟きながらエリウスは腰の動きを徐々に早めてゆく。最初は肉の擦れる音がしていたヴァギナは徐々に潤いを帯び、ジュブジュブといやらしい水音を奏で始める。それにあわせるようにサクラの苦痛に歪んでいた顔も憂いを帯び、うっすらと赤みを差してくる。サクラの膣はそれに呼応するように小刻みに律動し、エリウスのペニスを絞り上げる。その心地いい締め上げにエリウスはあっという間に我慢の限界に近付いてゆく。
「サクラ、そろそろいいかい?」
「はい・・・んんっ、エリウス様のお情けをサクラのここにたっぷりと出してください」
腰を動かしながら限界が近いことを告げると、サクラは両手で自分の下腹部を触りながら妖しく笑いながらそう言ってくる。その妖しくも美しい笑みにエリウスはさらに腰の動きを加速させる。子宮を突き破らんばかりの勢いでサクラを突き上げ、自分を高みへと押し上げて行く。サクラもまたエリウスの動きに最後の階段を登りつめる。
「え、エリウス様〜〜〜!!!」
「うくっ、サクラ!!!」
サクラの絶叫とともに膣道が激しく収縮し、エリウスのペニスを絞り上げる。その締め付けにエリウスが我慢できなくなり思いきり自分の分身をサクラの子宮にぶちまける。その熱くも愛しい感触にサクラは酔いしれながらエリウスに抱きつき、いつまでもいつまでも彼を離そうとはしなかった。エリウスもまたサクラを抱きしめたままその心地いい倦怠感に身を任せるのだった。静かな時間が2人を包み込む。今だけの幸せを2人はじっと噛み締めるのだった。
そして時が流れる・・・・・
白い霧に包まれていた視界が開けてゆくのをクリフトはじっと見つめていた。そのクリフトの後ろには怪我から回復したばかりのセツナ、リューナ、アンナ、リリスにエリザベートを加えた”五天衆”勢ぞろいで控えていた。さらにその後ろには半数の第8軍の血に飢えた妖魔たちが今か今かと戦いのときを待ち構えていた。
「さてと・・・この霧が晴れるまであとどれくらいだ、リリス?」
「5分、といったところでしょうか・・・」
「そうか。なら霧が晴れると同時に進軍!一気に王都を目指すぞ!」
クリフトも何の妨害もなく王都まで目指せるとは思っていない。自分たちの大軍も今は半数にまでなってしまっている。それでもクリフトの自信は揺らいではいなかった。いくらストラヴァイド軍が立ちはだかろうとも、四方八方からの進軍を止めようと自軍を分散させるはずである。そうなればいかに第8軍が半数に減っていたとしても何の問題もない、この数の軍勢でも押しつぶすことは可能なはずである。それがクリフトの見解であった。
「とはいえ、俺たちが守っているのはヴェイスの国境線、一番多くの軍隊が廻されているんだろうな・・・」
「だと思います。敵国の国境ですから・・・」
半数に減った軍団で目の前に展開された大軍を抜けて王都一番乗りを果たそうと計画していたクリフトはこれから始まるであろう激戦を前に心が躍っていた。体の芯から熱くなり、戦いのときを待ちきれずにいた。それは今自分の後ろにいる妖魔たちと同じであることは分かっていたが、それを押さえるつもりはさらさらなかった。敵の数が多ければ、強ければそれだけ燃えてくる。そしてそれを打ち破って王都に入ってこそ、意義があることなのだ。
「セツナ、リューナ、エリザベート、アンナ、リリス!準備はいいか?」
「我は準備万端・・・」
「いつでもいいです、クリフトさま!」
「いつでも出られますわ!」
「あたいはすぐにでも始められるぜ?」
「準備、OKです!」
後ろに控える五人の少女達に問いかけると、五人ともいつでも戦えると答えてくる。その声はいつになく高揚しているようにクリフトには思えた。おそらく彼女たちもまた気分が高揚し、胸躍る状況なのだろう。クリフトはそれを咎めるつもりはなかったし、それでいいと思っていた。そんなクリフトの眼の前の霧が晴れてゆく。時間が来たと悟ったクリフトは愛用の双剣に手をかけると、ゆっくりと腰を落とす。セツナもまた太刀に手を添え、リューナは拳を握り締める。エリザベートは弓に矢を番え、アンナは愛用の鎚を握りなおす。リリスも呪文の詠唱を開始し、いつ戦いが始まってもいい様に身構える。そしてついに霧が完全に晴れ渡る。
「おいでなすったぞ!!」
嬉々とした口調のクリフトの視界には手に手に槍を、剣を構えたストラヴァイド兵が広がっていた。皆霧が晴れるのを待ち構えたかのように雄たけびを上げてクリフトたちに襲い掛かってくる。それをおとなしく受けるようなクリフトでも、”五天衆”でも、第8軍でもない。逆にそれを打ち消すような雄たけびを上げて、大地を震わせるような勢いでストラヴァイド軍に突っ込んでゆく。勢いよくぶつかり合った両軍の乱戦が始まる。
「もう少し何か策を弄しているかとも思ったが・・・」
「思い過ごし・・・」
ストラヴァイド兵の攻撃を背中合わせで捌きながらクリフトとセツナは拍子抜けした表情を浮べる。数で劣るストラヴァイド軍がこうまで正攻法で攻めてくるとは逆に予想していなかった。罠を張り、敵を混乱させてから攻撃してくるものとばかり思っていた。半数とはいえ自分達と同数の兵をヴェイス国境付近に配置してきたことは驚きであった。
「この様子だと他の国境線は守備隊くらいしかいないんじゃないか?」
「たぶん・・・」
「そうすっと・・・いそがねえと一番乗りできねえな!」
他の国境線から侵攻した軍が守備隊を破って王都ストラーヴに自分達よりも早く迫ることは明白であった。クリフトたちが一番乗りを果たすにはこの目の前にいる軍をさっさと全滅させるか、撤退させるしかない。そのことを改めて認識したクリフトは双剣を握る手に力がこもる。
「それじゃ、さっさとこいつらを倒しちまうとするか!!」
「承知!」
クリフトの言葉にセツナがすぐさま動く。迫り来るストラヴァイド兵の大群目掛けて飛び込んでゆく。飛び込んできたセツナに繰り出される無数の槍、その槍をセツナは手にした太刀で事も無げに受け止めて見せる。その槍を力任せに弾き返すと、片足を軸にその場で一回転する。
「”閃夢舞刀・紅牡丹”!!」
回転とともに繰り出された一撃が周囲のストラヴァイド兵を切り裂く。その瞬間、セツナの顔が曇る。太刀を握り締めた手をじっと見つめながら何事か考え込んでしまう。そしてそれを確かめるかのように、自分目掛けて突撃をしてきたストラヴァイド兵の胴を易々と薙ぐ。
「なんだ・・・この感じは・・・」
奇妙な違和感を覚えたセツナは切り倒したストラヴァイド兵を見下ろす。胴を切り裂かれた男は腹部から内臓とどす黒い血を撒き散らしながらすでに絶命していた。だが、セツナは言い知れない不安に駆られていた。それは他のところで戦うリューナたちも同様であった。
「何なの、こいつら・・・」
”双天武拳”の拳を胸に喰らった男が大地に倒れ伏す。その胸元は拳大に抉れ、その先にある心臓はその鼓動を留めている。しかし、その拳が当たった瞬間、リューナはこれまでにない感触を感じ、首を傾げていた。その違和感は相手が頑丈だから感じたものではなかった。逆に手ごたえがなさ過ぎるのだ。
「くそ!いっくらなんでも手ごたえなさ過ぎだぞ??」
大槌を振り回して4、5人の兵をまとめて吹き飛ばすアンナも同じような感じに戸惑っていた。今までに感じたことのない軽さがかえって不気味で仕方がなかった。吹き飛ばされたストラヴァイド兵は大量の血を撒き散らしながら絶命している。戦いに大きな影響があるわけではない。ないのだが、どうにも不気味で仕方がなかった。
「こいつら・・・簡単に死ぬ??」
エリザベートの放った矢を喉に受けたストラヴァイド兵ががっくりと両膝をついて大地に倒れ伏す。エリザベートの矢は確実にストラヴァイド兵の急所を射抜いているのだが、避けられるかもしれない攻撃まで簡単に喰らっているようにエリザベートには思えてならなかった。敵に自殺願望があるとは思えない。だが、そうとしか思えないような動きをストラヴァイド兵は見せているのである。
「この人たち、死を恐れていない・・・ううん、違う。感情がない??」
無数の氷の矢で自分を取り巻くストラヴァイド兵を串刺しにしながらリリスはストラヴァイド兵の様子に素直な感想を漏らす。次々に襲いかかってくるストラヴァイド兵の目には生気は感じられる。なのに感情のようなものを読み取ることがリリスにはできなかった。まるで全員が戦いの中で死のうとしているようにさえ思えてならなかった。
「こいつら、いったい??」
クリフトもまた相手を倒したときの手ごたえに違和感を覚えていた。そんなクリフトに槍をかざしたストラヴァイド兵が襲い掛かる。易々とその攻撃をいなしたクリフトは目にも止まらないような速度でそのストラヴァイド兵の横を通り過ぎる。通り過ぎる瞬間、何度も双剣を振い、その男を切り刻む。これまでと変わらないスピードを生かした攻撃であったが、その速度、切れ味は格段に上がっていた。クリフトの中に眠る”腐敗”のグラシアスがクリフトに力を与えているかのような攻撃であった。無数の肉塊に切り刻まれた男は自身の血の海に沈む。
「肉が柔らかすぎる??」
切り刻んだ感触をクリフトはそう表現することしかできなかった。手ごたえは確かにある。なのにその切った瞬間の手ごたえが軽すぎるのだ。脂肪まみれの体でも、肉付きの悪い体でも、筋肉質の体でも関係ない。一律に易々と切り刻むことができるのだ。そしてそれは自分たちの力が増したからでないことは間違いない。首を傾げるクリフトであったが、今のところそれがどうかしたわけではない。切り刻まれたストラヴァイド兵は確実に息の根を止めているし、生命活動も停止している。生ける屍と化して再び立ち上がってくるかとも思ったが、いくら待ってもその様子もない。それが逆にクリフトたちの不安を駆り立て、不気味さを増していた。
「切った手ごたえが軽すぎる・・・なのに何の変化も見せない・・・何なんだ、こいつらは??」
いくら戦っても、敵を倒しても不安だけが大きくなってゆく。もしかするとこの不安を増幅させるための策なのかとも思ったが、そんなことをしても自分たちの進行速度が鈍るだけで王都に攻め込まれるという結果は変わるわけではない。つまりこの策は時間稼ぎにはなってもそれ以上にはならないことになる。
「時間を稼いで何かを探している・・・もしくは回収しようとしている??」
その何かがこの戦いを左右するようなものである可能性は高い。そしてそれを手に入れるためにストラヴァイドは一年間、大結界の中に隠れていたことになる。それが何なのかはわからない。存在するかもわからない。しかし、もしそれが存在するとすれば、それをストラヴァイドに手渡すことがまずいことだけはクリフトにもよくわかっていた。
「なんだ・・・何を探している、何を狙っている・・・」
ストラヴァイドの狙いがわからずクリフトは苦悶の表情を浮べる。しかし、すぐにその表情は明るいものに変わる。何か吹っ切れた表情を浮べてにやりと笑う。
「何を悩んでいるんだか、おれは・・・相手が何を求めようと関係ない!さっさとぶっ潰す!ただそれだけだ!!」
自分がいかに相手の術中に嵌まっていたかを認識したクリフトは自嘲気味な笑みを漏らして愛用の双剣を握りなおす。相手がどのような策を練っていようと、時間稼ぎを弄そうと関係ない。目の前にいる敵を叩き潰して敵大将の首を獲る。ただそれだけの話だったのだ。ここで敵がどんな策を立てているかなどクリフトには知ったことではない。どんな策を練っていたとしても答えは一つしかなかったのだ。どんな策を弄していてもその策が成就する前に戦いを終わらせてしまえば何の意味も持たない。逆にここで考え込んで相手に時間を与える方が愚かな行為でしかない。
「全軍!眼の前の敵を叩き潰せ!どんな敵だろうと関係ない!時間を与えるな!!」
クリフトの鼓舞するような命令に同じように考え込んでしまっていたセツナ達もはっと我に返る。考え込んでしまっていた自分達がいかに愚かであったかを悟り、唇を噛む。自分たちが敵を切る手ごたえのなさを気にするあまり、相手に時間を与えてしまうという愚行を自分達から犯してしまったことを恥じる。
「そうだ、何を愚かな・・・」
「うん。手ごたえがなくたって、相手は死んでいるんだ・・・」
「倒れた敵のことを考えても詮方ないこと」
「なら眼の前の敵をぶっ飛ばすだけだ!」
「そう!敵大将の元にたどり着くまで!!」
迷いの晴れたセツナたちの動きは早く、そして強かった。襲い来るストラヴァイド兵をまとめてなぎ倒し、押しつぶし、吹き飛ばし、切り刻む。手ごたえのなさなどもうどうでもよかった。ただ眼の前の敵を倒す。今のセツナたちにはただそれだけしか考えることができなかった。必死になって抵抗するストラヴァイド兵であったが、もはや巨大な台風と化したセツナたちを止めるほどの戦力はありはしなかった。それでも無駄な抵抗とわかっていても槍を構え、セツナたちに無謀な戦いを挑み続ける。一方的虐殺の果てに何もないと分かっていながら・・・
「第二軍、第四軍、ストラーヴに向けて進軍開始!第一軍、敵守備隊を粉砕!」
エリウスの元にもたらされる情報はヴェイス軍の一方的な勝利だけであった。エリウスはその勝利に喜んではいなかった。自分たちの戦力が圧倒的に上であることはわかりきっていたことだし、何より無駄な戦いが続くことが空しくてたまらなかった。もちろん、降伏勧告は出させてはある。しかし、ストラヴァイド兵は一人としてこの降伏勧告に応じることはなく、ただ無駄な戦いを挑んでくるのだった。
「第八軍、ストラーヴ西10キロのところで王都守備隊と遭遇!戦闘を開始した模様!」
「やはりこちらの降伏勧告には?」
「はい。一切応じておりません!」
その報告にエリウスは大きな溜息を漏らす。いくら闇は滅するべきと幼い頃から教えられているとはいえ、自分たちの命と引き換えにしてまでそれを実行しようとする意味がエリウスにはわからなかった。ここまでストラヴァイドが徹底抗戦に打って出る事はエリウスにも予想しきれないことであった。
「エリウス様、ご報告が・・・」
「んっ?なんだい?」
「今戦っているストラヴァイド兵ですが、どうやら感情が消失しているようです」
「感情が??・・・・・そうか、そう言うことか・・・」
そんなエリウスにフィラデラがクリフトたちからもたらされた情報を報告する。それを聞いたエリウスはしばし考え込み、その報告の重要性を理解する。今戦っているストラヴァイド兵に自我はない。あるのは目の前の敵と戦うという戦闘意欲だけなのだ。だから徹底抗戦を仕掛けてくる。だから逃げようとはしないのだ。これではレオナたちの降伏勧告など効果は期待できない。最初から降伏するという心が失われているのだから。
「厄介なことをしてくれる・・・」
エリウスは事態を深刻に受け止めていた。これまではルードとリンゼロッタの二人を討ち取る、または捕縛すれば全てが収まると思っていた。しかし、ストラヴァイド兵全てがこの状態であるとするならば2人をどうにかしただけでは収まらないはずである。しかし、エリウスはそれ以上の最悪の事態を想像して身震いしてしまう。
「これが兵士だけの話ならいいが・・・もし国民全員がこの状態だったら・・・」
エリウスが漏らした最悪のシナリオを聞いたフィラデラもまた身震いする。もし国民全員が今のストラヴァイド兵と同じ状態であったとしたら、戦いはストラヴァイド国民全てを討ち取らなければ終結はありえない。もし、そんな最悪のシナリオが描かれていたとしたら、それを描いた人物は最悪の趣味をしているといえる。
「そこまでして僕を討ち取ろうというのか、ギルガメッシュ・・・」
怒りに満ち満ちた表情でエリウスは拳を握り締める。もしこのまま戦いが続けばこちらの被害も甚大なものとなるだろう。それ以上に国民を皆殺しにしなければ終わらない戦争など、最悪以外のなにものでもない。その最悪のシナリオを平然と実行してきたのである、”九賢人”が1人、ギルガメッシュ=ヴォータスは。そしておそらくこの一件にはルードとリンゼロッタも関わっているはずである。国政の中枢にギルガメッシュの姿がなかったのだから、誰か権力のあるものにこの策を進言しているはずである。そしてそれを実行できるだけの権力者となれば数は限られてくる。
「あの恥知らずどもが・・・」
それだけの権力者となればおそらく現国王、その国王の命で命を投げ出す薬がばら撒かれているのだろう。もちろん自分達はその薬の効果の及ばない安全地帯にいることだろう。大結界を張るために先王を殺し、その遺体を贄にしたほどの者たちが、自分達からその薬を飲むはずがないし、何より自分の命の方が大切なはずである。危なくなれば真っ先に降伏するような連中が、死ぬまで戦う危ない薬を飲むとは思えない。自分の身を案じるあまり、周りが見えない、回りを平然と犠牲にする連中にエリウスは反吐が出る思いであった。
「今は王城にいるのか、ギルガメッシュ・・・」
いまだ戻らない力に不安を覚えながらエリウスは最大の難敵、ギルガメッシュとの戦いが近い事を実感していた。そしてその者は今王城で高笑いをしながらこの戦いを見下ろし、自分が来るのを待ち構えているはずである。そのギルガメッシュとの戦いを前にエリウスは気分の高揚を抑えられずにいた。
部屋の外では多くの兵が行き交う。今アリスの部屋の中には彼女以外誰もいない。気分が悪いと言って部屋にこもったまま、アリスはじっとしゃがみ込んだまま、一点だけを見つめていた。その表情は青く、息遣いも荒い。不安に心が押しつぶされそうだった。
「なんなのかしら、これは・・・???」
サクラの記憶が戻ったときからアリスの頭の中に様々な記憶が駆け巡っていた。記憶が駆け巡るというより、記憶が遡ってゆくと言った方が正しいだろう。エリウスと出会った頃の記憶、レオナやステラとの楽しい日々の記憶、今は亡き父母に抱かれた幼き頃の記憶、そしてそれはどんどんさかのぼり、アリスの知らない記憶が甦ってくる。
「これは、エレナ様の・・・」
最初に甦ってきたのはエレナの記憶。光の巫女としての日々、母エリスと語らう日々、叔父ルードのレイプされ、ヴェイスに捨てられた記憶もアリスは目の当たりにし、思わず悲鳴を上げてしまう。そんなアリスを無視するように脳裏に甦る記憶は止まるところを知らない。
「これは・・・歴代の”巫女姫”の記憶・・・」
これまでアリスが夢に見てきた”巫女姫”の記憶よりも鮮明で、それぞれの”巫女姫”の名前や生き様、恋の行く末まで全てがアリスの脳裏に鮮明に刻まれてゆく。そしてその”巫女姫”たちは皆幸せそうな顔をしていながらどこか物足りない生を送っていったことがアリスにはよくわかった。
「皆様、心のどこかでエリウス様を求めていたのですね・・・」
生涯巫女として生きた女性もいれば、恋に生きた女性もいた。そういった様々な生き方をアリスは涙ながらに脳裏に刻み込んでゆく。そして記憶はもっとも古き物へとさかのぼってゆく。
「これはヴェイグサス神が封じられたあと・・・」
アリスの目の前で繰り広げられていたのは”九賢人”によって倒されたヴェイグサス神の魂が二つに分けられ、一つが自分の中に、一つがヴェイグサス神とともに戦っていたバーグライドに封じられる光景であった。バーグライドはすでに力の殆どを失い、魔界へと消えてゆくところであった。こうして二つに分かれた魂は時を越えてバーグライドとエリスが出会うことで一つに戻り、エリウスが誕生したのである。その記憶を見つめながらアリスはそのときに自分がいたことに感謝した。同時にある疑問が頭を過ぎっていた。
「何故わたしにはこの記憶があるのですか・・・???」
ヴェイグサス神は12人の”巫女姫”の力を封じられたがゆえに”九賢人”に封じられたはずである。もしそうであるならアリスはすでに封じられており、この記憶は存在しないはずである。しかし、アリスの記憶にはヴェイグサス神が封じられるところが鮮明に残っている。それは自分が”九賢人”に封じられていなかったことを意味していた。
「ならば何故”九賢人”は私を封じなかったのです?何故・・・」
アリスは両手で肩を抱えながら考え込む。その答えなど最初から出ていたのだ。”九賢人”が自分を封じていなかった理由、それは自分が彼らの仲間だったからに相違ない。仲間であるならすぐに封じる必要性などどこにもない。全てが終わったあとに封印をすれば済む話である。そして彼らがもっとも恐れた自分の封印がすべての”巫女姫”の復活が鍵となるように仕組まれていたのは自分が最後に封印されたからである。
「私が・・・エリウス様を・・・裏切った・・・」
アリスには衝撃的な事実であった。とても信じられるようなことではなかった。そのアリスに突きつけるように新しい記憶が甦ってくる。それはかつての自分の心、ヴェイグサス神を愛し、独占したいという想い、他の”巫女姫”達への嫉妬心。そんな醜い感情がアリスの中に流れ込んでくる。そしてその独占欲はついに他の”巫女姫”達を封印するという暴挙となって表れてしまう。一人、また一人と”巫女姫”達を封じていった事がヴェイグサス神を弱まらせる結果となったのだ。そのことは自分もよくわかっていた。それでもヴェイグサス神を独占したい思いを抑えることが出来なかったのだ。その結果、ヴェイグサス神は封印され、自分を含めた”巫女姫”達が甦るまでに永き時を要することとなった。
「私が・・・私が・・・」
見たくなかった、知りたくなかった過去にアリスは号泣して泣き崩れる。今他の”巫女姫”たちと嬉しそうに笑いながらエリウスと過ごす資格など自分にはなかったのだ。嫉妬に狂い、仲間を、父神を裏切った自分がこの幸せな地にいられるはずがない。それはエリウスも他の”巫女姫”たちも想いは同じだろう。表面的には笑っていても内心は怒りに満ち満ちているに違いない。それは実の姉であるレオナも例外ではない。
「私は・・・ここにいる資格なんて・・・ない・・・」
ボロボロと大泣きしながらアリスは何度も何度もそう呟く。自分が過去に犯した罪に押しつぶされそうになりながらアリスの心はただ傷ついていくだけであった。その過去から逃げ出すようにアリスはよろよろと立ち上がると、部屋を出て、魔天宮を抜け出して、夜の闇に消えてゆく。その姿を追うものは誰もいなかった。
「もう・・・帰れない・・・エリウス様・・・ごめんなさい・・・」
『帰れないのですか?ならば我が元に来るといいでしょう!』
泣きながらふらふらと夜の闇の中を裸足のまま歩くアリスはそう何度も呟く。そのアリスの呟きに答えるような声があたりに響き渡る。その声に立ち止まったアリスは辺りを見回す。空間が歪み、誰かがアリスの目の前に降り立ってくる。顔はフードに隠れていて見ることはできない。しかし、声の感じから男であることは間違いない。
「貴方・・・は・・・」
「貴方のその力、俺が使ってあげるよ・・・」
怯えるアリスに男はそう言い放つ。そしてフードから覗く口元を邪悪に歪めるのだった。その邪悪さにアリスは身の危険を感じ、逃げ出そうと試みる。エリウスの元に逃げることはできない。逃げる場所などどこにもない。そんなことはアリスにもよくわかっていた。それでもこの男に捕まるのはまずい、そう彼女の直感が感じていた。しかし、踵を返して逃げ出そうとしたアリスだったが、その体から力が抜けてゆく。眼の前が霞み、強烈な睡魔が襲い掛かってくる。抗っても抗ってもその睡魔から逃れることは出来ない。
「エリ・・・ウ・・・ス・・・様・・・」
愛する人の名前を呟きながらアリスの意識は完全に闇に包まれる。全身から力が抜け、糸の切れた操り人形のように崩れ落ちるアリスを男は易々と受け止める。そのか細い体を抱きとめた男の邪悪な笑みはさらに色濃くなってゆく。そして喉を鳴らして不気味な笑い声を上げる。
「手に入れた・・・ついに手に入れたぞ・・・」
その言葉にはなにかに勝ち誇ったような響きが含まれていた。男は二度と放すまいといわんばかりにアリスのそのか細い体を抱きしめる。そしてドレスから覗くその真っ白な首筋に痕が残るほどの口付けをする。それはまるでアリスが自分のものであることを誇示するしるしを刻み込むような口づけであった。
「お前のその力、俺が有効に活用してやるぞ・・・くくくっ」
もう一度喉を鳴らしながら笑った男は何事か呟く。やがてその姿は現れたときと同じく空間の歪みへと消えてゆく。あとにはただ風だけが空しく吹いているのだった。
→進む
→戻る
→ケイオティック・サーガのトップへ
|
![]()
![]()