|
第4話 ピンチ?敗北?覚醒?新たなる力、その名は”蒼雷”!!
「増えましたねぇ〜〜」
「増えたなぁ・・・」
「増えちゃいましたね・・・」
「ッて、どうするのじゃ、この人数を!!」
豪拳寺家の地下に作られた秘密基地内にシルヴァの悲鳴にも似た絶叫が響きわたる。シルヴァの絶叫に基地内にいる奴隷たちが一斉にシルヴァの方を振り返る。それも一人や二人ではない。30数人にも及ぶ数の奴隷が一斉にシルヴァの方を振り返ったのだ。思わずシルヴァが仰け反ってしまう。
「仕方ありませんよ、姫様〜〜。勝ったら相手のパートナーを奴隷にできるルールなんですから」
「しかも相手が勝ち取った奴隷まで全部引き受けなくちゃならないからねぇ・・・」
「ここまでセイシロー様は16連勝。奴隷もこれだけになっても仕方がないです」
同じく増えすぎた奴隷を見つめながらアル、倫、エルも深い溜息を漏らしながら感想を漏らす。精子朗が勝てば勝つほど奴隷が増えていく現状にシルヴァは怒りを覚えていた。理由は一つ、皆が皆、精子朗に手を出そうとしていることだった。隙あらば精子朗に近寄り、ご奉仕しようとするのだ。しかも、性質の悪いことに精子朗がそれを喜んでいるのだ。それがシルヴァの怒りをさらに増幅させていた。
「こやつらをどうにかできぬのか、アル、エル!!」
「できませんよ。彼女たちはセイシローさんの奴隷。わたし達にはどうこうできませんからね」
「では、セイシローに言って追い出してくれる!!」
「それもできませんね。指輪と奴隷、双方の数が合わなければ最終的勝利者にはなれませんから」
ケラケラと笑いながら答えるアルにシルヴァは静かな殺意を覚える。とはいえ、精子朗に最終的勝者になってもらわなければ自分の望みは叶えられない。どこの誰ともわからない馬鹿に優勝されては堪ったものではない。ここは耐えるしかないと大きな溜息を漏らす。
「あたし的には出て行ってもらっても構わないけどね。精子朗をあんた達から解放できるし」
それまで黙ったまま話を聞いていた倫が口を開く。ここで精子朗の参加資格が剥奪されてもシルヴァのわがままによるもので、精子朗に罪はない。精子朗は自分の元に戻ってきて、シルヴァたちは母星に戻される。倫にとってこれ以上望む展開はなかった。その意図を読み取ったシルヴァは今度は倫を睨みつける。
「そのようなこと、認めるわけなかろう!!それにそなたもあやつらは邪魔で・・・」
「あたしは邪魔に思ってないわよ?上にさえ来なければ」
倫は平然とした顔でそう言い放つ。その言葉の裏には精子朗は地下には行かせないという意味が含まれていた。それを察したシルヴァはにやりと笑う。精子朗が地下に行きさえしなければ彼女たちが寵愛を受ける心配はない。精子朗を自分が独占することができるのだ。もちろん倫がシルヴァのためにそんなことを言った訳ではない。
「ついでだから精子朗はうちに泊めようかしら・・・教育上こんなところにいたらよくないし」
「おい、なにを勝手なことを言っておる!セイシローはわらわのものじゃ!」
「勝手なこと言わないでよ!それとも名前でも書いてあるのかしら?」
「うむ、あたりまえじゃ!!」
「へ??」
「昨晩夜伽のあと、あれのおちんちんに『しるば』とマジックで書き込んどいたぞ!」
半分笑いながらの倫の問いであったが、シルヴァはその大きな胸を反り返らせて即答してくる。あまりにきっぱりと答えてくるので倫の方が唖然としてしまう。そのあまりな答えに倫が茫然自失していると、階上で悲鳴にも似た叫び声が聞こえてくる。おそらく自分の異常に気付いた精子朗の悲鳴だろう。
「何をやっているんだか・・・」
倫は思わず溜息を漏らす。そんな倫を嘲笑うかのようにシルヴァは胸をさらに反り返らせながら高笑いを響かせる。そんな毎度の光景にアルもエルも表面上平静を取り繕いながらも内心はあきれ返っているのだった。
「こりゃ!セイシロー!!何の真似じゃ、これは??」
「今朝、イタズラをしたお仕置きだ!!」
全裸のまま両手をロープで縛り上げられ、ベッドの上に放り出されたシルヴァは悲鳴交じりの声で精子朗を問い咎める。が、精子朗の方は半眼でシルヴァを見下ろしながら平然とそう答えてくる。剥き出しのペニスにはまだシルヴァの名前が書かれたままである。その様子を見ても精子朗が相当怒っているのは一目瞭然であった。
「の、のう、セイシロー・・・わらわもそなたのことを・・・」
「言い訳は聞かないよ、シルヴァ・・・お仕置きとして今晩はこれが消えるまで犯るからね」
必死になって言い訳をしようとするシルヴァに精子朗はにっこりと笑ってそう断言する。シルヴァは思わず息を呑む。油性のマジックで書かれたそれが消えるまで犯るなどどれほどの時間嬲られるのかと想像するだけで股間が濡れて、もとい恐ろしくなってくる。そんなシルヴァの気持ちを知ってか知らずか、精子朗はシルヴァの股間に手を伸ばしてくる。
「こりゃ、セイシロー!!?」
「期待してるんだ、シルヴァ・・・」
「な、なにを言うて・・・」
「だってこんなに濡らしているじゃないか、何もしてないのに・・・」
顔を真っ赤にさせて否定するシルヴァに精子朗は自分の指を股間から離してシルヴァに見せつける。指先はびっしょりと濡れそぼり、トロトロと煌めく愛液が手首の方にまで垂れてくる。自分がもうそんなに濡らしていたとは思いもしなかったシルヴァはその信じがたい光景に弱々しく頭を振る。
「そんな・・・嘘じゃ・・・」
「嘘じゃないよ。でもこれなら前戯なしでもいけそうだね」
指先の愛液をゆっくりと舐め取りながら精子朗はシルヴァの否定をさらに否定する。そして自分のペニスに指を伸ばして唾液と交じり合った愛液をこすり付けてシルヴァに見せ付ける。すでに期待に大きく反り返ったペニスは血管を浮かび上がらせて大きく脈動する。そのペニスにいやらしさにシルヴァは思わず息を呑む。あんな太くて硬いものに貫かれた瞬間を想像すると、心臓がさらに激しく脈打ち、あそこがさらに濡れて来るのがいやでもわかる。
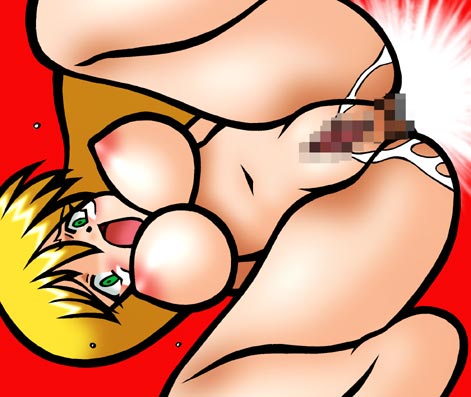
「シルヴァも我慢できないみたいだね?じゃあ、おねだりしてご覧??」
「え??そのようなことできるわけが・・・」
「できないならお預けだよ?」
精子朗はイジワルそうに笑いながらそう言ってくる。まだ朝のことを根に持っているのは間違いない。しかし、シルヴァの方も我慢が限界に近付きつつあった。呼吸はどんどん荒くなってゆく。シルヴァの視線は精子朗のペニスから離れない。いつしか自然に腰が浮き、自ら足を開いて精子朗を求めてしまう。
「セイシロー、わらわのここに入れておくれ・・・」
「だ〜〜め、もっと卑猥に言ってくれなくちゃ入れてあげない」
「そ、そんな・・・」
体は火照っているのだが、そんなおねだりをするなど王女の誇りが許さない。シルヴァが何も言わず、モジモジとしていると、精子朗は早く言えといわんばかりにそのいきり立ったペニスをシルヴァのその潤ったヴァギナに押し付けてくる。敏感になったヴァギナを通してその肉棒の固さと熱さが伝わってくる。その熱い肉棒がヴァギナにこすり付けられると、愛液が絡みつきクチュクチュとイヤらしい音を立てる。その音がシルヴァの欲望をさらに掻き立てる。シルヴァは切なそうに精子朗を見つめるが、精子朗は何も言わずにじっと見つめ返してくるだけだった。
「セイシロー、わらわの、オマンコに・・・セイシローのおチンチンを入れてたもれ・・・」
「はい、よくできました!」
顔を真っ赤にしておねだりすると、精子朗は待ていましたとばかりにそのいきり立ったペニスをシルヴァのヴァギナに捻じ込んでくる。熱く脈打つ肉棒が柔肉を掻き分けて圧し進んでくる感触にシルヴァは思わず歓喜の悲鳴を上げる。潤ったそこは肉棒をあっさりと受け入れ、最奥にまで到達する。
「シルヴァはここをこつこつされるのが大好きだったよな?」
「んくぅぅっっ!!そうじゃ、そこを・・・そこをこつこつされるのが・・・」
「この辺りを擦り上げられるのも好きだったよね??」
「あああんんっっ!!セイシロー!!!」
雁首を肉壁にこすりつけ、亀頭の先端で子宮の入り口をこつこつしてやると、シルヴァは恍惚の表情を浮べて喜びの声を上げる。その声とともに溢れ出す愛液の量も増し、肉棒によって押し出された愛液は玉袋を伝ってシーツに大きなシミを作ってゆく。そんなシルヴァの蜜壷の感触をもっと味わおうと精子朗は彼女の両脚を抱え込んでその動きをさらに加速させてゆく。肉棒がシルヴァの蜜壷をかき回し、彼女の欲望をどんどん押し上げて行く。
「だめ・・・もうだめじゃ・・・セイシロー、もう限界・・・」
「こっちもそろそろ・・・このまま膣内で出していいかい??」
「うむ、許可する。思い切り出すがよいぞ!!」
お互いに登りつめ、限界が近いことを告げあう。そこからの精子朗の動きはさらに激しくなる。シルヴァのもっとも喜ぶ箇所をかき回し、突き上げる。自身も気持ちのいいところをシルヴァの肉壁に押し付けて快楽を得る。二人はそろって限界へ向かって登りつめてゆく。その限界はすぐに訪れる。
「シルヴァ、もう!!!」
「セイシロー、セイシロー!!うああああぁぁぁぁぁっっっっ!!!」
精子朗はシルヴァの最奥で思いきり自分をぶちまける。お腹の中で熱いものが吐き出され満たされてゆく感触にシルヴァは満足感を覚え、体を大きく震わせて絶頂へと至る。収縮したヴァギナがペニスを絞り上げ、最後の一滴まで絞り上げる。お腹の中に幸せをいっぱい感じながらシルヴァは嬉しそうに微笑む。が、精子朗の方はペニスをシルヴァのヴァギナの中に入れたまま動こうとはしない。どうしたのかと訝しむシルヴァは精子朗に問いかける。
「どうかしたのか、セイシロー??」
「・・・・・何言っているんだい?さっき言ったじゃないか。今晩はこれが消えるまで犯るって」
精子朗はイジワルそうな笑みを浮べると自分の下半身を指差しながらそう囁きかけてくる。その言葉にシルヴァは絶句してしまう。先ほどの言葉は冗談ではなかったと言うのか?おろおろとするシルヴァを他所に精子朗のペニスは元気を取り戻し、シルヴァのヴァギナをまた押し広げてくる。
「セイシロー、冗談は・・・」
「冗談なんかじゃないよ。今晩はシルヴァで思い切り楽しむんだ!!」
「やめ、やめるのじゃ・・・あああああああぁぁぁぁっっ!!」
青ざめるシルヴァを他所に精子朗は腰をまた動かし始める。強弱をつけながら擦りあげるペニスの感触にシルヴァは歓喜とも悲鳴とも取れる声を上げる。そんなシルヴァの声をおかずに精子朗はどんどん動きを加速させてゆく。今宵も精子朗の部屋から喜びの声が途絶えることはなかったという。
ちょうどそのころ・・・・
「あれがシルヴァ姫のいる地球とかいう星か?」
月軌道上、真正面に地球を見据えながら三体の決闘機が並び立つ。
一体は細身で細身の剣を腰に差すロボット、背中には翼が生えている。
一体はやや大型のロボット、手には三叉矛が握られている。
一体は大型でその機体に見合った装甲を施した重量型のロボット、大型の鉄球もその巨体に見合っている。
「そうだ。そこの原住民がシルヴァ姫と契約、すでに16連勝を飾っている」
「はっ、どうせ姫様狙いの弱小騎士どもを倒したくらいでしょうに?」
「奴を甘く見るなよ?奴は初めての戦いで、それも5対1のハンディキャップを背負いながら圧勝している」
一人が自分にもたらされた報告を他の二人に聞かせる。他の二人もその報告に思わず感嘆の声を漏らす。こんな辺境の、それもロボットの操縦とは縁のない文化レベルの原住民が初めての戦闘でそんな戦果を挙げられたことはまさに奇跡と言ってもいい。いや、何か八百長じみたことが行われたのではないかと勘繰りたくなる。
「残念ながら正面からぶつかり合って負けたらしいぞ、こいつらは・・・」
「まったく情けないわね・・・こんな文化レベルの低い原住民にやられるなど、帝国騎士の名折れよ!」
「まったくだ!」
報告を聞いていた二人は憤慨し、負けた騎士たちを罵り始める。そんな2人を溜息交じりに見つめながら報告をしていた男は2人から目を逸らし、手元の報告書に目を落とす。そこには精子朗のこれまでの戦いに記録が収められていた。正直言ってパワーの面では自分を遥かに凌駕している。これほどの機体を創造した地球人のことを侮るわけにはいかない。文化レベルは低いかもしれないが、それを補ってあまりある何かを彼らは持ち合わせているのかもしれない。負けた者たちはその何かを見落としたがために完敗を期したのだ。自分はそのニの鉄は踏む訳にはいかない。
「で、誰が最初にこいつに戦いを挑む?」
「俺様が一番に決まっているだろう?」
「ないを言っているのよ!僕が一番に決まっているでしょ!!」
報告書に目を落としている間に他の2人の言い争いはいつの間にか、どちらが先にシルヴァ姫を護る騎士に戦いを挑むかに変わっていた。正直情報が少なすぎる今、戦いを挑むのは危険である。こいつらが先に戦いを挑むというならその情報を元に相手の弱点を見つけ出せるかもしれない。しかし下手にしり込みしたら何か勘繰られたら厄介でもある。ここは下手に口を出さずに他の2人の話の流れに任せることにする。やがて自分を無視して話を進めていた二人は勝手に順番を決めてしまう。案の定、自分は一番最後にされてしまう。
「まったく、きみたちは勝手だなぁ・・・」
「話に乗ってこなかった方が悪いのよ!シルヴァ姫は僕はのものよ!」
「残念だが、お前まで回らねえよ!姫と皇帝の位は俺様のものだ!!」
大型の機体に乗った男は勝ち誇った笑みを浮べると大笑いを始める。そんな男に三叉矛を持った機体に乗った男は不機嫌そうな顔をする。そんな2人に細身の機体に乗った男はやれやれと肩を竦めてみせる。案の定単純な2人は自分の思惑など知りもせずに勝手に順番を決めてくれた。内心男はほくそえみながら、二人の健闘を祈ると笑って見せるのだった。
「よっしゃ、なら早速決闘場を出すとするか!!」
「戦場はこの月と呼ばれる星でいいんだっけ?」
「ああ。ここを我々に有利な地形にして待ち構えておけばいい」
自分たちの機体に絶対の自信を持つ3人はその機体のもっとも得意とする領域での戦いで戦えば決して負けないと自負していた。たとえそれがこれまで破竹の勢いで勝ち進んできたものであっても負けるはずがないと信じきっていた。三人は月に降り立ち、決闘の準備を始める。自分たちの勝利を信じきって・・・
そしてまた戦いが始める・・・
「決闘状?それも三通、同じ日付で???」
「はい。それぞれ一対一で戦いたいと申し出ています」
これまでも結果的に一対一になることはあったが、正面から一対一の決闘を申し込まれたのははじめてであった精子朗は正直驚いていた。正々堂々とした奴もいたのかと感心してしまう。もっとも三連戦という辺りは気になったが。そんなしきりに感心する精子朗を諭すようにアルは注意を促してくる。
「精子朗さん、あまり感心しない方がいいですよ?」
「?どうしてだい??正々堂々一対一なんて清々しいじゃないか??」
「一対一には裏があるということです。この決闘に参加している連中なんて欲望の塊みたいなものですから」
精子朗の理想をすっぱり一刀両断するようにアルは言い切ってみせる。アルにしてみれば、一対一の決闘での連戦は相手に疲労を蓄積させること、エネルギーの補給を低下させること、相手の弱点を探るための方便でしかないと思っている。ということは今回の戦いで一番得をするのは一番最後に戦いを挑んでくるものということになる。
(たしか高速戦闘用の機体でしたね。名前は”ラウンジ”搭乗者はハーフ=リップ・・・)
その名前はアルも聞き覚えがあった。ある騎士の懐刀であり、策士的役割を演じいるとウワサされているある。策と言っても相手を嵌める策略が多く、何の前情報もなしに正面からぶつかって来るようなタイプではなかったはずだ。そんな男が一番最後ということは前の2人、”ガ・リュード”のレストン、”マーメイデン”のスイカーンのふたりは精子朗と”シュテンカイザー”の力を計るための道具にしか思っていないはずである。
「セイシローさん、できる限り力を出さないで勝つ様にしてください!」
「そんな奴が相手ならそうしたいところだけど、相手も並じゃないだろう?」
アルはハーフの存在を気にして力を押さえて戦うように精子朗に求める。だが、精子朗の言うようにレストンもスイカーンも若手騎士の中でも屈指の実力者であったはずである。そんな連中と真正面からぶつかり合えば、余力を残して勝てという方が無茶な話である。
「一応努力はしてみるけど・・・」
「せめて弱点を晒すような真似だけはなさらないように・・・」
「まあ、そのときはそのとき・・・まだね・・・」
弱点を晒せばそこをハーフが付け入ってくることは目に見えている。そうなればいくらパワーで勝る”シュテンカイザー”でも負ける可能性は高くなってくる。それだけは防がなければならない。そんなアルの心配を他所に精子朗は余裕綽々であった。そんな精子朗に不安そうな顔をするアルであったが、心配そうなアルに聞こえないように精子朗はボソリと何かを呟く。その意味ありげな笑い方があるには気に掛かったが、精子朗が何かしらの策を立てていることだけは間違いなかった。そしてその精子朗の策がシュテンカイザーの謎に関わっていることはアルもわかっていた。
「まあ、なんにしろ、敵さんが待っているんだろう?行って来るよ」
「こりゃ、セイシロー!!」
売られた喧嘩は買わなきゃ損、とばかりに決闘を受ける気満々の精子朗はシュテンカイザーで月へと向かおうとする。その精子朗をシルヴァが呼び止める。まだ寝起きらしくシーツを体に巻いただけのあられもない格好をしている。その後ろには姫のドレスを手にオロオロするエルの姿があった。
「何か用かい、シルヴァ??」
「そなた、これから決闘じゃそうだな??」
「そうだけど??」
「うむ・・・あの・・・ま、負けるでないぞ??」
気恥ずかしそうに顔を真っ赤に染めながらシルヴァは精子朗にエールを送る。そんなシルヴァが可愛らしくて精子朗はにやりと笑うと、シルヴァのおでこに軽くキスをしてやる。
「姫様がそれをお望みでしたらこの決闘、見事三連勝で飾って見せましょう?」
「そ、そんなの当たり前のことじゃ!!」
精子朗の言葉にシルヴァはむっとした顔をする。その両手はおでこに当てられ、少し恥ずかしそうな顔をしている。精子朗はケラケラと笑いながら手を振ってシュテンカイザーの方に向かってゆく。その後ろ姿を見送るシルヴァの胸には言い様のない不安が渦巻いていた。何かよくない事が起こるかもしれない、そんな不安がシルヴァの心をかき乱す。そんなシルヴァの不安を他所に精子朗はシュテンカイザーを起動させると、月へと向かってゆく。新たな決闘に勝利するために。
月面の一角に作られた決闘場ではすでに第一の対戦相手ガ・リュードが待ち構えていた。登場するレストンはその機体に似てずんぐりむっくりとした小柄な体格ながら筋肉質な体つきで、端からみればドワーフのような風貌であった。レストンは決闘の時間までまだ三十分以上あるというのにもう我慢できないとばかりに鼻息荒くコックピットで捲し立てていた。
「遅い、遅すぎる!!!このまま決闘を放棄する気か!!!??」
あまりの短気ぶりにスイカーンとハーフは思わず吹き出してしまう。決闘状を出してまだ10時間ほど、相手にだって準備というものがある。そんなことまで考えられないレストンの単細胞振りがおかしくてたまらなかった。そんな笑う二人を他所にレストンは1人荒れ狂い、武器の鉄球を振り回して何度も地面に叩きつける。
「で、スイカーン殿。どう見ますか、この戦い??」
「まあ、レストン殿もそれなりに戦えるでしょうけど、相手はゴゴットを倒した程の男。パワー一辺倒じゃ、ね・・・」
「でしょうね。まあ、レストン殿はゴゴットのような小物とは一味違いますからね」
ニヤニヤ笑いながらレストンとの通信を切った状態でこれから始まるであろう決闘の結末を2人は予想する。同じパワー型でもゴゴットのように力押し一辺倒で行かないのがレストンであることは2人がよく知っている。どんな隠し技を持っているのかも確認できるのも2人にとっては幸運であった。
「どうやらお出でなさったようよ?」
スイカーンの言葉どおり、対戦相手の出入り口から真紅の機体が姿を現す。ガ・リュードの前に降り立ったシュテンカイザーはすぐさま距離を置き、戦いに備える。その姿にレストンは獰猛な笑みを浮べて狂気の歓声を上げる。これから戦う相手のその動きから油断していないことが伝わり、嬉しく感じたのだ。
「なかなかすばやいじゃないか?奇襲対策って訳だ?だがな・・・」
レストンは笑みを浮べたままレバーを握り締める。再起動したガ・リュードは鉄球を肩に担ぐような体勢を取ると、臨戦態勢を整える。決闘開始時刻までお互いに一歩も動かず、じっとお互いを睨みつけたまま時を待つ。スイカーンとハーフもまたそのときを固唾を呑んで見守り続ける。
「俺様はガ・リュードのレストン・・・キング・オブ・パワーのレストンだ!!!」
レストンは大声で名乗りを上げると、精子朗が名乗りを上げる間もなく大きく鉄球を振りかぶってシュテンカイザー目掛けて投じてくる。唸りを上げて襲い来る鉄球に精子朗は瞬時に反応し、その攻撃を紙一重でかわす。シュテンカイザーを通り過ぎた鉄球は地面に叩きつけられたそれはは易々と固い岩盤を砕き、大きく陥没する。レストンが得意とする固い岩盤での戦いであったが、その岩盤をレストンは自分から破壊してしまう。
「どうだ!!この大鉄球の威力は!!」
レストンはそう叫びながら鉄球を振り回す。振り回す勢いが増すほどに鉄球の破壊力は格段に増してゆく。最初こそ華麗にかわしていた精子朗だったが、スピードが増すとその攻撃を受け止めざるを得なくなってくる。金属と金属のぶつかり合う音があたりに響き渡る。シュテンカイザーの装甲が震え、激しい衝撃がコックピットにまで伝わってくる。
「こりゃ、相当なパワーだな・・・でもね!」
ガ・リュードのパワーを目の当たりにした精子朗は一頻り感心するが、すぐさまレバーを押して攻撃に転じる。大地を滑るように走るシュテンカイザーは鉄球を掻い潜り、ガ・リュードの懐深くまで潜り込んでゆく。そのシュテンカイザーの攻撃はガ・リュードの重装甲の隙間を縫うようにしてヒットしてゆく。その攻撃を嫌がり、距離を置こうとするレストンだったが、精子朗はそれを許さない。一定以内の距離を保ち、確実にダメージを与えてゆく。
「ダメですね、これは・・・」
「ええ、まるで相手の動きに付いていっていないわ・・・」
スイカーンもハーフもシュテンカイザーの動きに翻弄されるガ・リュードの姿に溜息を漏らす。その姿はあまりに哀れで、滑稽でしかなかった。ここまで一方的ではシュテンカイザーに関する情報を集める前にガ・リュードが負けるのではないかと思えてしまう。仮にもここまで生き延びたレストンをここまで翻弄するシュテンカイザーのスペックが異常なまでに高いことだけが理解できた。
(まったく、せめて相手に本気を出させてくださいよ)
このままではまともな情報を仕入れられないままスイカーンに託さなければならないとハーフは内心悪態をつく。そんなハーフの悪態が聞こえたのか、急にガ・リュードの動きを止める。突然のことに何をする気かと警戒する精子朗の眼の前でガ・リュードはその機体を覆い尽くすような装甲を外してゆく。一個、また一個と外れる装甲が地面に落ちるたびに轟音が鳴り響き、土煙が舞い上がる。
「装甲を外した??スピードで対抗する気ですか」
「まさか・・・武器があれでは機体のスピードが上がっても・・・」
レストンの突然の行動に驚いたのはハーフとスイカーンも同じであった。これまでのレストンの戦い方はその堅固な装甲で相手の攻撃を受け止め、その鉄球で相手を粉砕するというものであった。その武器ともいえる装甲を外すのはハーフもスイカーンも始めてみる光景であった。
「ガ・リュードの装甲を外すのは久方ぶりだな!」
レストンは機体の軽さを確かめるようにガ・リュードの肩を二度、三度廻すと、シュテンカイザーを睨みつけながらそう叫ぶ。あれだけの装甲を外したとなれば相当軽くなったはずである。しかし、同時にその防御力は先ほどまでの半分にも満たないだろう。シュテンカイザーの一撃で沈みかねないほど、薄くなっていることは間違いない。一撃で沈みかねない装甲にしてまでもスピードで対抗するつもりとしか考えられない行動であった。それはレストンが精子朗をそれだけの敵とみなしているのかもしれない。装甲の軽くなったガ・リュードが鉄球を真正面に構えなおす。
「うごらっしゃぁぁぁぁぁっっっっ!!!」
奇声とともにレストンは鉄球を振り回し始める。勢いよく回転させると、そのままガ・リュードの踵を軸にして回転を早めてゆく。ガ・リュードを中心に回転する鉄球、それはまるで小さな台風のようであった。にわかに現れた小型の台風は回転したままシュテンカイザーに襲い掛かってくる。
「くらえ!!ハンマー・タイフーン!!!!」
ものすごい勢いで回転するガ・リュードがそのままシュテンカイザーに襲い掛かる。精子朗はその軌道を読み、綺麗に回避して見せる。だが、その動きは回転が増すごとに不規則になり、精子朗の読みを上回ってくる。やがて回避しきれなくなり、肩口に鉄球の先端がかすり、その装甲を一部もぎ取ってゆく。
「こいつは驚いた・・・こんな戦い方もできたのか・・・」
「ええ。攻撃が不規則だから相手も読みきれていないわ」
スピードは上がっているが攻撃パターンは不規則であり、精子朗も徐々に追い詰められてゆく。しかし、精子朗の方にはまだ余裕が残っていた。まだフルパワーを出していない以上、自分の方が有利であるという思いこみであった。同時にガ・リュードの攻撃をどう捌くかを考え、それを実行する。
「いくぞ!!」
精子朗は掛け声とともに襲い来るガ・リュードに向かってゆく。その向かい来るもの全てを粉砕せんばかりの勢いで回転し続けるガ・リュードの鉄球の動きを注視し、その懐まで入り込んでゆく。だが、回転する体への攻撃は全て弾かれてしまい、ガ・リュードの動きを止めることはできなかった。
「装甲は薄い分、回転で防御力を挙げているのか・・・なら!!」
精子朗は状況をすばやく分析すると、地面を思い切り殴りつける。シュテンカイザーの拳が地面にめりこみ、大きく陥没する。その砕けた岩を手にすると、それをガ・リュード目掛けて放り投げながら逃げ回り始める。もちろんシュテンカイザーのパワーで加速した岩であったが、それでどうこうなるようなものではなかった。
「そんな攻撃、通じるか!!!」
さらに加速して攻撃してくるガ・リュードの鉄球を避けながら精子朗は小刻みにステップをしながら動き回る。二度、三度鉄球がシュテンカイザーの装甲に触れるが、それで動きを止めるようなことはしない。その精子朗の動きにハーフもスイカーンも何かを感じ取っていた。
「何かを誘っている??」
「何を誘うっていうのよ?攻撃が通じないんじゃ・・・」
精子朗の考えていることがわからない二人は首を傾げるしかなかった。しかし、その意味はすぐに分かることとなった。大きく跳び退ったシュテンカイザーを追って来たガ・リュードが突然大きく傾ぐ。回転の軸である両脚が、先ほど精子朗が作り出した陥没にまんまと嵌っていたのである。これによって回転軸がぶれたガ・リュードの回転は大きく揺らぐ。その瞬間、シュテンカイザーが攻めに転じる。再び懐深く飛び込むと、回転の緩まった鉄球の鎖目掛けて蹴りを見舞う。シュテンカイザーの鋭い蹴りが鉄球の鎖を見事に分断する。
「なるほど・・・回転を止めるのが狙いですか・・・」
「しかし、こんなこともわからないレストン殿とも思えないんですけどね?」
首を傾げるハーフとスイカーンの眼の前でレストンは吹き飛ばされた鉄球を空中で見事にキャッチすると、そのままシュテンカイザー目掛けて放り投げてくる。しかし、シュテンカイザーはその攻撃すら読んでいたかのように体の位置を少しずらして鉄球を回避する。その瞬間だった。レストンの顔に笑みが広がる。
「もらったぁぁぁっっっ!!」
シュテンカイザーがガ・リュードの攻撃を回避した瞬間、その足元が崩れ、その下から巨大な手が現れシュテンカイザーを握り締める。その圧倒的なパワーの前にシュテンカイザーは身動き一つ取れず、装甲はぎしぎしと軋み始める。精子朗は何とか脱出を試みるが、シュテンカイザーを握りつぶそうとする手はびくともしない。
「見たか!俺様の奥の手、ゴッド・ハンドの威力を!!」
レストンは勝ち誇って大笑いをする。巨大な手はシュテンカイザーを引きずるようにしてガ・リュードのもとまで移動すると、ガ・リュードの腕と合体する。そしてガ・リュードのパワーを合わせてさらに強力な力でシュテンカイザーを握りつぶしに掛かってくる。
「あれは・・・先ほど外したパーツ類ですか・・・」
「なるほど、さっきまでの無謀な攻撃はそこに追い詰めるための囮ってことなのね?」
ハーフもスイカーンも予想外の展開に感嘆の声を漏らす。さすがはレストン、パワー一辺倒の力馬鹿ではないと思わず感心してしまう。最後は力技であるが、そこに至るまではたいした知略である。自分たちが戦ってももしたら同じ目にあっていたかもしれない。そう考えると、この先の決闘の際のいい前情報を得られたことになる。そうこうするうちにシュテンカイザーを握り締める力は最高潮に達し、握り締める手の各所で爆発が起こる。
「この勝負、これで終わりですかね?」
「まあ、文化レベルの低い原住民にしてはよくやった・・・」
レストンの勝ちを確信したハーフとスイカーンは鼻で笑う。が、その表情はすぐにそのまま凍りつく。爆発を起こしているのはシュテンカイザーではない。それを握り締めるガ・リュードの手の方である。いつしか握り締める力は弱まり、ガ・リュードの手はぎしぎしと軋み、そこらじゅうで小爆発を繰り返す。
「まったく、余計なことしやがって・・・」
そうぼやく精子朗操るシュテンカイザーがガ・リュードのゴッド・ハンドの親指を握りつぶし、引き千切る。そこから現れた姿は先ほどまでと違い、真っ赤な炎に包まれていた。関節部から噴出した炎がゴッド・ハンドの装甲を溶かし、指をその絶対的パワーで引き千切り、無力化してゆく。
「そんな・・・俺様のゴッド・ハンドが・・・・」
「三連戦だからパワーを押さえて戦うはずだったのに・・・」
呆然とするレストンに対して精子朗はブツクサ文句を言い続けている。この三連戦パワーを押さえ目にして戦っていくつもりでいたのでここでフルパワーを出すことは予定外であった。しかし、そうしなければゴッド・ハンドからの脱出はできなかったし、あのまま握りつぶされていた可能性が高い。
「ここまで手間をかけさせたんだ。ご褒美をくれてやるぜ!」
精子朗がそう叫ぶのと同時にシュテンカイザーの各部から噴出していた炎が両腕に集約されてゆく。その噴出す炎の量に合わせるようにシュテンカイザーのパワーも増してゆく。レストンはゴッド・ハンドを握り締めて必死になって抵抗するがまるで歯が立たない。易々と指を握りつぶされ、引き千切られてゆく。
「これがシュテンカイザー・パワーフォームだ!!」
ゴッド・ハンドの全ての指を引き千切り、握りつぶすと、シュテンカイザーは大きく跳び退り、ガ・リュードから距離を置く。そして今度は両腕の炎が両脚へと移ってゆく。ゴッド・ハンドを捨て新たに取り出した鉄球でシュテンカイザーを狙い撃ちしようとしたレストンだったが、シュテンカイザーのその動きは先ほどを遥かに上回っていた。
「これがシュテンカイザー・スピードフォーム!!」
そのスピードでレストンを翻弄したシュテンカイザーは土煙を撒き散らしながらその動きを止める。そして今度はその炎を胴体に集約させてゆく。動きが止まったその瞬間を逃すような真似をレストンがするはずがなかった。ここぞとばかりに鉄球を振いシュテンカイザーを攻撃する。唸る鉄球は確実にシュテンカイザーを捕らえ、破砕するはずだった。しかし、次にレストンが見た光景は驚愕するものであった。シュテンカイザーのボディに激突した鉄球はその勢いをなくし、地面に落ちる。そしてシュテンカイザーのボディには傷一つつけることはできていなかった。
「これがシュテンカイザー・アーマーフォーム!!」
「なんなんだ、これは・・・夢でも見ているのか・・・」
「原理は簡単だよ。シュテンカイザーの溢れ出るエネルギーを各部に集約させて力を増強させているのさ!」
驚くレストンに精子朗は簡潔にその力の秘密を教えてやる。原理は簡単だし、理解できる。しかし、恐ろしいのはそれを平然とやってのけるその度胸である。一歩間違えば自分の機体がばらばらになるかもしれないようなことである。それを平然とやってのけるということは、それだけ精子朗がシュテンカイザーを信頼していることに違いなかった。
「まあ、フルパワーを出させただけでもよくやったよ。じゃあ、終わりにしようか!!」
精子朗はそう言うが早いか、全パワーを両腕に集約させてガ・リュードの襲い掛かる。ガ・リュードの両腕を掴むと、そのままおもむろに引き千切る。いやな音を立ててガ・リュードの両腕が引き千切られ、もぎ取られてしまう。さらに逃げようとするガ・リュードの両脚も同じように引き千切り、粉砕する。そして逃げ場を失ったガ・リュードをさらに引き千切り、解体してゆく。やがてガ・リュードはコックピットを除いてばらばらに引き千切られてしまう。ガ・リュードのコックピットを握り締めるシュテンカイザーの足元でガ・リュードは大爆発を起こす。
『この勝負、豪拳寺精子朗、シュテンカイザーの勝利です!!』
アルの勝利宣言が響き渡る中、シュテンカイザーは勝利の咆哮をあげる。足元かっら巻き起こる爆炎と、関節部から噴出す炎とが交じり合い、辺りを赤々と灯す。そのシュテンカイザーの雄姿をハーフとスイカーンはじっと見つめている。終わってみれば今回も圧勝であったが、スイカーンとハーフにとっては有意義な戦いであった。
「なんともはや、なんと言うパワー・・・」
「まさかレストンが力負けするなんて・・・しかもあの絶対的不利な状況から・・・」
「下手に殴りあいになったらこちらに勝ち目はありませんね・・・」
「そうね。まずはあのパワー、いやあの動きを封じる方が得策」
そこまで言うとスイカーンはにやりと笑う。そう言う戦い方に自分は慣れているからだ。そのための戦場もすでに用意済みである。自分が得意とする戦場ならばシュテンカイザーの力を削ぐ事もできるはずである。つまり自分に完全に有利な状況で戦うことが可能なのだ。それを思うと笑いが止まらない。
(これは困ったな・・・)
そんなスイカーンを横目にハーフは内心舌打ちをする。このままではスイカーンにシュテンカイザーという獲物とシルヴァ姫という獲物、両方を持っていかれることになる。だが、今更戦う順番を代われとは言えず、憮然とした表情のままスイカーンが負けるのを祈るのみだった。
「次はこのスイカーンが決闘機、マーメイデン”と戦ってもらうわよ!!」
スイカーンは堂々と名乗りを上げると自分の決闘場へとシュテンカイザーを導く。そこは広大な水場であった。どれほどの深さの水場かはわからない。少なくとも1000メートルは下らないだろう。つまり次の戦いは水中戦ということになる。初めての戦いではあるが、どんな奴の挑戦も受けるとばかりに精子朗は水中へと飛び込む。
「ふふっ、水中戦こそ、僕の真骨頂。存分に楽しませてあげるわ!」
自分の闘いの場にシュテンカイザーが入ったのを見届けるとスイカーンは嬉しそうな顔で自分も水の中に飛び込んでゆく。そして腰のスクリューを全開にしてシュテンカイザー目掛けて一気に突っ込んでゆく。なれない水中戦に精子朗はしばし機体のコントロールに気を取られていた。その隙に迫ってきたスイカーンを回避することはできるはずもなかった。
「それ、それ!どう、どう??」
手にした三叉矛でシュテンカイザーを攻撃しながらスイカーンは何度も何度も嬉しそうに尋ねてくる。動きの鈍いシュテンカイザーはその三叉矛をその身に何度も受ける。だが、強硬な装甲はそれを受け止め、弾き返す。ならばと距離を置いたスイカーンは背中から魚雷を発射してくる。
「うし!水中戦のやり方、大体わかったぜ!!」
迫る魚雷を無視して精子朗はニッと笑う。そして操縦桿を押し込んだ瞬間、魚雷が着弾し、大爆発を起こす。あれだけの魚雷を食らえばかなりのダメージを与えたと確信していたスイカーンは間髪入れずに三叉矛を構えて飛び込んでゆく。魚雷によって装甲の破損した箇所に攻撃を加えるつもりでいた。
「おほほほ!水中で僕に勝てる・・・なに???」
笑みを浮べて特攻したスイカーンの表情が凍りつく。爆煙の向こう側にはシュテンカイザーの姿はなかった。先ほどの魚雷で討ち取ったのかとも思ったが、残骸がまるでないところを見ると大破したどころかダメージすら負っていないかもしれない。つまりはあの魚雷を回避したに違いなかった。
「あの魚雷を全て回避した???」
「その通りだよ!!!」
愕然とするスイカーンの真下からその声が聞こえてくる。そちらに視線を落としたスイカーンは急上昇してくるシュテンカイザーの姿を見止める。慌てて回避するマーメイデンの動きにシュテンカイザーは的確について行った。完全に水中での戦いに適応している動きであった。その精子朗の適応力の高さにハーフは思わず身震いする。
(まだ戦い始めて数分だぞ??なのにあの戦い方、こんな・・・こんな男がいるのか・・・)
シュテンカイザーの動きを見ればそれがまぐれでないことは間違いない。これまでシュテンカイザーが勝ち残ってきたのはその機体の性能ばかりによるものではない。精子朗という類まれな能力を有した戦士が存在していたからこそ、シュテンカイザーはその性能の限界まで発揮して戦うことができたに違いない。そしてそれはハーフにとって屈辱的なことでもあった。もしこのまままともに戦えば自分が負けるというのがいやでも察しが着いたからである。それほどまでに精子朗とシュテンカイザーの力は群を抜いていた。
(だが、まだ私にも奴を、シュテンカイザーを倒す手段は残されている・・・そう、あの致命的な弱点がある限り)
マーメイデンに追いつき、二発、三発と攻撃を加えてゆくシュテンカイザーの姿を見つめながらハーフはまだ自分にも正気が残されていることを思い出し、大きく息を吐く。これまでの情報、こに二戦の戦い、これらから得られた情報はハーフにとって大きな意義を持っていた。少なくともあの方が納得してくれる情報であろう。次の戦いまでそう時間は掛かるまいと踏んだハーフが準備に掛かろうとしたとき、スイカーンが新たな動きを見せる。
(何をする気だ?水中戦でも奴は倒せない・・・!そうか、奴の母星は・・・)
ハーフはスイカーンの母星のことを思い出し、まだマーメイデンにも抵抗する手段が残されていることを思い出し、戦いの行方を見つめる。そのハーフが見つめる中、スイカーンは新たな魚雷をシュテンカイザー目掛けて発射して来る。もはや水中戦になれた精子朗にそれを回避することはどうということのないことであった。
「こんな攻撃が何の意味があるんだ??」
「すぐに分かるわよ、そう、すぐにね・・・・」
不敵な笑みを浮べるスイカーンを他所に回避された魚雷はお互いにぶつかり合い、大爆発を起こす。しかしスイカーンはそれでも魚雷を何発もシュテンカイザー目掛けて撃ってくる。対して精子朗は冷静にシュテンカイザーを操り、その全てを回避する。精子朗はそのスイカーンの無駄な攻撃に首を傾げる。いくら魚雷を撃っても無駄なことはスイカーンにもわかっているはずである。それなのに何発も無駄弾を撃つ意味がわからなかった。何か企んでいるのかとも思い、爆発のあったほうに視線を移す。
「??なんだ・・・この水場・・・何かヘンだぞ??」
そこで精子朗はようやくその異常に気付く。爆発のあった箇所から緑色の粉のようなものが水に溶けてゆくのが確認できた。その粉はどんどん水に溶けて交じり合ってゆく。やがて緑色になった水がシュテンカイザーの機体を取り巻いてゆく。その水はシュテンカイザーの体に纏わり付き、その動きを鈍くする。機体の表面をゼリーのような、ゲル状の何かが覆いつくし、その動きを疎外しているのである。
「くそ!!でもこんな水じゃ相手だって・・・」
「この水は僕の故郷のゲル状の水なのよ。僕らはこの水の中で生まれ育ったの!」
スイカーンはそう叫びながらマーメイデンで悠然と泳いでいる。その姿は先ほどまでの人型から、下半身が魚の半漁人型に変形していた。スイカーンはその下半身を器用に動かしてそのゲル状の水の中を動き回り、身動きの取れないシュテンカイザーの死角から三叉矛を繰り出してくる。ゲル状の水によって勢いが削がれているとはいえ、少しずつ装甲を削り、内部にダメージを与えてゆく。それを防ごうにも動くことの出来ないシュテンカイザーは徐々に徐々にダメージを増してゆく。その様子をハーフは鼻を鳴らして見学していた。
「ふん。相手の動きを封じての攻撃か。なかなかいい趣味をしているな・・・」
半分バカにした口調でそんなことを言いながらこの試合がこのまま終わるのではないかと不安に感じていた。シュテンカイザーのフルパワーを象徴でもある炎が各関節部から噴出していない。これはシュテンカイザーのパワーがゲル状の水によって押さえ込まれていることを意味していた。その特異な形態でゲル状の水を己が物とし、相手の動きを封じて戦うスイカーンの巧妙さにハーフは唸ることしかできなかった。このまま行けばこのあと自分がこいつと一騎打ちをすることになる訳だが、どうやって自分の有利な状況に持ち込むかを考え込んでいると、戦いに変化が生まれる。
「いい加減に、しやがれ!!!」
まともに動くことも出来ない状態でいい様に三叉矛で攻撃されていた精子朗だったが、そのあまりにせこい戦い方に思わず絶叫する。その怒りに呼応するようにシュテンカイザーが大きく咆哮する。同時に各関節部から先ほどまでをさらに上回る真紅の炎が噴出し、ゲル状の水を蒸発させてゆく。
「うざったいんだよ!こんなセコセコした戦い方しやがって!!」
精子朗の怒りに呼応して関節部から噴出す炎の勢いが増してゆく。シュテンカイザーを取り巻くゲル状の水は完全に蒸発し、体の自由を取り戻す。それでも収まらない怒りはさらに炎の勢いを増し、ゲル状の水をさらに蒸発させてゆく。このあまりに非常識な戦い方にスイカーンは驚きとともに悲鳴を上げる。
「な、なんて戦い方をするのよ、あんたは!!??」
「うるせぇ!!ねちねちした戦い方する奴がなに言いやがる!もう頭にきた!来い、斬漢刀”暁”!!!」
精子朗の呼びかけに答えるように空間を越えて巨大な何かがシュテンカイザーの手の中に現れる。それは刀であった。それもシュテンカイザーの1.5倍ほどもある巨大な。シュテンカイザーはその大太刀を軽々と振り回すと、肩に担ぐような格好をする。そして手の平のカバーが開き、その大太刀と直結する。するとシュテンカイザーの各関節から溢れ出す炎がその大太刀の集約され、炎を纏った大太刀に変化する。
「これがシュテンカイザーの武器、斬漢刀”暁”!!!!」
精子朗はそう叫び大見得を切って見せる。炎の大太刀は赤々と燃え上がり、いかなるものも切り裂かんばかりの雄々しき姿をしていた。そのシュテンカイザーの雄姿をいつものごとくポッドの中から見ていたシルヴァは首を傾げる。
「斬『艦』刀???『艦』の字が違う発音に聞こえたのじゃが・・・」
『ええ、違いますよ〜。斬『艦』刀ではなく斬『漢』刀です。『漢(おとこ)』が切り裂く刀です』
『またヘンな武器を・・・』
首を傾げるシルヴァにアルが答える。精子朗の機体に関する登録は全てアルの元に集められていたのでこの大太刀に関する情報はすでにアルは知っていた。それを聞いた倫は思わず頭を抱えてしまう。まったくもってしてとんでもないネーミングである。聞いていると力強さよりも、暑苦しさを感じてしまう。
「『漢(おとこ)』に切れぬモノなし!!!!」
精子朗はその絶叫とともに斬漢刀を振り下ろす。紅蓮の炎を纏った大太刀が煌めき、一拍置いてゲル状の水が真っ二つに裂け、じゅうじゅうと煙を上げて蒸発する。周囲のゲル状の水が蒸発する中、スイカーンは恐慌をきたした表情を浮べてこの非常識な状況に悲鳴を上げていた。
「何むちゃくちゃなことしてるのよ、この原始人は!!??」
「うるせぇ、このオカマ!!」
周囲のゲル状の水がなくなり、自由に動けるようになった精子朗はゲル状の水という壁のなくなったマーメイデンを睨みつける。精子朗の怒りに呼応した紅蓮の炎はさらにその勢いを増し、燃え盛る。一方のスイカーンのほうは三叉矛を構えて護りに入る。ゲル状の水はしばらくすれば元通りになるはずである。それまでシュテンカイザーの攻撃を捌ききらなければならない。しかし、思い通りにならないのが世の中である。
「斬漢刀、一刀両断!!!」
精子朗の叫び声とともに斬漢刀が縦一文字に振り下ろされる。斬漢刀を受け止めようとしたマーメイデンの三叉矛はいとも簡単に真っ二つにされてしまう。そして遮るもののなくなった斬漢刀はそのままマーメイデンを通り過ぎ、地面に叩きつけられる。その破壊力を象徴するかのように大地には大きな亀裂が走る。
「あ・・・ああああっ・・・」
よたよたと後退するマーメイデン。その頭から股間にかけてまっすぐに一筋の亀裂が走る。シュテンカイザーが大太刀を地面から引き抜き、マーメイデンに背中を向けて肩に担ぐのと同時に、マーメイデンの体に走った亀裂は完全にその体を分かち、一拍おいて大爆発を巻き起こす。
「次はお前の番だ!」
「いやはや、まさか貴方が勝つとはね・・・
精子朗はアルの勝利宣言を聞きながら、最後に残ったハーフを指差す。精子朗のその不適な挑発にハーフもまた不敵な笑みを浮べ、肩を竦ませて見せる。ハーフからしてみれば対抗策を練り直さなければならないスイカーンやレストンよりも、今までのデータと今日の戦いから弱点を看破できたシュテンカイザーの方が戦いやすかった。
「では今度は私、ハーフ=リップが決闘機”ラウンジ”がお相手しましょう!」
ハーフは名乗りを上げるとともに背中の翼を全開にして空中に舞い上がる。同時に重力がシュテンカイザーの体を大地に縛り付ける。地球より少し強いくらいの重力ではあったが、空中を飛べないシュテンカイザーを大地に縛り付けるには十分すぎるほどの重力であった。
「これは・・・」
「そう、空を飛べないこと。それがお前の決定的弱点だ!!」
ハーフは高笑いとともに高速でラウンジを移動させながら、腰の剣を抜く。しかし、それは剣などではなく細長い剣の形をした銃であった。ハーフはそれの先端をシュテンカイザーに向けると、高速移動しながらランダムに発射する。狙いは定めていないので命中確率はあまりよくない。しかも長距離からの射撃なので、ビームの威力は極端に落ちている。
「??何じゃ、ハーフの奴は・・・あのような攻撃が何の意味があるのじゃ??」
『いやぁ、効果的な攻撃ですよ?セイシローさんは何の手出しもできませんから・・・』
ハーフの攻撃に不思議そうな顔をするシルヴァにアルは平然とした顔で説明する。威力が弱くてもビームはビーム。徐々にそのダメージは蓄積されてゆくはずである。そして空を飛べない精子朗には反劇の機会はまったくない。つまりハーフのビーム攻撃の的となることしか今のシュテンカイザーには為す術がないのだ。
「この・・・お前もせこい闘い方しかできないのかよ!!」
怒りに顔を歪ませた精子朗は両脚に全ての力を集中させると勢いよくジャンプする。そして空中から攻撃して来るラウンジに迫る。だが、シュテンカイザーの拳はラウンジに届くことはなく、途中で失速して地表へと落下してゆく。その光景をケラケラ笑いながらハーフはさらにビーム砲で攻撃を加えてゆく。
『ほら、ダメだったでしょう?シュテンカイザーは空を飛べませんから・・・』
「なんじゃと??どうにかせぬか、アル!!」
『う〜〜〜ん、こう見えても私立ち見届け人ですよ?片方に手心加えるわけには・・・』
「そんなこと言うておる場合ではないわ!早くせねばセイシローが・・・」
慌てるシルヴァにアルは全然困った顔もしないでいて、口調だけは困ったようなことをいう。もちろんアルにどうにかできるわけがない。アルは見届け人であって決闘に手出しをできる立場にないのだ。もちろんそれはエルも同様であった。もし手を出したらその場で精子朗の負けは決定してしまう。
『まあ、思ったよりあれがでるのが早かった、ってことですか・・・』
「む?何か言うたか、アル???」
『いいえ、なんにも!!』
戦いを見つめていたアルがボソリと呟く。その呟きをシルヴァは聞き逃さなかった。そのことをアルに問い詰めると、アルは空々しくそっぽを向くと、口笛を吹いてごまかしてくる。その態度は誰の目にも不自然に映った。この女、何かを知っている。明らかにそう思わせるような態度であった。
「言え、アル!!何を知っておる!!??」
『見ていればわかりますって、姫様!!』
あくまで問い詰めるシルヴァであったが、その追及にアルは不敵な笑みを浮べて戦いに注目するように促す。シルヴァが戦いに視線を戻すと、シュテンカイザーがなす術もなくラウンジの攻撃に晒される光景に変わりはなかった。やがてシュテンカイザーの各部で爆発が起こり始める。装甲が過負荷に耐え切れなくなったためだ。
「くぅぅっ・・・やっぱりパワーが強くても当てられなくちゃこうなるか・・・」
「くくくっ、どうです?諦めますか?」
「そうだね。シュテンカイザーではあんたに敵わないみたいだ」
勝ち誇るハーフに精子朗は平然とシュテンカイザーでは敵わないと言い放つ。ハーフは精子朗の言葉に攻撃をするのを止める。すると精子朗は何を思ったのか、コックピットを開き、外に出てくるのだった。その行動にハーフは精子朗が完全に降参したものと思い込み、シルヴァの元に近付いてゆく。
「おい、何人の姫様に手を出そうとしているんだ?」
「?貴様、先ほど降参を・・・」
「降参なんて一言も言ってないぜ?シュテンカイザーでは勝てないっていっただけだ!」
精子朗の言葉の意味がハーフにはわからなかった。それはシルヴァも同様であった。精子朗の決闘機はシュテンカイザー、それで勝てないのだから降参ととられても仕方がない。しかし、精子朗はまだ勝負はついていないと言っている。何がなんだかわからずにいると、精子朗はにやりと笑って見せる。
「訳がわからないみたいだな?こういうことだよ、来い!『蒼天の雷』”ソウテンカイザー”!!!」
精子朗の雄たけびに答えるように豪拳寺家が大きく揺れ始める。大型のモニターで戦いを観戦していた倫たちもその揺れの大きさに慌てて近くにあった物にしがみ付き、事なきを得る。やがて揺れは収まり、かわって大型のモニターの向こう側、決闘場に何かが姿を現す。
「なに・・・あれ・・・」
その抜けるような蒼い機体に目を奪われながら倫はそう漏らす。蒼い色のその機体はシュテンカイザーに近いフォルムをしていた。大きく違う点は巨大な翼を背負い、頭部の角が一本である点であった。その蒼い機体がシュテンカイザーのすぐ側に着陸すると、精子朗は迷うことなくその機体に乗り移り、そのコックピットの中に姿を消す。
「貴様、負けそうだからと、別の決闘機を・・・反則だ、反則負けだ!!」
「反則負け?何がだ?俺はルールに反することはしていないぞ?」
「なにをいうか!2体目の決闘機を持ち出してきておいて!おい、見届け人、この勝負は・・・」
『残念ですが、セイシローさんは違反行為はしていませんよ?』
その蒼い機体の登場にハーフは怒り狂い、精子朗の反則負けをわめき散らす。ルール上、与えられたブロックから作り出された決闘機以外のメカで決闘を行うことは反則とみなされる。この場合、その蒼い機体の登場はこれに当たるはずである。この様子を見ていたシルヴァもまた、そう思っていた。しかし、当の精子朗の方は平然としている。まるで反則などしていないといわんばかりに悠然としていた。そんな精子朗の態度にハーフはさらに頭に血を上らせてアルに精子朗の反則負けを取るように要求してくる。しかし、アルもまた精子朗は反則ではないと言い放つ。その言葉にハーフはさらに激昂する。
「貴様、この男と親しいからと言ってそのような戯言を!!」
『ではハーフ殿、ここ決闘における決闘機とはどのようなものですか?』
「何を今更・・・”IEM”のよって50個のパーツから作られた・・・」
そこまで言ってハーフはアルが言わんとしている事を漠然と理解する。いや、理解などしたくなかった。そんな非常識な話、あるはずがないのだから。しかし、今までの会話のことを考えれば、どうしてもその結論に帰結してしまう。まさかそんなことを想像するものが、それを可能にする機体を生み出せる人間がいるとは信じられなかった。
「まさか・・・シュテンカイザーとは・・・」
『その通り!IEMによって20個のパーツを使って生み出された決闘機』
「そしてこのソウテンカイザーが残り20個のパーツから生み出した決闘機だ!」
精子朗は蒼い決闘機に飛び移るとその決闘機を紹介する。そしてそのコックピットに飛び乗ると、ソウテンカイザーを起動させる。両目に光が灯り、各関節が軋みをあげながら動き始める。コックピット内のエネルギーゲージはどんどん上昇し、背中の翼が大きく広がり、ラウンジ目指して飛び上がる。迫り来るソウテンカイザーから距離を取ろうとラウンジは高速で動き始めるが、ソウテンカイザーはそれを上回るスピードでラウンジを追いかけてくる。ラウンジとの距離を詰めたソウテンカイザーは両手の甲から鋭い爪を出し、襲い掛かる。
「喰らえ、ソウテン・クロウ!!」
鋭い爪が大気を引き裂きラウンジに迫る。一撃目は何とか回避したハーフであったが、二発目、三発目とどんどん高速で繰り出されてくる爪を回避しきることはできず、次々に装甲に傷をつけられてゆく。徐々に切り刻んでゆくのが目的かとハーフは考えたが、精子朗の真意はそこにはなかった。爪で切り裂き、内部構造を露わにしてゆくことにあった。
「これくらいでいいか・・・いくぜ!ソウテン・タイフーン!!」
精子朗の掛け声とともにソウテンカイザーの両肩から突風がラウンジ目掛けて放たれる。雷を帯びた竜巻はラウンジを包み込み、露わになった内部構造に雷撃を見まい、放電させる。雷によって内部を徐々に破壊されたラウンジは本来のパワーを出すことができず、竜巻からの脱出ができなくなってしまう。その動きを封じられ、動けないラウンジの正面に立ったソウテンカイザーはその爪を引っ込める。
「いくぜ、これがソウテンカイザー、最強の武器!来い、ソウテン・ドリル!!」
精子朗の掛け声に合わせて巨大なドリルがソウテンカイザーの前に姿を現す。そのドリルを両手で受け止め、胸元に引き寄せると巨大なドリルが回転を始める。唸りを上げて回転するドリル、爆炎を上げる背中のバーニア。そして各関節部で巻き起こる放電。それは今ソウテンカイザーがフルパワーを出していることを意味していた。ソウテンカイザーが何を狙っているのかハーフにもすぐに理解できた。
「よ、よせ!!!」
「くらえ、ライトニング・バースト!!!!」
轟音を上げてソウテンカイザーがラウンジ目掛けて特攻する。唸りを上げるドリルがラウンジの装甲を砕き、破砕する。一筋の矢となって駆け抜けたソウテンカイザーがソウテン・ドリルを外して肩に担ぐのと同時に、その背後で大爆発が起こる。その爆炎を背に受けながらソウテンカイザーはドリルを高々と掲げる。
『この勝負、ソウテンカイザーの勝利です!!!』
アルの勝利宣言が高らかに響き渡る。今度も勝利した精子朗の雄姿を見つめながらシルヴァはほっと胸をなでおろす。残すところはあと1人、この間見た記録で残っているのは宰相の息子ファッタンだけである。ファッタンの事は昔からよく知っているがまともに戦闘など出来るような男ではない。正直今回の婚約の儀に出場したこと自体奇跡である。その彼が未だに、最後まで生き残っていたことがシルヴァには不思議でならなかった。
「まあ、あやつならばセイシローも楽勝じゃろうて!」
あと一笑すれば自分の婚約者は精子朗に確定する。それはたとえ父王であっても違えることはできない。その瞬間が近付いてきていることを思うと、自然と笑みがこぼれてしまう。不気味な笑みを浮べてにまにまと笑うシルヴァの元にエルから通信が入る。何事かと思いつつ、通信を受けたシルヴァの元に驚くべき情報がもたらされる。
ザムザイール皇星連邦の主星サザンで大規模な戦闘が起こったとの報告を最後に通信が途絶した、と・・・
→進む
→戻る
→絶倫鬼神シュテンカイザーのトップへ
|
![]()
![]()