|
【蹂躙のファリオン村】
魔女とせせらぎの月19日 21:15 ファリオン村
既に日は落ち、雲一つなかった青空は、雲一つない星空へとその装いを変えていた。
昼間鳴いていた鳥たちに代わって、あちこちの草むらから聞こえてくるのは静かな虫たちの声。
針葉樹林の一本道を越えてきた一行の視界に映るのは、魔法で不思議な形に変形し、実の代わりに小屋のぶら下げた大木の数々。
自然と一体となったエルフたちの集落、ファリオン村だった。
「ダノン姉、ここがファリオン村?」
「そうよ。さあシア様も、ここで一休みできますからね」
「はぁはぁ・・う、うん・・」
しかし、そこでミュラローアが不意に怪訝な顔をする。
「ねえ、ダノン?いくら夜だからって、こうもあちこち家の明かりが消えているものなのかしら・・?」
ミュラローアの言う通り、沢山あるエルフ小屋の中には、どこ1つ見ても灯りが灯ってはいない。
何もかもが寝静まったように静まり返っている。
しかし、ダノンはそれをさらりと受け流す。
「ミュー、空を見て御覧なさい、今日は満月が見えるでしょ?エルフたちは完全な満月の晩にマオフェプリト(月光祭)と呼ばれる祭りを執り行うの。ほら、向こうの大木の奥に隠れているけど、焚き火の明かり、見えるでしょ?」
「ああ・・なるほど、そういう事なの」
「ただし。祭りといっても、彼らにとっては重要な儀式だから、絶対に邪魔になるような事をしちゃだめよ。私たちは彼らに会って、挨拶をして、助けを求める交渉をするだけ・・決して許可なく祭りの輪の中に入ってはダメ。ソネッタも、それとシア様もお願いしますよ」
ミュラローアとソネッタは、ダノンの神妙な口調に思わず息を飲むが、すぐにうなづいて応える。
とにかく、今はシアフェルを治す薬と馬を手に入れる事が最優先だ。
3人の侍女たちは、意識も朦朧とした姫君を支えつつ、焚き火の灯りの方へと足を速めた。
しかし・・
「ギャッハハハ!いいぜいいぜ、こいつのケツ!オレ様のマ〜ラにぴったり吸い付いてきやがる!」
「ヒヒヒ!やっぱりエルフと人間じゃ味も違うもんだな・・オラ!もっと自分から腰振るんだよ!お前らの細い腰は、男を喜ばせるためにあるんじゃねぇのかァ!?」
「オイ!そっちの青髪ちゃん、早く回せよ!てめぇら、もうそいつばっか4発目じゃねぇか!」
「バカ言うな、こいつはお持ち帰りでオレたちの専用便所にするんだからよ!ま、ガキの1匹でもこさえて、ガバガバになったあとでよけりゃ譲ってやるけどな♪」
焚き火から幾らか距離のある大木の陰、一行は皆表情を凍りつかせていた。
そこにあるのは神秘的なマオフェプリトの光景ではなく、むわっとした酒臭さと、品性のかけらもない笑い声と、弱者蹂躙の光景に他ならなかった。
焚き火の周りでは、キルヒハイムの紋章入りの鎧を半脱ぎにした50人近い兵士たちが、拘束された12、3人ほどのエルフの娘たちを、それぞれ取り囲むようにして犯していたのだ。
ファリオンの森に落ちた夜の闇。
それを照らす焚き火の灯りが作り出す牡と牝の淫らな影絵が、あちらこちらで蠢いていた。
「オラオラッ!アッツイのがぁ、出るぜ出るぜ出るぜェ〜っっ!!行くぞ・・気持ちよぉ〜く・受け取れェェ〜〜ッッ!!」
「ぐっ・・うぅぅぅむ・・っ!」
「・・クハァ〜ッ、た〜っぷり出たぜェ!今のは、改心の1発だったァ♪」
「コラ、お前のザーメンの量なんてどうでもいいから、終わったらとっとと変わらんか!後がつかえてるんだぞっ!!」
悪鬼の如き兵士たちは、それぞれ彼女たちの細やかな肢体を力任せに嬲り回しては、その凝縮された悪意の塊の射出を楽しみ・陶酔し、一方、エルフの娘たちはそのプライドの高さからか、もしくは既に精根尽き果てているのか、まるで人形のようにぐったりとして、ほとんどされるがままになっている。
そしてよく見れば、その周りには無残に変わり果てたエルフの男たちの肉片が散乱していた。
「・・なんて酷いっ!」
「ゲルニスはこんな横暴をしたいがためだけに・・国を?・・許せない・・!!」
思わず両手で口元を押さえるソネッタの言葉に、ミュラローアが同調する。
今まで長きに渡って続いてきたファリオンとキルヒハイムの友好関係も、ゲルニスは積み木の城を倒すかのようにあっけなく破壊してしまったのだ。
2人の体を形容しがたい怒りが震わせていた。
「可愛そうだけど・・私たちではどうしようもないわ。とにかく今は、薬と馬、あと食料を探しましょう」
しかし、そこでダノンの一言が2人に水をかける。
冷酷な内容ではあったが、今の彼女らには、まさにそれこそが正論なのだ。
しばらくして、力なく振り向いたミュラローアとソネッタだったが、ダノンに肩を抱えられた主の姿を見るや気を入れ直し、小屋の方へと忍び足を走らせた。
▽ ▽ ▽ ▽ ▽
あれから15分ほどが経っていた。
一行は、ダノンが薬、ソネッタが馬、ミュラローアがシアフェルと共に食料の調達と、それぞれ手分けをして事に当たっていた。
ソネッタは焚き火の広場を迂回しつつ村の外周を駆け回り、後の2人は城の逃亡時に持ち出したランタンの明かりを最小限に抑えつつ、暗い小屋を周ってはその中を物色しているるのだ。
「ミュー、薬は見つかったわよ。そっちはどう?」
ミュラローアたちのいる一際大きな小屋に、ダノンが吉報を持ち帰る。
しかし、ランタンの灯りに照らされたミュラローアの顔には困惑の色が浮かんでいた。
「そ・・それが、あるにはあったのだけれど・・」
シアフェルとミュラローアの周りあちこちに散乱しているのは、様々な色形をした無数の木の実や乾燥した草々、運良くここはそういったものを貯蔵する倉庫だったのだ。
しかし、恐らく食料はこのうちの一部のみ。
エルフたちが薬草作りや狩りの名人である事は有名だ。
となれば、ここには食料だけでなく、塗り薬の材料や、下手をすると毒を持った植物さえも保存されている可能性がある。
一箇所にまとめて貯蔵しておいても、エルフたちが間違える事はまずないのだろうが、この状況でそれはまさに最悪の光景だった。
「・・ダノン、どれを持っていけばいいのか、わからない・・?」
「・・ッ」
弾かれたようにその場に駆け込み、無数の草や木の実を1つ1つ手にとってみるダノン。
暗闇の中でもはっきりわかるほど、その手は震え、吐息は荒れている。
時間をかけども、ない知識に答えを求めるのも無駄な事。
結局、彼女もミュラローアの二の足を踏むだけに止まってしまう。
マオフェプリトの広場では、今も牡が牝を貪る狂乱の祭が続いている。
吼えんばかりの邪悪な嘲笑が、絶え間なく響き渡っている。
だが、か弱い女ばかりの一行にとって、好機はその間だけなのだ。
時は一刻を争う。
無駄にできる時間など全くなかった。
「・・馬、見つけたよ!」
そこに、最も長い距離を駆け回ったにも関わらず、ほとんど息を乱していないソネッタが戻ってくる。
動揺に取り付かれた眼差しが一斉に彼女を見やった。
「ど・・どうしたの?」
「まずい事になったのよ・・」
「ねえ、ソネッタ。貴方は、この中でどれが食べられるものだかわからない・・?」
「よし、見せてっ!」
ダノンとミュラローアは年下の同僚の手馴れた采配に、しばし言葉を失っていた。
まさに、思わぬところに救いの女神。
ジプシー育ちの体力が自慢のソネッタは、また、こういった知識にも長けていたのだ。
「これでオッケー!さあ、行こう。シア様、ダノン姉、ミュー姉!」
一行が荷物袋に必要なだけのものを詰め込むまでにかかった時間、ものの10分。
動きの鈍い1人を抱えつつも、4つの人影は貯蔵庫を足早に離れていく。
ランタンを消し、月光だけを頼りにくねった大木たちの間を抜け、マオフェプリトの広場を迂回し、2分ほど行ったところに小さな馬小屋らしき建物が見えてくる。
だが・・
「管理小屋に灯りがついてる・・!」
「そうなの、ダノン姉。でも・・それでも、馬を手に入れるならここしかないよ・・」
駆け込んだ大木の陰に身を潜め、声を殺してソネッタが続ける。
「馬はね・・恐らく兵士たちのものだと思うけど・・広場の近く、向ってここから反対側にも沢山いるの・・でも、そっちは見張りも沢山いて、とても近づけない。でもここは、見た所だと見張りは2人しかいなかった・・し」
「・・し?」
妙なところで言葉を切るソネッタに、ダノンとミュラローアが怪訝そうな顔を向ける。
顔を伏せがちだったソネッタは、そこで何かを噛み殺すと、潜めていた腰を上げて駆け出していた。
「・・とにかく、今のあたしたちには好都合な状況なの!」
「ちょっと!待ちなさい、ソネッタ・・!」
「シア様、ミューと一緒にお馬のところまで走れますね?」
「・・う、うん・・ミュー、シアの事、置いていかないでね・・」
「何をおっしゃいます・・我ら『R.I.D』は、いついかなる時でもシア様の御味方ですよ・・さあ、行きましょう!」
何か確信めいたものを匂わせるソネッタに、まずダノンがつられ、ミュラローアとシアフェルもそこに続く。
馬小屋は、さすがのエルフたちも木の上からぶら下げるわけにもいかないらしく、人間の町で見かけるのと同じようななりをしている。
掘っ立て小屋の馬房に草が敷き詰められて、そこに馬たちが、また外と馬房内部の扉から繋がる小さな管理小屋には、見張り番の兵士たちがそれぞれ陣取っている。
管理小屋の方に気付かれないよう注意しつつ、馬房に駆け込んだ4人は、その内部が思った以上に狭い事、そして先ほど謎めかせたソネッタの言葉の意味に気付く。
「ハッハッハ・・オラオラァ!どうだぁ、森のメスザルめ!そんなにいいか?そんなにたくましいかぁ?人間様のチ○ポコはよぉ!!」
「うぐぁ、ぐんぅっ・・んん〜〜っ!!」
「つっ・・!イッてェなァ!歯ァを立てんなっつってんだろォ〜!?歯ァ全部、引っこ抜かれてェのかァ!?」
「あぐ・・いや、やめて、ごめんなさいぃ・・」
「ハッハハ!まあまあ、どうせ動物のやることだ。許してやぁれよ、ベイジ!それに・・それだけ、オレ様のチ○ポコが気持ちいいって証拠なんだからな♪」
「う・・うっす」
「ハハハァ!人間様に慈悲までかけられて、お前は幸せなメスザルなんだぞぉ?ま、せいぜいそのちっちぇ〜ケツを一生懸命振ってぇ、オレたち人間様にズッコンバッコン気持ちよく恩返ししてくれよなァ!ハッハハハァッ!」
「・・うぅぅ・・」
馬房内の一角に光を落とす、壊れて閉じきらない扉の奥から響くのは、そんな乱痴気騒ぎの声と古くなった小屋の床が軋む音。
そして、漂ってくるのは酷い生臭さと酒臭さだ。
管理小屋の中では、まだ年端もいかない、外見的にはシアフェルより幼く見えるくらいのエルフの娘が、兵士たち2人に蹂躙されていた。
その幼い少女は、長寿のエルフたち独特の『達観』を、未だ身に着けていないのだろう。
マオフェプリトの広場にいた娘たちとは違い、その表情に恐怖を露にして、必死に兵士たちに許しを請っている。

「・・関係のない貴方たちまで巻き込んでしまって、本当にごめんなさい・・!」
思わず、頭を抱え込んで顔を俯かせるミュラローアだったが、そこにダノンが間髪入れず活を入れる。
「なにやってるの。さあ、行くわよミュー」
「う、うん・・」
馬は表からちらりと見えた1頭の他に、もう1頭しかいなかった。
だが、どちらも美しい純白のタテガミを持つ、見るからに駿馬だ。
それに中途半端な頭数いるよりは、飛び出す際に馬たちがパニックに陥りにくいという点で好都合だった。
「2頭いれば、用は足りるよね」
「ええ、大丈夫・・では、まずミューは私と」
「・・わかったわ」
「で、ソネッタは馬の扱いが上手いから、シア様と一緒に乗って」
「うん、任せて」
美貌の侍女隊『R.I.D』の結束が、場の判断を速やかに促していく。
一方、管理小屋の兵士たちの方は、酒とみずみずしい少女の肉体が最高のカモフラージュとなり、馬房内の侵入者になど全く気付いてもいない。
ミッションは完璧な段取りを踏んでいるかのように見えた。
だが・・
「はぁ・・はぁ・・シアね・・ミューと・一緒に・・お馬に乗りたい・・」
「なっ・何をおっしゃるんです、シア様。乗馬術はソネッタがもっとも優れているのです。ですから、シア様はソネッタと・・」
「・・お願いよ・・シアは、ミューと一緒がいいのぉ・・」
「シ・・シア様、ミューはダノンと一緒にすぐ近くにおりますから。どうか、ソネッタと一緒に・・」
「はぁ・・はぁ・・ミュー・・」
思わぬ落とし穴だった。
そんなに年齢の開きはないとはいえ、温室育ちのシアフェルには、叩き上げでここまで来た侍女たちのような割り切った判断力などない。
『どうしても欲しいものがあれば、駄々をこねればいい』
それがシアフェルの中での常識なのだ。
それに、病と慣れない旅路で不安も最高潮なのだろう。
ここまでも、彼女は1番のお気に入りであるミュラローアから、決して離れようとしていなかったのだ。
「ねぇ、お願いよダノン・・シア、ミューと一緒がいい・・」
「くっ・・」
「仕方ないわ、ダノン・・・・わかりました。では、シア様はミューと一緒に行きましょう。それでいいですね?」
「うん・・ミュー・・」
「じゃあ、これで決まり。早く行こう」
「・・待って・・!」
馬に乗ろうとしたソネッタを不意にダノンが引き下ろし、そのまま口元と腰を抱き込むように物馬の影に身を潜める。
一方、ミュラローアもシアフェルに対し、ちょうどダノンたちと同じような形となっていた。
「うぃ〜〜ック♪おぉ〜?そ〜こにいるのは、誰だぁ〜?」
突如、馬房の入り口奥の木陰から響くそんな声。
それはどうやら、管理小屋にいる2人ではない、酷く泥酔した3人目の兵士らしかった。
一気に悪化する状況に、息を殺して身を潜めるダノンたちは思わず息を飲む。
そこに刻まれる1秒1秒が、妙に重々しく感じられた。
「ダノン、気付かれたのかしら・・」
「シッ・・どうやら、違うみたいよ・・」
アイコンタクトを交え、蚊の鳴くような声で言葉を交わすミュラローアとダノンだったが、どうやら先程の声の主は彼女らに気付いてはいないようだった。
「おぉ〜?その威勢のいい声はぁ・ベイジちゃんとぉ・・ガルベン殿かなぁ〜?」
馬房の入り口越しに姿を現した人影は、どうやら管理小屋の方に興味を持ってくれたらしかった。
頭の悪い言葉を連ねる酔っ払い特有の素っ頓狂な大声は、時折大笑いのタイミングで足を止めつつも、ふらふらとこの建物へと近づいてくる。
「ガルベンさ〜ん、あの声は〜・・ドトールさんっスかね?」
「らしいな。おぉう、外にいんのはドトールかぁ!?」
「イエ〜〜ッス!そうよ、そうよぉ〜、ドトールちゃんですよぉ〜♪」
「ドトールゥ!・・こっちにも、可愛いメスザルちゃんがいるからよぉ・・一緒にエンジョイしよおや!おら、入って来いよぉ!」
少女とのセックスに夢中になっている管理小屋の兵士たち2人は、外に迎えに出ようとはしない。
こちらもまた、先方に負けないような大声で外の兵士を管理小屋へと誘っている。
「いい、皆?あの兵士が管理小屋に入ったら、少し待ってから出るわよ・・」
そう示し合わせる馬房内の4人。
だが、ドトールと呼ばれた3人目の兵士は、ダノンたちの思いもよらない行動に出てしまう。
「ふぃ〜・・よっこらせっと・・」
「・・なっ・・!?」
ダノンたちの顔から、一気に血の気が引く。
なんと、ドトールは管理小屋には入らずに、場房の入り口に腰を下ろしてしまったのだ。
そして、そこで腰の水筒の酒をのんきに呷っている。
「オイオイ、ドトールゥ!・・なんだぁ、ヤらねぇのかよぉ〜?」
「うい〜〜ック♪ヤリましたよ、ヤリましたよォ・・向こうの大〜っきな木の下でぇ〜、綺麗ぇ〜な姉ちゃんたちと、ズッコズッコ・ドッピュ・あぁんっ☆・・ってな感じによ?たぁ〜っぷり、楽しんでぇきましたヨォ〜〜っだ♪」
「なんスかァ…ドトールさ〜ん。一緒に楽しみましょうッスよぉ〜?」
「いい〜の、いい〜の!オレはぁ、君たちが幸せならそれでぇ〜ック、いいんだからよぉ〜・・オ〜イ、じゃ、オレはここで寝るぞォ〜!!」
「仕方ねぇ、ドトールの奴はほっとくするかぁ・・オレたちはオレたちで、たぁっぷり楽しもうぜぇ!」
「うぅっす!」
状況的には蛇に睨まれた蛙に近かった。
3人の侍女は暗闇の中、困惑した顔を見合わせる。
「・・どうする?」
「とにかく、少し待つしかないと思う・・」
「そうね。それに、あの手合いは一度寝てしまえば簡単には起きないわ。それを待ちましょう・・」
「でも、ダノン姉・・もし、寝なかったら?」
「その時は・・ナイフで首元をバッサリやってやるわ。上手くすれば、声も出せずに死んでくれるはず・・」
今はとにかく、息を殺して好機がくるのを待つしかない。
ダノンは持ち慣れない大型の戦闘用ナイフを握り締めると、一同を静める。
すると、『待ち』に徹する決意を固めた彼女たちの耳に、管理小屋内の喧騒は一層騒がしく響き始めた。
「あぶ・・うぉぅ・・んむぁうっ・・」
「ハァハァ・・ほォ〜ら・・ま〜たメスザルちゃんにィ、美味し〜いエサの時間がやってきたぜェ・・オ、オラ飲めっ!人間様の慈悲だ、のっ飲めェェっっ!!・・くぅぅぅぅッッ♪」
「・・う、うぶぅっ・・うぇ・・ぶぁうっ・・」
「ッハァ〜!・・エ〜クスタシィィ〜〜♪」
「おうお〜う、山ほど出しやがったなぁベイジ・・おう!ほらメスザル!ちょぉ〜っと口ん中開けて見せてみなぁ?んん〜・・ウワッハハ・・あちこちドッロドロにへばりつてやがる・・きったねぇなぁ、オイ♪」
「・・かふっ・・けふっ」
管理小屋の中のそんなやり取りは、視界が通っていないはずの場房の中に、ありありとその惨状を伝え続ける。
侍女たちの背筋を怒り、寒気、恐怖、嫌悪感・・様々な負の感情が、統制の取れていない多足虫の群れのように、絶え間なくゾロゾロと這い登っていた。
だが、そんな耳を犯されるかのような感覚に、ミュラローアが耳を塞ごうとしたその時だった。
「・・にしても、こ〜いつらにはマ〜ジ同情するっスよォ・・ちょ〜っと親切心出してシアフェル姫様たちをかくまっちまったばっかりに、このザマっすからねェ・・」
不快極まりない喧騒の中、チラリと聞こえてきたのはそんな言葉だ。
『シアフェル姫様たちをかくまったばっかりに』
慣れて来た闇の中、意外なキーワードの登場に侍女たちは思わず顔を見合わせる。
「・・どういうことだと思う?」
「そうだよ、シア様はここにいるのに・・」
「しっ・・」
――ドン・・ギシギシ・・
侍女たちのすぐ横、管理小屋と馬房を隔てる木の薄壁が俄かに軋む。
突然の事に思わず体をビクつかせるソネッタの肩を、ダノンの手がすかさず押さえ、なだめた。
「・・若い方が、壁の向こうに寄りかかっただけだわ・・」
ダノンの言う通り、管理小屋の中ではベイジと呼ばれた若い兵士が壁に背をもたれかけて一休み。
その対角で、年配のガルベンという兵士がエルフの少女を壁に押し付け、その肉体を後ろから楽しんでいる。
少女の子宮口に巨根が突き当たるインパクトのタイミングに合わせ、天井から吊るされたランプがグラグラと揺れ続けていた。
「こぉら!おっ前もメスならメスらしくぅ、こうゆう時はぁ・・もっと、こうイロっぽく、ケツを突き出すんだよぉ・・おらっ!」
「・・ひ・・ひっく・・は、はいぃ・・」
「っふぅ・・おら、こっちのが、お前だって気持ちいいだろぉ〜?おらっおぅらっ♪」
「・はひっ・・ぐ・うふあぁっ・・」
「グビッグビッ・・プッハァ!・・と。あ、そうだ、ガルベンさ〜ん?」
「あぁん?」
「んんっん・・!!」
ベイジに呼ばれ、腰の抽送そのままに、首だけを振り向かせるガルベン。
その強靭な肉体が作り出す大きな影の下、少女は不意に小刻みに頭を横に振り乱すと、だらりと脱力する。
それは、今日何度目かの絶頂だった。
しかし、ベイジとの会話に気をやっているガルベンが、それに気付く事はない。
崩れ落ちそうになる少女の肉体を無造作に掴み、元の体勢に立て直させるだけ。
そして、その間もピストン運動は、何事もないかのように一定のリズムを刻み続けているのだった。
「そいやぁ〜、オレたちぁ、こ〜れからど〜なるんスかね?」
「あぁ?これからってなぁ、どうゆう事だぁ?」
「いやぁ・・姫様たちの追跡ぃ・・しなくていいんスか?だってほらぁ、ここを発ったのがぁ〜、たしか昨日の夜らしいじゃないすかぁ?」
「おう、そうだな・・っお?」
「だったらぁ、オレたちも、とっとと出立した方がいいんじゃ・・」
「・・ち・ちょ〜っと待ってろよぉ、ベイジ・・そろそろ、イキそうなんでな・・」
ガルベン太い首が再び前を向き直ると、嗚咽を漏らしていた少女は小さく『ひっ』と体をビクつかせる。
そして無意識に尻を持ち上げ、ガルベンの方へと差し出していた。
今に至るまで、逃げようとして捕まるなどして、何度か2人に暴力を振るわれていた少女は、どうすればその暴力を振るわれずにすむかを、その肉体で感じ取っていたのだ。
それは、悲しい条件反射に他ならなかった。
「うぅ〜し!頭よくなってきたじゃねぇかぁ、メスザル!人間様のザーメンを口にマ○コにしこたまぶち込まれてぇ、人間様に近づいてきた・ってワケかぁ?ハハハァ!!」
「ひぐ・・うぐぅ・・」
「じゃあ、この1発で、お前を完全な人間にしてやるぜぇ!オラ、感謝しろぉっ!」
――ズブ・・ズブブ・・
「い・・痛っ・・痛いですっ・・う・・ぐぅああうっっ!!」
激痛と異物感、そして言いようのない恐怖感に、少女は思わずくぐもった悲鳴を上げる。
貫かれたのは膣ではなく、愛らしい蕾だったのだ。
何の準備もできていないそこに、ガルベンは容赦なく力で腰を沈めてゆく。
「・・痛いっ!やぁぐ・・い、痛いですぅッ!!」
「んぐらい、耐えろ!お前のケツの穴はぁ、この試練を乗り越えてこそ、人間の穴になれるんだからなぁ!ハァッハッハァ!!」
小さくキュッとつぼまった肛門に、血と精液にまみれた芋虫のような巨根が侵入していく様はグロテスクの一言に尽きる。
やがて、少女の肛肉を食い破りながら突進していた芋虫は、その体全てを直腸内に隠す事に成功するが、少女が一息ついたのもつかの間、今度はそこで派手にのた打ち回り始めたのだ。
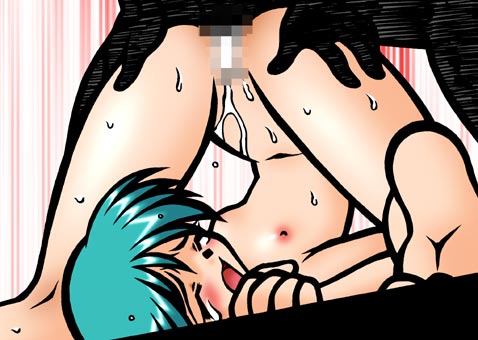
「あんだぁメスザル・・こ・こっちも結構いい穴してんじゃねぇかっ・・いいぜぇ、人間様のチ○コは、す〜っかりご満悦だ・・っ♪」
「ふっ・・ふぐっ・・うぐいぃぃ・・も・もう、許してぇぇ・・」
「よぉっし!・・来た来た来たぁっ!・・行くぞぉ〜・・っ・・お前の体がぁ、メスザルから人間の牝に変わるぅ・・瞬間だぁぁ・・ッ!!」
「ひ!・・やぐぅぅぅぅ〜〜ッッ!!!!」
吐き出された大量の精液を最後の一滴まで受け止めると、少女の尻はやっと肉食の芋虫をひり出す事を許される。
その直腸内、あちこちの粘膜が破れて血を噴出し、そこに汚らしい精液がまとわりつく様は、あまりにもむごたらしい。
だが、すっかり力を消耗し尽くした小さな体がどさりと床に転がると、ガルベンはそこに見向きもせずにそこを離れた。
「おう、ベイジ!明日の昼頃なぁ・・城から、増援の騎兵がぁ・・400到着する事になってる。オレたちぁ、そいつらと合流してからの出発だぁ・・わかったなぁ?」
「ィィック・・うぅ〜っス!じゃあ要は、ま〜だまだっ・時間があるって事っすねェ♪」
「そぉ〜だ・・グビグビッ・・ッハァ!」
「じゃっ、オレもケツにトライしちゃおうかなっ・・オラ立てェ、ぶ〜ち込むぞォっ♪」
「・・い・・いや・・ぁ」
その夜、少女が兵士たちの肉欲から解放される事はなかった。
朝、場房入り口で目を覚ました兵士が、そこから2頭の白馬が消えている事に気付くが、結局、それは大した騒ぎになる事もなかった・・
→進む
→戻る
→ロワイヤルゲームのトップへ
|
![]()
![]()