|
第五章 舞踏会
1
高らかにファンファーレが吹き鳴らされ、華美に装われたホールを静寂が通り抜ける。国王たるスカリーの入場だった。スカリーは居並ぶ身分の高い招待客達に軽く手を挙げて応え、一言も発せずに、右手を水平に上げて横手を指し示した。
大扉が開くと、八組の男女がペアを組んで現れる。
「今宵の主役は彼等である。余は客の一人に過ぎぬゆえ、皆気にせぬように」
スカリーは笑みを含んだ声でそう告げた。
招かれた者達の間に、称賛のざわめきが起こった。便宜的に男女一組になった彼等は、言うまでもなく武闘大会を勝ち残った選手達である。彼等もこの場に相応しく盛装して現れたのだが、そうして着飾ると、女性選手達は輝くばかりに美しく映えた。
初日を勝ち残ったのは、以下の十六名である。
レオスリックの王女戦士、ディアーネ。若き炎の魔術士、ルフィーア。ダイヤモンドを守護する聖騎士ロクサーヌ。同じく、黒真珠を守護する聖騎士ジュリエール。華麗な剣技を見せる女戦士、ミリエーヌ。弓を使うエルフ族、ナーダ。剣、弓、精霊魔術を使いこなすエルフ、ロリエーン。植物と風を操る魔術士、シェフィールド。
騎士アルシャルク。戦士タムローン。エルフのエルサイス。魔術士リンク。魔術士ボールガード。魔術士ダルーアン。エルフのラスィ。ドワーフのニムレム。
女性に比べると、男性は魔術士達の活躍が目立つ。普段は飾り気のないローブ姿の彼等も、今宵は洗練された華美な衣装をまとっている。
衣装そのものは用意されていたものらしいが、着付けや装飾品類が、闘技場での姿と類似するように工夫され、対比がいっそう華麗さを引き立てている。迎賓館の大広間に集った男女は、惜しみない喝采を注いだ。
「音楽を」
スカリーが声をかけると、宮廷楽士達は直ちに反応し、一糸乱れぬ円舞曲が流れ出した。武闘大会の勝利者達はそのまま組になり、広間のあちこちに散っていく。最初の何組かは誘うべき相手が決まっているが、その後は好みの相手に申し込んでいいことになっている。皆我先に大会の選手――特に女性――にダンスのパートナーを申し込んだ。この場はある程度身分の高い者達ばかりであるとはいえ、一応無礼講ではあるので、可愛い侍女やハンサムな付け人なども申し込みの相手として人気があった。
選手達は申し出を拒まず、誰とでも踊った。女性選手達は、踊り出したパートナーに、耳元で一言囁かれることがあった。すると彼女達は一瞬目を伏せ、大抵の場合おずおずと微笑む。そのような相手のときは、踊りながら心持ち密着の度合いが上がるようだったが、そんなことに気付くものはいなかった。
シェフィールドは踊り始めた相手に、耳元でそっと一言囁かれた。風の魔術士は瞬間笑顔を強張らせる。意味のない一言であるようなそれは、合い言葉である。奴隷に主人を知らせるのがその目的だった。
彼女達選手のドレスは、あらかじめ細工が施されていた。フリルやレース、波打つ襞などに巧妙に隠されてはいたが、彼女達のまとうドレスは、あちこちにあるスリットから手を差し入れれば、乳房や臀部、股間などを直接に触れて自由に弄べるように作られていた。合い言葉は、この男がシェフィールドを好きなようにできる相手であることを証すものであるのだ。合い言葉を知らない相手であれば不躾さを抗議できるが、この相手に対しては口答えも抗う素振りも一切許されない。
男は巧妙だった。ターンに、ステップに紛れて、さり気なくドレスの狭間に手を差し入れる。それは微妙な動きを示し、シェフィールドの性感を巧みに掻き立てた。
「は、ふ…」
押し殺した悩ましい吐息が、薄めの唇の間から押し出される。声を上げないようにするのが精一杯で、荒い呼吸を隠すこともできない。敏感になった肌は、ドレスの布地と擦れ合うだけでも刺激されてしまう。
犯して欲しい、虚ろな胎内に熱い肉棒をねじ込んでもらいたくてたまらない、潤んだ瞳は媚びを含んで男にそう告げていたが、男はシェフィールドの淫らな渇きを煽るだけ煽っただけで、曲が終わるなり、シェフィールドから離れていった。
「あ……」
一瞬シェフィールドは後を追うような素振りを見せたが、間を置かず次の申し込みをする男性が現れ、果たせなかった。
彼女にとってはもはや、この舞踏会は拷問と変わらなかった。時々に現れる『主人』達によって肉体は淫欲に狂わされていき、本格的な凌辱を欲して疼く。心づいて広間を見渡すと、ほかの七人の女性選手達は一様にたまらなく切ない表情を見せていた。彼女自身と同じ状態にあるらしいことは、シェフィールドには一目で察せられた。
昼間の、ローブを着て高度な魔法を行使する姿も、こうして着飾って高貴な人々と交歓する姿も、今の彼女にとっては仮のものに過ぎない。彼女は奴隷なのだ。男達に犯され、白濁液を浴び続ける姿こそが、本当の彼女なのだ。こうして焦らされることで、シェフィールドはそれを、疑う余地のない事実としてわからされた。
真の姿に戻り、御主人様方の性に仕えるときのことを想像するだけで、シェフィールドは待ち切れなくて甘い吐息をついた。
2
宴は酣となっていた。
女性選手達は何十回となく踊らされていた。鍛え上げた戦士達はいまだステップに乱れはないが、体力のない魔術士のシェフィールドは、もう足元が覚束無くなっていた。その原因は疲労だけではないのだが、ともかく彼女は今、強靱な精神力でやっと立っている状態だった。
舞踏会は立食形式となっており、踊り疲れた男女はテーブルに乗せられた料理や酒を食べて元気を取り戻していた。踊るのに飽きたり、より親密な語らいを求める者達は、迎賓館の広大な庭園に足を向けた。
疲労と焦らされた快感にふらふらになっていたシェフィールドは、彼女を弄ぶ権利を持つ男の一人と踊った後、この庭園に導かれていた。冴えた美貌が上気し、まっすぐ歩くのも難しい様子は、この宴の中であればワインを飲みすぎた風にも取れる。男の手は彼女の腰に添えられ、支えているかのようだが、実際は隠されたドレスの隙間から手を入れ、尻肉を揉み、菊門の皺をほぐし、潤み切った花びらの襞をなぞって、シェフィールドの性感を掻き立てていた。蹂躙に身を任せている知性的な美女の、半開きの唇からは震える吐息が洩れ、潤んだ瞳は何も見てはいない。今の彼女には、男の与える刺激だけしか感じられなかった。
ふと心づくと、周囲には人影がすっかり絶えていた。遠いワルツが緩やかに月光を横切る。枝葉を整えられたブナのそよぎが、翼持つ乙女の彫像にかかる月明かりを揺らしている。
「そこに手をつけ」
シェフィールドは頷き、示された白い彫像に手をかけ、伸ばした足を心持ち開いて、尻を突き出すような姿勢を作った。
「こ……これで、よろしいでしょうか…御主人様」
声が震えるのは恥辱のためではなく、疼く情欲の表れである。命じられるまでもなく嬲りやすい姿を差し出した娘の腰に、男は手を置いた。ぴくりと震えるシェフィールドの表情は、期待に甘く蕩けている。男が隠された結び目をいくつか解くと、シェフィールドのドレスのスカート部は、音もなく二つに分かれた。それまでの見た目からは全くわからなかったが、彼女のドレスのスカートの後ろは、腰から下すべてにスリットが入っていたのである。男がその隙間を閉じ合わせていた結び目を解いたため、スカートは自重に負けて左右に開き、シェフィールドの肉の締まった尻をすっかり露にした。
夜気に曝された秘部を見遣った男は、唇を嘲笑に歪めた。シェフィールドの焦らされ濡れそぼった秘唇から溢れた愛液は、彼女の内腿をぐっしょり濡らし、ストッキングを伝って足首まで垂れ落ちていた。
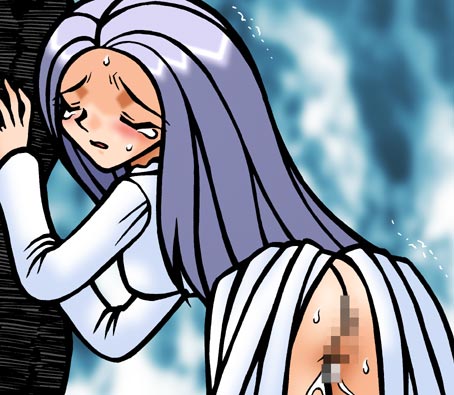
「ひ!」
シェフィールドは鋭く息を吸い込んだ。男の指が、開いた陰唇を撫で上げたのである。男はシェフィールドに指を広げて見せた。僅かな接触で、男の指には彼女自身が分泌した液体がたっぷり絡み付いて糸を引いていた。
「何だ、これは。何曲分か触られただけで、この有様か? 慎みとか自制とか言う高尚なものには縁がないようだな、この、低劣な、淫乱奴隷め」
侮蔑の言葉を浴びせながら、男は触れるか触れないかの繊細なタッチでシェフィールドの性感帯を撫で回した。彼女は砕けそうな膝で必死に体を支えながら、答えを返す。
「はっ…はいっ……。シェフィールドは、卑しい、淫らな…最低の淫売です。ちょっと…可愛がっていただくだけで、発情してしまう……牝犬以下の、家畜奴隷です。……どうか、御主人様……この、淫乱な性交奴隷の、シェフィールドに…お、お慈悲を………お慈悲をくださいませ……」
「ほう。どうして欲しいんだ?」
男の手は停滞を見せず、白磁のような魔術士の肌を刺激し続けている。剥き出しの性感が波立ち、微妙な接触が、冷静な試合運びで勝ち残った魔術士を、別人のように狂わせていく。
「あっ! ふ、あ…はぁぁぁぁぁ…………っ。お願い、します。御主人様の、逞しいモノを、シェフィールドの汚らしい穴に……捩じ込んでくださぁいっ! どうか…御主人、さまぁ……」
哀願の甘え声にはたっぷりの媚びが詰まっていた。男は奴隷娘の哀れな懇願に応じる気配を見せず、懐から二本の棒を取り出した。
一本は肘から先程度の長さで、握りがあり、拳一つ分から先は、連なった楕円球から成っていた。楕円球は指の第一関節から第二関節程度の直径のもので、大きさは不揃いだった。楕円球同士の間には指一本くらいの隙間が開いている。男はこの棒の横腹を、シェフィールドの秘所に何度か擦り付けた。たまらず、青みがかった銀髪の娘は甘い悲鳴を上げる。少しの接触で棒には多量の愛液が絡み付いた。
彼女自身の潤滑液にまみれたそれを、男は娘の菊座にあてがい、無造作に繰り込んだ。シェフィールドは容易くそれを腸内に飲み込んでいく。快美な声が長く尾を引いた。楕円球が送り込まれてくる度に、括約筋が拡張と収縮を繰り返す。肛腔性交の味をたっぷりと覚え込まされた彼女にとって、たまらなく甘美な侵入だった。
「逞しいモノと言うと、こいつのことか?」
最後まで押し込んでも男は手を放さず、角度と速度を変えて五回、六回と抜き差しした。シェフィールドの答えは言葉にならない。背骨を駆け上る快い電流がまっとうな発声を妨げていた。
「……! ――っ…! っ! ――――ッ!」
彫像に突いた手で体を支え切れなくなって、シェフィールドは天使像に抱きついた。形のいい大理石の乳房の間に顔を埋め、声なき声を殺す。男が手を休めても、彼女は顔を上げることができなかった。埋められた部分から湧き出す快感は、いまだ虚ろな部分の痺れるような疼きを際立たせた。震える呼吸を取りまとめて、彼女は何とか言葉を絞り出した。
「御……主人…さまぁ…っ。前…も……前も、塞いでぇ……。犯して、くださぁあ…いっ…」
「わがままな奴隷め。少々躾が足りないようだな。が、まあ、いいだろう。望み通りにしてやる」
男はもう一本の棒を、シェフィールドの足の付け根に向けた。それは、心持ち先細りの、ガラスの円筒といったものだった。表面に余分な突起は一切なく、磨き抜かれたように滑らかである。太さは、先端で並の男根程度、後端では指三本分ほどそれに加わっている。長さは手首の関節から肘の関節くらいまで。女魔術士の腸内に収められたものよりは少し短かった。
男はやはり無造作に、それをシェフィールドの陰唇に飲み込ませていった。
「くぅううん……っ」
我慢し切れず、薄めの唇から小犬のような鼻声が洩れる。試合前の凌辱以来の侵入である。今の彼女は、半日放置されるだけでも淫らな衝動を抑え切れなくなるほど、淫猥で堪え性のない、発情期の獣も同然の体に変えられてしまっていた。
男はガラスの棒を根元まで咥え込ませてから、手を貸してシェフィールドを立たせた。スカートのスリットは立ち上がるとほとんど目立たなくなる。何とか一人で立ったシェフィールドの耳に、男は囁いた。
「もっとしっかり立て。これから広間に帰って、そのまま踊るんだからな」
「えっ……」
シェフィールドは青くなった。こんなものを入れられて踊ったりしたら、何でもない顔ではとてもいられない。もし一般の招待客にばれたりしたら……。
動揺を煽るかのように、男は口の中で何事か呟いた。シェフィールドは悲鳴を上げる。腸内に収められた棒が、激しくうねり始めたのである。崩れ落ちかかる体を、背後から男が支えた。
「あぅぅうん……っ」
柔襞を抉られる快感に負け、それを逃がさないとでもいうかのように、彼女は二本の棒を思い切り食い絞めた。当然の結果として、引っかかりのないガラス棒は、内圧に押されて抜け落ちた。
チィン! チィン、チン……。
ガラス棒が石畳で跳ねる澄んだ音が、蕩けそうになる彼女の意識を引き戻した。
男は後ろでうねる棒の動きを止めると、奴隷を叱責した。
「ダメだな、お前は。望み通り入れてやったものを咥え込んでおくこともできないのか? また入れてやるから、もう落とすんじゃないぞ。踊ってるときにもう一度動かして、落とさないかどうか確かめるからな」
「そっ! それは…」
男の言葉の意味を、聡明な彼女は瞬時に理解した。広間の床は、磨いた白大理石が敷き詰められている。再び後ろのものを動かされて、前のものを落とさないでいられる自信は、彼女には全くなかった。落ちれば、ただの石畳よりもっと高く澄んだ音が出ることだろう。床に転がったそれを全員が注視し、意味を悟るに違いない。彼女は一瞬にして、嫌悪と侮蔑の対象に堕ちるのだ。
「お、お許し下さい、御主人様…! し……締まりのない、牝犬奴隷の、シェフィールドには……、落とさずにいるのは、できそうも…ありません。どうか、お許しを…」
シェフィールドは自らの評価を下げることで、必死に男にへつらい、慈悲を賜ろうとした。男は奴隷娘の脅えた目を見下ろし、考える振りをする。
「ふん。……仕方のない奴だ。そんなに言うのなら、落とさずに済むようにしてやってもいいが……」
「お願いします! はしたない性奴が、御主人様の下さったものを落とさずに済むように、どうか、お計らい下さい……ああ、御主人様!」
男が考えを変えないうちにと、シェフィールドは熱っぽく懇願した。男は辟易したような顔でシェフィールドの後ろに押し込まれた棒に手をかける。
「わかった、わかった。だが、そのかわり……」
「ひぃぃいンッ! あムぅう、きゃううぅぅんっ!」
腸内に収まった棒を大きく抽送され、シェフィールドは内臓全部持っていかれるような感覚に幻惑された。そのために、男の次の言葉を深く考えずに容認してしまう。
「そうしてやる代わりに、踊っている間中こいつを動かしておくからな。どうだ、寛大な処分だろう? 嬉しいか?」
「ひぁ! あっ、は、はい……御主人様のぉ、か、寛容な、お心にぃ……ふぅっ、ふ、深く、感謝ぁ……ぁああん……致し……ま、す、う…ぅんん……っ。…………え……?」
その意味するところに彼女が気付いたのは、反射的に迎合するような答えを返した後のことだった。しかし、おどおどと男の目を見上げただけで、前言を撤回することなど許されないのがわかる。衆目の中ガラスの円筒を落とさずに済むらしい事だけでよしとしなければならなかった。
再び男が手にしたガラスの円筒を見て、シェフィールドは、その後端に鉄の環がはまっていることに気付いた。男に命じられ、彼女は長いスカートを頭上にまでたくし上げた。彼女の下半身はガーターベルト、ストッキング、靴を身に着けただけのあられもない姿を露にしていた。自ら巻き上げた布地に遮られ、彼女には、男が何をしようとしているのか知ることはできない。まず滑らかな円筒の侵入があり、男が再度ガラスの棒を膣に押し込んだことを彼女は知った。最奥部まで刺し込まれ、彼女は括約筋がそれを締め上げないよう懸命に抑えた。また落としたりしたら、男にどんな罰を受けるかわからない。次の刺激に、彼女は身を震わせた。既に勃起している彼女の最も敏感な部位にまといつく被膜を、男がいっぱいに剥き上げたのである。緊張しようとする陰唇の反射的な作用を阻む努力で、肌にどっと汗が浮かぶ。その次の刺激で、彼女の努力は瓦解した。陰核に何かが巻き付き、ぎゅっと締め上げて、彼女に激痛を与えたのである。
「ぎ……っ!」
苦痛による筋肉の緊張は、ガラス棒の落下をもたらさず、代わりに更なる一点の痛みを彼女に与えた。
「手を放していいぞ」
意識は苦痛に痺れていたが、体の方が男の命令に従わねばならないことを覚えていた。スカートはふわりと落ちてシェフィールドの腰の回りにまとわりつく。
「落ちないように、してやったぞ」
男の唇には馬鹿にしたような笑みが浮かんでいた。
「あっ……有り難う、ございます、御主人様……。…ですが…何を、して下さったの…ですか?」
絞り出すような問いに、男は手にしたものを見せることで答えた。小さな糸の束である。
「絹糸で、棒とお前とを結んでやったのさ。さて、約束通り、後ろのものを動かすぞ」
「え! あ、ま、待っ……ひ! ひっ……く! あひ、あ、くぅああああっ…!」
快感と苦痛に彼女は悶絶した。腹の中で暴れる楕円球は彼女にめくるめく快感をもたらし、楕円球の運動による圧力と刺激された性感のため否応なく収縮してしまう膣の内圧とで、ガラス棒は押し出されようとする。が、陰核に結ばれた絹糸がそれを引き止め、ガラス棒の自重と押し出す圧力の合わさった力で陰核を締め付ける。愉悦と激痛の織り成す苦悶に、彼女は陥れられた。
「あああ……あっあっあっ」
悦楽の陶酔に浸ることを、鋭い痛みが許さない。痛みに覚醒した明晰な意識で、シェフィールドは、腹腔を掻き回される常軌を逸した快感を味わうことを強いられた。時間感覚が曖昧になり、気が付くと、男に肩を抱かれ、広間のそばまで連れてこられていた。
「あ……?」
彼女は慌てて、心を奮い立たせた。快楽に酔い痴れた表情で広間に入っていくわけにはいかない。休まずくねる器具のため、彼女はまともに立っていることも難しかった。そのため、男に背を押されると、必死でバランスを取ろうと、交互に足を繰り出すことになる。いつの間にか彼女は単身、広間の中央に進み出ていた。
間を置かず、貴族の若者からダンスを申し込まれる。断ることは許されていないので、彼女としては受け入れるしかない。
ステップもターンも、無意識の動作だった。彼女の感覚は、暴れ回る腸内の楕円球と、それがもたらす淫獄の法悦、甘美な激痛だけに集中していた。こみ上げる圧倒的な快感が甘いよがり声に変わろうとするのを押し留め、無理に呼吸を整え、作り笑いを浮かべる。それだけでも超人的な自制心を必要とした。
一曲が終わるまで果てしない時間がかかったような気がした。疲れ果て、へたり込まずにいるのが精一杯である。しかし、責め苦はそれだけでは終わらない。会釈してパートナーから離れると、すかさず次の男性からダンスを申し込まれる。愛想よく承諾し、再び曲の流れに乗る。
それから何曲踊ったのか、彼女には全くわからなかった。時間感覚はもはや消え失せ、腹腔と陰核に加えられる甘美で痛烈な拷問に耐え続けることだけがシェフィールドにとってすべてになった。
自制心は時としてひび割れ、共にステップを踏む男性の胸に頬を預けながら、清楚な美貌からは想像もつかないような淫蕩な表情を浮かべてしまう。荒い呼吸と絶え間ない発汗は、踊りのせいにすることができたが、小さく漏れてしまう甘い喘ぎ声に適当な言い訳は思いつかなかった。それを葡萄酒のせいにすることを思いついたのは、まともに会話する能力がなくなりかけていることに対して謝っていたときである。
何曲目か――あるいは何十曲目かを踊り終えたあと、遠くで誰かが話しているのが、蕩けそうな女魔術士の意識の端で、辛うじて引っかかった。
「……では、明日の試合もありますので、我々はこれにて失礼致します。どうぞまた、闘技場へお運び下さい」
誰かがシェフィールドの腕を取り、広間から連れ去った。性感を現さないための戦いを続ける彼女は、もはや外部の出来事はほとんどわからなかった。
3
迎賓館の奥まった一室が、女性選手達の控室になっていた。引きずるようにしてここに連れてこられると、シェフィールドは床に崩折れた。
「あうっ……はぅううっ…」
楕円球の動きに合わせ、体をくねらせる。淫らに悶える彼女を、誰かが両脇から抱え上げた。どこか扇情的なメイド服をまとった娘達である。よく見ると首には黒革の首輪を絞めている。
メイド達は容赦なくシェフィールドのドレスを剥ぎ取った。女魔術士のスリムな裸身が露になる。少々小さめだが形のいい乳房、コルセットの必要がないほど細い腰、引き締まった尻。股間に埋まった二本の棒以外の衣装をすべて脱がされ、一糸まとわぬ姿にされたシェフィールドは、次の間に連れていかれた。
控室は続き部屋からなり、そのうちの一室は、広々とした浴室になっていた。七、八人は楽に入れそうな浴槽には、浅く湯が張られている。メイドはシェフィールドをここに運び込み、湯の中に浸した。服が濡れないよう、メイド達も衣服を脱ぐが、首輪ははずさない。首輪だけを着けたメイド、いや、奴隷少女達は、手に手にスポンジ状の塊を持つと、シェフィールドの肌を擦り始めた。石鹸が染み込ませてあるらしく、たちまちシェフィールドの体は泡に覆われていく。全身の皮膚感覚が鋭敏になっている彼女には、奴隷少女達に磨き立てられるのは、性感帯を舐め回されるのに等しかった。
あられもないよがり様を見せるシェフィールドを、奴隷少女達は事務的に洗い立てていく。慎みのかけらもない乱れ切った声をうるさく思ったのか、癖のある黒髪をボブカットにした生意気そうな奴隷少女が、シェフィールドの唇に唇を重ねた。暴れるシェフィールドの舌に、舌を絡めていく。シェフィールドはそれに応え、情熱的なキスに没頭した。さらさらの茶色がかった黒髪を長く伸ばした、どことなく気品のある顔立ちの奴隷少女が、シェフィールドの耳に舌を這わせながら囁く。
「お行儀良くしていてくださいな。そうできるだけの教育は、していただいているはずですわ。それができないのでしたら、躾が足りなかったということになり、御主人様に恥をかかせることになります」
唇を解放されてから、シェフィールドは喘ぎながら答えた。
「行儀……良く、します…からぁ…っ。う…しろ……後ろの……お尻の棒を、ぬ、抜いてぇ…。抜いて……くださぁいっ…」
「それはできないわ。御主人様に固く禁じられていますからね」
シェフィールドの哀願を、彼女の唇を奪っていた奴隷少女は一蹴する。
「そっ…それなら……後ろのモノのことを…忘れさせて……ください」
意外な頼みに、少女は少し考え込んだ。
「……いいわ。そのかわり、私達の仕事が終わるまで、おとなしくしているのよ。いいわね?」
「はっ…はいっ……。あ…有り難う、ございますぅ…」
少女達は一旦シェフィールドの体にまとわりついた石鹸を洗い流すと、浴槽から引きずり上げた。浴槽の側にしつらえられたマットレスに横たえると、三人の奴隷少女は、シェフィールドの肌に舌を這わせ始める。
「はっ……はぐっ……くふぅ…ぅんっ…」
シェフィールドは必死で声を抑え、跳ね上がろうとする肢体を抑え込んだ。震えながら横たわる彼女の肌の隅々まで、奴隷少女達は舐め回した。シェフィールドに快感を与えると共に、舌で汚れを舐め取っているのだった。
少女達の責めは的確だった。責めるべき場所と責め方を心得切った様子は、女性の快楽に奉仕するのに慣れていることを思わせる。女性らしい繊細な愛撫に、シェフィールドはたちまち虜になった。快感を与えてくれる者は主人であり、主人の命令は絶対である。少女達の言葉は、シェフィールドにとって至上命令となった。
舌での作業を終え、余すところなく少女達の唾液にまみれたシェフィールドに、少女達は今度は手に直接石鹸を塗って、全身を撫で回し、揉み立て始めた。仕事を続けるうちに、当然ながら、少女達の肌も石鹸の泡にまみれる。シェフィールドを抱き起こしたりひっくり返したりする必要性から、乳房や腹などがシェフィールドの肌と擦れ合い、少女達はいつしか頬に血を昇らせ、呼吸を乱していた。そしてそのうち、濃い赤毛のスリムな少女が、もっと手っ取り早く、そして一石二鳥の方法に気付いた。
奴隷少女は手ではなく体の前面すべてに石鹸を塗り伸ばすと、全身をシェフィールドの裸身に擦り付け始めた。それを見て、ボブカットの少女も彼女に倣った。少しためらって、長髪の少女も同じようにする。シェフィールドは、三人の少女達に押し揉まれ、快楽の絶叫を半狂乱で押し殺した。シェフィールドの腸内でうねるものは、少女達の体にも振動を伝える。彼女達も徐々に、だが確実に乱れ始めていた。頬に血が昇り、呼吸は浅く、早くなる。少女達の動きはもはや事務的なものではなく、快感を貪ろうとするもののそれだったが、シェフィールドを清めるという所期の目的は忘れていないらしく、微妙に角度を変えて彼女の全身を磨き立てるような動きを見せた。やがて少女達は一人一人絶頂に達し、シェフィールドにぐったりと身を預けた。
少女達はしばらく余韻に浸っていたが、やがて一人が目的を思い出して、他の二人を促し、再びシェフィールドを浴槽に浸ける。石鹸を洗い流し、髪を良く手漉き洗いすると、三人の少女はシェフィールドを浴室から運び出した。
シェフィールドはまた別の部屋に導かれた。濡れた身体を拭かれると、ソファのようなものに座らされた。背もたれがかなり倒れていて、寝ているのと座っているのの中間くらいの姿勢になる。長髪の少女はシェフィールドの青みがかった銀の髪をまとめてソファの後ろに垂らし、梳り始める。あと二人は手を香油の瓶に浸け、シェフィールドの肌に塗り込んでいく。シェフィールドに約束した通り、その手の動きは淫ら極まるものだった。いまだ腹腔内を蹂躙する楕円球に耐えているシェフィールドは、愛撫に反応して跳ね上がろうとする肢体を抑え付けるのに必死になる。
波打った赤毛をショートにした少女は、シェフィールドの秘部に収められたガラスの円筒に手をかけると、ぐっと押し込んだ。
「ひ……! ひっ……」
瞬間、シェフィールドは堪え切れずに声を洩らしてしまう。絶えず陰核を責め苛んでいた刺激が消え失せ、おなかの中を掻き回される快感と少女達の愛玩のすべてが、遮るものなく襲いかかってきたからである。

「こら。おとなしくする、約束でしょ?」
ボブカットの少女が、右手で腹の皮膚を押し揉み、左手でシェフィールドの右の乳房を弄びながら、耳元で囁く。
「だっ……だってぇ……あううっ!」
赤毛の少女が二、三度ガラスの円筒の金具を引くと、シェフィールドはひとたまりもなく声を上げ、大きく跳ね上がった。一旦休めた後で、更に強い刺激を加える。赤毛娘は、責め方をよく心得ていた。
「うふふっ。約束を破ったわね。お仕置きしてあげる」
ボブカットの少女は、素早くシェフィールドの傍らを離れると、髪を結ぶためのものだろう細く長いリボンと、かなり大きな香水瓶を持ち出した。少女はリボンを使い、香水瓶をガラス棒の金具にぶら下げてしまった。この余分な荷重で、シェフィールドの陰核はより強く締め付けられることになった。
「あああっ! ゆ…るし…てぇ……っ……」
「うふふふっ……っ。ダ・メ・よ。しばらくこのままでいなさい。これはお仕置きなんだからね」
微笑を浮かべる少女に、髪に櫛を入れる手を休めずに長髪の奴隷少女が唇を尖らせて見せる。
「キャロルったら。ダメよ、お仕事を忘れては」
少女はむっとした様子で言い返した。
「はいはい。仕事をすればいいんでしょ」
言うなり、香油の瓶を取り上げる。
「エイダ、ちょっとまっすぐ立って」
「?」
不思議そうな顔をしつつも、赤毛の少女は言われた通りにする。黒髪の少女は赤毛の少女の乳房の上辺りで香油の瓶を傾けた。とろ味のある透明な液体が、少女のスレンダーな裸身の前面を覆って流れ落ちていく。
「キャロルぅ……?」
「さ、これで、さっきみたいにしてあげるのよ」
赤毛の少女は納得した顔で、ソファにぐったりと横たわるシェフィールドに馬乗りになった。乳房と乳房、肌と肌を合わせて、体中で香油を塗り伸ばし始める。香油の瓶を置いたキャロルと呼ばれた少女は、赤毛の少女の背後に立ち、背中に手を当てると、赤毛娘の体を激しく前後に動かし始める。
「ちょ、ちょっと、キャロル、何を……あうっ!」
赤毛の少女とシェフィールドは、共に悲鳴を上げた。ぬるぬるした香油が二人の肌を淫らにぬめり合わせ、たまらない刺激が湧き上がる。体の動きを黒髪の少女が強制しているため、赤毛娘は快感を適度に抑制することができず、乱れていった。
「あ、やめ…っ、キャ、キャロ……あああんっ」
勝手に零れ出ようとするよがり声を噛み殺しつつ制止の声を上げる少女の体の下で、シェフィールドはすべての慎みを忘れて、あられもない快感の絶叫を放っていた。
「うるさいわね。エイダ、黙らせて」
黒髪の少女は、赤毛の少女の頭をシェフィールドの頭部に押し付ける。促されるまでもなく、赤毛の少女はシェフィールドの唇に貪り付き、激しく舌を絡み合わせた。
「ううう……っ、うぅっん……」
忙しなく吸い合う唇の隙間から、どちらのものともつかない、悩ましい呻きが洩れる。
赤毛の少女は既に理性を蕩かされてしまったらしく、香油を塗り込む目的とは思えない淫らな動きで、組み敷いた裸体に裸体を擦り合わせた。目を細め、愉しげな笑みを浮かべてそれを見下ろしていたボブカットの少女は、赤毛の少女の動きが性急になってくるのを見計らって、二本揃えた指を彼女の菊座に突き立てた。
「ひぅっ…!」
瞬間、赤毛娘の動きがぴたりと止まった。次いで、黒髪の少女が指を上下左右に動かしたり折り曲げたり広げたりするのに反応して、腰が小刻みに揺れ始める。
「あっ! あ、あ……!」
指の動きに応じて喘ぐ少女の表情を見れば、彼女が肛虐から苦痛ではなく愉悦を得ているのは明らかだった。赤毛の少女の快楽の中心をこじりながら、黒髪の少女が意地悪く囁く。
「気持ちいいのね。エイダは、お尻の穴を苛められるのが大好きだものね? 確か、特に念入りにお尻を調教していただいたんでしょ? 御主人様方のお話では、お尻専門の奴隷になさるおつもりもあったと聞いたけど」
赤毛の少女は答えない。背中の皮の内側を無数の蛆虫が這っているような、悪寒と紙一重の、筆舌に尽くしがたい快感に襲われて、意識が痺れ、答えることができないのだった。
「キャロル……」
呼びかける声に目を上げると、長髪の少女が、シェフィールドの髪を手入れしつつ、非難がましい視線を向けている。
いいところで水を差され、むっときたボブカットの少女は、それでも仕方なく赤毛の少女を嫐る指を抜こうとした。それを赤毛の少女が、括約筋をきゅっと食い締めて押し留める。
「や、抜いちゃ、ダメぇ……。…お…お願い…っ…」
艶っぽい喘ぎに、黒髪の少女の理性は蕩けそうになる。少女を快感で意のままに支配する悦びが、彼女の背筋をぞくぞくと震わせた。少女はわざと指をほとんど引き抜いてしまってから、いきなり目一杯突き込んだ。
「ひゃああああんっ!」
赤毛の少女は快感の悲鳴を上げてそれを受け入れる。再度赤毛の少女を弄び始めた彼女に、長髪の少女は再び、強く呼びかけた。
「ちょっと、キャロルったら! 悪ふざけが過ぎるわ。早く仕事を終わらせてちょうだい!」
きつく言ったものの、叱った相手にじっと見つめられて、少女は気押されてしまった。視線の冷たさに圧倒され、凍りついたようになってしまう。
ボブカットの少女は、眼下の少女からは一切の興味を失った様子で、無造作に指を引き抜き、長髪の少女の背後に回り込んだ。
「キャ……キャロル?」
やや脅えた声を上げるのを無視し、背中から手を回してくる。片方の手が乳首に伸ばされ、ぎりっ、と挟み潰した。
「いぎ……っ!」
叫び声を上げようと開く口に、もう片手の指を入れる。赤毛の少女の汚物の絡んだ指を。
「うぶっ! く、むぅうううっ!」
涙を浮かべ、身をよじって嫌がる少女の耳に、ボブカットの娘の声が吹き込まれた。
「――随分、偉そうな口を聞くじゃない、パメラ? まさか、まだ自分が大公女殿下だとでも思ってるわけ? 三月前はともかく、今じゃ立派な犯罪者じゃない。国家反逆罪でギロチンにかけられてもおかしくなかったのを、陛下の恩情で奴隷になるだけで済んだのよ。その辺りがよく理解できてないんじゃないの?」
続く言葉を後押しするように、乳首をひねり上げる指に力が込められる。
「ほら、舐めなさいよ! 奴隷としての躾が足りないみたいだから、よく自分の立場をわからせてあげるわ。大体、何故私達まで奴隷にされたのかわかってるの? 私達は、たまたまあんたの侍女をやってただけなのよ。言わば、あんたのとばっちりなの。それがわかってる? ねえ、わかってるの?」
言い放ちながら、長髪の少女の口に押し込んだ指を更にぐいぐい押し込む。
「うぐぅ……!」
吐き気を堪えつつ、長髪の少女の舌が動く。従順に、指に絡んだ汚物を清めるために。すっかり舐め取るまで、乳首は解放されなかった。
「んっ!」
長髪の少女の背筋が跳ねる。乳首を解放した指が、彼女の股間に忍び入っていた。
「あら、これは何? こんなに濡らしちゃって、酷い目に遭わされて欲情してるのね? 口の利き方はなってないけど、体の方は、よく心得ているじゃない。――自分が、奴隷だってことを」
「はああん!」
長髪の少女は背を反らせて喘いだ。口から抜かれた、彼女の唾液に濡れた指が、二本揃えて菊門にねじ込まれたのである。前と後ろに二本ずつ入り込んだ指に粘膜をくすぐられ、間の肉壁を押し揉まれて、湧き上がる倒錯した快感から逃れようと、無意識に爪先立ちになる。が、そんなことで逃げられるはずもない。
「ふぁ……。ダメ、キャロル、ダメぇ……っ。あっ、ダメだったらぁ……! や、やめてぇ……っ」
「何がダメなの、パメラ? こんなに濡らして、こんなに締め付けて。それに、どうしてもやめて欲しいんだったら……言い方が違うでしょ?」
囁きながら、指を微妙に蠢かすのはやめない。
「は、ひ……! ダメ、そこ……っ! く…あ……。やっ……やめ……お……お許し……ください、御主人……様ぁ……っ」
「よく言えたわ。じゃ、正直に言えば、許してあげる……ねえ、パメラ? 意地悪されて、痛いことをされて、おもちゃみたいに悪戯されて……気持ちいい? ねえ、気持ちいいの?」
呼吸を乱し、羞恥と快感に頬を染めて、かつて第七位の王位継承権を有していた奴隷少女は、ためらいながらも正直に今の気持ちを告白した。
「…………。き……気持ち……いい、です……」
「じゃあ、パメラは、恥ずかしい目に遭わされて感じる、淫乱な肉奴隷なんだ。そうよね?」
「はい……パメラは、苛められるほど欲情する、いやらしい淫売奴隷です。生まれついての、牝犬です。パメラは、奴隷として御主人様の快楽に御奉仕するためにこそ生まれてきたんです」
台詞の後半は、調教で教え込まれる定型の文句だった。
「ふうん、そうなんだ。じゃ、約束通り、許してあげるわ……快楽に溺れることをね」
意地悪く告げて、少女はひときわ激しい責めを加え始めた。
「きゃうううっ! あああっ! ダ、ダメっ、キャロル、ほんとに…ダメぇ! くはっ、は、早く、お仕事しなきゃ……御主人様に、叱られ……あああああん!」
長髪の少女の最後の言葉が、責め立てる愉悦に浸り切っていたボブカットの少女を正気に戻した。
「そうね……あんまり遅れたら、ひどく叱られてしまうわね」
言葉の内容とは裏腹に、少女の独白はどこか陶酔したような調子を帯びていた。主人から受ける「罰」を期待するような……。
「それじゃ、早く済ませてしまいましょ……エイダ、いつまでよがってるの! この子に香油を塗ってしまうわよ!」
乱暴に指を引き抜かれ、長髪の少女は、仕事に戻るボブカットの少女を潤んだ瞳で追いかけた。甘い溜め息をついて、軽く頭を振り、自分も再度仕事に取りかかった。
4
髪の手入れが終わり、背中にも香油が塗られると、タオルで余分な香油が除かれた。続いて少女達は、シェフィールドに化粧を施し始めた。もともとシェフィールドは、肌の色が白く、唇は赤々としているので、化粧が必要であったことはない。しかし少女達は美しさを引き立てる方法をよく知っていた。少女達が施したものはほんの薄化粧と言ったものであるが、シェフィールド生来の清楚な美しさと、調教されて身に付いた艶やかさを最大限に引き出していた。
最後に、シェフィールドは衣装を着せられた。それは先程舞踏会で着せられていたものを基本にデザインされていたが、淫猥極まりない変更を加えられたものだった。下着は黒革の長手袋、黒革のストッキング、ガーターベルト、黒革のコルセット。ドレスは白絹であるが、乳房はさらけ出されているばかりか寄せ上げられ、左右から絞り出されていた。スカートは膝までで、殊更薄地の絹が使われ、下半身はほとんど透けて見える。その上前後に大胆にスリットが入っており、直接触れることを妨げない。レースやフリルがふんだんに使われているのがかえって淫らさを引き立てていた。
少女達はこれを着せたあと髪を結い上げて繊細なうなじの曲線を露にし、仕上げとばかりに、首に黒革の首輪を巻き付ける。肌に首輪の感触を感じると、シェフィールドは奇妙な安心感を覚えた。首輪の金具に、強く引けば切れてしまいそうな、繊細なデザインの銀の鎖を繋げる。しかしそれが切れることはないだろう。引かれる鎖に、シェフィールドが逆らうことはないからである。
少女達が引いていくままに、シェフィールドは別室へ導かれた。
「――遅かったわね。随分待ったわ」
気怠げな様子で、瀟洒な丸テーブルに頬杖を突いているその人物に、シェフィールドは一目で惹き付けられた。
きつめの美貌を取り巻く髪は緑がかっていて、常人とは異なる神秘的な雰囲気を漂わせている。女性らしい体の線を覆う衣装は簡素な意匠のものだが、生地も仕立ても質がよく、高価なものだろうことが一見してわかる。そして彼女のまとう独特の神秘性を際立たせるかのように、その瞳は、左右の色が異なっていた。右目が碧、左目が翠。シェフィールドは魅せられたように、その瞳から目が離せなくなった。
「申し訳ありません、ゼルダ様……」
長髪の少女が、身を竦ませて謝った。脅えを見せる少女を咎めるような態度で、ボブカットの少女が付け加える。
「パメラったら、この子に悪戯していたものですから。遅れてしまいましたわ。いくら止めても聞かないんですもの」
「な……!?」
当然のように事実を逆に述べられて、慌てて振り向く少女に、小憎らしいほど落ち着き払った少女は、たしなめる口調で言葉を重ねた。
「誤魔化そうとしても駄目よ、パメラ。この際だから、きつく叱っていただくといいわ。そうでないといつまでも、仕事に集中するってことを覚えそうにないものね、あなたって」
「そんなっ……それは、キャロルの……キャロルが……!」
「まあ! 私のせいにしようっていうの? …呆れた。いつまで甘ったれたお姫様のつもりでいるのかしら、この人。少しは、自分で責任を取るってことを教えていただいたら? 二度と忘れられないよう、体にたっぷりとね」
自信たっぷりに言い切って、ボブカットの少女は気怠げな様子の女魔術士に問うような視線を向けた。目線で「このわがまま娘を罰していただけませんか?」と告げている。
ゼルダは自分を見つめる少女の目に視線を合わせた。
「あ……」
少女は何か物理的な衝撃を受けたかのように、一瞬、びくんと跳ねる。だが、それ以上何も起こらず、少女は首を傾げた。
(今のは、一体……?)
厚顔な少女も、気を呑まれ、饒舌な口を閉ざしてしまっていた。思い出したのだ。目の前にいる女が、魔術士であると言う事実を。
「……なるほどね。ま、責任の所在がどうあれ、皆で楽しんできたことは確かのようね。服を着てくるのを忘れるくらいだもの」
「あ」
「っ!」
少女達は指摘されて初めて、自分達が首輪一つを着けた裸であることに気付いた。シェフィールドを磨き立てたり、悪戯したり、それをたしなめたりすることに注意を奪われ、服を着直すことに気が回らなかったのである。愛戯に時間を取られて気が急いていたこともある。だが、間違いの要因として一番に挙げられるのは、こういうことだろう。つまり、彼女達にとっては、服を着ていない状態というのが、きわめて自然に感じられていたのである。
「それは置いといて、手早く仕事をしないとね。ただでさえ、誰かさん達が時間を食い潰してくれたもの」
穏やかに揶揄されて、少女達は頬を桜色に染める。
「さ、その娘を連れていらっしゃい」
女魔術士は優雅な身のこなしで席を立つと、背後の床に描かれた魔法陣の傍らへ足を向けた。
「はい、こっち……この陣の中心に跪かせて」
指示されるままに、少女達は半ば持ち運ぶように支えたシェフィールドを魔法陣の中に据える。全員が魔法陣に踏み込むと、ゼルダは薄く笑って、小さく呪文を唱えた。
シェフィールドに言われた通りの姿勢を取らせ、魔法陣から出ようとした赤毛の少女は、見えない壁にぶつかったような衝撃を鼻の頭に感じた。
「――きゃ!」
鼻に手を当てて涙を浮かべ、少女は目の前の空間を探る。掌は滑らかな壁の感触で跳ね返されてしまう。
「これは……!」
魔法陣の境界に見えない障壁があり、少女達を閉じ込めているのだった。
「ゼルダ様、これは!?」
少女達が狼狽して異口同音に問いかけるのに、ゼルダは微笑んで答えた。
「本当は、その娘を仕上げたら貴女達には別の仕事があったのだけれど、遅れた罰よ。その娘がこれから行くところに、一緒に行ってらっしゃい」
「あの……それとこれと、どういう関係が……?」
長髪の少女がおずおずと尋ねる。
「そこに行ってもらうためには、私がこれからかける魔法が不可欠なのよ」
あっさりとゼルダは答えを返した。その言葉に身を固くする少女達を見て、微苦笑して言い添える。
「……別に、危険な魔法じゃないから、安心なさい。ちょっと、精神体に働きかけて、認識能力を狂わせるだけだから」
言っている意味が理解できないため、少女達の脅えは一向に治まらなかった。だが、もはや気にせず、ゼルダは呪文の詠唱を始める。調整した魔力が注がれ、魔法陣が機能を開始して陣内の対象に効果を及ぼしていく。それが感じ取れるのは、この場では、術者のゼルダ以外にはシェフィールドだけだったろうが、シェフィールドはその内容を認知できる状態にはなかった。腸内でうねる楕円球と、陰核の継続的な痛みに心を奪われ、半ば人形のような状態に陥っていたからである。
術式のほとんどは魔法陣に組み込まれていたため、呪唱は短かった。呪文はどちらかと言えば起動用に用いられるだけである。一旦励起された魔術は速やかに作用を開始し、数十秒で完了した。軽い恐慌に陥って結界障壁を叩いていたボブカットの少女は、術が終わると同時に結界が自動的に消滅したため、たたらを踏んでつんのめり、床に倒れた。
「あっ!」
頭を振って身を起こし、彼女は自分の体を検分して、何か変わったことがないことを確かめた。
「――簡単な精神魔術で、危険なものじゃないって言うのに。明日の昼にはもう解けてるでしょうよ」
苦笑して声をかける相手を振り向いて、少女は妙な違和感を感じた。緑の髪、左右色の異なる瞳、知性的な美貌、すらっとして均衡の取れた艶やかな肢体。すべての身体的特徴を容易に見て取れたにもかかわらず、彼女は、それが誰なのかわからなかった。わかるのは女性であると言うことだけで、目にしている外見も、目を逸らした瞬間に意識からすっぽり抜け落ちてしまう。それでいて、他の人物と区別することだけはできた。他の者と混同することはないが、相手の個人的特徴を記憶すること、その個人を特定することができなくなっていたのである。
「な――何なの、これ!?」
少女は未経験の事態に脅え、混乱した。
「個体識別はできても、その相手が誰なのかはわからなくする必要があるのよ――これから、あなた達が行く場所ではね」
女性は落ち着き払って説明した。認識の混乱の中でも、その女性が首輪をしていない、つまり奴隷ではないことは理解できた。すなわち、その命令には従わなくてはならない。
魔術士は魔法にかかったメイド達に、シェフィールドを所定の場所に連れていくよう指示した。物入れから白い鳥の羽を一枚出し、魔法をかけて、案内役に仕立てる。羽はひとりでに宙に浮き、少女達の少し前を、ふわふわと移動して進むべき方向を示した。
不安に震えてはいたが、命令に逆らうことは許されていない。メイドの少女達は飾り立てた奴隷の鎖を取り、甘美な刺激に半ば痴呆状態になっている美しい家畜を、決められた場所へと牽いていった。
5
自分はどうしてここにいるのだろう。
少女は熱に浮かされたような気分で自問していた。
落ち着いた雰囲気の舞踏曲が奏でられ、曲の流れに乗って、彼女の前に立つ男性が踊る。その男に抱えられ、手を取られた少女は、引きずられるようにしてステップを共にする。
少女は記憶の混乱を感じた。武闘大会に勝ち残り、迎賓館で催された舞踏会に招かれたのは覚えているが、その舞踏会の半ばから意識が混濁し、後はわからない。今踊っているということはまだ舞踏会が続いているのだろうか。
少女は踊っている相手を見上げ、更に困惑した。男の顔かたちを見て取ることができなかったからだ。目には映るが、意識には映らない。
彼女はぼんやりと周囲を見回した。広大な広間で、何十組もの男女が曲に合わせて踊っているのが見て取れた。だが、彼女はすぐに自分の間違いに気付く。広間はそれほど広くはなく、四囲すべてを鏡に囲われているのだ。映り込んだ像が広間を無限に広く見せているだけだった。踊っているペアも実際は十組足らずのようだ。
壁の一つは1ヤーム半(2.4メートル)ほどのところにあった。少女は鏡に映り込む自分の姿に見入る。鏡の像でも相手の姿形を心に留めることはできなかったが、さすがに自分の鏡像は見ることができた。
少し癖のある土の色の髪は美しく結い上げられ、小さな宝石を多数散りばめた金細工の髪飾りでとめられている。トパーズの耳飾りを付けた耳は先が尖っていた。彼女が、森の民であるエルフ族だという証だ。彼女の肢体はスリムで均整が取れていた。それがわかるのは、彼女が実質、何も着ていなかったからである。絹と思しき光沢のある白い長手袋は、二の腕の金細工の腕輪で終わっている。翡翠、エメラルド、ペリドットなどグリーン系の宝石をふんだんに使った首飾りが胸元を飾っているが、大きすぎも小さすぎもしない均整の取れた乳房は剥き出しのままだ。すらりと伸びた足はやはり白絹のストッキングに包まれ、白いレースで飾られたガーターベルトで吊られている。腰の回りには、透明に近い薄絹が、霞のように取り巻いていた。ほとんど重さがないと見えて、ターンの度にふわりと巻き上がり、ゆっくりと舞い下りる。少女の体を隠す目的には全く役に立たない代物だった。首飾りの下の、露になった張りのある柔肉の頂上では小さな乳首がつんと上向いて、彼女の興奮を雄弁に示している。そして少女の細い首には、黒光りする皮の首輪が着けられていた。首輪の金具には楕円形の金属プレートがぶら下がっている。直接見ることはできないが、彼女はそこに刻まれている内容を知っていた。そこには少女の名と身分が記されている。
ナーダ 性交奴隷 ――と。
男性に引きずられてステップを踏む度に、ナーダの体内で、チン、チン、と硬質の音が響いた。その音は外に洩れることはないが、一つ鳴る毎に、エルフの少女の腰に甘い痺れを走らせる。
音の正体は、直径3ヤッチ(4.8センチ)前後のガラスの球だった。ナーダはこの球体を、直腸内に十数個あまりも収めさせられているのである。ガラス球は非常に振動し易い作りになっているらしく、動くと腸内で触れ合って、振動して互いを弾き、腹の中を掻き回すのだった。
「あ、あん……はん……ふあっ……くぅん……」
優しげな美貌は欲情の紗がかかり、絶え間なく甘い喘ぎ声を洩らす。ナーダは特に後腔での奉仕に主眼を置いた調教を受け、腸内の性感覚を念入りに開発されてきていた。腹腔内で暴れ回るガラス球は、ナーダにとっては、たまらない快感だった。
「ふふふ。確か、君はこちらに色々仕込まれているのだったね」
男は踊りながらナーダの耳に囁きかけた。ナーダには言葉の意味は伝わってくるものの、言い回しや声の特徴を記憶することができない。ナーダの背中に回されていた男の手が背骨に沿って滑り、内部の刺激のためにひくついている菊門に添えられた。指先を当てて、軽く揉み込むようにする。
「やぁん…っ! だ、駄目です……御主人様ぁ……。そんなことを……なさっては……あん! くあぁん!」
ナーダはびくんと跳ねた。
調教の過程で、ナーダは肛門括約筋の拡張訓練を受け、どんな男性でも受け入れられるようになった。加えて、ナーダ自身の意志で思う通りの締め付けができるよう、緊縮訓練も施されていた。菊門の微妙な収縮を自在に操り、高度な調教を受けた性交奴隷にだけ可能なやり方で、主人の快楽に奉仕するためである。生き物のように蠢くガラス球をこぼさないでいられるのは、そうして蕾を締め付ける力を鍛えられていたからだった。だがそれも、ガラス球を腸内に留め置くのがやっとで、それ以上の仕打ちを受ければどうなるかナーダにもわからない。
男の指がナーダのすぼまった部分をほぐすように動くと、湧き上がる心地好さと共に、締め付ける力がすうっと抜けていくのを感じて、エルフ奴隷は狼狽の色を見せた。
「あ……御主人様、お願い……です……。それは、そこは……駄目なんです……ひうっ! ひん……はふ……っ。お…お許し……くださいぃ……きゃん! ああ、あ……許してぇ……」
指から逃れようと、ナーダは腰を前に出した。指先の狙いを外そうとして、左右に腰をくねらせる。それは男の腰に擦り寄って、男根を刺激するかのような動きだった。男はその動きを続けさせようとして、繰り返しナーダの後ろの急所を責める。

たまらず、ナーダは絶頂に追い上げられてしまった。その瞬間、ついに限界を突破して、食い締めていた括約筋が緩む。堰が切れたように、ガラス球が吐き出された。二個、三個。あとは雪崩を切って、何個も、何個も。滑らかな球体が出口を押し広げてつるりと通り抜ける度に、たまらない刺激がナーダの背中を駆け上がった。
「は、ふわっ! あ、い、ああああああああああああ――――ッ!」
立て続けの絶頂がナーダの神経をぞくぞくと震わせた。快美な悲鳴に重なって、ガラス球が連続して床を叩く澄んだ音が、高く響いた。
6
鏡張りの小広間の一隅に、一段高い舞台がしつらえられていた。急ぎ整えたものか、木箱を並べて布を被せただけの代物である。舞台の上には、美しく淫らに着飾った二匹の奴隷が据えられていた。
「――では、舞台の主役をご紹介いたしましょう。この栗毛の奴隷は、先程不躾な粗相を働いた、ナーダ。こちらの青銀色の毛色の牝奴隷が、身の程知らずにも開場に遅れ、主人を待たせるという大罪を犯した、シェフィールド。この度はこの場をお借りして、この二匹の懲罰と余興を兼ねまして、再調教を公開致しますので、しばらくはお楽しみのほどを。只今、会場内を飲み物を持ったメイドが回っておりますので、そちらも御自由にどうぞ」
優しげなエルフ娘と知的な白貌の娘とは、微かに震えながら跪いていた。知性と美貌に恵まれた二人は、相応しからぬ好奇と軽侮の視線を浴びせられ、ただじっと耐えている。この地下広間にはガンダウルフの結界はない。二人が本気になれば、居並ぶ客達を全員薙ぎ倒すことも、その後逃走を果たすこともさして困難ではないはずだった。
だが、二人は「跪け」と命じられていた。命令以外のことをするわけにはいかない。何故命令に逆らえないのかは、彼女達にももうわからなかった。ただ、命令に違反することへのきわめて強い禁忌の念があることだけは確かだった。
哀訴も懇願も、その口から洩れることはない。ただ主人の命令を待ち望んで頬を染める、それは理想的な奴隷の態度と言えた。再調教が実際に必要なほどに矯正すべき奴隷であるのなら、そもそも彼女達がこの場に居合わせることはありえない。この会場に残っている時点で、二人は今回『出品』された中でも、厳選された最高級品であることを意味していた。
今回のこれは、些細なミスを口実にした、淫らなショーであるに過ぎないのだ。
『再調教』の準備は手早く整えられた。二本のロープが天井の梁に渡され、ナーダの両手首とシェフィールドの片足、シェフィールドの両手首とナーダの片足を、それぞれ半端に高く差し上げた状態で連結する。奴隷達は足を下ろすことができず、かと言って吊り下げられることもなく、中途半端な片足立ちを強いられる。均衡を求めて嫌でも動く体は、しかし、自分のものではない動きを受けて静止してはいられず、よろめき、ぐらつき、無様なステップやターンを繰り返した。
滑稽で淫らなペアダンスを踊る二人の傍らに、男が歩み寄った。ひゅっと空気が鳴り、男が手にした乗馬鞭が二人の背に、尻に浴びせられる。
「きゃあぅん!」
「ふあっひいぃぃ!」
不意の痛みに悲鳴を上げるナーダとシェフィールド。が、鞭の打撃が充分手加減されていたためもあり、苦痛の悲鳴のはずが、その声音には多分に甘いものが混じり込んでいた。彼女達、調教され尽くした牝奴隷にとって、適度な痛みは激しい愛撫と等しい効力を肉体に及ぼすのだった。
痛みのためか快楽の故か、身をよじり悶える二人の動きはいっそう激しくなり、あられもない姿を観客の目に曝した。透明に近い紗は耐久力も無に等しく、鞭が振るわれる度に裂け、千切れて宙を舞った。奴隷用のパーティードレスはたちまち装飾を失い、無残な拘束服に成り果てていく。
体重と体動のすべてを支え、通常の数倍の荷重を加えられた二人の片足は、すぐに疲労の極に達し、がくがくと膝を揺らし始めた。幾度目かに膝が抜けかけたとき、ナーダの足がずるりと滑った。
「あっ……!」
内腿を伝い、足裏までを濡らすほどに垂れ落ちた愛液のためだった。均衡を失い、倒れかかるナーダの体を、両手首に繋がれた縄が支える。当然、シェフィールドの足は股関節が悲鳴を上げるほどに引き上げられ、これ以上ないほどに股間を衆目に曝し出す姿勢になった。
「くあああっ!」
限界を超えた大股開きを強いられ、シェフィールドが苦鳴を発した。ナーダの足に両手首を引き上げられ、倒れることも許されない。一方、ナーダも片足と両腕とで天井からぶら下がるような恰好となっていた。関節が軋み、床との接点を失った細身の肢体が、苦痛によじられる体の動きにつれて前後に揺らぐ。
「あうう……!」
焦って、滑った足で床を捕まえようとするナーダだが、萎えた膝は回復しておらず、力の入らない足先で床を撫で回すため、滴った愛液を広く塗り伸ばして、いっそう床との摩擦を失うだけの結果に終わっていた。
そこへまた、乗馬鞭が浴びせられる。狙いは大きく割り広げられた股間だった。
「ひぃっ!」
「くあああぁっ!」
二人の甘い悲鳴が広間に響き渡った。
鞭打たれて艶かしく身を捩る美しい奴隷達を横目に、トレイにグラスを乗せたメイド達が、淫靡な見せ物を悠然と見物している客達に飲み物を配って回っていた。だが――『それ』をメイドと認識するのは、少々困難だったかも知れない。メイドと呼べる衣装は、髪に飾ったレースのブリム(頭飾り)のみ。それ以外には、さすがに踵の低い靴の他は、手首と足首に巻かれた黒い革のベルトと、やはり黒い革の首輪。それが彼女達が身に着けているすべてだった。要はほとんど全裸だったのだ。
この簡素な装束はおそらく、着飾った奴隷達との差別化が計られたものだろう。
言うまでもないことだが、この鏡の広間には、ナーダとシェフィールド以外の残った6名の女性選手達が揃い、淫らにドレスアップして舞踏の相手を務めさせられている。この再調教ショーの間だけは、ワルツやメヌエットは静かなコンチェルトやセレナーデなどの環境楽に近いものに切り替えられ、彼女達にはしばしの休息――ナーダがしていたような責め具や、客の悪戯などにさらされてはいたが――が許されていた。
だが、メイド達にとっては、この幕間こそが一番忙しくなる時間だった。
「飲み物をどうぞぉ」
どこか脅えのある表情で、赤毛をショートヘアにした少女は、小麦色の肌の美女を囲んで談笑する男達にトレイを差し出す。
「ふむ、これは……ベングの白、52年物ですな。スカリー陛下も気前がよろしい」
「こっちはブルガンディのラム酒か」
「……お、これは――珍しい。ドワーフの黄金酒ではないですかな?」
「ほう。火酒をドワーフが秘伝の法で熟成させたと言う、あの?」
「それをおっしゃるなら……これはもしかして、エサランバルの天蜜酒では……」
「何と! あの幻の?」
「いや、まさか…」
次々にグラスを取って薀蓄を傾けながら、男達の手はトレイ以外の場所にも無造作に伸びた。
「ん……ふっ」
メイドの鼻声が洩れる。少女の張りのある肌を男達の指が這い回り、背中を、脇腹を、首筋を撫で、乳房と尻房を揉み込んで柔らかさを堪能する。指先は物欲しげに涎を垂らす下の唇と、恥ずかしげに引き結ばれた上の唇に進入し、濡れた襞と舌を捕らえて掻き回す。勃起し切った乳首が、陰核がつままれ、扱かれ、転がされる。
男達の触れ方は穏やかで、優しくすらあったが、それがメイドの少女への思いやりによるものではないことは明らかだった。それはただ自らが触れて楽しむためだけの手つきであり、少女は今、手触りの好さを提供するだけの肉人形に過ぎない。彼女はこの客達に、人間と扱われないのはもとより、家畜、いや生き物とすら見られていないのだ。
それでも――いや、それだからこそ、少女はひとたまりもなく、男達の無遠慮で無機質な愛撫に官能を蕩かされていく。魂の芯にまで彫り込まれた被虐の悦びが、貶められるほどに欲情の手綱を弛めずにはいないのだ。
「あ、んむっ…ふああ、あっ! きゃうん、んああん!」
メイドの口から、抑え切れない快美の悲鳴が洩れる。頬はほんのりと上気して髪の色に近付き、瞳はとろりと潤んで、切ない視線を客達に向ける。吐息には熱がこもり、膝はがくがくと震え、その乱れ振りは一目見るだけで明らかだった。だがそれでも、トレイを支える手には辛うじてまだ力を残している。全身を襲う快楽に翻弄される少女の手の震えがグラスに伝わって互いに触れ合い、かちかちと鳴っていたが、トレイそのものは何とか保持されていた。
見事な義務感ではあったが、それも、客の一人が彼女の急所を見つけ出すまでのことだった。
「ひぅんっ!」
赤毛のメイドは甘い悲鳴を上げて、びくんと背を反らした。二本揃えた指先が、彼女の後ろの窄まりを前触れなく貫いたのだ。
「――ほう?」
過敏な反応に、男達は揃って面白そうな表情になる。楽しいおもちゃを発見した顔だ。
男達の手が少女の尻に伸ばされた。
「うあああっ! あひぃっ!」
何本も菊門に指が差し入れられ、ぐいぐいと押し広げる。少女の窄まりは驚くほどの伸長を見せ、五人もの男の指先を受け入れて、なおもぱっくりと口を開いた。
「はあああっ!」
メイドの膝ががくりと砕け、前のめりに倒れ込む。一番の性感の源に激しい蹂躙を受け、耐え続けていた少女はたまらずイってしまったのだ。腕の力も抜けてしまい、トレイを取り落とすが、グラスが床に散ることはなかった。男の一人が素早く落ちかけたトレイを掬い上げたのである。
「おっと、危ない。さすがに大理石に振る舞うには、少々惜しい酒だ。……君も味わってみたまえ」
そう言って男は、ドワーフ族の好む酒精分の高い酒を満たしたグラスを手に取り、少女に近付けた。口に、ではなかったが。
彼の意図を察し、他の男達が指を鉤状に曲げ、赤毛娘の括約筋を引っ掛けて持ち上げるような動作をする。
「――ああああああっ!」
後門を限界まで広げられ、強く引き上げられて、少女は萎えかけた足を必死で踏ん張り、尻を真上に高く掲げた。そうしなければ本当に裂けてしまいそうだった。
真上を向き、大きく口を開けたそこに、男は静かにグラスを傾ける。琥珀色の液体が、筋を作って流れ落ちた。
「ひ!? あ、ああ、いや、いやああ……」
加圧されずとも流体を受け入れられるほど、彼女のその部分は拡張され切っていた。腹腔を冷やしていく感覚に、脅えた声を上げる。酒がメイドの腸内に注がれてしまうと、男達は指を引き抜き、少女を取り巻いて観察し始めた。
うずくまって荒く息をついていた少女は、やがて、下腹の感触の変化に戸惑いの色を見せた。
「あ? 何……。あ…熱い…お腹が……」
一旦引いていた肌の色が、再び朱を帯びて、髪の色に近付いていく。下腹部がかーっと熱を持ち、その熱がどんどん全身に広がっていくような感覚。少女は下腹を抱え込むようにして縮こまり、唇を噛んで違和感に耐えた。
「どうかね? ガルテーの黄金酒の味は?」
下の口から強い酒を呑まされてしまった少女に、酒を注いだ男が面白そうに問い掛けた。問いながらメイドの腰を持ち上げる。
「ああ…嫌、動かしちゃ……ひぅあああああっ!!」
男は無造作に、酒精に冒された少女の菊門に肉槌を打ち込んだ。その瞬間彼女はまた絶頂に達し、秘裂から潮を噴きながら男の肉幹をぎゅうっと食い締める。
「お……これは、なかなか」
「ほう、それは。こちらはどうですかな」
四つん這いのメイドを抱え上げ、別の男が秘唇を犯す。前後を同時に埋められ、少女は快楽の絶叫を上げた。
少し離れたところから、その姿に心配そうな視線を向ける少女がいた。
「ああ、エイダ……」
やや視線を外すと、癖のある黒髪をボブカットにした、赤毛の少女と同じ格好をした少女が、男の前に膝をついて男根を咥え、忙しなく顔を動かして奉仕しているのが見える。生意気な言動を咎められでもしたのか、後ろに立った別の男が間を置きながら少女の尻を平手で叩いていた。何度もスパンキングを受けたらしく、彼女のお尻は真っ赤に腫れている。相当な痛苦を感じているのは明らかだったが、にもかかわらず、彼女の内股にはとろみのある液体が垂れ落ちた跡が、いくつもの光る筋を残していた。
「キャロルも…」
だが、彼女自身も、他人の心配などしているような状況ではなかった。先程までのエイダと同じく、数人の男達に全身を舐めるように撫で回されているのだ。
先程、舞台で司会役が『ご自由に』と言っていたのは、つまり、こう言うことだった。
客達は、女性選手達には、触れて嬲る、品定め程度のことしか許されていない。
だが、会場を回っているメイド達は、自由に楽しんでくれていい――そう言ったのである。そしてこれが、彼女達がゼルダに与えられた『罰』だった。
他の二人と同じくレースのブリムと首輪、手足首の革ベルトと靴だけを身に着けた少女は、背に流れ落ちている茶色がかった黒髪を大事そうに手梳きされ、ぶるっと震えた。艶やかな長い髪にまで神経が通っているかのような所作である。
背後に立ってメイド少女の髪を弄んでいた男が、彼女の耳元で囁いた。
「この美しい髪の艶には覚えがありますよ。先の陛下の弟君であられた、マクネイル大公の御息女、パメラ大公女殿下……そうでしたね?」
びくっと身を固くするパメラ。
「――いえ、私は…そのような者では、ございません。一介の、身分卑しき牝奴隷……殿方の快楽を満たすためだけの、単なる性玩具に過ぎない存在です…御主人様」
応じる声は妙に平板で、語尾が震えていた。動揺を隠しきれていない。
男の指摘が正しければ、少女はスカリーやメディアの従妹にあたり、内乱で多く王家の男子が落命した今では、普通に考えれば第二位の王位継承権を持っている事になる。だが無論、奴隷が王位に就くことなどあり得ない。そう言う意味では少女の言葉は真実ではあったが……そう答えるに至った真情は、それだけのものではなかっただろう。
かつての自分を知る相手に弄ばれるのがたまらなかったのだ。王族の一員から、一介の性交奴隷――それも、特別なことなど何もなく、他の奴隷と一切変わるところのない『単なる』奴隷――への、落差の激しすぎる凋落ぶりを思い知らされるようで。
そんな想いを見透かしたように、背後の男は笑みを含んだ声を返す。
「ふふふ、ならばそういうことにしておいて差し上げてもよろしいですよ。――ただの奴隷と言うのなら、スカリー陛下にお願いすれば、あなたを譲っていただくのも難しくはなさそうですね。上手くあなたを手に入れられたら、ブリムの代わりに、百合の紋をあしらった銀のティアラを着けた姿で飼って差し上げますよ――パメラ姫」
「あ……」
ぞくぞくっと背筋に震えが走る。百合の紋をあしらった銀のティアラ、それは、マクネイル大公の愛娘が、公式の場で着用すると知られている物だった。奴隷でありながら、大公女の装いを同居させられる――ただ諦めのままに奴隷に堕ちることを受け入れるよりも、たとえようもなく恥辱を誘発する想像だった。
だが、強烈な羞恥と屈辱の他に、彼女の体を満たすものがあった。
「くぅん…っ!」
パメラの体が不随意的に痙攣する。絶えず分泌していた、内股を伝う欲情の証が急に量を増す。
「今、軽くイったね? ……淫乱なお姫様だ」
「あ、イヤあ……そんな風に、呼ばないでください……」
恥ずかしさのあまり消え入りそうな声で、パメラはかぶりを振った。だが、言葉に反して、辱められる度に彼女の興奮の度合いが高まっていくのは、一見して明らかだった。
「確かに今の君は、淫らな牝奴隷に過ぎないようだね。それでは、そろそろ奴隷の義務を果たしていただきましょうか、殿下?」
「ああ……はい……御主人様」
パメラは恥ずかしそうに、だが嬉しげにも見える表情で、回り中から差し出された肉棒に、技巧を尽くした奉仕を捧げ始めた。
三人の奴隷少女の嬌声と、六人の奴隷の悶える喘ぎと、二人の奴隷の甘美な悲鳴とが、淫靡な協奏曲となって鏡の広間に響き渡る。
深夜の舞踏会は今しばらく、終焉を迎えることはないようだった。
|
![]()
![]()